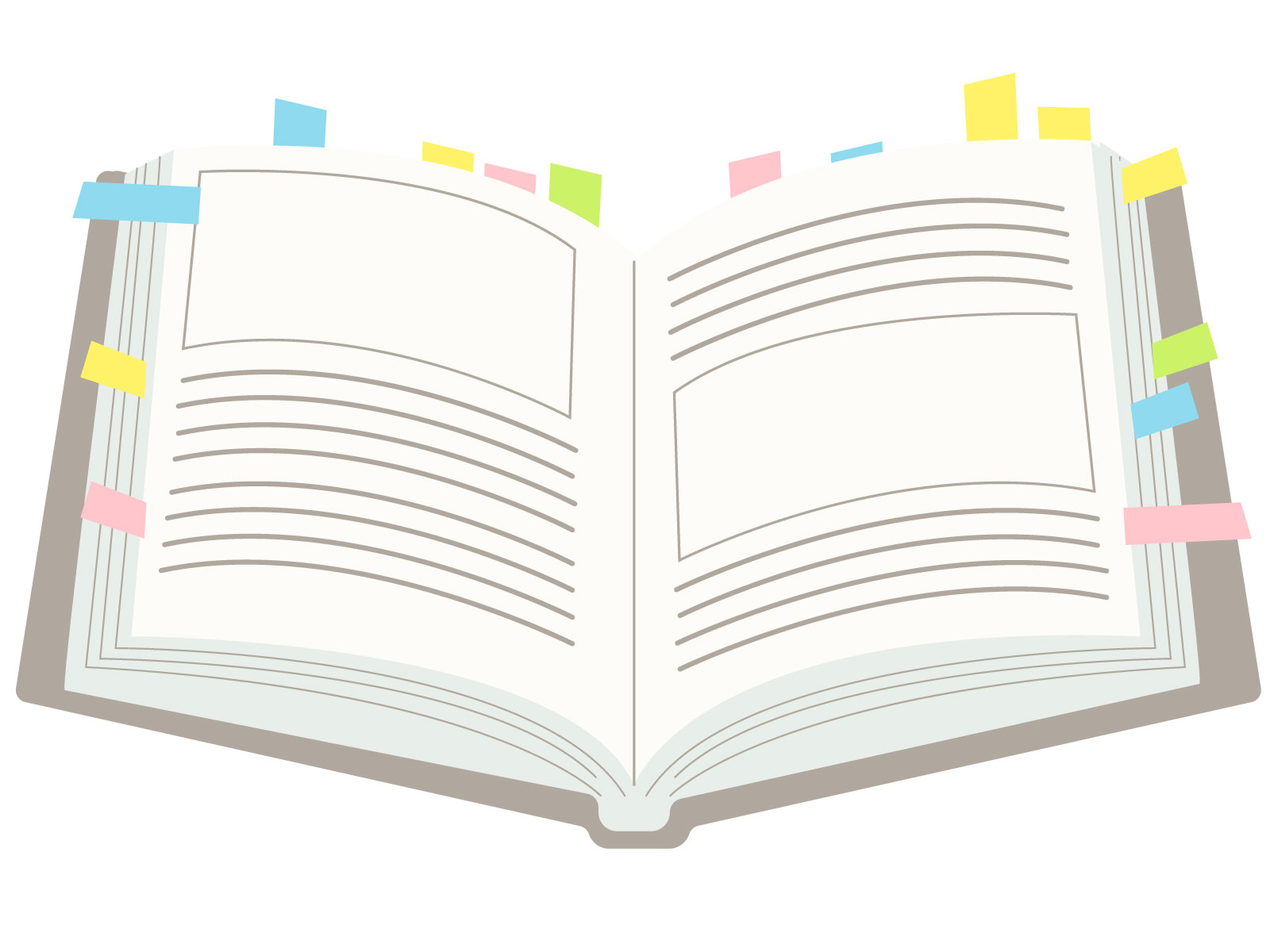目次
多くの先生方が、日ごろから生徒に対し「しっかりと復習してほしい」と思っていることと思います。しかし、「復習をきちんとしなさい」と指導したところで、やらない生徒には響かないのではないでしょうか?
そんなお悩み解消のために、今回は復習に取り組むための基本知識から実践編、復習の効率を高めるコツまで解説します。
効果的な方法で復習を行うことで、効率的に時間を使って、その生徒の能力を最大限に引き出すことが可能です。
この記事では、これまでの復習方法の見直し方と、個々の生徒に合った復習方法の提案を的確に行えるよう、「復習」についての情報をお届けします。どうぞ最後までお読みください。
復習の基本【知識編】
まず最初に、全教科に共通した内容として、効率的に復習を行うための基本知識をご紹介します。
繰り返し復習する
復習は一度だけ行うよりも、何度も繰り返すことでより効果がアップします。とはいえ、やみくもに繰り返すのは非効率的です。一般的には、一度覚えたことを忘れそうなタイミングで再度復習する「分散学習」と呼ばれる方法がよいとされています。
分散学習のタイミングに決まりはありませんが、「忘れかけてきたころに復習する」ことがポイントです。
ただし、初めて学習した内容を復習するまで時間を空けすぎてしまうと、間違った内容を思い出してしまい、その誤った知識が記憶に定着してしまう可能性があります。そのため、初回の復習は、授業で習った当日や翌日など、学習時の記憶がそのまま残っているうちに行い、次は3日後、その次は1週間後など、徐々に期間を空けて繰り返し復習するのがよいでしょう。
復習時にはアウトプットを意識する
復習をするときは、教科書を読んだりするインプットだけで済ませず、必ず記憶した内容をアウトプットする過程も取り入れましょう。復習した内容をノートに書き出してまとめたり、復習した内容を含む問題をいくつか解いたりすると、より正しい知識の定着につながります。
とくに、「覚えたと思っていたのに、テスト本番で思い出せなかった」という現象は、学習時のアウトプットが不足していた場合によく起こります。教科書や授業でとったノート、参考書を読んだりして知識をインプットしたあとは、次のようなアウトプットの時間を必ず確保するよう指導しましょう。
- 復習した内容を含む問題や類題をいくつか解いてみる
- グループ学習などで誰かと教え合う
復習には「習った知識を正しい記憶として定着させる」という意味があることを、生徒に理解してもらいましょう。
ゲーム感覚でアウトプットできる方法としておすすめなのが「自作クイズ」です。アウトプットに役立つクイズの例はこちらの記事で紹介しています。
最終的には必ず自力で解く
復習時のアウトプットとして練習問題などを解く際には、はじめは解説等を見たり他の人の力を借りたりしていても、最終的には自力で解いてみることも重要です。この工程が抜けていると、学習内容を応用するための理解度、知識の定着が不十分になりやすく、アウトプット学習の効果が小さくなってしまうからです。
たとえば英単語の復習ならば、日本語だけを見て、それに当たる英語を自力で書けるようになる必要があります。また数学の復習であれば、解説や参考書を見ずに問題を解けるようにならなくてはいけません。
さらに、アウトプットで重要なのは、本番の試験と同じ状況を作ることです。勉強が苦手な生徒ほど、解けない自分が明らかになることを無意識に回避しようとします。「覚えた」「わかった」という気になることが最も危険なので、最終的に自分一人の力で解くことを必ず徹底させましょう。
復習の基本【方法編】
ここでは、「生徒に推奨したい基本的な復習の方法」をお伝えします。ぜひ参考にしてください。
付箋を活用する
付箋は、効果的な学習のための必須アイテムです。付箋を使って復習したいポイントを可視化することで、見落としを防ぎ効率よく復習を進められます。
授業中、後で確認したい内容や、繰り返してきちんと覚えたいことが見つかったときには、その箇所に付箋を貼っておけば、忘れずに復習に取り組めるでしょう。また模試の返却時に、不正解だった問題を確認して問題用紙の当該箇所に付箋を貼れば、復習すべきポイントをすぐに見つけられます。
復習で見つかった疑問点の質問し忘れ防止にも、付箋が役立ちます! 付箋の活用法を詳しく生徒に伝えたい方は、以下の記事もご覧ください。
付箋の使い方で勉強効率が上がる!勉強法のアイデア7選
定期テストや模試の見直し時間を活用する
定期テストや模試の実施時に、解答時間が余った場合は「見直し」をするよう生徒に指導している先生は多いと思います。その見直しの際に、問題用紙に印を付けておくと、復習の効率を高めることに役立ちます。
たとえば、「解答時の感触」を以下のようにランク分けして印を付けておくと、時間が経っても復習の要否が瞬時に分かり、効果的な復習ができるでしょう。
| 解答時の感触 | 印の例 |
| 自信がある | ✓または印なし |
| 曖昧な点がある | 三角印 |
| わからない | 星印 |
とくに三角印や星印をつけた問題は、正解・不正解に関わらず見直しをしましょう。もちろん、印を付けなかったにもかかわらず不正解になってしまった問題も、間違えてしまった原因をしっかり確認して復習しましょう。
テストや模試の見直し時間も、能動的な工夫次第で復習の効果アップに役立ちます。
復習をルーティン化する
復習の習慣を確実に身につけさせたい場合は、生徒の学習スケジュールに「復習」の時間をルーティンとして組み込みましょう。習慣化のために、教科ごとに曜日や時間を固定してしまうのもおすすめです。
ただし、模試の復習にはできるだけ早く取り組むことを推奨します。試験中の解答時の思考の記憶は紙面に残らず、覚えているようでも日が経てば薄れてしまうからです。数日内と言わず、模試が終わったら早めに復習するよう指導しましょう。
内容に優先順位をつけて取り組む
復習に取りかかる前に、内容に優先順位をつけることも重要です。各種テストや模試の前までに、完璧に安心できるレベルの知識を定着させるのは、誰にとっても至難の業です。
復習のテーマとして、まず優先してほしいのは「弱点の補強」です。生徒に以下のような傾向が見られるなら、改善が必要かもしれません。
- いつも、まんべんなく総復習している
- 得意な教科や好きな教科ばかりに復習の時間をかけがち
- 復習の時間や量(回数)にこだわっている
単元の総復習は、学習内容の体系的な整理・理解には役立ちますが、その分かなりの時間を要しますし、補強が不要な箇所まで繰り返すことになり非効率的です。まず弱点を把握させて、ピンポイントで復習するよう伝えましょう。「覚えたいこと」や「克服したいこと」にフォーカスして学習し、理解不足の穴を埋めるイメージです。
また、各種テストや模試の直前にやる出題単元の復習では、伸びしろの少ない得意教科より、苦手教科の復習を重視したほうが、トータルでの成績アップにつながります。
復習の優先順位を決めるポイントは「克服できたか」どうかです。時間や量より、弱点の穴埋めにフォーカスさせましょう。
効果的な復習の実践例
ここからは、より実践的な復習の方法を説明するために、生徒に指導しやすいテストや模試の復習を中心として、取り組み例を解説していきます。英語と数学の2教科を説明しますので、ぜひ参考にしてください。
事例1:英語の復習
英語の復習は、以下の4つのカテゴリーに分けて解説します。
- 語彙・文法の問題
- 長文・対話文の問題
- 英作文の問題
- リスニング問題
生徒には、それぞれの特性を踏まえて復習をさせましょう。
語彙・文法の問題
語彙・文法の分野の問題の復習は、単語や熟語の暗記、文法や構文の確認が必要となります。
まず、単語や熟語の学習には、その生徒ごとに向いている勉強方法があります。自分にあった勉強方法を取りつつ、アプリなどを使って隙間時間に効率よく学習を進めることで、小学・中学で学ぶ大量の英単語を網羅することができます。
一例として、勉強方法の診断と英単語学習を行えるアプリ「Learn&Pace|ラナペ!」をご紹介いたします。
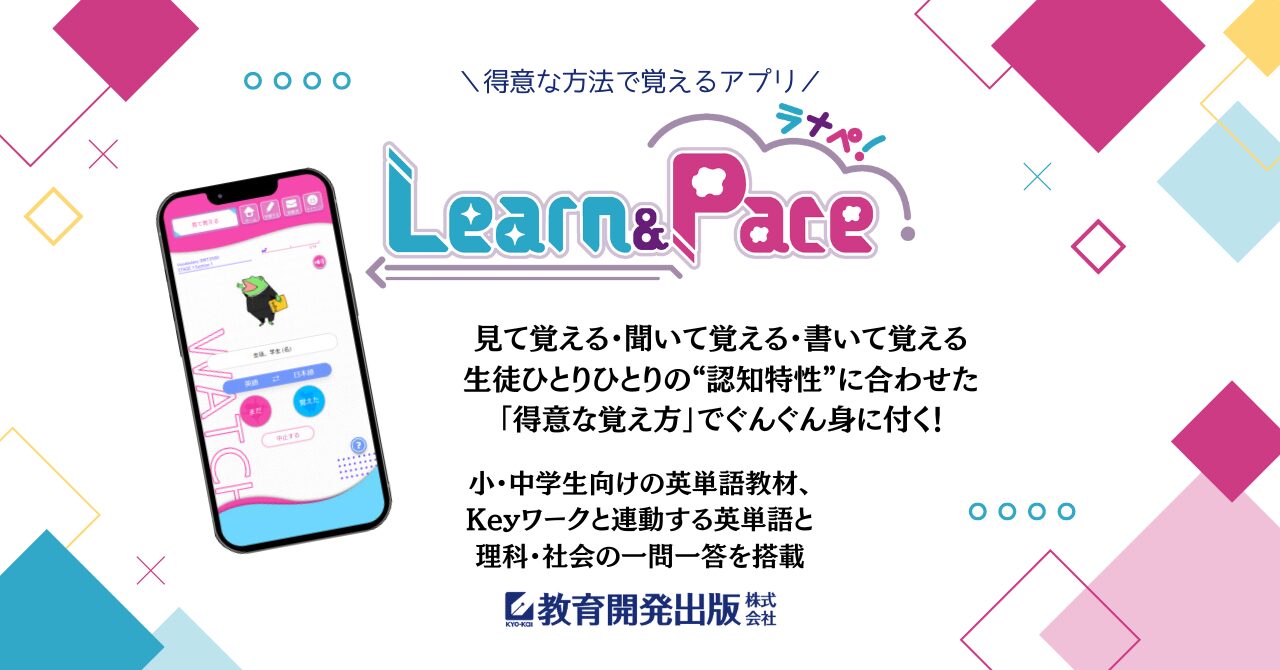
文法や構文の復習は、ルールの再確認をしたうえで、本当に理解できたかを問題演習を通じて確かめることが重要です。文法の中には基本的なルール以外に、例外的な使用方法のある文法もありますが、まずは基本的なルールの定着に取り組み、徐々にパターンを変えて例外との違いを理解していきましょう。
また自力で授業ノートや参考書を見返しても、ルールを整理できない生徒もいます。そんな自力で復習するのが難しい生徒には、先生からのフォローも必要です。
語彙の復習には、隙間時間を有効活用しましょう!
長文・対話文の読解問題
長文や対話文の問題は、再度解き直すより、正解を確認したうえで本文を精読しながら内容の確認と解答の根拠探しを行うほうが、復習の効果があります。また、同時に生徒の解答を分析して「問題を解けなかった原因」を探ることで、どんなことに力を入れて復習すれば良いのかもわかります。
たとえば、次の英文訳が問題に出たとき、その生徒がどの部分でつまづいてしまったのかわかれば、復習として語彙力を主に伸ばせばよいのか、文法・構文の見直しをすればよいのかがわかります。
However, some people who want to keep koalas safe say we should follow some rules when we take photos with koalas.
訳の例:しかしながら、コアラを大切にしたいと思う人の中には、コアラと写真を撮るときは、いくつかのルールに従うべきだと言う人もいます。
①「However」の意味を知らない場合は、語彙力不足です。単語の復習を行いましょう。
②「who」が関係代名詞であることや「say」の後が「that節」になっていることが判別できない場合は、文法・構文の理解不足である可能性が高いです。
模試や定期テストの場合は、脚注の確認不足や時間配分のミスなど、復習しづらい原因である場合も多くありますが、生徒が自分で間違えを分析できていて、次に生かせるなら、得点アップへの道を一歩進めています!
英作文の問題
英作文の問題の復習は、解き直しをすることが最も効果的な方法です。並べ替えなどの和文英訳では、解答を覚えてしまう可能性がありますが、なにも見ずに自力で正解が書けるまで解き直しましょう。冠詞や時制など細かな点まで、完璧を目指すことが大切です。自由英作文は減点方式で採点されるので、足りなかった部分を仕上げるイメージで解き直しに取り組ませましょう。
自由英作文の場合は生徒が自力で採点を行うのは難しいため、解き直した英文は再度添削してあげましょう。良い点や悪い点をフィードバックすることで、英作文の力をより効果的に養うことができます。
また、それぞれの生徒の状況をチェックして、語彙や文法の知識が圧倒的に足りていないなら、英作文を解くよりも先に知識を増やすための学習メニューを提示しましょう。逆に語彙や文法の理解があっても、自由英作文が書けない生徒には、使いやすい構文やフレーズを教え、書き出しやすくするのも指導のコツの1つです。
特に自由英作文の学習初期は、知識のある生徒ほど「書きたいこと」を書こうとして、書けない現実に苦しみます。得点をもらうために、まず「書きたいこと」ではなく「書けること」を書くという姿勢が大事であることも伝えましょう。
リスニング問題
リスニングの復習は、基本的に「スクリプト(放送原稿)」を使って放送内容を把握するところからはじめましょう。正解率によっての復習の方法は、下の表を参考にしてみてください。
| 正解率 | 主な失点の原因 | 必要な復習 |
| 9割以上の生徒 | ケアレスミス | スクリプトと解答を参照する |
| 6〜8割ほどの生徒 | 一定箇所の聞き取りと理解の不足 | ①スクリプトを音読する ②聞き取れなかった文章、理解できなかった文章を和訳してみる ③スクリプトと解答を照らし合わせて「解答」が正解となる根拠をつかむ ④放送音声を聞く |
| 5割未満 | 広範囲の聞き取りと理解の不足 | ①スクリプトを音読する ②読めない語彙を調べる ③聞き取れなかった文章や理解できなかった文章を和訳してみる ④スクリプトと解答を照らし合わせて「解答」が正解となる根拠をつかむ ⑤スクリプトを何度か音読する |
正解率が低い生徒はリスニング力が足りないというよりも、語彙や文法の知識が不足しているケースがほとんどです。スクリプトを読ませて、まずはわからない単語を調べさせましょう。一定の語彙力がつけば、あとは英語の音声をたくさん聞いてリスニングの経験値を増やし、さらに問題形式に慣れることで得点力が身につきます。
シャドーイングに取り組ませたりするのもおすすめです!
事例2:数学(算数)
数学の復習にも、公式などの重要な知識を「覚える(見直す)」時間がもちろん必要です。ただ、覚える(暗記)よりも、実際に練習問題を解いて、正解に至るための解法を「考える」ことにかける時間が多くなるため、文系科目とは復習の質が異なる点を生徒に伝えましょう。
効果的な復習を実践するための方法は、以下の2つのカテゴリーに分けて解説します。
- 基礎力不足が問われるケース
- 応用力不足が問われるケース
他の理系科目の復習にも活かせますので、ぜひ参考にしてください。
基礎力不足が問われるケース
数学(算数)において基礎力の補強のために復習する必要があるのは、以下の2つのケースです。
- 解法に必要な公式などの知識が足りていない、または理解が曖昧である
- 四則計算などの技能的なミスがある
数学は、公式や定理・条件などを正確に覚えて使えなければ、多くの問題が解けなくなってしまいます。そのため、それら最低限の知識が不足している場合には、知識事項の見直しからはじめさせましょう。そして、単に公式などの形を覚えるだけでなく、その意味を理解し、実際に練習問題を解いて正しく使えることまでを復習することが大切です。
また、計算ミスなどのケアレスミスは、一見小さな問題にも思えます。しかし、不注意に起因するミスが多い生徒はこれが癖のようになっている場合が多く、甘く見ていると、入試本番でも点が伸びない原因となってしまいます。試験のたびに、ケアレスの有無とミスの内容を確認し、ミスをなくせるような訓練を、繰り返し行ってください。たとえば、タイムプレッシャーをかけて同じ問題を繰り返し解かせることで、解答の精度を高める慎重さとスピードの両立が身についていきます。
「式を省略せずにすべて書く」といった工夫で、計算ミスは減りますよ!
応用力不足が問われるケース
数学(算数)の応用力は、自力であれこれ解法を考える時間によって身につくものなので、復習も一から自分で解きなおすところから始めるのがベストです。時間をかけながらいろいろと試行錯誤することで、理解不足だったポイントを認識できたり、新しい視点を発見できたりします。
また、解きなおす際には、必ずノートに問題や図表を書いて、解く際に使った計算式やメモも、必ず残すことを習慣にさせましょう。後で見返したときに視覚的に理解しやすい状態を作っておくのがベストです。
数学(算数)は、自分の頭で考えながら解いて答えにたどり着けること、類題でも自力で解法までのプロセスを再現できることが、もっとも大事です。生徒には、解答・解説を見て復習が終わりではないことを伝えましょう。また、自分で解けた問題についても、解答・解説を見ることを推奨します。自分の解き方と解答とを比較することで、より効率的な解き方や別解を学べ、理解や応用力を深めることができます。
苦手な生徒が多い単元の問題は、定期的に出題して解き方を定着させましょう。
復習に打ち込めない生徒には、先に効果を伝えよう
なかなか復習のために時間を確保できない生徒は、具体的な学習方法を知らないだけでなく、その効果や重要性を理解していない場合が多いものです。まだ復習の効果を実感する経験に乏しければ、受け身の姿勢で漠然と取り組んでしまうのも仕方ないことかもしれません。
そのような生徒には、効果的な復習の方法だけでなく、「なぜ、復習が大事なのか」を同時に伝えることが大切です。言語化して論理的に説明することで、復習の重要性を理解してもらえ、能動的に取り組むきっかけになるでしょう。
なお、生徒にわかりやすく復習の効果を伝えるためには、以下の2つのポイントに分けて説明するとよいでしょう。
- 記憶の定着:脳は何度も繰り返し学習したことの重要性を認識し、長期記憶を形成する
- 理解度・応用力の向上:繰り返し問題を解くことで、正確な理解が深まり、解答・解法に至るまでのスピード・精度の向上につながる
復習をして成績を上げた先輩の具体的な事例も伝えれば、説得力や復習への意欲がさらに高まります。
成績アップのために復習はとても重要!
毎日の復習を漫然と行うのは時間がもったいないですし、モチベーションアップにもつながりにくいもの。先生は、より効率の良い学習方法を生徒に伝えるだけでなく、復習の意義も上手に伝えて、復習の習慣化、能動的な取り組みを軌道に乗せるサポートをしてあげましょう。
復習の習慣化は、学力向上のために欠かせないプロセスの1つです。的確な方法で行えば、生徒の成績アップに間違いなくつながります。今回紹介した方法も参考にしながら、効果的な復習を促していきましょう。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。