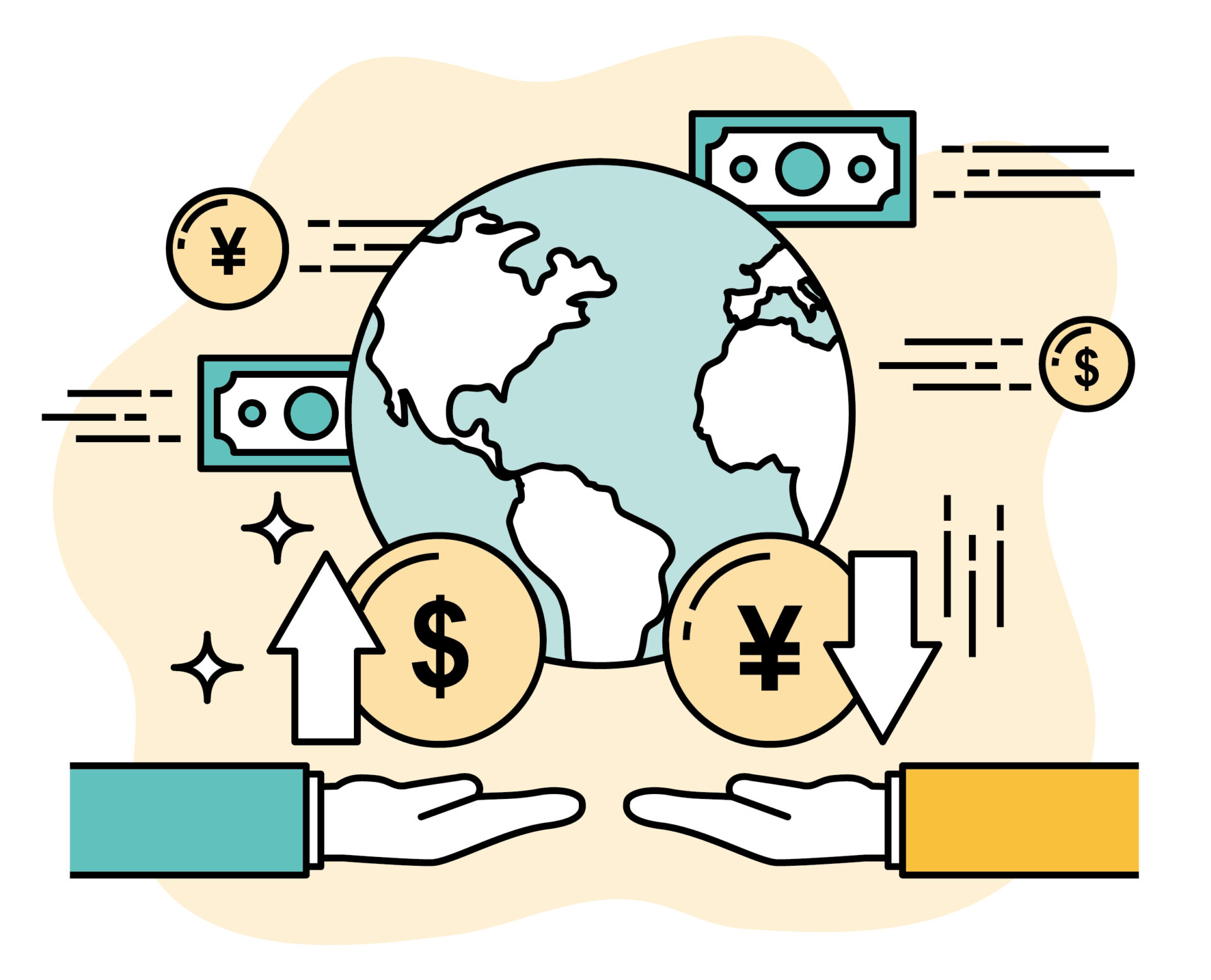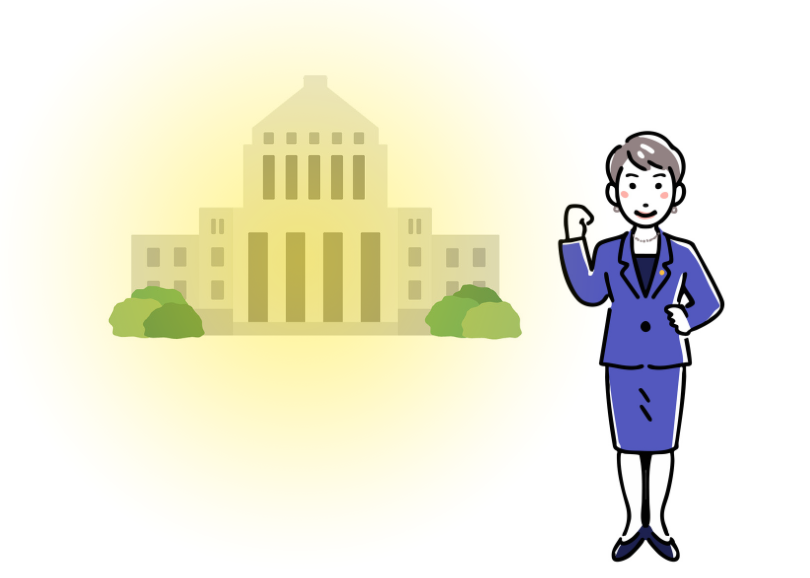目次
「どんな学年レクを企画すれば、生徒が楽しく参加できるのか、悩んでいる」
「毎年同じようなアイデアばかりなので、マンネリを打破したい」
「新しいレクのやり方を知りたい」
このようにお悩みの先生方も、いらっしゃることでしょう。
生徒の緊張をほぐしたり交流を活性化させたりする学年レクは、和やかな雰囲気を作るアイスブレイクとして有効です。
この記事では「盛り上がる学年レクのアイデア」として、具体的なレクの種類や内容のほか、事前の準備や注意事項について解説します。これを参考に、生徒が安全に楽しく盛り上がれるレクを開催しましょう。
ただし、大人数での移動を伴うレクでは怪我の発生リスクがあるため、くれぐれも事前の安全確認や生徒へのルール説明を忘れないようにしてください。
教室内で楽しもう!中学生の学年レク5選
教室内で盛り上がる人気の学年レクは、NGワードゲームやお絵描きリレーなどです。
これらは席を移動せず短時間で盛り上がれるので、年度初めのぎこちないクラス内の人間関係をほぐしたり、席替え直後に近くのメンバーと交流したりする場合に役立ちます。
NGワードゲーム
NGワードゲームは、各自に設定されたNGワードを避けながら、フリートークを楽しむゲームです。
NGワードは、対決相手やゲームに参加しない人がメモ書きして、本人だけは見られないようにしておきます。日常会話に使う単語はもちろん、あいづちや相手の口癖を設定してもおもしろいでしょう。参加者が大人数なら、班ごとにNGワードを設定しても楽しめます。
設定された言葉を口にすると負けの単純なルールですが、自分のNGワードを探りながら会話を続けたり、相手のNGワードを引き出そうとしたりする駆け引きで盛り上がります。
かぶっちゃダメゲーム
かぶっちゃダメゲームは、出されたお題に対し、他の回答者(チーム)と同じことを言わないように答えるゲームです。先生が出したお題に対し、他のチームとかぶらないように回答を考えます。
例)お題「数字と言えば?」
A班「3」B班「4」であれば、お題をクリア。児童の勝ち。
A班「3」B班「3」で答えがかぶってしまった場合、先生の勝ち。
お題は「何曜日が好き?」や「お寿司のネタと言えば?」など、回答に複数の選択肢がありつつも、答えの範囲が限定されるものがおすすめです。ただし「好きな食べ物は?」のような選択肢が多すぎる出題は、盛り上がりに欠ける可能性があるので、あらかじめ適したお題を用意しておいた方がスムーズに進行できます。
他の人の気持ちを考える客観的な視点や、回答を予想する推理力が必要なゲームなので、楽しみながら思考力を鍛えられます。
後出しじゃんけん
後出しじゃんけんは、いつでもどこでもできて盛り上がる定番レクです。
まずは親を決め、親が「あと出しじゃんけん、じゃんけんぽん、ぽん」というかけ声をかけます。 最初の「ぽん」で親が手を出し、2回目は挑戦者が手を出します。勝負の結果、親に勝てればそのまま勝ち、負ければ負けです。
掛け声とともにお互い同時に手を出す通常のじゃんけんは、勝つことが前提です。しかし、後出しという要素が加わることで、先に出す側が相手に「勝つ」だけではなく「あいこ」「負ける」などの条件を指定でき、いつもと違う楽しみ方ができます。
ペアでも楽しめますが、クラス全員が先生と対決しても盛り上がります。景品を用意した勝ち残り戦や、給食の人気デザート争奪戦などにアレンジすれば、ワクワク感が増し、間違いなく楽しめるでしょう。
後出しじゃんけんは、相手の指示に合わせるとっさの判断力や瞬発力が必要になるため、盛り上がりやすいレクの1つです。
お絵描きリレー
お絵描きリレーは、お題を絵で順に伝えていくゲームです。内緒話で内容を順に伝える「伝言ゲーム」の、お絵描き版をイメージすると良いでしょう。
1人目は、与えられたお題を描いて2人目に見せます。2人目は、絵から読み取ったお題を自分で描き直して次の人に伝えます。これを繰り返し、最後の人まで伝わったら、出題者と回答者で答え合わせをします。
このゲームに必要なのは、紙と筆記用具です。また、描く時間とお題を読み取る時間が必要なので、使える時間に合わせて、グループの人数や時間配分を調整してみてください。
伝わり方が画一的な文字と違い、お題の解釈や伝えるポイント、参加者の絵心によって個性が出やすいので、それぞれの違いを楽しめます。また、お題と大きくかけ離れたときでも、みんなの絵を見て検証できるので盛り上がること間違いなしです。
バースデーチェーン
バースデーチェーンとは、声を出さずに非言語コミュニケーションだけで、誕生日が早い順に参加者が並ぶゲームです。全員で協力してバースデーチェーンを完成させる必要があるため、アイスブレイクにも最適です。ルールはシンプルですが、参加者1人につき2〜3秒の制限時間を設けると難易度が上がるので、ドキドキ感も楽しめます。
この遊びのポイントは2つです。
・発言や筆談を禁止し、ジェスチャーによるコミュニケーションだけをOKにする。
・最後に全員が自分の誕生日を言い、答え合わせをする。学年開きなどのタイミングでは、名前を一緒に伝えるのもオススメです。
これらのポイントを押さえることで、ゲーム中のコミュニケーションを促進され、参加者が自己紹介のようにお互いを知るのに役立ちます。また、誕生月が一緒など自分との共通点を見出すことで、生徒同士の親近感が増す効果もあります。
教室内レクは準備もルールも簡単なので、短時間で気分転換をしたいときにも楽しめます。
体育館で盛り上がる!中学生の学年レク5選
屋内でありながら広い空間が使える体育館は、悪天候でも予定通りレクが楽しめて、クラスや学年全体の絆を強めるのに最適の場です。ただし、屋外と比べて使えるスペースが限られており、雨の日などは床も滑りやすくなるので、安全への配慮や実施人数を工夫して効果的に楽しみましょう。
空気読みゲーム
空気読みゲームは、参加者全員で輪になって行うレクリエーションです。開始の合図とともに1人ずつ、1から順に数字を言いながら立っていき、全員が立ち上がれば成功です。
いつ誰が立つかは自由ですが、タイミングがかぶったら最初からやり直しなので、参加者は同じ輪にいる人をよく観察して互いに息を合わせる必要があります。また少人数で行う場合は、全員が立ち上がり終わったら次は順に座っていくと、より大きな数にチャレンジできます。
学年レクとして行う場合は、制限時間内にどのグループが一番多くの数を数えられるかで競うと、盛り上がりそうです。仲間の動向を見極める必要があるゲームなので、結束力を高めるのに一役買ってくれるでしょう。
伝言ゲーム
伝言ゲームは、グループが1列に並び、順々に内緒話で後ろ(または隣)の人に内容を伝えていく定番ゲームです。
列の最初の人に伝言の内容を伝えるときは、口頭もしくはメモを使用します。その後、1人目は2人目に、2人目は次の人にと、ほかの人には聞こえない声のボリュームで列の最後まで伝えます。すべての人に伝言が伝わったら、最後尾の人は自分に届いた伝言の内容を発表します。最初の内容に一番近いチームが優勝です。
中学生の場合は、長文や早口言葉、現実にありえない設定の内容などにすると、正確に伝わらなかったり、笑いが起きたりして盛り上がるでしょう。先生の固有名詞など、伝わりやすい言葉をあえて混ぜ込んでもおもしろいかもしれません。
学年集会後の余った時間などでもすぐできて、場が盛り上がりやすいゲームです。
大縄跳び
複数人で一緒に縄を跳ぶ大縄跳びは、体を動かす定番レクリエーションとして人気があります。
跳んだ回数を競うため全員が息を合わせる必要があり、結束力や一体感が強まるきっかけになります。準備する用具は参加チーム分の大縄だけです。あとは、チームの中から縄を回す人を2人決めましょう。
大縄跳びを長く続けるには、以下のようなコツがあります。
・全員が高く飛びすぎない。
・2列で跳ぶときは、左右の人との間隔を広くしない。
・回数の掛け声で、全員が跳ぶリズムを合わせる。
運動能力だけではなくチームワークの良さも問われる大縄跳びは、全員で協力する楽しさを、体を使って実感できます。
陣取りゲーム
陣取りゲームは、敵陣にあるボールを蹴るか、指定の場所にたどり着けば勝利のチーム対抗戦です。走り回るゲームなので、体育館で行うのにもぴったりです。
基本的なルールは、以下の通りです。
・参加者と敷地を2つに分け、敵と味方で対決する。
・敵チームの陣地内で捕まった場合、捕虜として指定のゾーンで待機する。
・捕虜になっても、捕虜ではない味方がタッチしてくれれば再び参加できる。
実施には陣地の設定が必要ですが、体育館ならば床の線を使って陣地の設定に対応できるので、特別な準備は必要ありません。
敵陣の目標に到達したり相手の攻撃を阻止したりするには、作戦や協力が必要不可欠なので、自然と団結力が強まります。プレイしている生徒だけでなく、周りで応援する生徒たちの気持ちも大いに盛り上がるでしょう。
カバディ
カバディはインド発祥のスポーツで、鬼ごっこの要素を含むゲームです。参加者はドッジボール程度の広さのコートで2チームに分かれ、攻撃と守備を順に繰り返します。
攻撃する人は、相手の陣地に1人で入り「カバディ」と言い続けながら相手にタッチをして、得点を狙います。タッチできた人数が多いほど高得点なので、守備の人はタッチされないよう逃げましょう。
もし、攻撃している最中に「カバディ」の声が途切れてしまった場合は、守備チームに得点が入ります。攻撃が終わったら攻守交代です。
海外発のゲームでありながら簡単なルールで実施できるため、学年レクには最適です。
体育館でのレクリエーションは、簡単なものから大掛かりなものまで、多人数でもバリエーション豊かなゲームが楽しめます。
屋外で体を動かそう!中学生の学年レク5選
屋外でのレクリエーションは、思いきり身体を動かしながら仲間との絆を深める絶好の機会です。競争心をくすぐる遊びなら、クラスの一体感を高めることもできます。
腕立てじゃんけん
腕や肩、体幹を鍛えながら楽しめるレクが、腕立てじゃんけんです。使うのは身体だけなので、動きやすい格好をしていればすぐ始められます。
参加者は、2人向き合った状態で腕立ての姿勢になり、その状態をキープしつつ片手を上げてじゃんけんをします。もし腕立ての姿勢が厳しいようなら、膝をつくのはOKなど、生徒たちの体力や筋力に合わせたアレンジをしましょう。
勝利の条件や罰ゲームを決めてからプレイすると、じゃんけんへの真剣度が増すので、よりいっそう盛り上がって楽しめます。
ブラインドスクエア
ブラインドスクエアは、目隠しをした6〜10人のメンバーが大きな輪になっているロープを握り、制限時間内に正方形を作ります。このゲームでは、自分たちが作っている形が見えない分、お互いの声掛けによるコミュニケーションやチームワークが求められ、生徒同士が打ち解けあうのに役立ちます。
用意する道具は、10mくらいのロープと目隠しです。目隠しはハンカチやバンダナでも構いません。また、チャレンジする形は正方形だけでなく、三角形や多角形にするなど、さまざまなアレンジが可能です。
気をつけたいのは、ゲーム中に大きな移動はないですが、目隠しをすると他人との距離がわからないので、生徒たちが不安になりやすい点です。他のチームとぶつかったり転倒の危険がないよう、屋外でも十分なスペースを確保したり見守る人を決めると、存分に楽しめそうです。
ボール渡し競争
ボール渡し競争は、チームごとに縦1列に並び、頭上を通過させてボールを受け渡すゲームです。
列の最前の人は、スタートの合図とともに後ろへボールを送ります。最後尾の人は、回ってきたボールを持って列の一番前まで走り、今度は自分から再びボールを列の後ろへ送ります。これを繰り返し、列にいる全員が一巡したらゴールです。勝つためには、ボールを素早く渡すだけではなく、前後の人たちの身長差を考慮したり、メンバーの間隔を詰めて移動距離を減らしたりするなど、戦略を練る必要があります。
チーム全体の工夫と協力によって一体感が生まれ、盛り上がるゲームです。
リングビースピード競争
リングビースピード競争は、リングビーの受け渡しを行いながらゴールを目指します。リングビーは弾力のある素材でできたドーナツ状のフライングディスクで、身体に当たっても衝撃を吸収してくれます。少人数でも大人数でも安全に楽しめるゲームです。
競争では、スタートからゴールまでの手渡し方法に「頭上から」「股下から」「とにかく早く」などのルールを設けると、バリエーション豊かに楽しめます。
チーム対抗戦にすると、圧倒的なスピード感で盛り上がること間違いなしです。
キックベース
キックベースは、投手が転がしたボールを打者が脚で蹴り飛ばして、得点を競うゲームです。野球のルールを脚とサッカーボールで行うゲームと考えると、わかりやすいかもしれません。
野球と異なる点を簡単に説明します。
・1チームにつき5人以上であればプレイ可能。
・グラウンドのサイズは自由。
・投手は、ボールがバウンドしないように、下投げでボールを転がす。
・使用するボールは、サッカーボールやドッジボールくらいの大きさがおすすめ。
・柔らかいボールを使えば、より安全。
屋外の広い場所で行うと、よりダイナミックに楽しめます。3チーム以上あるなら、総当たり戦やトーナメントを行うと試合も白熱するでしょう。
屋外でのレクリエーションは、体力だけでなく戦略や思考もフル稼働!それぞれの得意分野を活かしながら楽しめそうです。
【番外編その1】小学生におすすめの学年レク
小学生におすすめの学年レクは、軽くて強い力を使わず楽しめる「風船ラリー」です。軽くて扱いやすい風船は当たっても痛くないので、ボールが苦手な子でも楽しめます。
このゲームは、風船を床に落とさないようにラリーを続けながらゴールを目指します。1チームは何人でも良いのですが、4〜6人程度に分けると進行がスムーズです。ラリーだけでも十分楽しめますが、たとえば下記のようなアレンジを加えても、より一層盛り上がります。
・チーム全員が手を繋いだままラリーを続けてゴールを目指す。
・手を使わず、うちわの風で風船を飛ばしてラリーする。
・1チームで使う風船を2つに増やす。
時間や回数で勝敗を決めても、おもしろいかもしれません。
ただし、風船を使うと視線が上にいきがちなので、ほかの子とぶつからないよう広い場所で行うようにしましょう。
風船は風向きに影響されやすいので、屋内での実施がおすすめです。体育館であれば、のびのび楽しめるでしょう。
【番外編その2】高校生におすすめの学年レク
高校生には「Just One(ジャストワン)」という、言葉を当てる連想ゲームがオススメです。3人から8人程度で遊べますが、特に8人くらいでプレイするのが最も面白いでしょう。
まず、プレイヤーの中から1人を回答者として選びます。選ばれた回答者以外のプレイヤーは、お題となる単語を確認します。このとき、回答者にお題が見えないように注意してください。
次に、回答者以外の全員が、そのお題に関連するヒントを1つずつ考えて紙に書きます。プレイヤー同士で同じヒントを書いてしまうと、そのヒントは使えなくなるので注意です。たとえばお題が「りんご」だった場合に、複数の人が「赤い」というヒントを書いてしまうと「赤い」というヒントは回答者に見せることができません。
ヒントを書き終わったら、回答者以外のプレイヤーでヒントを見せ合います。同じヒントを書いていた場合は、そのヒントを除外します。残ったヒントだけを回答者に見せて、回答者は1回だけ答えを言うことができます。
▼勝利条件
・チーム戦の場合:制限時間内に、より多くの正解を出したチームの勝利。
・協力プレイの場合:できるだけ多くの問題を正解することを目指す。
▼ポイント&コツ
・ヒントは具体的すぎず、抽象的すぎない言葉を選ぶ。
・他のプレイヤーと同じヒントを書かないよう、独創的な視点を心がける。
・チーム内で相談せずに、各自でヒントを考えることが重要。
▼注意点
・ヒントを出すときは、お題に関する相談や話し合いは禁止。
・ジェスチャーや、その他の手がかりを出すことも禁止。
・回答は1回のみ。複数回の回答はできない。
最初は簡単そうに思えるかもしれませんが、実際にプレイしてみると意外と難しく、そして非常に盛り上がるゲームです。みんなで知恵を出し合いながら、協力して正解を目指してみましょう。
問題を解決するために、いろいろな角度から考える必要があるので、高校生の探究心を刺激すること間違いなしです。
学年レクで生徒同士の絆を深めよう
この記事では、場所ごとに盛り上がる学年レクの内容や、必要な道具、注意事項を紹介しました。
学年レクは、アイスブレイクとして役立つだけではなく、クラスメイトや学年全体の一体感や結束を強める効果が期待できます。ご紹介した内容を参考に、レクリエーションの企画や運営をしてみてください。
また、修学旅行や校外学習に向かうバスの中でできるレクリエーションについて知りたい方は「学年別おすすめバスレクまとめ」の記事が参考になります。
【関連記事】「学校行事をより楽しく実りあるものにしたい」と感じている先生には、以下の記事もおすすめです。
・修学旅行スローガン例50選|決め方・言葉の工夫・生徒と作るコツも紹介
・小学校・中学校の運動会「あるある」11選!今と昔の違いはどこ?
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。