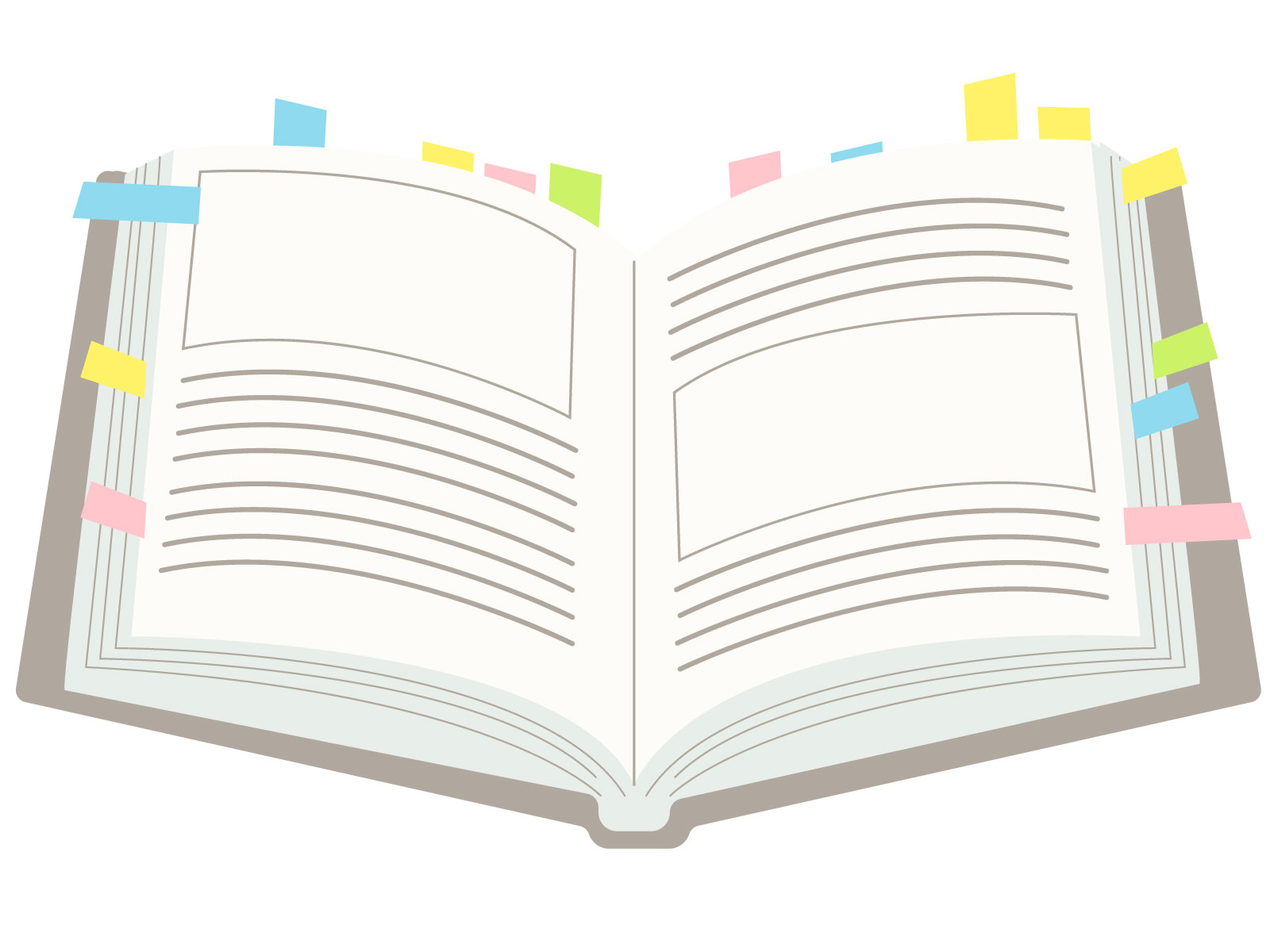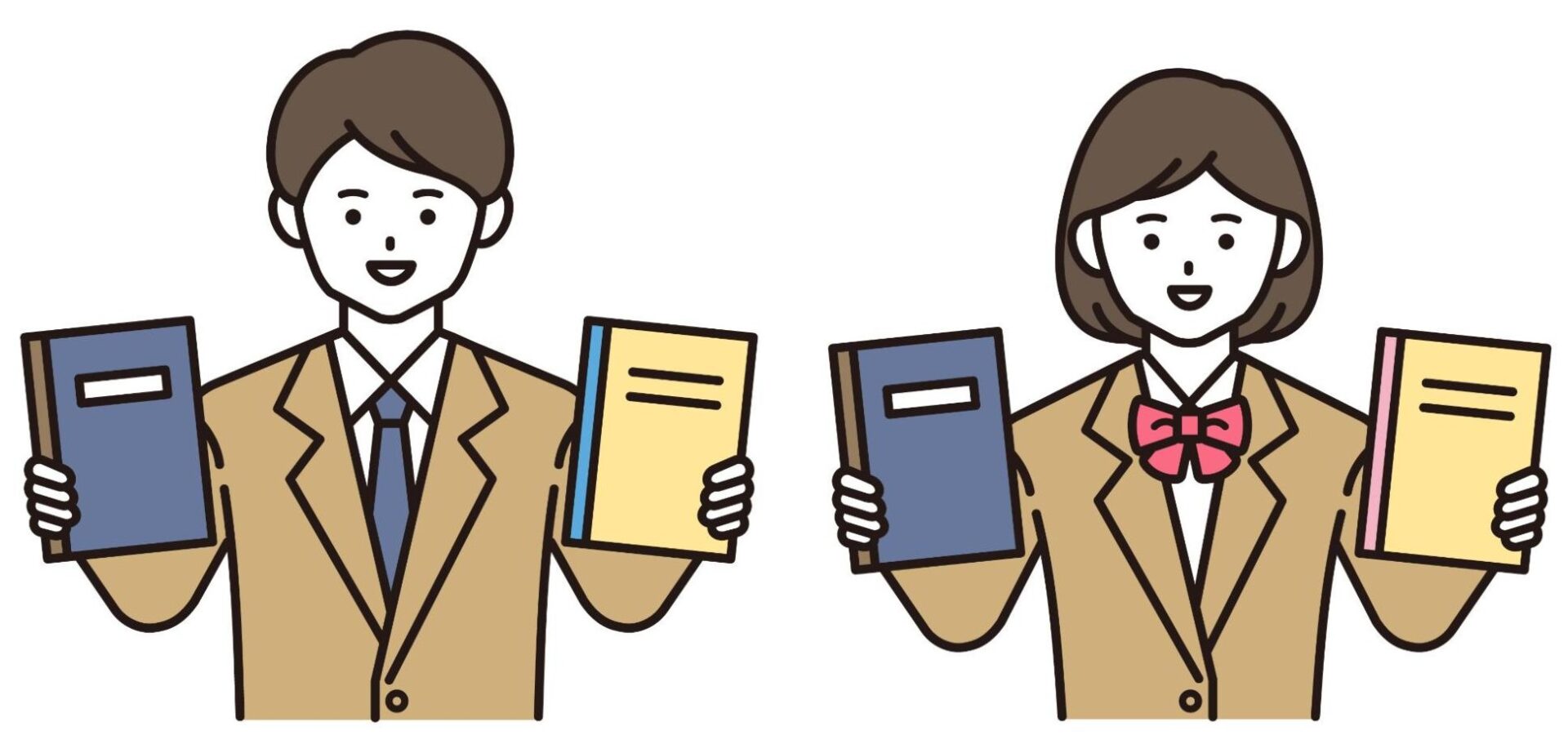
目次
「授業の内容や進度に合わせて効果的に教材を使いたい」
そんな思いを持つ先生におすすめなのが、『教科書準拠教材』です。
教科書準拠教材は、学校の授業で使う教科書に沿った内容で問題が構成されているため、生徒は授業で学んだ内容をすぐに復習でき、定期テスト対策にも活かしやすい教材です。先生にとっても、学校の授業と家庭学習をスムーズにつなげやすいのが特長です。
この記事では、教科書準拠教材の基本的な考え方から、メリット・注意点・選び方、そして実際の活用例までをわかりやすく解説します。ぜひ、塾での教材を選ぶ際の参考にしてください。
教科書準拠教材とは?
「教科書準拠教材」とは、学校で使っている教科書の内容や単元構成に対応して作られた教材を指します。たとえば「数学〇ページの二次方程式」「英語△ページのbe動詞」というように、教科書で扱う内容が、そのままの学習順で扱われているのが特長です。
一方で、一般的な教材は、教科書の進度に逐一対応しているわけではなく、各単元の内容を体系的に学べる構成になっているものが多いです。基礎から発展まで幅広く対応できるので、生徒の学力に合わせた学習に向いています。
教科書の内容に沿った教科書準拠教材は、生徒が授業の延長的にスムーズに取り組めるのが大きなメリットです。授業内容の理解度を確認する補助教材としても、定期テスト対策としても、安心して活用できます。
教科書で学ぶ内容の理解度を深めるためには、教科書準拠教材は最も適した教材と言えるでしょう。参考書を何冊も揃えるより、まずは教科書準拠教材にしっかり取り組むことをお勧めします。
教科書準拠教材を使うメリット
教科書準拠教材を塾で活用することの主なメリットを、4つに整理して紹介していきます。
学校の授業内容の理解度をより高めることができる
教科書準拠教材を使えば、塾でも「今、学校で習っている内容」にぴったり対応できます。学校の授業とのズレがないため、生徒の理解もスムーズで、学習内容を確実に補強しやすくなります。
たとえば、数学の「連立方程式」を学校で習ったあとに、対応するページの問題を塾で解けば、授業で理解が不十分だった箇所をその場で確認できます。学校の授業の先取り学習として使う場合も、後で同じ内容を授業で習うことで復習効果が得られます。
このように、基礎の理解をしっかり支える教材として安心して活用できるのが、大きな特長です。
生徒に成功体験を積ませ、自信を持たせることができる
教科書準拠教材は、塾で学校での学習内容を補う場合も、先取りする場合も、生徒が「できた!」という達成感や自信を得やすい教材です。
たとえば、学校の英語の授業で教科書の本文を習ったあとに、塾で練習問題に取り組むと、「授業で出てきた表現を自分で使えた」という達成感につながります。逆に、塾で先に学習していた場合は、学校の授業中に「この内容は、もう知っている」「この問題なら解ける」と感じられ、前向きな気持ちで学習に取り組めます。
こうした成功体験の積み重ねは、自信を育てるだけでなく、家庭学習への意欲を高めるきっかけにもなります。
塾で先取り学習を取り入れるメリットや効果について、こちらの記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。
▶️中学生の先取り学習は効果ある?塾で導入するメリット・ステップを解説
定期テスト対策を効率的に進めることができる
定期テストの出題範囲は、基本的に学校の教科書や授業内容が中心です。教科書準拠教材は教科書の内容に沿って構成されているため、テスト範囲の対象がわかりやすく、指導に利用しやすいのも強みと言えます。
「テストまでに、この単元をもう一度、一問ずつ解き直そう」「このページを重点的に確認しよう」など、教材を使って具体的にテスト対策の指示をしやすいため、先生にとっても効率的な指導ができます。生徒も迷わずテスト勉強を進められるでしょう。
学校・塾・家庭の学習をスムーズにリンクさせることができる
教科書準拠教材は、学校の学習内容を補強するための塾の授業や宿題に、そのまま活用できます。
- 学校で習った単元を塾で復習する
- 塾で先取りした内容を学校の授業で再確認する
- 家庭で繰り返し練習問題を解き、定着させる
このように、教材を活用することで「学校・塾・家庭」間での学習サイクルを作れるのが特長です。学校・塾・家庭の学習がスムーズにつながることで、生徒も安心して効果的な学習を積み重ねていけるでしょう。
学校・塾・家庭での学習で共有できる教科書準拠教材は、生徒にとって弱点克服に効果的です。保護者にとっても学習の流れが分かりやすくなり、塾と一緒に学習サポートを進めやすくなります。
教科書準拠教材の注意点
教科書準拠教材はメリットが多くありますが、実際の授業や生徒の学習状況に合わせて使い方を工夫しないと、十分に力を発揮できない場面もあります。ここでは、塾の先生が知っておきたい注意点を整理します。
発展的な学習には物足りないことがある
教科書準拠教材は、あくまで「学校の授業内容を確実に理解させる」ことを目的に作られているのが基本です。そのため、難関校受験や模試対策として高得点を取るための学習で使うには、発展的な問題が不足するケースもあります。
発展的な力をつけるためには、応用問題を扱うための教材を別に用意し、併用するとよいでしょう。
学校の進度や改訂に合わせて調整が必要
学校により学習の進度は異なります。たとえば、教科書の章立て通りの順番ではなく、授業では単元の順番を入れ替えて学習するケースも見られます。そのため、塾で予習や復習に教科書準拠教材を扱う場合は、生徒が通う学校の進度を把握しておくことが大切です。
また、教科書は数年ごとに改訂されます。改訂があった年には、準拠教材も最新の内容に対応しているか、必ず確認しましょう。
教材選びは生徒の学習効果を高めるうえで、とても重要なポイントです。教科書準拠教材を選ぶ目的をはっきりさせて、生徒の学習状況に最適なものを選定しましょう。
教科書準拠教材を選ぶときのポイント
教科書準拠教材と一口に言っても、出版社によって難易度や解説の仕方などに違いがあります。ここでは、自分の塾で教材を選ぶ際に意識しておきたいポイントを整理します。
① 学校で生徒が使用している教科書に対応しているか
教科書の出版社ごとに、単元の掲載順や例題の扱いは異なります。そのため、学校の授業内容に合わせてカリキュラムを組むのであれば、生徒が使っている教科書と一致する教材を選ぶことは、必須事項と言えます。
たとえば、学校で東京書籍の教科書を使っているのに、啓林館の教科書に準拠した教材を選んでしまうと、授業との進度がずれて生徒の混乱を招きやすくなってしまいます。
② 生徒の学力に合った難易度か
同じ教科書に準拠した教材でも、基礎を中心にしたタイプから応用問題を含むタイプまで、内容はさまざまです。そのため、生徒の学力に合った難易度の教材の選定は、とても重要です。
たとえば、塾内で平均点前後の生徒には標準的な教材を、上位の生徒には応用問題も扱える教材を選ぶ、といった工夫が考えられます。少人数授業や個別授業を行っている塾であれば、一律に同じ教材を配るのではなく、クラスや生徒のレベルに応じた使い分けが効果的でしょう。
③ 解説は分かりやすいか
教科書準拠教材は、授業の解説や、予習・復習、宿題など、活用する場面が幅広くあります。そのため、解説の分かりやすさは、生徒にとっても先生にとっても大切なポイントです。
たとえば、例題に解き方の手順や要点が明確に示されていれば、そのまま板書や口頭説明に活かすことができます。また、図や表を使った解説が充実していれば、生徒に視覚的に伝わりやすく、理解を深めるのに役立ちます。
④ 学習を続けやすい仕組みがあるか
学習を習慣化できるかどうかも、教材を選ぶ際に大切にすべき視点です。到達度の視覚化など、生徒が達成感を実感できる仕組み・工夫がある教材は、学習の継続につながります。
たとえば、各単元の最後に「確認テスト」や「まとめ問題」がついていると、生徒自身が到達度を測れる区切りになります。また、チェック欄や進度記録のためのページがある教材なら、「ここまで終わった」という達成感や学習の振り返りにつながりやすいでしょう。
近年では教科書準拠教材のデジタル版も充実しており、「解説動画」「追加問題」「自動採点機能」などを備えた教材も登場しています。こうした機能は、家庭学習のサポートにも役立ちます。
教科書準拠教材の効果的な取り入れ方
教科書準拠教材は、ただ生徒に「やらせる」だけでは十分に力を発揮できません。ここでは、塾の授業や宿題への効果的な取り入れ方を、具体的に紹介します。
授業の導入で活用する
塾の授業の始めに教科書準拠教材を活用すると、生徒が授業の内容を理解しやすくなります。たとえば、以下のように活用できます。
【学校の授業の復習として扱う場合】
学校で習った単元の問題を、授業冒頭で「確認」として解かせる。
⇒ 理解が不十分な箇所をその場で把握でき、授業で理解すべきところが明確になる。
【学校の授業の先取りとして扱う場合】
新しい単元に入る前に、教材の例題を取り上げる。
⇒「これから、こういう内容を学ぶんだ」という見通しをもって授業に臨める。
このように授業の冒頭で教科書準拠教材を使うことで、復習では理解の確認、先取り学習では学習内容の意識づけができます。どちらの場面でも、スムーズに学習をスタートできるでしょう。
授業中の説明・演習で使う
教科書準拠教材は、例題と解説がセットになっている構成が多いため、授業中の説明にそのまま活用することもできます。
たとえば数学であれば、例題を見ながら「解き方の手順」を確認し、必要に応じて板書やホワイトボードで補足解説する、といった方法です。英語であれば、本文で扱われている「文法のまとめ」等を示しながら授業を進めると、ポイントを整理しやすくなります。
そのうえで、すぐあとにある練習問題を解かせれば、「解説→演習」の流れを1冊で完結させることができます。教材を「先生による解説の補助的資料」としても「生徒の確認演習」としても使えるため、先生は自分自身の授業準備の負担を減らしながら、生徒の理解度を把握できるでしょう。
宿題で活用する
授業では例題や基本問題を扱い、残った「練習問題」や「単元のまとめ」「チャレンジ問題」などを宿題に設定することで、家庭でもスムーズに復習に取り組めます。
同じ問題を繰り返し解くことでしっかり定着させたいときには、授業中はノートに書いて解かせ、宿題では教材に書き込ませる方法も効果的です。授業と宿題をうまくつないだ活用で、学習内容の定着が確実になるでしょう。
テスト前の総復習に活かす
教科書準拠教材には「定期テスト対策問題」や「確認テスト」が用意されているものもあり、テスト前の復習にそのまま使えます。
たとえば、テスト前の授業では次のような流れが考えられます。
- 対策問題を解かせて、生徒一人ひとりのつまずきを把握する。
- 授業で、誤答の多かった問題や理解が不十分な単元を解説する。
・集団指導の場合は、多くの生徒がつまずいた問題や単元を取り上げる。
・個別指導の場合は、その生徒が間違えた問題や苦手な単元を重点的に扱う。 - 生徒に、自分の間違えた問題を解き直させたり、確認テストを解かせたりして、理解の定着を図る。
このように苦手克服にポイントを置いた活用の仕方で、「やりっぱなし」にならず、得点力アップにつながるテスト勉強になるでしょう。
間違えた問題には赤で印をつけ、解き直して正解したら青で丸をつけるといった色分けで、生徒自身に理解度をチェックさせるのも効果的です。どこでつまずき、どこを克服できたかが一目で分かるため、あとで復習するときに、どの問題を再確認すべきかが明確になります。
おすすめの中学教科書準拠教材「Keyワーク」
中学校の教科書準拠教材としておすすめなのが「Keyワーク」です。「Keyワーク」は、教科書の内容を、生徒が確実に理解できるようになることを最優先に考えて作られた教材です。塾や学校で指導することを前提に作られた、一般書店には並んでいない、塾・学校専用教材となっています。
授業で扱いやすい構成
「Keyワーク」は、ひとつの単元の中に「ポイント」「例題」「確認問題」「練習問題」「応用問題」といった項目が、段階的に配置されています。
授業中は例題や確認問題を扱い、宿題には練習問題を設定するなど、場面ごとに使いやすい構成になっています。「Keyワーク」1冊で、授業と家庭学習の両方に対応でき、毎日の学習サイクルをしっかり作ることができます。
重要指導ポイントを明確に提示しているため、各単元でどこがポイントなのか、どう教えたらよいか、迷うこともありません。また、思考力・判断力を養うことができる問題や難易度の高い問題も扱っているため、幅広い層への指導が可能です。
定期テスト対策に、そのまま活用可能
「Keyワーク」は、単元ごとに「定期テスト対策問題」が用意されているため、テスト前の総復習にそのまま活用できます。指示の出しやすさに加え、厳選された問題による演習で、得点力を養成できます。
さらに、対策問題は「標準」「応用」と難易度別に取り組めるようになっており、生徒の学力に合わせて無理なくテスト対策を進められるのも、先生・生徒の双方にとって安心できるポイントです。
デジタル機能で学習を強力サポート
「Keyワーク」には電子書籍版もあり、映像解説や追加問題、学習記録などの機能が備わっています。充実したデジタル機能で、理解度の向上、学習意欲の向上に利用することが可能です。
教室内での指導だけでなく、家庭学習のサポートにも活用できるため、生徒が学習を継続しやすい環境づくりにつながります。
多様化する個々の生徒の学びに対応した指導が可能で、効果的に生徒・先生をサポートする「アナログ(紙の問題集)とデジタルによるハイブリッド型教材」となっています。
「Keyワーク」は、塾の授業、宿題、家庭、生徒の学習をフルサポートできる、デジタル時代に対応した教科書準拠教材です。
🔽 詳細は、こちらでご確認ください。
教科書内容をマスターできる準拠教材

教科書準拠教材で、授業をもっと分かりやすく、もっと効果的に
教科書準拠教材は、学校の授業と同じ流れで生徒が学習を進められる、安心感がある教材です。授業中の解説や演習、家庭での復習、そしてテスト前の総仕上げまで、場面に合わせて取り入れることで、生徒の理解度・定着度アップに確実な効果が期待できます。
もちろん塾で取り入れる場合、各生徒の学校ごとの進度に応じた調整・工夫は必要ですが、それ以上に、「学校と塾、家庭での学習を効果的にリンクできる」という強みは大きな魅力です。
教科書準拠教材を活用することで、生徒は「しっかり覚えた!」「できた!」という小さな成功体験を積み重ねやすくなり、自信を持って授業やテストに臨めるようになります。
この記事を参考に、ご自身の塾に適した教科書準拠教材の活用を、ぜひ検討してみてください。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。