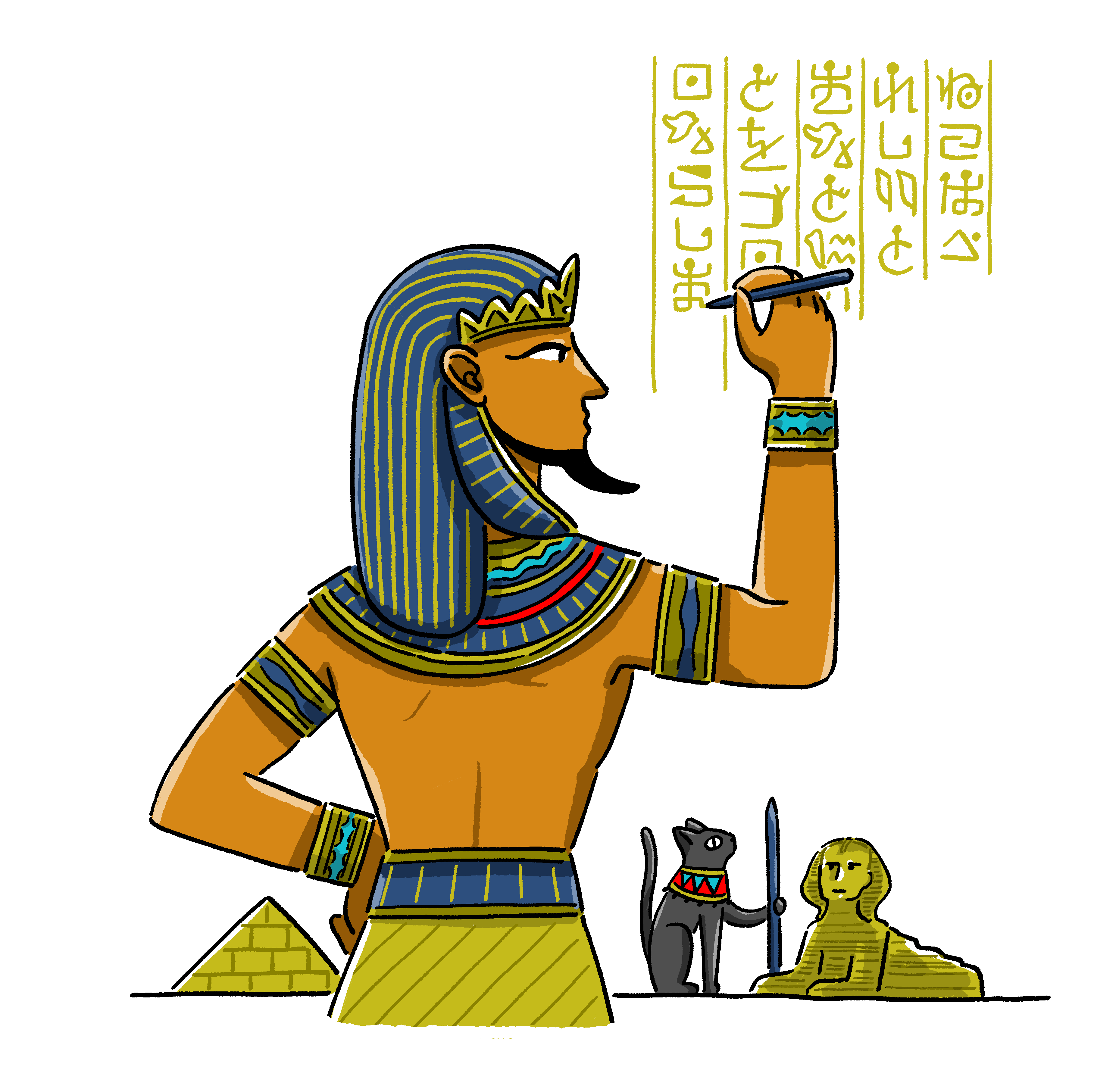目次
「受験勉強、思うように集中できなくて心配だなぁ」
「テスト前には、どんな食事を摂ったら万全のコンディションで臨めるのかな?」
「記憶力を高める良い方法があったら知りたい!」
受験生のこんな悩みに、どうアドバイスすればいいのか悩んでいる方へ。実は、毎日の食事が日々の学習効率にも大きく影響します。
本記事では、脳機能を最大限に引き出し、集中力や記憶力を向上させる食べ物を10品目ご紹介します。ここで紹介する食品を日々の食事に取り入れることで、学習の効率アップだけでなく、試験本番での実力発揮にも効果が期待できるでしょう。生徒たちが受験期を乗り切るための「食事戦略」として、ぜひ参考にしてください。
脳の仕組みと集中力の関係は?
脳の働きと集中力には密接な関係がありますが、とくに重要なのが血糖値のコントロールです。適切な血糖値を保つことで、脳は効率よくエネルギーを得て、高い集中力を発揮できます。
また、人間の身体には、タンパク質、脂質、糖質という三大栄養素が必要ですが、脳のエネルギー源として直接利用できるのは糖質のみです。そのため、適切に糖質を摂取することが、脳を最大限に活用することにつながると言えます。
脳や身体の仕組みを知っておくことで、勉強も効率よく進められますよ。
集中力・記憶力を高める!6つの重要栄養素
「集中力が続かない」「覚えたはずなのに忘れてしまう」といった悩みは、栄養素の摂り方で改善できる可能性があります。脳が最高のパフォーマンスを発揮するためには、特定の栄養素が必要不可欠です。
ここからは、集中力と記憶力を高めるために重要な、6つの栄養素をご紹介します。栄養素の働きを知り、日々の食事に取り入れることで、より効率的な学習ができるようになるでしょう。
ブドウ糖
ブドウ糖は、人間の身体の働きに必須の重要な栄養素で、脳の主要なエネルギー源です。穀類やいも類、果物などに多く含まれます。脳は常にエネルギーを必要としているため、1日を通してなるべく血糖値を安定させましょう。
食事の後、急激に血糖値が上昇すると、眠気やダルさを引き起こすのとともに、心筋梗塞や脳梗塞などの発症につながる恐れもあります。玄米やオートミールなどのゆっくりと消化される食品を選び、朝食を抜いたり早食いをしたりするのは避けましょう。
長時間にわたって安定したエネルギー供給が行われることで、集中力を保つことが可能です。
ビタミンB1
ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変換する過程(代謝)で使われる栄養素です。積極的に摂取することで、脳にも十分なエネルギーが行きわたり、脳機能の活性化や疲労回復に役立ちます。豚肉、玄米、豆類、ナッツ類などに多く含まれ、野菜ではブロッコリーや芽キャベツ、ニンニク、アスパラガスなどの含有量が多めです。
ビタミンB1が不足すると、疲れやすくなり、集中力や記憶力の低下、さらにはやる気や食欲の減退にもつながるため、注意が必要です。また、熱に弱く水に溶けやすい水溶性ビタミンの一種ですので、短時間での加熱調理や、スープや煮汁に溶け出た栄養素を出汁ごといただくなど、調理法にも工夫が必要です。
オメガ3脂肪酸(DHA・EPA)
DHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサペンタエン酸)は、いずれも人の体内では作られない必須脂肪酸の一種で、血液をサラサラにする成分として有名です。身体によい脂質で健康維持に欠かせないので、食事で積極的に摂取する必要があります。魚、とくに青魚(サンマ、サバ、イワシなど)に多く含まれ、マグロの脂身も含有量が豊富です。動脈硬化や心筋梗塞、成人病の予防に役立つだけでなく、脳や網膜など神経系の保護・機能維持にも作用し、脳内の情報伝達や認知機能に重要な役割を果たします。
記憶力や判断力など、学習に必要な能力向上に効果があるので、効率よく摂取できるメニューを工夫しましょう。旬の魚を刺身で食べるのが一番ですが、魚から出た脂分を無駄にしないホイル焼きやつみれ汁など、豊富な栄養素をそのまま摂取できる調理法がおすすめです。なお、オメガ3脂肪酸は、植物油ではとくにアマニ油、エゴマ油に豊富に含まれています。
レシチン
レシチン(フォスファチジルコリン)は細胞膜の主成分であるリン脂質の一種で、特に脳神経や神経組織に多く含まれています。記憶力向上に効果があるとされ、活発な脳の働きを助けてくれる栄養素です。脳内神経伝達物質であるアセチルコリンの材料で、レシチンの不足は、記憶力や学習機能の低下につながってしまいます。
卵黄や大豆に含まれるので、卵料理、豆腐、味噌、納豆などの大豆製品や、マヨネーズを使った料理で積極的に摂取しましょう。ただ、レシチンには酸化しやすい性質があるので、酸化を防ぐ効果のあるビタミンEと一緒に摂ることをおすすめします。ビタミンEが豊富な食品には、植物油(ヒマワリ油、サフラワー油、オリーブオイルほか)、カボチャ、アボガド、ナッツ類(とくにアーモンド)、ピーナッツ、大豆、卵、一部の魚介類(ウナギ、ブリ、タラ、魚卵ほか)などがあります。
フラバノール
フラバノールは抗酸化作用のあるポリフェノールの一群で、緑茶やカカオ豆(ココア)に多く含まれます。血管機能を改善する働きがあり、脳への酸素供給を促進するので、これにより脳の機能が活性化され、集中力や記憶力の向上につながります。また、抗酸化作用により脳の老化防止にも役立ちます。
ココアと緑茶以外では、ブドウ、リンゴ、ベリー類といった果物に多く含まれています。
チロシン
チロシンは、たんぱく質に広く含まれるアミノ酸の一つで、脳内の神経伝達物質であるドーパミンなどが体内で合成される前段階の物質です。ドーパミンは、やる気アップや集中力の向上・維持に重要な役割を果たすので、チロシンのこまめな摂取が受験生には必要不可欠です。
幅広い食品・食材に含まれる栄養素ですが、摂取しやすい例として、チーズなどの乳製品、豆腐や納豆、ナッツ類、バナナなどが挙げられます。なお、脳内でのドーパミン産出にはチロシンと併せてビタミンB6も必要なので、不足に注意してください。ビタミンB6は、赤身の魚や脂が少ない肉類(ささみ、ひれ肉など)、サツマイモや玄米などに多く含まれます。
栄養素の効用について知っておけば、食事のメニューを選ぶときの参考になりますね。
受験生が避けるべき食べ物と飲み物
受験生が意識して摂りたい食品だけでなく、避けるべき食品や飲み物もあります。まずは、受験生がとくに注意すべき3種類の食品・飲み物について解説していきます。ご紹介するなかには、一時的に気分をよくしたり、やる気が出たりする食品もあるかもしれません。しかし、長期的には集中力や記憶力の低下、体調不良につながる可能性もあるので、十分に注意しましょう。
とはいえ、受験勉強に打ち込んでいる時期には、日々の気分転換も必要でしょう。完全に制限するのではなく、食べ過ぎないよう適度な量を保ちつつ、ストレスにならないような食生活を心がけてみてください。
糖分の多い食品
糖分の多い食品は、なるべく避けましょう。急激な血糖値の上昇と下降が繰り返されると、強い眠気や疲労感に襲われる可能性があるためです。とくに摂取に注意が必要な食品としては、たとえば以下のようなものがあります。
- 清涼飲料水
- スナック菓子
- ケーキやクッキーなどの甘い菓子
- 市販の菓子パン
これらはおいしいので、つい手が伸びてしまいがちですが、学習に集中したい時期にはあまりおすすめできません。お腹が空いたときには、糖分が少なくて栄養価の高い食品を選びましょう。たとえば、以下のような食品を意識して取り入れてみてください。
- フルーツ(バナナ、りんごなど)
- 干し芋
- 小魚チップス
- ナッツ類
- 玄米おにぎり
- 全粒粉のパン
カフェイン含有量の多い飲み物の摂取に注意
カフェインを多く含む飲料、とくにエナジードリンクの多飲 多用は避けましょう。適度なカフェインの摂取なら集中力を高められますが、飲みすぎは逆効果です。カフェインを摂り過ぎると不安感や焦燥感を引き起こし、かえって集中力を低下させてしまいます。また、睡眠の質を悪化させ、寝つきが悪くなり翌日のパフォーマンスにも悪影響が出る可能性があります。
緑茶(煎茶)やほうじ茶、玄米茶などに含まれている程度のカフェインならば問題ないのですが、1日200~300mg程度(コーヒー2~3杯分、エナジードリンク355mlなら1缶)を目安に、午後3時以降は控えめにしてください。
とくに注意が必要な飲み物には、具体的には以下のようなものがあります。カフェインを含む温かいコーヒーは、適量であれば眠気覚ましに効果的です。
- エナジードリンク
- 多量のコーヒー
- カフェイン含有量の高い清涼飲料水
受験生向けの飲み物としては、たとえば以下のようなものがオススメです。
- 温かい緑茶や紅茶(適量)
- ホットココア(適量)
- 麦茶、ルイボスティー
- 水ミネラルウォーター
- ハーブティー
- フルーツジュース
ココアにはポリフェノールをはじめ、さまざまな身体にいい栄養素が多く含まれており、脳の活性化や疲労回復にいい飲み物です。また、麦茶やルイボスティーはノンカフェイン、ノンカロリーで身体に優しい飲料と言えます。ハーブティーは、眠気覚ましになるミントティーや、リラックス効果のあるカモミールティーなどが、とくにおススメです。
なお、適量とした飲み物にはカフェインが含まれているので利尿作用があります。トイレが近くならないよう、テスト当日の摂取量には注意してください。
脂肪分の多い食品
脂肪の多い食品は、消化に時間がかかり、眠気を引き起こす可能性があります。また、血液が消化に集中することで脳への血流が減少し、集中力が低下することもあります。集中力の妨げになる可能性の高い食品は、以下の通りです。
- 揚げ物全般
- 脂身の多い肉
- クリーム系のデザート
- インスタントラーメン
代わりに、脂肪分の少ない肉や魚、オリーブオイルなどの健康的な油を適度に使用した料理を選びましょう。日々の食事には、以下のようなメニューを多く取り入れてみてください。
- 蒸し物や煮物
- 脂肪の少ない肉や魚
- あっさりした和食
- サラダ
試験当日に実力を発揮できるよう、コンディションに悪影響のある食べ物・飲み物はなるべく避けましょう!
受験生にオススメ!学習機能を助けてくれる「脳にいい食べ物」10選
受験勉強の効率を上げるには、適切な栄養摂取が欠かせません。とくに脳の働きを高める食品を意識して摂ると、集中力や記憶力を高められるでしょう。ここからは、受験生にオススメの「脳にいい食べ物」10選をご紹介します。毎日の学習にコンディションの波は付きものですが、これらを日々の食事に取り入れて、最高のコンディション維持を目指しましょう。
玄米
玄米は、白米と比較すると、より豊富な食物繊維とビタミンB群、ミネラルといった栄養素を含みます。血糖値の上昇がゆるやかな低GI食品で、ゆっくりと消化・吸収されるため、脳にエネルギーを安定して供給し、長時間の集中力維持に効果的です。リラックス効果があり脳の興奮を鎮めてくれるGABA(ギャバ)も含まれており、ストレスや緊張、疲労感の軽減に役立つでしょう。
鮭(サーモン)
和食の定番と言える鮭は、体内で合成できない必須アミノ酸をバランスよく含み、消化吸収率の高い良質なタンパク質を摂るのに適した食材です。脂身には上述のDHAとEPAも多く含まれており、脳機能の活性化、学習能力の向上に効果があります。また、育ち盛りの学生に必要なカルシウムの吸収を助けるビタミンDほか、健康維持に必要なビタミン類など、いろいろな栄養素が含まれていますので、受験生にうってつけの食材と言えます。
卵
卵は「完全栄養食品」とも呼ばれ、食物繊維とビタミンCを除く、実に多くの栄養成分が含まれています。エネルギー源となる良質なタンパク質や脂質が主成分で、豊富なビタミン、ミネラルを含む栄養価の高い食品ですから、受験生の体力づくりの強い味方と言えるでしょう。そして、脳内での情報伝達や記憶の維持に関与する卵黄コリンのはたらきもあり、脳の活性化に効果がある食品としても注目されています。
ブルーベリー
ブルーベリーに多く含まれるアントシアニン(ポリフェノールの一種)には強力な抗酸化作用があり、疲労原因である活性酸素など有害な物質を無害に変え、免疫力を高める効果があります。眼精疲労の予防や、ブルーライトをはじめとする光刺激からの保護効果、視覚機能の改善など、目に良い食品として有名ですが、脳の疲労感を軽減する効果もあり、脳機能の向上が期待できます。
バナナ
バナナは季節を問わず入手しやすく、身体に必要な栄養素をバランスよく手軽に摂れる食品です。脳のエネルギー源として大切なブドウ糖をはじめとするさまざまな糖類(炭水化物)が持続的に消化吸収され、食物繊維が急激な血糖値の上昇を抑えてくれるので、受験生のエネルギー補給に適しています。朝食はもちろん、集中力アップや疲労回復のため、昼食や午後のおやつに摂るとよいでしょう。
また、ビタミンB群やマグネシウム、カリウムなどの栄養素も含まれますが、特筆すべきは、脳内の神経伝達物質のもととなり精神の安定に効果のあるトリプトファンという必須アミノ酸を多く含んでいること。これがビタミンB6と結びつくことでリラックス効果や安眠効果が高まるので、不安や緊張に悩む生徒にもおすすめです。
ナッツ類
代表的な脳にいい食べ物の一つが、ナッツ類です。脳の働きを活性化させる不飽和脂肪酸、脳の健康を守り自律神経を整えてくれるビタミンE、神経伝達に関わり脳機能をサポートしてくれるミネラルなどを含み、脳機能の向上・活性化に効果のあるおすすめの食品です。記憶力アップや、集中力の向上・持続に役立ちます。
とくに昔から日本人に親しまれてきたクルミは、ナッツ類の中でもオメガ3脂肪酸を多く含み、脳機能の維持・活性化に効果があります。また、うつ症状の軽減効果があることから、受験ストレスの軽減やリラックス効果も期待できます。
ひとつ注意点としては、近年、ナッツアレルギーへの留意が必要とされており、とくにクルミとカシューナッツはアレルギー表示の推奨品目に入っています。過剰摂取にならないように注意してください。
ほうれん草
ほうれん草は、赤血球中の主成分で全身に酸素を運ぶヘモグロビンの生成に必要な鉄分と、造血作用があり、正常な代謝に必要なビタミンである葉酸を多く含む緑黄色野菜です。貧血予防や体の発育・健康維持の筆頭に挙げられる野菜ですから、健康管理が肝心な受験生は積極的に摂取しましょう。ただ、葉酸は水に溶け出やすく熱にも弱いので、短時間でサッと茹でたり炒めたりするのが、豊富な栄養素を失わない調理のポイントです。
ほかにも免疫力アップに効果のあるβ-カロテンや、多くのビタミンやミネラル、食物繊維などを含みますが、とくにマグネシウムによる気分の安定(ストレスによるイライラの軽減)、睡眠の質の向上などの効果が、受験勉強で疲れた脳に良いと言えます。なお、冬が旬の野菜なので、冬に採れるほうれん草は夏に比べて3倍のビタミンCを含みます。
豆腐
豆腐は良質なタンパク質と、脂肪の中でもコレステロールが少なく体に良いリノール酸を多く含み、健康の維持・増進に役立つ機能のある機能性食品として注目されています。豆腐の機能性成分の中でも、レシチンが記憶力や集中力を高め脳を活性化させ、精神を安定させストレスにも効果のあるカルシウムを吸収しやすい食品でもあります。冬は湯豆腐として食べると、身体の芯から温まるのでおすすめです。
ダークチョコレート
カカオ含有量70%以上のダークチョコレートには、カカオフラバノール(ポリフェノール)が豊富に含まれます。これは脳の血流を改善し、脳機能を活性化させてくれる効果がありますが、併せて認知機能の向上も認められているので、集中力や記憶力の向上が期待できます。また、疲労回復にも役立ちます。カフェインとテオブロミンという成分も含まれており、これらの覚醒作用による効果としては集中力アップや、気分が落ち着きリラックスできることが挙げられます。
緑茶
緑茶に含まれる渋み成分であるカテキンは、ポリフェノールの一つで抗酸化作用があり、病気の予防に役立ちます。適度なカフェインも含まれているため、覚醒作用による集中力の向上が期待でき、もうひと頑張りしたいときなどに、やる気を高めてくれるでしょう。 ます。また、緑茶の旨味成分であるテアニンというアミノ酸にはリラックス効果があります。気持ちが落ち着いて、睡眠の質の向上や、疲労感の軽減、集中力の持続などへの効果も期待できるでしょう。
日頃の食事や間食に、効率よく脳にいい栄養素を摂れる食べ物を取り入れましょう。
勉強がはかどる!効果的な食事の摂り方
受験勉強の効率を上げるためには、適切な栄養素の摂取だけでなく、毎日の食事の摂り方も重要です。ここでは、受験生のコンディションアップのための効果的な食事の摂り方と、オススメの献立例をご紹介します。
規則正しい食生活を心がける
規則正しい食生活は、体内リズムを整え、脳の働きを安定させるための重要な要素です。一日三食を決まった時間に摂ることで、血糖値を安定させ、集中力を持続できます。また、適度な間食を取り入れることで、長時間の勉強にも対応できます。夜遅い食事は避け、十分な睡眠時間を確保することも大切です。
受験生にオススメの献立例
では、具体的にはどのような食事を摂ればいいのでしょうか。受験生にオススメの献立例をご紹介します。
▼朝食
玄米ご飯
焼きサケ
ほうれん草のお浸し(かつおぶしをプラス)
味噌汁(豆腐入り)
卵焼き(卵1個分)
フルーツ(リンゴ、イチゴ、キウイなど)
緑茶
▼間食(午前)
ミックスナッツ
ブルーベリー
▼昼食
ツナアボカドサンド
・全粒粉のパン
・チーズ
・ツナ
・アボカド
・レタス
・トマト
・くるみ(刻んで散らす)
・マヨネーズソース
バナナ
ブルーベリー入りヨーグルト
▼間食(午後)
カカオ70%以上のダークチョコレート3~4カケラ(15~20g)
干し芋
▼夕食
玄米ご飯
豆腐ハンバーグ
蒸し野菜(ブロッコリー、にんじんなど)
小松菜の胡麻和え
わかめスープ
ほうじ茶
▼就寝前
ホットミルク
この献立例では、脳にいい食べ物として紹介した栄養素をバランスよく取り入れています。本人の好みや食物アレルギーなどに合わせて、適宜調整してみてください。
ナッツアレルギーがある場合は、カルシウムや良質なたんぱく質を含むチーズ、カルシウムや脳の活性化を助ける栄養素の入った小魚チップスなども、間食にオススメです。また、干し芋は低カロリーで、食物繊維を多く含むので腹持ちがよく、ビタミンやカリウムも摂れるので、健康的な間食にはぴったりです。
正しい姿勢で食事を摂る
食事のときの姿勢も、栄養の吸収と消化に影響があります。背筋を伸ばした良い姿勢で、かつリラックスした状態で食事をすることで、消化器官が活発に機能し、栄養の吸収も効率よく進むでしょう。また、正しい姿勢は脳への血流も改善し、食後の眠気を軽減する効果もあります。
よく噛んでゆっくり食べる
消化と栄養の吸収を助けるだけでなく、脳の働きにもよい影響があります。一口30回程度を目安に、よく噛むと満腹中枢が働き、過食を防ぐ効果もあります。
食事の時間は脳をリフレッシュさせることもできるため、「ながら食べ」はやめましょう。勉強はいったん休憩して、食事中は食べることを楽しみましょう。
テスト直前の食事アドバイス
テスト直前のタイミングでは、消化によい炭水化物中心の、軽めの食事を摂りましょう。たとえばバナナやおにぎりは、適度なエネルギーを供給してくれ、胃への負担も少ないためオススメです。逆に、油分の多いものは、胃もたれなどの原因になりやすいので要注意です。
また、食事の量にも気をつけましょう。食べ過ぎは眠気を誘う原因となり、テスト中の集中力を低下させる可能性があります。腹八分目という言葉がありますが、適度な量をテスト開始の2時間前までに摂るのが理想です。
水分補給にも気を配りつつ、当日は利尿作用の強い飲み物を避けて、ベストなコンディションでテストに臨みましょう。
試験中にトイレが気になったり、「具合が悪い、お腹が痛い」ということになっては大変です。直前の食事には、とくに気を配りましょう。
バランスの取れた食生活で効率的に勉強を進めよう!
受験期は、生徒の身体にも心にも、負担がかかる時期です。この記事でご紹介した「脳にいい食べ物」を、受験生の日々の食事に取り入れ、規則正しい食生活を心がけていただけたなら幸いです。バランスの取れた食生活は、脳の働きを最大限に引き出し、効率的な学習をサポートする強い味方となるはずです。受験生の皆さんのご健闘を、心より祈っています!
【関連記事】食生活のほかにも、さまざまな面から受験生を応援することができます。受験生へのサポート方法についてはこちらの記事も参考にしてみましょう。
・受験生の睡眠時間、どれくらいとればいい? 目安、質のよい睡眠のポイントを解説
・【高校受験】受験生のメンタルケア ~心に寄り添う指導・声かけガイド~
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。