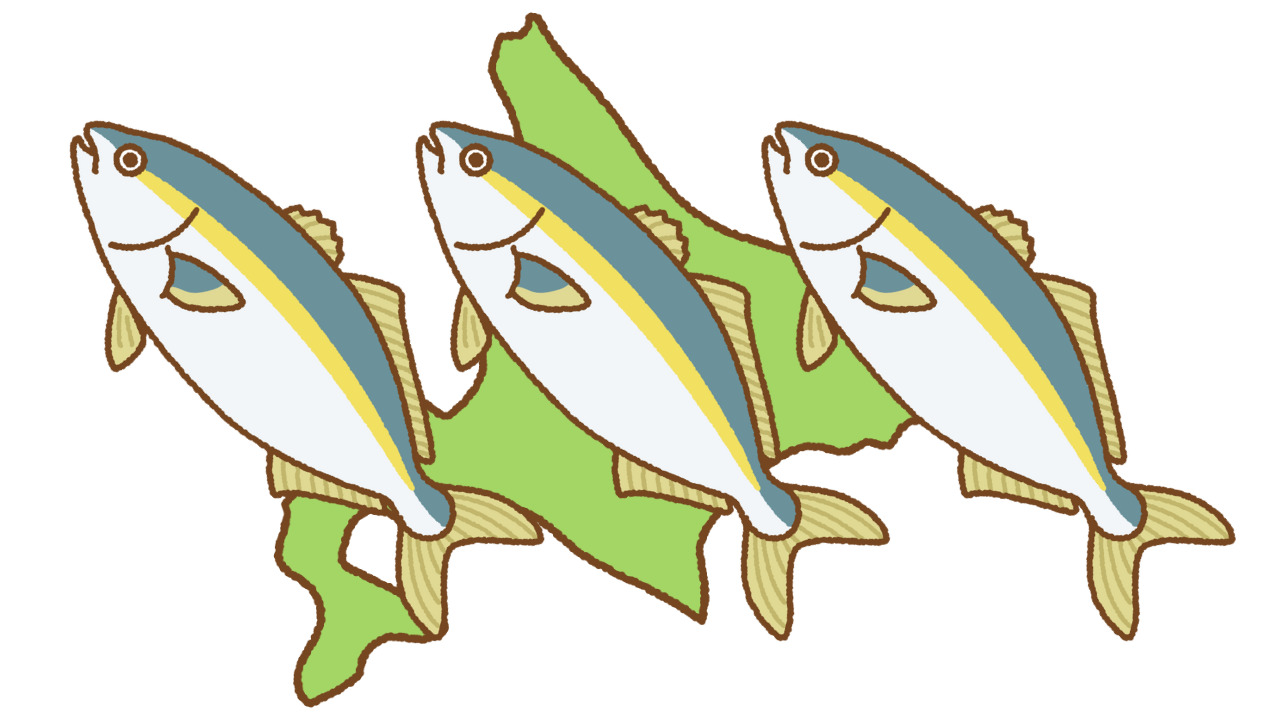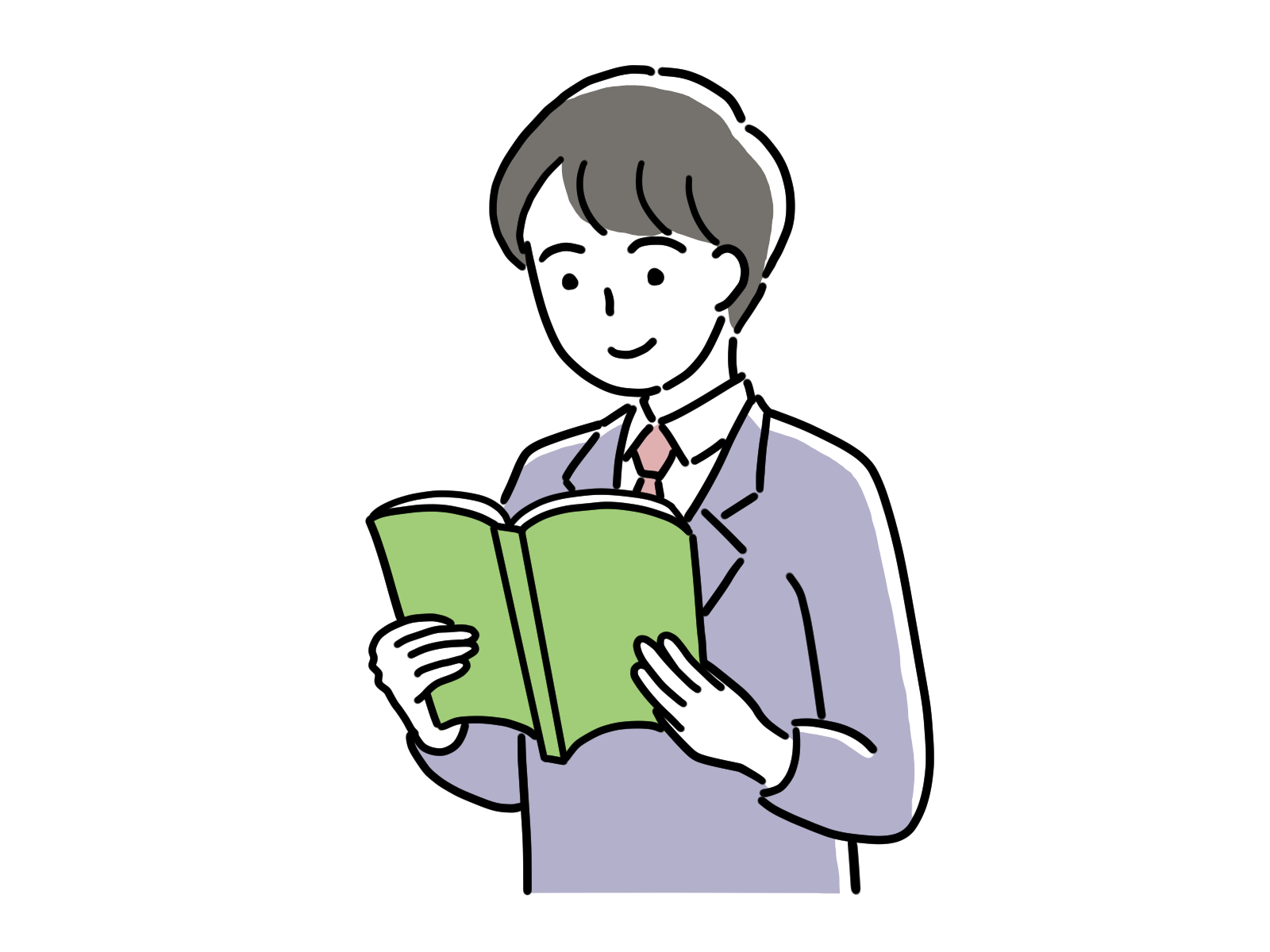
目次
読書感想文の宿題、どんな本を選んだらよいのか迷ってしまいませんか?
読書感想文を上手に書くための一歩として、感想を書きやすい本を選ぶことが挙げられます。この記事では、中学生におすすめの本12冊を厳選してご紹介します。本選びのポイント3つもあわせて解説しますので、自分に合う1冊を見つけて、読書感想文を攻略しましょう!
【中学生向け】読書感想文を書きやすい本を選ぶポイント3つ
読書感想文は、本の内容を要約するのではなく「この本を通して、自分は何を感じ、考えたのか」が問われる課題です。だからこそ、感想文を書くのに適した本を選ぶことが、読書感想文を上手に書くコツだと言えます。
ここでは、読書感想文に向いている本を選ぶポイントを、3つご紹介します。以下を参考に、自分に合った本選びに挑戦してみてください。
ビフォーアフターのあるストーリーを選ぶ
主人公や登場人物に成長や変化が見られるストーリーのほうが、読書感想文を書きやすいでしょう。たとえば、はじめは落ち込みがちで悩んでいた主人公が、友達との関わりによって前向きな状態に変わった、というようなビフォーアフターがはっきりしている作品がおすすめです。登場人物の心情の変化を追いながら、それに対する自分なりの解釈を交えて感想を書くことができます。
感情移入しやすいキャラクターが出てくる本を選ぶ
主人公が自分と同年代であったり、悩みや境遇に共感できるような人物が登場する作品も、読書感想文に向いています。登場人物に感情移入することで、より深く作品世界を味わうことができ、「自分ならどう思うか」「どう行動するか」を想像しながら感想をまとめられます。親近感が湧くキャラクターが登場する本を探してみましょう。
長すぎず、短すぎない本を選ぶ
読書感想文を書く本は、長すぎず、短すぎずが最適です。たとえば、400ページを超えるような大作だと、読み終えるだけでも一苦労です。逆に数十ページ以下の短編は、短い中に象徴的に作品のエッセンスが込められていて、かえって読解力が試されることもありますから、読書の習慣がない人や書くことに苦手意識のある人は、読書感想文の既定文字数を超えるのに苦戦する場合もあります。
特に本を読むのが苦手な場合は、ストーリーをじっくり読み込める分量で、適度に盛り上がりのある作品を選ぶと、感想文を書きやすいでしょう。
では、ここからはカテゴリー別に「読書感想文におすすめの本」をご紹介していきます。
気になる本があったら、ぜひチェックしてみてください!
【中学生向け】映画化された作品3選
まずは、映画化されている3作品を紹介します。
「本を読むのが苦手」「読みたいと思える本が、なかなかない」という人は、話題になった映画作品の「原作」を読んでみるとよいでしょう。映画を先に見ておくと、読書が苦手でも、読む際に話の展開や情景をイメージしやすいのでおすすめです。
▼かがみの孤城(辻村深月/ポプラ社)
https://www.poplar.co.jp/pr/kagami
『かがみの孤城』は、不登校の中学生・ココと、彼女が出会った6人の仲間たちが、異世界のような不思議な城で過ごす物語です。ミステリー要素も交えたファンタジー小説で、彼らの冒険と心の成長が描かれています。作家・辻村深月さんによるこの作品は、2018年に第15回本屋大賞を受賞し、多くの読者の心をつかみました。
また、2022年には、アニメーション映画として上映され、話題になりました。
〇ポイント1 登場人物への感情移入がしやすい
主人公・ココをはじめ、登場人物たちは中学生です。不登校や家庭環境など、さまざまな悩みを背負っており、特に読者が中学生なら、登場人物と同じ目線で物語を追体験できます。等身大の姿に共感しやすく、感想文でも「もし自分だったら」という視点で話を展開しやすいでしょう。
〇ポイント2 心に響くテーマが詰まっている
本書には、中学生が直面するさまざまな悩みが描かれています。そして、その根底には、いずれも「自分らしく生きること」「仲間と支え合うこと」「勇気を持って一歩を踏み出すこと」といった、人生における普遍的なメッセージが込められています。感想文では、これらのテーマを通して「自分はこの本から何を学んだか」を、素直に書くことができるでしょう。
揺れ動く中学生の心に寄り添う1冊。登場人物に感情移入したり、自分の状況を重ね合わせたりしながら感想をまとめたい人におすすめです。
▼君の膵臓をたべたい(住野よる/双葉社)
https://www.futabasha.co.jp/introduction/2015/kimisui/index.html
高校生の「僕」は、病院で1冊の文庫本を拾います。それは、クラスメイトの山内桜良が綴った「共病文庫」でした。本の中身を読んだ「僕」は、桜良が膵臓の病気で余命いくばくもないことを知ります。そんな桜良と過ごす日々のなかで、人とのコミュニケーションが苦手な「僕」は、少しずつ自分自身や他者との向き合い方を変えていくのです。
この作品は、「死」と「生」を真正面から描きながらも、温かな交流や心の成長を描いた青春小説です。2016年には単行本フィクション部門で年間ベストセラー1位(日販調べ)を記録し、映画化もされました。
〇ポイント1 「生」と「死」というテーマに真正面から向き合える
本書は、余命宣告を受けた女の子・桜良と「僕」の交流を軸に、展開していきます。しかし、重苦しい雰囲気ではなく、桜良の明るくポジティブな姿勢が描かれています。そんな彼女との交流を通して、「僕」は人に心を開くことや、今を生きる大切さを学んでいくのです。
感想文では、「死」について考えたことや、「命の尊さ」や「生きる意味」についての自分の思いを書くと、深みのある感想になるでしょう。
〇ポイント2 予測不能な展開で感想が書きやすい
本書は、最後にどんでん返しが待っている物語です。後半の衝撃的な展開は、読者の心を大きく揺さぶります。このラストを受けて、「自分だったら、どう思うか」「終盤の桜良の気持ちをどう受けとめるか」などの視点で感想をまとめるのも、自分らしさが出て面白いでしょう。
予測できなかった結末だからこそ自分なりの解釈を自由に書ける、という点も読書感想文向きだと言えます。
『君の膵臓をたべたい』は、語り手「僕」とヒロインの交流を通して、かけがえのない日常や人とのつながりの尊さを描いた、心に残る青春ストーリー。「生と死の意味」や「人との絆の大切さ」について考えてみたい人は、ぜひ手に取ってみてください。
▼西の魔女が死んだ(梨木香歩/新潮文庫)
https://www.shinchosha.co.jp/book/125332
学校へ行けなくなってしまった中学1年生の少女・まい。彼女は、英国人である祖母、「西の魔女」のもとで過ごすことになります。心癒される自然と穏やかで優しい暮らしのなかで、まいは大好きなおばあちゃんから「魔女の手ほどき」を受けることに。その修行の核心は、呪文を唱えたり魔法を使ったりすることではなく、「何でも自分で決める」ということでした…。
少女の心の成長を描いたこの作品は、児童文学として高く評価され、いくつもの文学賞を受賞。また、2008年に映画化され話題を呼びました。
〇ポイント1 読みやすく、ページ数も手頃
文庫本のなかでも、やや薄めで比較的読みやすい分量です。また文章もわかりやすく、テンポ良く読み進められるので、読書が苦手な子も作品世界へ自然に入っていけるでしょう。感想文の本として取り組みやすい1冊だと言えます。
〇ポイント2 おばあちゃんの教えが心に響く
おばあちゃんは、まいに「何でも自分で決める」ことの大切さを教えてくれます。これは、まいだけでなく読者にとっても、心に響くメッセージではないでしょうか。おばあちゃんが教えてくれた数々の「生きていくうえで大切なこと」を、「これからの生活のなかで、自分はどのように活かしていきたいか」という視点から感想を書くと、まとめやすいのでおすすめです。
穏やかに流れる日常のなかに、大切なメッセージが込められている『西の魔女が死んだ』。読後は、温かく優しい気持ちになれます。ぜひ、まいとおばあちゃんの交流を通して、「自分らしい生き方」について考えを深めてみてください。
【中学生向け】科学・数学の魅力が伝わってくる作品3選
「せっかくなら、自分の好きな分野の本を選んで感想文を書きたい」
「小説を読むのは苦手だけど、理数系がテーマの本なら興味がある」
そんな方におすすめの、科学・数学の魅力が伝わってくる3冊をご紹介します。数学の不思議を感じる物語、生物の観察記録、植物学者の伝記……科学・数学が好きな人はもちろん、苦手意識がある子にとっても興味をひかれるに違いない、名作ばかりを厳選しました。科学・数学の世界の奥深さ、面白さを堪能しつつ、楽しみながら読んでみてください。
▼博士の愛した数式(小川洋子/新潮社)
https://www.shinchosha.co.jp/book/121523
家政婦の「私」と息子の「ルート(√)」、数学者の「博士」との間に生まれた心の交流と、美しい数式によって深まっていく不思議な絆を描いた、心温まるヒューマンドラマです。博士は、交通事故による脳の損傷で新たな記憶が80分しか持続しませんが、長年の数学への情熱は失っていません。そんな博士と過ごす日々のなか、家政婦とルートは、数学をきっかけに少しずつ博士の人柄にふれ、3人の間に温かな絆が育まれていきます。この作品は、芥川賞作家・小川洋子の代表作で、2004年に第1回本屋大賞を受賞したベストセラー。2006年には映画化もされ、今なおファンの多い作品です。
〇ポイント1 記憶障害という状況での情熱
「80分で記憶がリセットされる」状況においても、数学への情熱を失わない博士の姿は、深く印象に残るでしょう。感想文では、記憶や時間、人間の情熱が持つ力について、自分なりに考えたことを書くこともできそうです。
〇ポイント2 数学の魅力に触れられる
作中には、数式の美しさや面白さが、いろいろな場面で描かれています。数学が苦手な人でも、この物語を通して新たな視点から数学の奥深さに気づき、興味を持つかもしれません。読む前と後とでの数学に対する印象の変化を書くのも、ユニークな視点でよいでしょう。
『博士の愛した数式』は、数学という学問の魅力を軸に展開していく、少し独特な優しい人間ドラマです。自分がルートだったら、博士だったら……など、視点を変えながら3人の関係性を捉えて読むのも面白いでしょう。数学が得意な方はもちろん、苦手な人も楽しめるので、ぜひ読んでみてください。
▼セカイを科学せよ!(安田夏菜/講談社)
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000354816
中学2年生の藤堂ミハイルは、ある日、超個性的な転校生・山口アビゲイル葉奈と出会います。自分を貫き規格外の行動ばかりとる葉奈は、オタクレベルで「蟲」が大好き!カミキリムシ、カナヘビ、ワラジムシ、ハエトリグモ…などを教室に持ち込んでは、クラスを騒然とさせます。そんななか、ミハイルと葉奈、科学部のメンバーは、生物班部の存続をかけて、学校に「科学的な取り組みの成果」を示すことに。シビアな状況下でも、イキイキと身の回りの生き物たちを観察し研究を進めていく彼らを描いた、熱い青春ストーリーです。
〇ポイント1 科学的な探究心や「好き」を追求する姿勢を育める
葉奈をはじめ登場人物たちが、自分の興味関心・好奇心に忠実に活動する姿は、まさに青春!身の回りの生き物を観察し、科学的な発見をしようと奮闘します。好きなことに一生懸命に取り組む、ひたむきな姿に触れることで、読者も科学への興味が高まるかもしれません。
本書を読んで自分が疑問に思ったこと、調べてみたいと思ったトピックについて、感想文に書いてみるのもおすすめです。また、登場人物同様に夢中になれるものがあるなら、彼らの情熱への共感を綴るのもよいでしょう。
〇ポイント2 科学部の活動を通して、仲間の大切さを実感できる
科学部のメンバーたちは、生物班の活動存続をかけて、力を合わせて頑張ります。時には意見が衝突することもありますが、共に困難を乗り越えて絆を深めていく様子から、仲間の大切さを感じることもできそうです。
登場人物から学んだ友情の大切さや、困難を克服するための意志や行動について、自分の経験と重ね合わせて考えたこと、思うことを書いてみるのもよいでしょう。
生き物についての知識は、とくに生物や科学が好きな人にとっては興味深く、新たな発見や学びのきっかけにもなるでしょう。また、本書は、科学的な探究心や知的好奇心を刺激すると同時に、同世代の中学生にとって、自分の「好き」やアイデンティティにまっすぐであることへの共感や、学びも多い作品です。コメディ要素もあるので、最後まで面白く読み通せるでしょう。
▼牧野富太郎【日本植物学の父】(清水洋美/汐文社)
https://www.choubunsha.com/book/9784811327341.php
小説(フィクションストーリー)が苦手な場合は、伝記を読んで感想文を書いてみるのも選択肢の1つです。ここでは、2023年にNHKのTVドラマで話題になった「牧野富太郎」の伝記をご紹介します。
本書は、明治から昭和にかけて活躍した植物学者、牧野富太郎の生涯を描いています。「日本植物学の父」と言われる牧野富太郎の、研究にかける情熱と生き方、彼を支えた周りの人物などをまとめています。
〇ポイント1 植物や自然に興味がある生徒におすすめ
とくに植物や自然に関心のある人にとっては、牧野の生き方に共感したり、学んだりできる部分もたくさんあるのではないでしょうか。それを感想としてまとめるのもよいですし、伝記を読むことで感じた、自分自身の植物や自然への思いを綴ってみるのもおすすめです。
〇ポイント2 夢や志を持つことの大切さを学べる
牧野は貧しい家庭の出身でありながら、独学で植物学者となりました。その原動力となったのは、植物への深い愛情と、研究への情熱です。牧野の生き方を通して学んだ「夢や志を持つことの大切さ」を踏まえ、自分の将来の夢、情熱の大切さについて語ってみると、ユニークで意義のある感想文が書けそうですね。
植物や自然への愛情、夢や志を持ち続けることの大切さなど、読者の心に響くエッセンスが詰まった1冊です。牧野の人生から学んだことを、自分のためにまとめる気持ちで、ぜひ感想文で表現してみましょう。伝記というジャンルの面白さを知るきっかけにもなるはずです。
なお、牧野富太郎についての関連書籍は数多く出版されているので、本書をきっかけに彼の一生や研究内容を深掘りしたくなった場合も、資料を集めやすいでしょう。
【中学生向け】命について考えさせられる本3選
日々の生活のなかで、あらためて「命」について考えたことのある人は、どのくらいいるでしょうか?
ここでは、当たり前のように過ごしている毎日や、「生きる」ということについて、立ち止まって考えるきっかけをくれる3冊を紹介します。
きっと、かけがえのない日常の尊さに気づかされるはずです。
▼カラフル(森絵都/文藝春秋)
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167741013
物語は、事故で命を落とした「ぼく」の魂が、生前に犯した罪によって輪廻(生まれ変わり)のサイクルから外されてしまうところから始まります。しかし抽選でチャンスをもらい、中学3年生の少年・真の体にホームステイすることに。真として生活していくなかで、主人公は真の家族や友人との関わりを通し、少しずつ新たな視点から、自分の心と向き合っていきます。
〇ポイント1 一人称の視点で語られ、感情移入しやすい
本書は、主人公「ぼく」の視点(一人称視点)で語られます。読者は主人公の目を通して、真の家族や友人との関係、周囲の出来事を追体験するかたちになります。「自分が主人公の立場だったら」と想像しやすいので、感想文を書くうえで、自分の思いや考えを述べやすいでしょう。さらに、「もし、自分が他の登場人物だったら?」という切り口から想像を膨らませ、多角的な視点で感想文を仕上げることもできます。
〇ポイント2 「生きること」や「命」について深く考えさせられる
本書は「生きる意味」や「命の尊さ」といった、普遍的なテーマを扱う作品です。主人公の魂が、再度チャンスを与えられ、真の人生を通して学んでいくプロセスは、読者にも「生きること」についてあらためて考えさせてくれます。
10代の繊細な感受性ゆえの人間不信、危うい心…一見重いテーマですが、「ぼく」の親しみやすい語り口もあって、軽快に読み進められるのも本書の魅力です。感想文では、中学生の自分なりの「生きる意味」について、考えを素直に綴ってみるのもよいですね。
中学生の真として生きる主人公、その視点で描かれる登場人物たちの多面的な姿や色彩豊かな日常は、物語の中に読者を引き込んでくれます。作品にちりばめられた心に残るセリフ、そしてラストに明かされる真実は、きっと読者の心を揺さぶるはず。何気なく過ごしていた毎日のなかで、立ち止まって自分の「生きる意味」について考えてみたい。新しい視点から、この世界を見て感じたい。そんな人におすすめの1冊です。
▼1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記(木藤亜也/幻冬舎)
https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344406100
15歳の木藤亜也は、ごく普通の中学生。しかし、ある日、突然手足の感覚が徐々に失われていくという異変に見舞われます。国が指定する難病を発症し、余命わずかと宣告された亜也さんでしたが、家族や友人に支えられながら、懸命に生きる道を模索します。「たとえどんな小さく弱い力でも私は誰かの役に立ちたい」 と、最期まで前向きに生き抜いた少女の言葉が綴られたノンフィクション。感動のロングセラーです。
2005年には、ドラマ化されて話題になりました。
〇ポイント1 実在した少女の遺した言葉と生きた記録に心を打たれる
本書は、木藤亜也さんの日記がまとめられた実話です。同年代の少女が難病と向き合いながら、懸命に生きた記録は、読む人の心に深く響くでしょう。感想文では、徐々に身体の自由を失いながらも周りへの感謝を忘れなかった亜也さんの生きざまから感じ取ったことや気づき、自分の生き方を振り返るきっかけになったエピソードなどを書くのもよいですね。
〇ポイント2 家族や友人の支えの大切さを実感できる
亜也さんを支え続けた家族や友人たちの存在は、読者の心を温かくしてくれます。治療法のない病気と闘う亜也さんを周囲の人々が懸命に支える姿に、勇気づけられる人は多いはずです。感想文では、亜也さんを取り巻く人々から感じ取った「支え合うことの大切さ」「無償の愛がもたらす救いや希望」などについて、自分の経験を交えて書いてみるのもよいかもしれません。
病気や障害、そして生きることの意味について、深く考えさせられる1冊です。亜也さんは若くして亡くなりましたが、彼女が遺した言葉は、今を生きる読者の心に「生きていること」への感謝を呼び覚ましてくれます。亜也さんから学んだことを、飾らない自分なりの言葉で整理していくと、読む人の心に届く感想文になるのではないでしょうか。
▼晴れたらいいね(藤岡陽子/光文社)
https://books.kobunsha.com/book/b10127580.html
現代を生きる看護師の主人公が、第二次世界大戦中のフィリピンにタイムスリップ。そこで彼女が目にしたのは、過酷な状況の中で命を支えようと奮闘する人々の姿でした。医療の現場に身を置く主人公が、戦争という極限の世界で何を感じ、どう変わっていくのか。戦争と平和、命の重さ、生き方を静かに問いかけてくれる1冊です。
〇ポイント1 戦争や平和について、自分の問題として考えるきっかけになる
現代に生きる主人公の紗穂が、1944年のマニラという戦争の真っ只中に移動してしまうという衝撃の展開から始まる物語。戦争を知らない紗穂の戸惑いや葛藤は、同じように戦争を知らない世代の読者が共感・理解できるところが多く、感情移入しながら読み進めやすいでしょう。感想文では、紗穂の気持ちを自分の目線でたどりながら、戦争の悲惨さや平和について感じたことを、率直に言葉にしてみるのがおすすめです。
〇ポイント2 命を守りぬこうとする人の使命感や強さにふれて、自分の生き方を考えられる
想像を絶する過酷な状況のなかでも、けが人を支え、仲間と励まし合いながら奮闘する従軍看護師たちの姿は、読む人の胸を打ちます。感想文では、人の命の重さや価値、信念・使命をまっとうする強さ、理不尽さや不本意なことに「No」を言える大切さ…など、本書が突き付けるテーマに対する自分なりの価値観や思いを書いてみるのもよいですね。
命が軽んじられてしまう戦争の中でも、誰かを支えようとする姿に、読む私たちも背筋が伸びる思いがするでしょう。現代に生きる私たちが、紗穂とともに「命」や「平和」の意味を見つめ直すことができる1冊。戦争や医療に興味がある人はもちろん、「生きること」や「命」について考えてみたい中学生に、ぜひ手に取ってほしい作品です。
【中学生向け】社会問題や現代社会について考えさせられる本3選
最後に、身近な社会問題について考えるきっかけを与えてくれる作品をご紹介します。
「社会問題なんて、自分の日常には無関係でピンとこない」「どうせ何もできない、大人が解決していくこと」そんなふうに感じている中学生も多いかもしれません。今回ご紹介する3冊は、そんな先入観を覆し、「自分たちの隣で起きているかもしれない」身近なこととして、リアルに感じさせてくれる作品ばかりです。
中学生の日常生活とも密接に関わる問題に触れているので、実体験や自分が見聞きしたことを交えながら、リアリティのある感想文を仕上げたい人にもおすすめです。
▼with you(濱野京子/くもん出版)
https://shop.kumonshuppan.com/view/item/000000002979
中学3年生の悠人は、ランニング中に夜の公園で出会った少女・朱音に惹かれていきます。朱音は、母親の介護と妹の世話を担う「ヤングケアラー」で、家庭の事情により、同年代の他の子たちとは少し違う日常を送っていました。そんな朱音の事情を知った悠人は、彼女の力になりたいと思い始め、少しずつ距離を縮めていきますが……。2人の繊細な心の動きと、ヤングケアラーという社会問題が絡み合う青春ストーリーです。
本書は、2021年の青少年読書感想文全国コンクール課題図書(中学校の部)になりました。
〇ポイント1 ヤングケアラーという社会問題を身近に捉え、関心を持つきっかけになる
中学生にとって共感できる恋愛要素だけでなく、「ヤングケアラー」という社会問題にも目を向けさせてくれる本書。朱音の境遇を通して、家庭の事情により自分と同世代の子どもが抱えてしまう困難や、家庭内の問題を相談・解決することの難しさに気づける機会になるでしょう。作品に描かれたヤングケアラー問題について思うことや、このような困難を抱える子に周囲や社会はどんなサポートができるかなど、「支え合い」について意見をまとめてみるのもおすすめです。
〇ポイント2 社会の問題について、自分と関連づけて考えられるようになる
本書をきっかけに、ヤングケアラーに限らず、自分たちの周りにさまざまな社会問題があることに気づくと、中学生の視界がぐんと広がります。自分が属する地域・自治体など身近で起きている社会問題や、ニュースになった事例など、気になる社会問題があれば、そこから考えたことを感想文に書いてみるのもよいでしょう。なお、社会問題について関心を高め、自分の考えが深まることは、受験の面接対策や作文対策にも活きてきます。
ヤングケアラーという同世代の抱える問題に目を向けさせてくれると同時に、恋愛ストーリーとしても楽しめる1冊。同世代の2人が悩みを打ち明け合い、徐々に心の距離が近づいていく姿は、人を想う気持ちの大切さも実感させてくれます。社会や家庭の問題について、または人間関係や誰かを大切に想うことについて、自分らしい視点から感想を書いていくのがおすすめです。
▼モモ(ミヒャエル・エンデ/岩波書店)
https://www.iwanami.co.jp/book/b269602.html
モモは、古い円形劇場の廃墟で一人暮らしをしている不思議な女の子。モモには「人の話を本当に聴くことのできる特別な力」があり、大人たちは彼女に話を聞いてもらうと、心が楽になり、悩みや問題が解決していくのでした。モモの周りには、個性豊かな仲間が集まり、大切な時間が流れていました。しかしある日、灰色の男たちが街に現れ、人々から大切な「時間」を奪い始めます。効率と利益だけを追求する冷たい社会を作ろうとする灰色の男たち。大人たちは次々と「時間」を奪われ、心を失っていきます。モモは、盗まれた時間を人間に取り戻すため、時間泥棒に立ち向かうことを決意するのでした。
「効率」や「無駄」を気にするあまり大切なものを見失いがちな現代人への、問いかけとメッセージが込められたファンタジーの傑作。世界的に有名なドイツの児童文学作家ミヒャエル・エンデの代表作の1つです。
〇ポイント1 「心の豊かさ」と「時間」について考えさせられる
本書には、効率と利益を追求する現代社会への警鐘が込められています。灰色の男たちに「時間」を奪われていく人間たちの姿、「心を失った社会」の様子は、現代の読者にとっても他人事ではないはずです。灰色の男たちが現れる前と後での、時間の流れの描かれ方を比較しながら、物語に込められた現代社会へのメッセージをどう捉えたか、感じたことを綴ってみるのもよいでしょう。「時間」に追われ大切なものを見失った経験や、自分にとって心地よい時間の過ごし方、人生で優先したいことなどについて、述べるのもおすすめです。
〇ポイント2 友情の力や勇気の大切さが描かれている
モモは、仲間たちと力を合わせて、灰色の男たちに立ち向かいます。後半のストーリーでは、モモの勇気や友情の力が描かれ、その大切さを実感することができるでしょう。感想文では、モモが人々のために時間泥棒に立ち向かう姿に焦点を当て、恐れを上回るだけの強い気持ちや、困難に挑む勇気について、思うことを書いてみるのもよいでしょう。また、モモと仲間たちの絆から感じ取ったことや、自分の友人関係を盛り込みつつ「友情」について書いてみるのも一案です。
『モモ』は現代社会の問題を鋭く突きつつも、友情や「心」の大切さを描いた作品として、時代を超えて愛されている名作です。効率と利益を追求する社会のなかで、本当に大切なものとは何なのかを深く考えたい。そんな「自分らしい豊かな時間」を持ちたい人は、ぜひ、モモの物語から感じ取ったメッセージを、自分なりの言葉で綴ってみましょう。
▼江戸のジャーナリスト 葛飾北斎(千野境子/国土社)
https://www.kokudosha.co.jp/search/info.php?isbn=9784337187641
元新聞記者である著者が、浮世絵師・葛飾北斎の生き方を追いながら、その素顔に迫るノンフィクション作品です。代表作「冨嶽三十六景」をはじめとした数々の作品がどうやって生まれたのかが、丁寧に書かれています。また、鎖国下の江戸で海外にまで目を向け、独自に情報を集めていた貪欲な北斎の姿も描かれています。
2022年の第68回青少年読書感想文全国コンクール「中学校の部」の課題図書にも選ばれた1冊。知ることへの情熱や情報との向き合い方を考えさせてくれる作品です。
〇ポイント1 「知ろうとする姿勢」の大切さを北斎の生き方から学べる
北斎は、自分の目で確かめることを大切にしながら、独自の視点で絵を描き続けた人物です。たとえば、波の動きや馬の筋肉の動きを知るために、何度も観察や取材を重ねたそうです。
感想文では、「なぜ、それほどまでに知ろうとしたのか?」「自分も興味を持った対象をとことん追ってしまうので、気持ちがわかる部分がある」といった視点で書いてみるのもおすすめです。
〇ポイント2 情報にあふれる今だからこそ、自分で考えて選ぶ力の大切さについて考えられる
現代は、調べようと思えば、たいていの情報は簡単に入手できる時代です。一方で北斎は、本で見た話や人から聞いた話だけに頼らず、自分の目で見て確かめ、納得できるまで観察や取材を重ねていました。こうした北斎の行動からは、情報にふれるときこそ、「自分の頭で考え、選び取る力」が大切だということが伝わってきます。
感想文では、「情報が多すぎる今、私は、それらにどう向き合っていったらよいか」「自分の目で見て、自分で直に確かめることの意味とは何か」といったテーマで、自分自身の経験と結びつけて考えを深めてみるとよいでしょう。
自分の目で確かめ、納得できるまでとことん調べた北斎の姿からは、「学ぶことの面白さ」や「知ることの喜び」がきっと伝わってくるはずです。情報があふれる今の時代だからこそ、自分の目で見て考えることを大切にしていた北斎の姿勢は、今の私たちにも必要な視点だと気づかされます。感想文では、印象に残った場面をきっかけに、自分なりの「知ることの意味」について考えを深めてみましょう。
ポイントを押さえて、読書感想文を攻略しよう
読書感想文に適した本を選ぶことは、感想文を上手に書くための第一歩です。今回は中学生を対象として、読後の感想を掘り下げやすい本を12冊、紹介しました。
読書感想文を書くことは、本の世界と向き合い、自分と向き合い、考えを深める絶好の機会です。自分にぴったりの本が見つかれば、書くことへのハードルはぐっと低くなります。読書感想文に取り組む際は、最初に紹介した「本を選ぶポイント3つ」を参考にしつつ、自分の興味や関心に合った本を探しましょう。
ぜひ、今回ご紹介した12冊を参考に、自分だけの1冊を見つけてみてください。きっと、心に響き、感想を書きたくなるような本との素敵な出会いが待っています。読書を楽しみながら、自分らしい感想文を書き上げてください。
うまく文章が書けず、手が止まってしまうことはありませんか?
そんなときは「一つひとつの文を意識する」「パラグラフ・ライティングを活用する」など、読みやすい文章を書くコツを抑えてみましょう!
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。