
最新の時事に関するクイズを掲載します。解答後に表示される解説を授業の合間に話すネタ、関連事項を説明する際の資料などとしてご活用ください。
■ノーベル平和賞■
2024年12月10日、ノーベル賞の授賞式が行われ、平和賞を日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)が受賞しました。ノーベル賞についての説明で間違っているものは次の①~④のうちのどれでしょうか。
- ① ノーベル平和賞はノルウェー・ノーベル委員会が選考する。
- ② ノーベル賞は、個人に対しては各賞それぞれ一度に最大3人まで授与される。
- ③ ノーベル賞の受賞者が最も多い国は米国である。
- ④ 日本出身者が最も多く受賞しているノーベル賞は化学賞である。
正解!
不正解...
正解は④ 日本出身者が最も多く受賞しているノーベル賞は化学賞である。です。
問題に戻る
■日本の伝統的酒造り■
2024年12月5日、ユネスコ(国連教育科学文化機関)の無形文化遺産に、日本の「伝統的酒造り」が登録されることが決定しました。無形文化遺産に登録されていない日本の文化は次の①~④のうちのどれでしょうか。
- ① 茶道
- ② 雅楽
- ③ 和紙
- ④ 結城紬
正解!
不正解...
正解は① 茶道です。
②は2009年、③は2014年、④は2010年に登録されています。
2024年12月5日、ユネスコの「無形文化遺産の保護に関する条約」(無形文化遺産保護条約)政府間委員会は、日本が提案した「伝統的酒造り」を無形文化遺産に登録することを決定しました。「伝統的酒造り」とは、杜氏や蔵人などが麹菌を使って、長年の経験に基づいて築き上げてきた酒造り技術で、500年以上前に原型が確立したとされています。日本酒や焼酎、泡盛、みりんなどの酒は、日本各地の水や穀物、麹を使用して気候風土に応じて発展し、製法が伝承されてきました。酒は神へ捧げる物として、祭事や婚礼など社会文化的行事の場でも不可欠な役割を果たしており、酒造りはそれを支えてきた技術なのです。
無形文化遺産は2003年にユネスコ総会で採択された無形文化遺産保護条約に基づき、条約締約国から選出された24カ国で構成される政府間委員会で決定されています。世界遺産が有形なのに対して、無形文化遺産は口承による伝統・表現、芸能、社会的慣習、儀式・祭礼行事、自然・万物に関する知識・慣習、伝統工芸技術など無形のものが対象。日本からは「能楽」「人形浄瑠璃文楽」「歌舞伎」をはじめ、「和食」「伝統建築工匠の技」「風流踊」などが登録されてきました。「伝統的酒造り」の登録で、日本からの登録件数は23件となりました。
日本酒や焼酎など、日本の酒は近年海外でも人気が高まっています。たとえば、日本酒の2023年の輸出額は2014年の約4倍に増加。その一方で、国内での出荷量はピーク時(1973年)の約4分の1にとどまっています。無形文化遺産への登録を機に消費の拡大が期待されています。
問題に戻る
■マイナ保険証■
2024年12月2日、健康保険証が、個人番号カード(マイナンバーカード)を利用した「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しました。マイナンバーカードの説明で間違っているものは次の①~④のうちのどれでしょうか。
- ① 多くの地方自治体が、マイナンバーカードを利用すればコンビニで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できるようにしている。
- ② マイナンバーカードには有効期限はない。
- ③ マイナンバーカードのICチップには税金や年金、病歴などプライバシー性の高い情報は記録されない。
- ④ 2025年3月からは、運転免許証をマイナンバーカードに一体化した「マイナ免許証」の運用が始まる。
正解!
不正解...
正解は② マイナンバーカードには有効期限はない。です。
マイナンバーカードには有効期限があり、18歳以上の人は発行日から10回目の誕生日まで、18歳未満は5回目の誕生日までです。また、「マイナ保険証」として利用するには、年齢を問わず5回目の誕生日ごとに、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の更新手続きが必要です。
2024年12月2日、健康保険証が「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しました。マイナ保険証とは健康保険証の登録を行ったマイナンバーカードのこと。登録は①医療機関の受付にある顔認証付きカードリーダー、②スマートフォンやパソコンからマイナポータルに接続、③セブン銀行ATM――のいずれかで行います。使用する際は顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置き、顔認証か暗証番号(4桁)で本人確認を行います。
12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行は停止されましたが、有効期限内の健康保険証は引き続き最長で1年使用できます。また、「マイナ保険証」の登録をしない人には「資格確認書」が交付され、健康保険証と同様に使用できます。
マイナ保険証を利用したうえで、診療や特定健診、投薬の履歴といった医療情報を医療機関に提供することに同意すると、より多くの正確な情報に基づいた総合的な診断を受けられたり、投薬の重複や誤りを防いで適切な処方を受けることができたりするとされています。また、高額な医療費が発生する場合に、一時的な自己負担や限度額適用認定の申請手続きをする必要がなくなったり、税金の申告で医療費控除の手続きが簡単に行えたりするメリットもあります。
一方で、2023年にはマイナ保険証に他人の情報が紐づけされていた問題から、デジタル庁が個別データの総点検を行いました。また、医療機関は医療情報をデータセンターから呼び出して利用しますが、サイバー攻撃を受けて情報が外部に流出するリスクもないとは言い切れず、個人情報の点から不安も残っています。
問題に戻る
執筆:NPO現代用語検定協会
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。







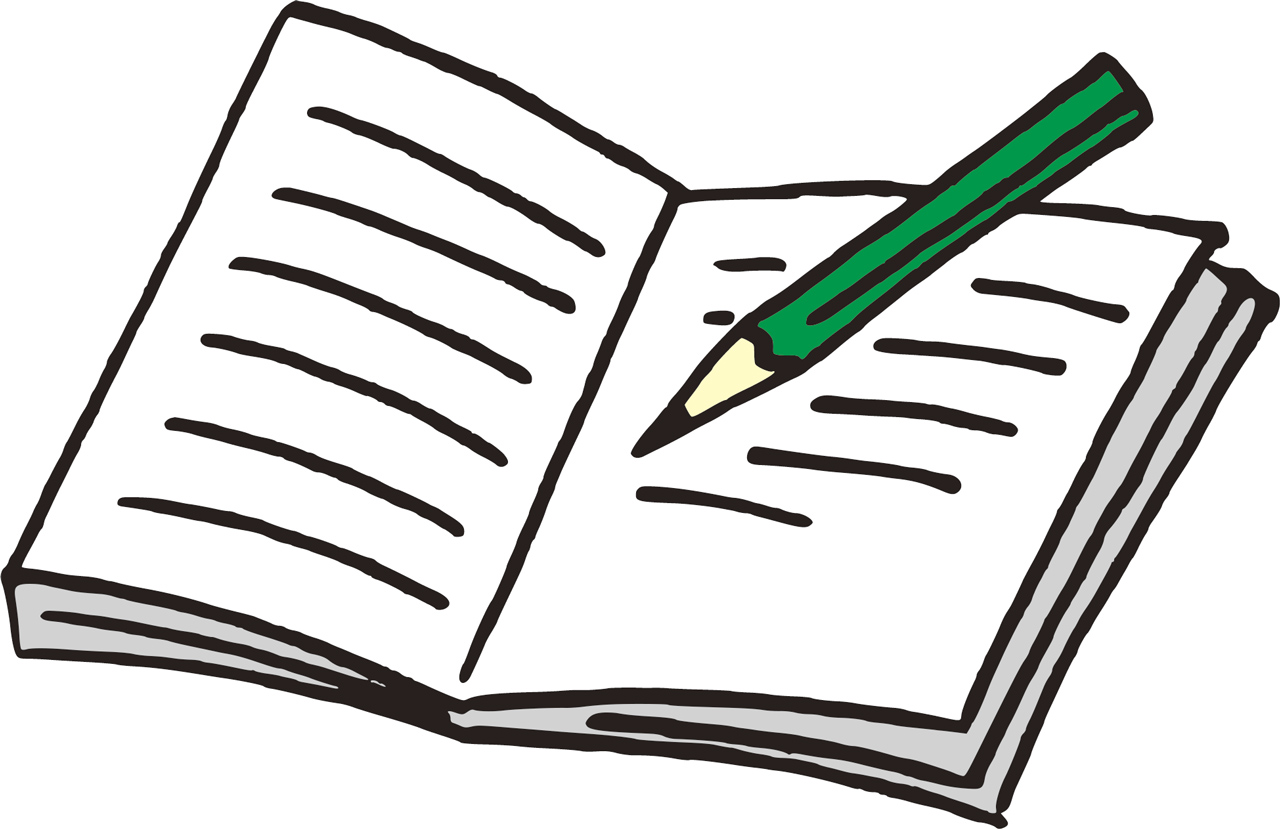






最も多いのは物理学賞で12人(日本出身の外国籍者も含む)。化学賞は8人です。
2024年10月11日、ノルウェー・ノーベル委員会は、平和賞を日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)に授与すると発表しました。日本からのノーベル平和賞の受賞は、非核三原則を表明し核拡散防止条約(NPT)に署名した佐藤栄作元首相が1974年に受賞して以来、50年ぶりです。12月10日の授賞式では日本被団協代表委員の田中熙巳さんが演説。自身の長崎での被爆体験を交えながら、核兵器も戦争もない世界の人間社会を求めて共に頑張ろうと訴えました。
日本被団協は、第二次世界大戦中に広島・長崎に投下された原爆の被爆者たちによる全国組織。1954年に米国のビキニ環礁水爆実験で第五福竜丸が被災したことを機に原水爆禁止運動が高まったことを受けて、1956年に結成されました。日本被団協では被爆者の立場から、原爆被害への国家補償を求めることや、日本政府・国連・国際社会へ核兵器の廃棄や撤去などを働きかけることに取り組んできました。2017年に国連で採択された、核兵器の開発・保有などを法的に禁止する「核兵器禁止条約」の交渉会議では、約300万人分の署名を集めて採択を後押ししました。こうした活動が、「広島と長崎の被爆者たちによる草の根の運動で、核兵器のない世界を実現するために努力し、核兵器が二度と使用されてはならないと証言を行ってきた」と評価されて今回の受賞に至りました。
核廃絶を訴える団体では、2017年に国際NGOのICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)が同じく平和賞を受賞しています。しかし、近年、核の脅威は一段と高まっています。日本被団協の受賞を、世界の核廃絶に向けた弾みとしていくことが望まれます。