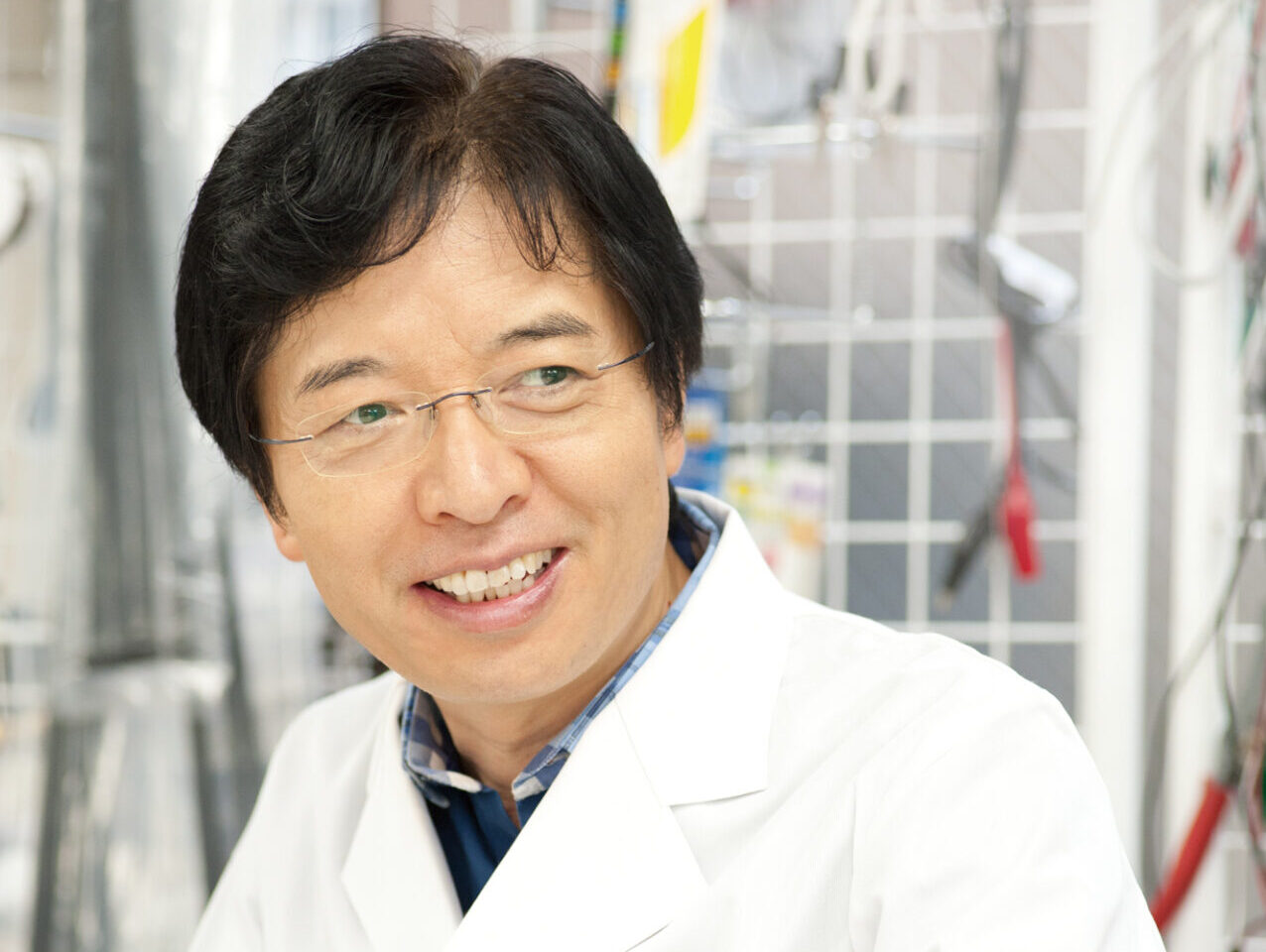目次
「論理的思考力を育てたいけど、授業だけでは時間が足りない…」
「日常生活の中で論理的思考力を育める、良い方法はないかな?」
このような悩みを抱える先生方は、少なくないでしょう。
子どもたちが特別な授業だけでなく、日常生活の中で自然と論理的思考力を身につけられるとよいですよね。
この記事では、小学校における論理的思考力(ロジカルシンキング)の基本的な捉え方・位置づけから、授業や学校生活の中で無理なく取り入れられる実践的な育成方法まで解説していきます。明日からでもすぐに取り組めるアイデアが満載ですので、ぜひ最後までお読みください。
「論理的思考力」って?教育者が知っておきたい基礎知識
子どもたちの「考える力」を伸ばしたいけれど、「論理的思考力って、具体的にはどんなスキル?」「どんな指導で育てていけばいいのだろう?」という疑問をお持ちの先生方は、多いのではないでしょうか。
ここでは、教育者として知っておきたい「論理的思考力」の位置づけについて解説します。
論理的思考力とは
まずは基本を振り返りましょう。論理的思考力とは、物事を筋道立てて理解し考える力のことです。具体的には、情報を抽出して分析する力や、問題を発見し解決の方向性を決定する力などが含まれます。
論理的思考力がある子どもは、たとえば「どうして、そう考えたの?」と質問されたとき、理由や根拠を明確に示すことができます。また、複雑な問題に直面したときに、その問題を小さな要素に分解して考えたり、問題を解決するためにはどうしたらよいか考えたりすることもできます。
そして、このような論理的思考力は、短い期間で身につくものではなく、日々の経験や学習の積み重ねを通じて徐々に育まれていくものです。
教育現場での論理的思考力の位置づけとは
論理的思考力は、子どもたちが将来、社会で自立的に生きるために必要な資質・能力の一つとして位置づけられています。学校教育においても、育成の重要性は近年ますます認識されており、各教科学習の中で取り組みがなされています。
▼各教科での論理的思考力を育む取り組み
| 教科 | 論理的思考力を育む取り組み |
| プログラミング学習 | 目的達成のための手順を論理的に組み立てる |
| 国語科 | 論理的文章の読解や筋道立てた表現力を育む |
| 理科 | 観察・実験結果の分析から思考力を培う |
| 社会科 | 資料から情報を読み取り、根拠を持って表現する |
| 算数科 | 問題解決の方法を論理的に説明する力を養う |
また、論理的思考力を育てる学び方としてアクティブラーニングがあります。子どもたちが主体的に課題について考え、対話により学びを深め、解決策を模索することで、論理的思考のプロセスを体験的に学ぶことができます。
論理的思考力は物事を筋道立てて考える力です。子どもたちが社会で自立的に生きるために必要な能力として、多様な学習活動を通じた継続的な育成の取り組みが大切です。
論理的思考力を身につけると、どんなメリットがあるの?
子どもたちが論理的思考力を身につけると、日常生活や学習の中でさまざまなメリットが生まれます。ここでは、論理的思考力がもたらす具体的な効果について紹介します。
論理的思考力は、学校での勉強だけでなく、人間関係や将来の仕事など、社会活動のあらゆる場面で活かせる大切な力です。これからの時代を生きる子どもたちにとって、必要不可欠なスキルといえるでしょう。
問題解決能力が身につく
論理的思考力が身につくと、子どもたちはさまざまな問題に直面したとき、その原因を冷静に分析し、解決策を見つけることができるようになります。
たとえば「友達とケンカをした」という問題が起こった時には、感情的になるだけでなく、「なぜケンカになったのか」「相手の気持ちはどうか」といった視点から、客観的に出来事を整理できるようになります。そして「どうすれば仲直りできるか」という解決策を考えられるでしょう。
また、算数の文章問題で「何がわかっていて、何を求めるのか」「どんな順序で計算すればよいか」を、順序立てて考えられるようになり、より複雑な問題が出てきたときにも対応できる能力が身に付きます。
このような問題解決能力は、学校生活で役立つだけでなく、将来社会に出てからも重要な力となります。問題の原因を探り、具体的な解決策を見つけられるようになれば、どんな場面でも活躍できるでしょう。
自分の考えを整理し、分かりやすく伝えられるようになる
論理的思考力を身につけると、自分の考えを整理して、相手に分かりやすく筋道立てて伝えることができるようになります。
たとえば「なぜ、この本が好きなのか」を説明するとき、「なんとなく」ではなく「主人公の、このような性格に共感できたから」「困難を乗り越えていく場面が感動的だったから」など、具体的な理由を挙げられるようになります。
また、学級会で話し合うとき、「◯◯がいいと思います。なぜなら〜だからです。こうすれば、〜というメリットがあります」と、根拠や理由を示しながら、自分の意見を分かりやすく述べることができるでしょう。
自分の考えを筋道立てて言葉にすることができると、相手に自分の意図がしっかりと伝わり、コミュニケーションがスムーズになります。将来、社会に出てからも、自分の考えを論理的に伝える力は大いに役立つでしょう。
相手の気持ちや考えをより深く理解できる
論理的思考力を身につけると、物事を多角的に見る力が養われるため、相手の気持ちや考えをより深く理解できるようになります。
たとえば、友達が悲しんでいるとき、「なぜ悲しいのか」「それが起きたとき、どのような気持ちだったのか」といった視点に立つことができるので、相手の気持ちに寄り添えるようになるでしょう。
また、議論の場面で意見が対立したときに、「なぜ、その人はそう考えるのか」「どんな経験や価値観がベースにあるのか」といった、相手の意見の背景を考えることができ、合意形成のポイントを見つけやすくなります。単に「正しいか間違っているか」という二択ではなく、多様な考え方があることを客観的に理解できるようになるのです。
このような共感力や理解力は、学校での人間関係を良好に保てるだけでなく、社会に出てからも、他者と協力して物事を進めるうえで非常に重要な力となるでしょう。論理的思考力は、人との関わりを円滑にするための大切な力であり、高い問題解決能力にもつながるのです。
論理的思考力は「生きる力」の基盤であり、学校生活から将来の社会生活まで、子どもたちの可能性を大きく広げてくれるでしょう。
論理的思考力を育てる日々の授業づくりのヒント
論理的思考力は、特別な授業だけでなく、日々の教科授業の中でも少しずつ育んでいくことができます。授業の基本的な流れの中に、論理的思考力を育てる工夫を意識的に取り入れてみましょう。
ここでは、授業の「導入→展開→振り返り」という各場面でできる工夫の、具体的なヒントを紹介します。
「導入」で知的好奇心を引き出す
授業の導入は、子どもたちの知的好奇心を引き出し、主体的に考える姿勢を育むための絶好の機会です。さまざまなことに疑問を持つことが論理的思考の第一歩なので、導入でそのための工夫をしましょう。
知的好奇心を引き出す導入にするためには、効果的な方法をいくつか取り入れることが大切です。
▼具体的な「導入」の例
- 理科「磁石」:磁石にくっつくものと、そうでないものがあることを、実際に体験的に確認させる。
- 社会科「工業」:「国内の自動車会社が世界で販売台数1位」という事実を提示する。
- 算数「かけ算」:教室の窓ガラスの数に着目させ、効率よく数える方法を考えさせる。
▼知的好奇心を引き出す「導入」のポイント
- 予想に反するような意外性や、新鮮さのある事実・現象を提示する。
- 子どもたちの日常生活と結びつきのある問題を取り上げる。
- 「なぜ?」と考え、より深く知りたくなるような謎や矛盾を提示する。
- 実際に物を見せる、体験してもらう、などを通して感覚的に理解させる。
ひと工夫した魅力的な導入は、単に「今日は〇〇について学びます」と伝えるよりも、子どもたちの思考を活性化させ、「調べたい」「解決したい」という内発的な動機づけにつながります。子どもたち自身が問題意識を持って授業に臨むことで、より深い思考へと導かれるのです。
「展開」で深い思考力を身につける
授業の展開部分は、子どもたちがワクワクしながら考えを深め、自分の言葉で論理的に表現する力を育てる貴重な時間です。子どもたちの思考を促進するためには、いくつかの効果的なアプローチがあります。
▼論理的思考力を育む「展開」でのアプローチ
- 子どもの発言に対して「どうして、そう考えたの?」と根拠を問う。
- 「具体的に説明してくれる?」と、詳細を引き出す質問をする。
- 異なる意見や視点を意図的に取り上げ、多角的な思考を促す。
▼「展開」部での効果的なディスカッション活動のポイント
- 賛成・反対だけでなく、「なぜ、そう思うのか」の理由を述べるルールを設ける。
- 相手の意見を「〇〇さんの意見は、〜ということですね」と要約してから、自分の意見を述べる。
- 根拠となる事実と、自分の主観的な考えを、区別して説明する練習をする。
特にディスカッションの場面では、必ず「私は賛成です。なぜなら〜だからです」と、根拠を示すことを習慣づけましょう。理由を分かりやすく言葉で伝える練習を重ねることで、子どもたちの論理的思考力が育まれていきます。
「振り返り」で言語化する能力を高める
授業の最後の「振り返り」は、学んだことを整理し、自分の考えを言語化するための大切な時間です。子どもたちが自分の考えを明確に言語化できるようになるには、そのための具体的な問いかけや、書き方のモデルを示すことが効果的です。
子どもたちが言語化に取り組みやすい仕掛けを用意することが、有意義な振り返りのためのポイントになります。
▼具体的な「振り返り」の例
- 理科の実験後:「予想と結果が違った。それは〜という理由からだと考えられる」
- 社会科の調べ学習後:「調べる前は〜と思っていたが、学習後は〜と考えるようになった。これは〜という事実を知ったからだ」
▼効果的な「振り返り」活動のポイント
- 「今日学んだこと」や「疑問に思ったこと」を具体的に書かせる。
- 「〇〇がわかった。なぜなら△△だからだ」という書き方を習慣づける。
- 授業の前と後での、自分の考えの変化を意識させる。
- 学んだことを、自分の生活や経験と結びつけて考えさせる。
効果的な振り返りを積み重ねることで、子どもたちは自分の思考を整理し、筋道立てて言葉で表現できる力を身につけていくでしょう。振り返りは、単なる授業の締めくくりではなく、論理的思考力を育てる重要な活動になります。
日々の授業の中でも、小さな工夫を積み重ねることで、子どもたちの論理的思考力は着実に育まれていくでしょう。
授業以外でも!学校生活の中で論理的思考力を育てる
学校での論理的思考力の育成は、授業の時間だけに限られるものではありません。授業以外の学校生活の時間も、有効的に活用することができます。たとえば、給食の時間、休み時間、清掃の時間など、日常の学校生活のあらゆる場面が論理的思考力を育む機会となります。
ここでは、授業以外の場面で論理的思考力を育てるための工夫を紹介します。
日常会話を通して論理的思考力を育てる
子どもたちとの何気ない会話も、論理的思考力を育む貴重な機会です。日常会話の中で簡単に実践できる工夫の例を紹介します。
▼具体的な言葉で表現させる
- 「どうして、そうなったの?」という問いで、起きたことと具体的な原因・根拠との因果関係を、子どもの言葉で説明してもらう。
- 「具体的には?」という問いかけで、イメージや漠然とした内容を、より具体的な言葉で明確に伝えるよう促す。
▼非言語的な「感覚」を言語化させる
- 「今日の給食おいしかった!」→「何がおいしかったの?」「どんな味がしたの?」
- 「図工の時間が楽しかった!」→「どんなところが楽しかった?」「何をしているときが一番楽しかった?」
読書をしやすい環境づくりで論理的思考力を育てる
読書は、論理的思考力を育む最も効果的な方法の一つです。以下に、クラスですぐに取り入れられる読書環境づくりのアイデアを紹介します。
▼読書の習慣化につながる時間の確保
- 授業前に毎朝の読書タイムを設定して、読書習慣の定着を図る。
- 週に一度は、15分以上、30分以上など一定の時間を決めて、家庭学習に読書の時間を設定する。
▼多様な本や、読書の機会・手段へのアクセスを促す
- 学級文庫に、子どもたちの個々の興味を考慮した、さまざまなジャンルの本を揃える。
- 学校図書館だけでなく、地域の図書館の活用方法も定期的に紹介する。
▼読書体験の共有
- クラスでブックトークの時間を設け、自分が読んだ本、好きな本の魅力を伝え合う。
- 教室内に「おすすめの本」を紹介し合うコーナーを作る。
日常の何気ない場面も、意識の向け方や工夫次第で、自然と成長できる学びの機会になります。
朝の会・帰りの会でできる!論理的思考力を育てるゲーム
毎日の朝の会・帰りの会の活動を通じても、論理的思考力を育むことができれば、さらに子どもたちの成長を促すことができます。
楽しみながら思考力を鍛えられるゲームを取り入れることで、子どもたちの論理的思考力を無理なく育てられます。ここでは、すぐに実践できる簡単なゲームを紹介します。
ノーカタカナゲーム
カタカナ語を使わずに、ある言葉(お題)について説明し、それが何かを当てさせるゲームです。ノーカタカナゲームを通して、言い換えに必要な表現力・言語力や、物事の本質を捉える力が自然と身につきます。
【遊び方】
- お題のカタカナ語を決める。(例:「テレビ」など)
- カタカナ語を一切使わずに、お題のものを言葉で説明する。
- 聞いている人が正解を答えられれば成功。
【例】お題が「スマートフォン」の場合
・ダメな説明の例:「メッセージのやり取りをしたり、動画を見たり、ゲームをできる、電話」(メッセージ、ゲームというカタカナ語を使っているので✕)
・良い説明の例:「平たくて写真も撮れて、指で触って操作する、人と話をするための機械」
マジカルバナナ
「マジカルバナナ」は、言葉の連想ゲームです。連想される言葉を、一人ずつ順番にリレーのように答えていくことで、思考の流れや言葉同士のつながりを客観的に意識する力が育まれます。クラス全体で行うと、一人ひとりの発想・考え方の違いや共通点を発見する楽しさも味わえます。
【遊び方】
- 最初の人が「マジカルバナナ、バナナといったら?」と質問する。
- 次の人は、バナナから連想した言葉を答える。
- 2.の人の答えから連想した言葉を、さらに次の人が答える。このようにして、順々に連想の輪をつないでいく。
【例】
A:「マジカルバナナ、バナナといったら?」
B:「バナナといったら黄色、黄色といったら?」
C:「黄色といったら○○、○○といったら?」 …以下、続く
すぐにできる言葉遊びゲームでも、楽しみながら思考力を鍛え、論理的に考えるコツを身につけられます。
始めてみよう!論理的思考力を育む環境づくり
この記事では、学校教育における「論理的思考力」の基本的な位置づけから、日々の授業や日常生活に取り入れられる実践的な育成方法まで、具体的に紹介してきました。
論理的思考力を育む環境づくりは、決して特別な準備や活動を必要とするものではありません。通常の授業や学校生活のさまざまなシーンに、今できる工夫を少しずつ取り入れていくだけでも、子どもたちの論理的思考力は着実に育まれていきます。まずは、気負わずに無理のない範囲で、できることから始めてみましょう。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。