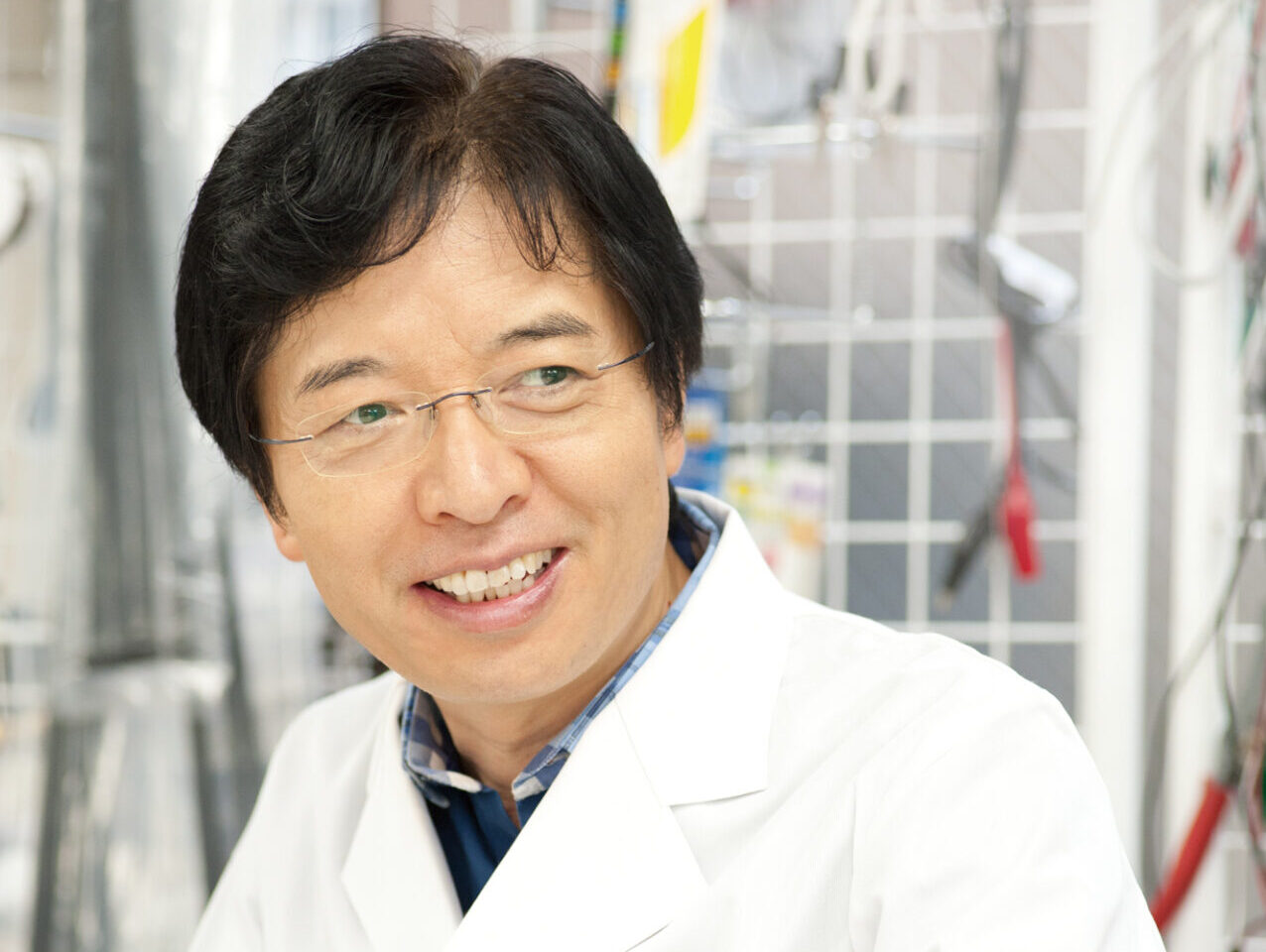目次
「子どものコミュニケーション能力を上手に育てる良い指導法は?」
「SSTを取り入れて、子ども同士のポジティブな関係づくりを効果的に支援したい」
小学生の学級内でよく見られる、児童同士のトラブルや、遊びの輪に入っていけない子どもたち。児童の人間関係づくりを支援したいけれど、具体的にどうすればいいのか悩んでいませんか?
この記事では、小学校低学年に向けた、教室ですぐに実践できるSST(ソーシャルスキルトレーニング)の方法を、わかりやすく解説します。
子どもたちが楽しみながらコミュニケーション能力を高められるゲームや活動例も豊富に紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
子どもたちにSSTが必要な理由とは?コミュニケーションの3つの課題
小学校低学年の子どもたちを見ていると、「どうして、そんなことで喧嘩になるの?」「なぜ相手の気持ちを考えられないの?」と思うことがありますよね。そんな子どもたちが抱える3つのコミュニケーション上の課題について、見ていきましょう。
自己中心的な考え方
小学校低学年の子どもたちは、自分の視点から物事を見ることが中心で、他者の立場に立って考えることがまだ難しい段階にあります。
- 「自分が使いたい物を友達が使っている」という状況で、「自分が使いたいから返して」と一方的に要求してしまう
- 「自分はそう思っているから、相手も同じように考えているはず」と思い込んでしまう
このような自己中心的な考え方が原因で、コミュニケーションがうまくいかず、トラブルになることがあるのです。
発達途上な感情コントロール
小学校低学年の子どもたちは、感情のコントロールが発達途上です。また、言葉で的確に感情を表すための言語化スキルも未熟です。そのため、自分の中に生まれた感情をうまく処理できず、集団の中で好ましくない行動をとってしまうことがよくあります。
- 悔しさや怒りといった感情を言葉でうまく表現できず、泣いたり、相手を叩いたりといった行動で表してしまう
- 勝敗のつく場面で、負けたときの悔しさをコントロールできずに、ルールを無視したり、「もうやらない」と投げ出したりしてしまう
このような感情コントロールの未熟さが、集団生活の中でトラブルを引き起こす要因の一つとなっています。
未熟な言語コミュニケーション能力
小学校低学年になると語彙も増え、言語能力は急速に発達しますが、まだまだコミュニケーションとしての表現力は未熟です。「言いたいことがあるのに、うまく言葉にできない」という状況はよく見られます。
- 友達に何か貸してほしい場面でも頼むことができない
- 「一緒に遊びたい」という気持ちがあるのに、声をかけられない
このような言語コミュニケーション力の未熟さゆえに、意思の疎通が難しく、誤解を生んでトラブルになることがあるのです。
まずは、子どもたちの抱える発達段階ゆえの課題を整理しましょう。
すぐに効果を実感!小学生向けSSTの基本と魅力
SSTは、小学校低学年の子どもたちが抱えるコミュニケーション上の課題に対して、効果的なアプローチとなります。ここではSSTの基本概念と、実際に取り入れることで得られる魅力的な効果について解説します。
SSTって何?初めての先生でもわかる基礎知識
SS(ソーシャルスキル)とは、対人関係を円滑に進めていくために必要な能力のことです。
具体的には、相手の行動や気持ちを理解したり、それに応じて自分の行動を適切に調節したりする力を指します。例えば、「あいさつをする」「順番を守る」「友達の話を最後まで聞く」といった行動が含まれます。
このソーシャルスキルは、生まれつき備わっているものではなく、家庭や学校などさまざまな場面での経験を通して、学習・獲得していくものです。そして、ソーシャルスキルは適切なトレーニングによって向上させることができるという考え方に基づいているのが「SST(ソーシャルスキルトレーニング)」です。
SSTの特徴は、単に「こうすべき」と教えるだけではなく、具体的な場面を設定したロールプレイや、助け合いながら作業を進める共働行動などを通して、実践的にスキルを身につけていくことにあります。「知っている」から「できる」へと橋渡しをする学習方法といえます。
なお、主なSST活動の方法には、ディスカッションやゲーム、ソーシャルストーリー(日常の中で出合う社会的な場面でのルールや適切な行動などを分かりやすく説明する絵カードや短い文章)の使用などがあります。
小学校低学年におけるSSTの効果とは?
SSTを小学校低学年のカリキュラムに取り入れることで、子どもたちへのさまざまな効果が期待できます。
▼コミュニケーション能力の向上
「相手の気持ちを考え、行動する」「自分の気持ちを適切に伝えられる」「よい友達関係をつくり、維持するために動く」といった対人スキルが身につくことで、人間関係のトラブルが減少します。
▼自己解決能力の向上
日常生活において困った場面でどう対処すればよいか、具体的な方法を学ぶことで社会的スキルの基本が身につき、小さな問題は自分たちで解決できるようになっていきます。
▼授業参加度の向上
「発表の仕方」や「質問の仕方」などのスキルを身につけることで、授業への積極的な参加姿勢や自発的な発言が促されます。
▼学級全体の雰囲気の改善
お互いを認め合い、一致協力する経験を通して、クラスの一体感や仲間意識が高まり、「居心地の良いクラス」という感覚を子どもたちが持てるようになります。
実践的な体験を通して「知る」から「できる」へと導くSST活動は、子どもたちの社会的スキルを育て、より良い学校生活につながります。
明日から使える!小学生向けSST実践の基本ステップ
ここでは、小学校低学年への指導にSSTを効果的に取り入れるために、まず導入すべき基本スキルと、実施の具体的なステップについて解説します。子どもたちの発達段階に合わせた取り組み方を知り、明日からの実践に役立てましょう。
低学年向けSSTの柱となる基本スキル
小学校低学年の子どもたちに対するSSTでは、まず、日常生活にすぐに取り入れられる基本的なコミュニケーションスキルとして、以下の3つを柱にして進めるとよいでしょう。
▼「ありがとう」の言葉で感謝を伝える習慣を身につける
友達や先生に何かしてもらったとき、すぐに「ありがとう」と言えるようになることを目指します。
▼「ごめんなさい」の理由と向き合い、適切な謝罪ができる
自分の言動が相手を傷つけたり困らせたりしたときに、素直に謝れるようになることを目指します。
▼「まあいいか」とこだわりすぎない柔軟性を身につける
小さなことや、勝ち負けにこだわりすぎず、「まあいいか」と受け入れられる柔軟性を身につけることを目指します。
これらの基本スキルは、子どもたちが日常生活でよく直面する場面に直結しているため、すぐに実践できる機会が多く、効果も実感しやすいでしょう。
教師が押さえておくべきSST実施の5つのステップ
SSTを効果的に実施するためには、以下の5つのステップを順に進めていくとよいでしょう。どのスキルを教える場合でも、この流れを意識することで、子どもたちの学びが深まります。
- 教示:目標と意義の説明
まずは、これから学ぶスキルについて、何を、なぜ学ぶのかを、子どもたちにわかりやすく説明します。 - モデリング:具体例の提示
次に、そのスキルがどのように使われるのかを、具体的な場面を通して示します。 - リハーサル:練習
子どもたち自身がスキルを練習する時間を設けます。ペアやグループでのロールプレイが効果的です。「遊びに誘ってもらった場面」など、具体的な設定を与えると練習しやすくなります。 - フィードバック:適切な評価と修正
練習後は、良かった点を具体的に褒め、改善点があれば優しくアドバイスします。子ども同士でも感想を伝え合うと、多面的な気づきが生まれます。 - 定着化:日常生活への応用
最後に、学んだスキルを実際の日常生活で使えるように促します。
まずは3つの基本スキルを5つのステップで丁寧に指導することで、子どもたちの社会性が自然と育まれ成長につながります。
教室で楽しく実施!小学生向けSSTゲーム3選とその効果
ここでは、教室ですぐにできる3つのSSTゲームを紹介します。紹介するゲームは準備も簡単で、朝の会や帰りの会、ちょっとした時間にも取り入れやすいものばかりです。さらに、各ゲームがどのようなスキル向上につながるのか、効果についても解説します。
「ま、いいか どんじゃんけん」
「ま、いいか どんじゃんけん」は、勝ち負けを経験しながらも、柔軟な心を育てるのに最適なゲームです。
【準備するもの】なし
【ゲームの進め方】
- クラスを2チームに分け、チームごとに教室の両端に並ばせる
- 各チームから1人ずつ、中央に向かって歩く
- 途中でぶつかったら、じゃんけんをする
- じゃんけんに勝った人は、相手陣地に向かって進み続ける
- 負けた人は自分のチームに戻り、次の人がスタートする
- 先に相手の陣地(ゴール)に到達したチームの勝ち
【ポイント】
このゲームでは、勝ったときには「やったー!」と1度だけ言う、負けたら「オーマイガー」「ま、いいか」と言うなど、適切な表現方法を事前に決めて共有しておくことがポイントです。特に、負けたときの気持ちの切り替え方や、勝ったときの謙虚な態度など、学校生活のさまざまな場面で必要なスキルを楽しみながら学べるのが魅力です。
「仲間で集まれ」
「仲間で集まれ」は、非言語コミュニケーションのスキルを高めながら、他者理解を深めるのに役立つゲームです。
【準備するもの】テーマカード(なくてもよい)
【ゲームの進め方】
- 教室内をそれぞれ自由に歩き回る
- 先生がテーマを発表する(例:生まれた月)
- ジェスチャーのみで、テーマに沿って自分と同じ属性の仲間を見つけて集まる
- 仲間が全員集まったら、先生が同じ属性の仲間で集まれているかを確認する
- 解散して、また次のテーマで繰り返す
【ポイント】
言葉を使わずに意思疎通することが、このゲームの肝となる点です。ゲームを通して、子どもたちは非言語表現による伝達スキルを磨くとともに、「自分と同じところ・違うところがある友達」への理解を深めることができます。
「私は誰でしょう?ゲーム」
「私は誰でしょう?ゲーム」は、相手の考えを読み取る力や、的確に質問する力を鍛えるのに効果的なゲームです。
【準備するもの】
お題カード(動物、職業、有名なキャラクターなどが書かれたもの)
【ゲームの進め方】
- 出題者を1人決めて、その子にだけお題カードを見せる
- 出題者は、そのお題になりきる
- 他の子どもたちは制限時間(3分程度)内に、ヒントを求めて出題者に質問する
(「あなたは生き物ですか?」や「食べ物ですか?」のような形式で) - 出題者は「はい」か「いいえ」だけで答える
- 質問を重ねながら、お題を当てる
【ポイント】
質問の仕方にはコツがあります。大きな概念を問うことからスタートし、徐々により具体的な特徴を問う質問へと進めていくことで、答えを絞りやすくなります。ゲームを通して、論理的な質問の組み立て方を自然と学べるように、質問の仕方・内容によっては適切な指導も行いましょう。普段の授業での発言や質問にも生きてくるスキルが身につきます。
遊びを通した学びの場を設けることで、子どもたちは楽しみながら、多様な社会スキルを身につけていけます。
教科と連動!小学生向けSSTを授業に無理なく組み込む方法
普段の授業にSSTを無理なく組み込むことで、時間の有効活用と学習効果の向上を同時に実現できます。ここでは、道徳や国語といった既存の教科学習を活用しながら、ソーシャルスキルを育む方法をご紹介します。
道徳の教材を活用したSST
道徳は、ソーシャルスキルの育成と非常に相性がよい教科です。特に「親切・思いやり」「友情・信頼」といった内容項目は、SSTとの関連が深いものが多いでしょう。
ここでは、謝罪の場面が含まれる教材を活用した例を紹介します。教材を読んだ後のロールプレイの場面で、「ゴリラ」という覚えやすいキーワードを使った謝り方を伝えます。
「ゴリラ」とは、以下の3ステップでの謝罪方法です。
- ゴ:「ごめんなさい」と言葉でしっかり伝える
- リ:「理由を言う」(自分の何がいけなかったのかを伝える)
- ラ:「ラッキーな提案」(これからどうするかを伝える)
このように、単に「ごめんなさい」と言うだけでなく、自分の何がいけなかったのかを相手に伝え、これからどうするかという提案まで含めることで、より効果的な謝罪になります。
子どもたち同士で道徳の教材に出てくる場面をもとにロールプレイをさせることで、実践的な学びにつながります。
国語科「話す・聞く」単元を活用したSST
国語科における「話す・聞く」の学習は、SSTと連動させやすい単元です。スピーチやインタビュー活動、グループでの話し合いなどの学習場面は、コミュニケーションスキルを練習する絶好の機会となります。
以下に、SSTを取り入れた指導の流れの具体例を紹介します。
- 「聞き方」に焦点を当て、良い例と悪い例を、教師が身振り手振りを交えて分かりやすく説明する
悪い例:相手の目を見ない、別のことをしながら聞く、相手の話に反応を返さない
良い例:相手の目を見る、うなずきながら聞く、「へえ」「そうなんだ」などの相づち - 1.を踏まえて、聞き方のポイントを整理する
・手を止めて聞くことに集中する
・体を相手の方に向ける
・相手の目を見る
・うなずきながら聞く
・あいづちをうつ - 聞き方のポイントを意識しながら、実際にペアを組んでインタビュー練習をする
- 実践後に、みんなで「聞き方」について振り返る時間を設けることで、スキルの重要性への理解を深める
このような活動で、国語科の学習のねらいである「適切に表現し、正確に理解する能力」を育てながら、同時にソーシャルスキルとしての「上手な聞き方」も身につけていきます。
既存の教科学習とSSTを効果的に結びつけることで、限られた時間の中でも実践的に社会性を育めます。
時間を有効活用!5分で完結する小学生向けSSTアクティビティ集
「SSTの必要性はわかったけれど、現状では実施する時間がとれない」と感じている先生も多いのではないでしょうか。しかし、授業の導入や帰りの会など、5分程度の時間でも効果的なSSTを実施することができます。
ここでは、短時間で取り組める小学生向けSSTアクティビティを紹介します。日々の学校生活の中で無理なく継続して、子どもたちのソーシャルスキルを着実に育んでいきましょう。
朝の会で使える「表情チャレンジ」
朝の会は、子どもたちの気持ちを整え、クラスの一体感を高める大切な時間です。「表情チャレンジ」は、短い時間で感情表現のスキルを楽しく学べる活動です。
【活動の進め方】
- 教師が「うれしい」「悲しい」などの感情を、少し大げさな表情で表現する
- 子どもたちに、その表情がどんな感情を表しているかを当ててもらう
- 次に、クラス全員でその表情を真似てみる
- 分かりやすい感情から始めて、徐々に「緊張している」など少し複雑な感情も取り入れていく
「表情チャレンジ」を通して、子どもたちは豊かな表情をつくる練習ができるとともに、他者の表情から感情を読み取る力も身につけることができます。
授業の始めに使える「落ちた落ちた」
「落ちた落ちた」は、聞く力と瞬発的な表現力を高める活動です。集中力を高める効果もあるので、授業へのスムーズな導入にもなります。
【活動の進め方】
- 教師が手を叩きながら「落ちた、落ちた」と言い、子どもが「何が落ちた?」と尋ねる
- 教師が「〇〇!」と答える(例:「りんご!」)
- 全員で、答えに合わせたポーズをとる(例:りんごをキャッチするポーズ)
「落ちた落ちた」を通して、相手の言葉をしっかり聞き、すぐに反応するという基本的なコミュニケーションスキルが鍛えられます。
帰りの会で使える「今日のハイタッチ」
一日の終わりの帰りの会で行う「今日のハイタッチ」は、感謝の気持ちを伝えるスキルを育みながら、クラスの結束力も高める活動です。
【活動の進め方】
- 隣同士または班のメンバー同士で向かい合う
今日、相手が頑張っていたことや、してくれてうれしかったことなど、ポジティブな一言を伝える(例:「体育で転んだとき、声をかけてくれてうれしかったよ」) - お互いの言葉を聞いたら、笑顔でハイタッチをする
- 時間があれば、別の友達ともハイタッチを交わす
「今日のハイタッチ」では、「相手の良いところに目を向ける」「感謝の気持ちを言葉で伝える」というソーシャルスキルを実践的に学び、習慣づけることができます。
短時間のアクティビティを日常的に続けることで、無理なくソーシャルスキルが身につき、クラスの雰囲気も友好的になっていくでしょう。
小学生向けSSTの効果を高める!保護者との連携ポイント
子どもたちのソーシャルスキルを効果的に育むためには、学校と家庭の連携も欠かせません。
まず学級懇談会で、現代の子どもたちがコミュニケーション上で抱えている課題を説明しましょう。そのうえで、学校で行っているSST活動の具体的な内容を紹介したり、可能であれば保護者同士でロールプレイを体験してもらったりすることで、保護者たちの理解が深まります。
家庭での協力をお願いする際は、スキルに関する行動を具体的に褒める方法や、トラブル時に子どもを責めるのではなく一緒に問題解決に向き合う姿勢、日常生活でスキルの練習・実践ができる場面の活用法を伝えましょう。例えば、店や公園での順番待ちを通した「譲り合い」の体験、友達の家へ行った際の「あいさつや礼儀」の実践など、日常の何気ない場面がスキルアップにつながることを伝えると効果的です。
また、保護者面談では、学校での子どもの成長の様子を具体的なエピソードを交えて伝えるとともに、家庭での様子も詳しく聞き取りましょう。
このような連携によって、子どもたちはさまざまな場面でスキルを発揮できるようになっていきます。
学校と家庭が同じ方向性でスキルトレーニングに取り組むことで、子どもたちがソーシャルスキルを発揮する場が広がり、さらに成長するでしょう。
すぐに実践!明日からSSTを始めてみよう
ソーシャルスキルトレーニング(SST)は、対人関係を円滑にするスキルを楽しみながら身につける方法です。
この記事では、小学校低学年の子どもたちに向けたSSTの基本と実践方法について紹介しました。
SSTを学校教育に日常的に取り入れることで、子どもたちのコミュニケーション能力が向上し、対人トラブルが減少するとともに、自己解決能力や授業への積極性も高まります。朝の会や帰りの会での短時間の活動、国語や道徳との連携、遊び感覚のあるゲームなど、学校生活のさまざまな場面でSSTを取り入れることができます。
また、子どもたちのソーシャルスキルを効果的に育むには、学校と家庭の連携も欠かせません。懇談会や保護者面談などを通じて、保護者ともSSTの考え方を共有していきましょう。
明日からさっそく、あなたのクラスでSSTを始めてみませんか? 子どもたちの笑顔と豊かなコミュニケーションが、教室をより温かな学びの場に変えていくことでしょう。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。