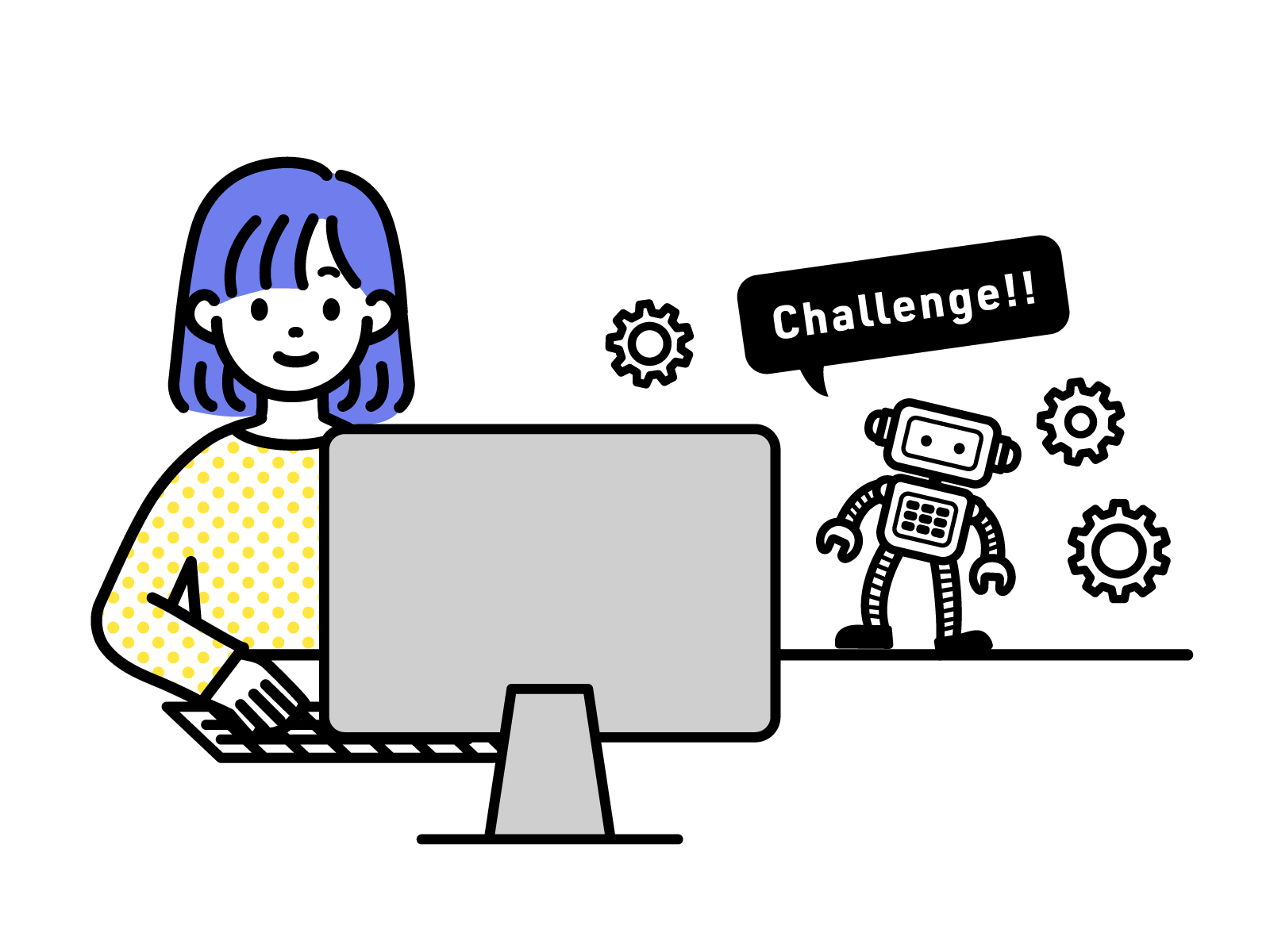目次
「ギャングエイジについて、基本的なことから知りたい」
「ギャングエイジ特有の行動を、見守ってよいのか指導すべきかの判断が難しい」
「ギャングエイジに悩む保護者への、適切なアドバイスや連携の仕方を知りたい」
このようにお悩みの先生方も、いらっしゃることでしょう。
ギャングエイジとは、小学校3年生から高学年までの子どもに見られる、言動が急に変化する時期を指します。発達段階においての特性で、大人より同年代の仲間の考えを重視したり、いつも決まった同性の友達と行動を共にしたりするという特徴があります。また、強い仲間意識ゆえに親への反発が強まったり、友人関係での悩みを持ちやすかったりする時期です。
この記事では、このような「ギャングエイジ」と呼ばれる年頃の傾向について、この時期の子どもによく見られる特性や、教師としての対応の仕方、保護者との連携方法など詳しく解説します。
ギャングエイジとは?
「ギャングエイジ」は、子どもが社会性を形成していく過程での、重要な発達段階の特性の一つです。ここでは、ギャングエイジの特徴が現れる時期、子どもの心理面での変化や行動の特徴など、基本的な知識をご説明します。
ギャングエイジとは何か?
ギャングエイジ(gang age)とは発達心理学や児童心理学の用語です。日本語では「徒党時代」「仲間時代」などといいます。9歳から12歳頃の子どもに現れる変化で、急に保護者や教師から少し距離を置き、言動が従順ではなくなるため、反抗期のように感じられる場合もあります。
この時期の子どもは、同性・同年齢の仲間と強い結びつきを持ち、決まったメンバーと過ごすことで、集団内での連帯・協働を学び社会性の基盤を構築していきます。
親への反抗が強くなる点では、自我が急速に発達する思春期の反抗期と似ていますが、この時期の子どもたちにとっては「仲間意識」が最も重要です。グループ内での同調的な行動を重視し、安心感を得る傾向が特徴的です。
ギャングエイジは、子どもから大人への成長過程のなかで、仲間の影響を色濃く受けながら、社会性や対人スキルを養い成長していく時期といえます。
変化が現れる時期と特徴が見られる期間
ギャングエイジは、一般的に9歳から12歳頃まで続きます。ただし個人差があるため、必ずしもすべての子どもに、ギャングエイジ特有の傾向が見られるとは限りません。
また、近年は以下のような要因から、ギャングエイジ特有の変化が発生しにくくなっています。
- 習い事や塾で予定が埋まり、友だち同士で連れ立って遊ぶ余暇がない
- 学校以外に子ども同士が集まって遊べる場所が少ない
- ゲームや動画配信サイトの視聴など、1人で完結する遊びが増えた
ギャングエイジは、決まった仲間と共に行動し影響を受け合うことで、学校の学習だけでは学びきれない社会性の基盤づくりを体験できる期間です。しかし近年は、子どもを取り巻く環境・社会状況の変化により減少している側面があることも、知っておきましょう。
発達段階としての特徴
仲間との連帯感が大切なギャングエイジの子どもたちには、心理面、社会性、行動において、共通する特徴が現れます。
▼心理面
- 仲間と同じ価値観や共通認識を持ち、一緒に行動することで安心する
- 集団内でのポジションや比較により、自分を客観視する能力が発達する
- 自己肯定感を持つ一方で、劣等感も生じやすい
▼社会性
- 社会や家庭のルールよりも、所属するグループ内の価値観や意見を優先する
- 集団内でのルールを作ったり守ったりするようになり、時に排他的である
- グループ内での自分の役割を認識し、助け合えるようになる
▼行動
- 同性・同年齢の友達同士で特定の小さなグループを作り、行動を共にする
- 親や教師に対して反抗的な態度をとったり、距離を置くようになったりする
- 仲間への過度な同調が悪く作用すると、危険性・反社会性のある行為や、いじめが発生する
これらの特徴は、成長過程の一時期であるギャングエイジならではといえるでしょう。
ギャングエイジは、家庭や大人と距離が生じ、同性・同年齢の仲間との結束や影響力が強まる時期です。
ギャングエイジの具体的な行動
急速に仲間意識が強まるギャングエイジの子どもたちには、特徴的な思考や行動が見られます。ここでは、具体的な行動例を「仲間内での行動」と「大人に対する態度」の2つの側面から説明します。
仲間内での特徴的な行動
ギャングエイジの子どもたちは、所属する小グループ内で特徴的な行動をとります。これは仲間からの影響を受けやすく、同一の価値観や意見を持ったり、一体感ある行動を好んだりする傾向にあるからです。
- 同性の少人数でグループを作り、そのメンバーだけで行動する
- グループ内で独自の言葉や規則を作る
- 価値観の合わない子、同調しない子をグループから排除する
- グループの仲間だけの秘密の共有や、秘密基地作りを楽しむ
ギャングエイジは、親や先生といった身近な大人との関係性から少し距離ができ、年齢や性別といった属性が同じ子ども同士の仲間意識や、自立心が急速に芽生える時期です。そのため、それまでの隣近所や親の付き合いといった家庭的な育成環境主体で作られてきた友人関係が、より自分で選んだ友人関係へと変化します。固定化したグループ内で親密で同調的な人間関係が作られることで、仲間の影響を受けやすく、独自のルールを設定したり、秘密を共有したりすることも少なくありません。
一体感を持って行動するために、グループ内にリーダー的な存在が生まれたり、自分の役割や立ち位置に関心を持つこともあります。ただし、わずかな価値観の相違や行き違いから仲間外れが生じやすいのもこの集団の特性です。
このようにギャングエイジには、子ども独自の社会を形成することで、家庭とは異なる価値観や協調性、対人スキルなどを学ぶ、自立や社会性獲得の準備期間という意味合いがあります。
大人に対する態度の変化
ギャングエイジの子どもは、大人に対する対応が変化します。
これは、子どもにとって、仲間からの承認や評価の方が重要になり、新たな価値観や自立心が芽生えてくるためです。この変化は精神的な発達によるところが大きく、自然な発達段階といえます。しかし中には、大人から見たときに好ましくないと思える言動も見られるようになるでしょう。
- 親や教師の言葉に反発し、自分の意思を優先する
- 仲間の意見やグループ内の価値観を重視し、家庭や社会のルールを無視することがある
- 大人からの指示や干渉、アドバイスを嫌がり、自分で行動を決めたがる
- それまで従っていた習慣や好きだった物事などに、急に否定的になる
幼少期には素直に受け入れていたアドバイスを突然拒否する、口答えや屁理屈が増えて大人に反発する、といった言動が見られるようになります。当然、従順だった子どもの変化に戸惑ってしまう大人も多いでしょう。また、仲間意識を重視しすぎた結果、家庭内の約束を破ったり、社会的に見ると迷惑な行為をしたりすることもあります。
この時期の大人に対する態度には反抗や反発が目立ち、叱っても効果が見られないことが多いので、対応する保護者や教師側も苦慮します。しかし、このような成長過程での変化が、自立した大人に成長していくうえでは重要な現象でもあるのです。
ギャングエイジ特有の大人への反発やルール無視は、仲間意識や自立心の表れなので、逸脱に注意しつつ見守りましょう。
ギャングエイジにおける心理的発達
ギャングエイジの子どもは、同年齢・同性といった属性が同じ仲間と同調し、グループ内で影響を受け合いながら、自立への一歩を踏み出します。このような経験は社会性の基盤を育み、人格形成に不可欠な自己認識力を養う良い機会です。ここでは、心理的な発達面から見た、具体的なギャングエイジの子どもの変化や人格への影響について説明します。
社会性を育む機会としての「居場所」
ギャングエイジは、将来に向けた社会性の基盤を育むチャンスとして捉えることができます。なぜなら子どもたちにとって、仲間同士のグループは大切な「居場所」だからです。そして、決まった仲間と遊びを楽しみながらも、いつしか以下のような過程を通して社会性の基礎を獲得していきます。
- グループ全員で遊ぶために、バラバラの意見を調整してひとつにまとめる
- 意見が割れた場合は、リーダー的な子が仲裁や調整を行い問題を解決する
- 公平に遊ぶためにルールを設定し、全員が認識を共有し、遵守する
この過程には、以下のような心理面での成長要素が含まれています。
- 協調性や共感力の発達
- 集団内での役割についての理解
- 対人関係の問題解決能力が養われる
- ルール作りの必要性や約束を守ることの重要性を学ぶ
また、仲間とのやりとりには、言葉による意思の疎通が必要です。そのため、遊びのなかで自然とコミュニケーション能力を磨いていくことになります。
このように、ギャングエイジのグループ行動は、日常生活や遊びのなかでのやりとりを通じてお互いを認め、影響し合い、時にいさかいを乗り越え絆を深めるという、社会性の基礎を養う学びになっています。
自己形成への影響
ギャングエイジの心理的な発達は、この後に訪れる思春期以後の自己形成にも、大きな影響を与えます。仲間とのやりとりという実体験から学んだスキルが、自然と活かされていくからです。
- 他者との違いに直面して、自己を客観的に見る目が養われ、自己肯定感や自己認識といった自我の確立のきっかけが生まれる
- 仲間内での自他の立ち位置や役割を認識することで、責任感や他人を尊重する気持ちを育む
- 遊びのなかで遭遇する課題やアクシデントに対処し解決する過程を通して、協働性や自主性が発達する
- 仲間との意見の相違や会話から、相互理解や協調性といった社会的スキルを獲得する
こうした経験の積み重ねが、子どもたちの豊かな人格形成の土台を築きます。ギャングエイジにおける仲間との時間は、将来自立した大人として社会で生きていくための基盤となっていくのです。
ギャングエイジ特有の仲間との関わりを通じて、子どもたちは社会的スキルを学び、自己形成や自立に向けた基盤をつくっていきます。
教師に求められる適切な対応とは?
では、日々接するギャングエイジの子どもたちに対して、教師はどのように対応すべきなのでしょうか。集団に対する場合と個人に対する場合に分けて、それぞれへの適切な対応方法を説明します。
ギャングエイジの集団への対応
教師がギャングエイジの子どもたちと接するときは、干渉を抑え、適切な距離感で見守る姿勢を保ちましょう。子どもたちへの過度な介入は、発達段階において必要な成長の機会を奪ってしまう可能性があるため、賢明な対応とは言えません。
例えば、学級内など子どもたちの集団に相対する場合の指導では、以下の点を心がけましょう。
- 「手を離して、目を離さない」くらいの適度な距離感を保ち、自主性を尊重する
- ギャングエイジの特徴がある子にも、そうでない子にも、区別せず公平な態度で接する
- 仲間同士の絆や競争を楽しむ姿など、良い面を具体的に評価する
- グループ内の仲間外れやいじめの兆候が見られた場合は、早い段階で適切な介入を行う
- 学校やクラスのルールを破る、過度ないたずらなどの調和・規律を乱す問題行動や、危険性のある行為には、改善を促す指導を行う
ギャングエイジの子どもたちは、団結によって自信にあふれているものの、行動は未熟です。そのため、つい手助けや注意、介入をしてしまいたくなります。しかし、自らの力で経験を積みながら学んでいるときは、小さなことに神経質にならず、失敗も勉強と捉えるくらいの大きな心で見守ることが、子どもを成長させるでしょう。
ただし、いつ危険性や問題のある事態が起きるかわからない年頃なので、油断はせず、目を離さないことです。とくに、いじめや仲間外れのような初期対応が大事な問題や、非行や事故につながる善悪・危険性に関する指導は、絶対に必要なものです。感情的にならず理性的に、なぜいけないのかをわかりやすく、時間を取って伝えましょう。
個別対応で心がけたいこと
ギャングエイジの子どもに個別に接するときのポイントは、基本的には集団への対応と同じです。
そのうえで、それぞれの子どもの特性・性格を踏まえた柔軟な対応を心がけましょう。
- 自立心・自主性への理解を示し、本人の意思を尊重して指示は最小限にする
- 個別の声かけで「先生は、いつでも見守っている」という姿勢を伝える
- 小さな成功体験や良い行動を具体的に褒め、自己肯定感を後押しする
- 日頃から、子どもが悩みを打ち明けやすいオープンな雰囲気を心がける
- 以前と比べ元気がない、他の子と話をしない、度重なる欠席など、友達間のトラブルのサインに注意する
ギャングエイジは、仲間意識が高まる一方で、友達関係でのトラブルも起こりがちです。日頃から、過度な介入にならない程度に個々の子どもの様子を見るのはもちろん、深刻な事態に発展しないよう、SOSのサインが出ているときはすぐに気づいて迅速に対応できるような関係作りを心がけましょう。
ギャングエイジの子どもの自主性を尊重し、適度な距離感で見守るのが基本ですが、問題行動や深刻なトラブルには迅速かつ適切な介入が必要です。
注意すべきNG指導の例
ギャングエイジの子どもたちへの接し方には、いくつか必要な注意点があります。
この時期の子どもたちは、仲間との関係を通して自尊心や主体性を養っています。そのため指導の仕方を間違えると、その後のアイデンティティの形成や人間関係の構築に、ネガティブな影響を及ぼす可能性があります。
ここでは、配慮が必要な場面や適切な指導方法について、具体例を交えて見ていきましょう。
必要な配慮と避けるべき指導の例
ギャングエイジの子どもたちを指導するときは、この年代ならではの特性への配慮が必要です。子どもの探求心や自立心・自尊心への配慮を欠いたサポートや指導を行うと、せっかくの成長の芽を摘んでしまう可能性があるからです。
具体的に、してはいけないNG指導の例をいくつか挙げてみます。
- トラブルを起こしたグループを強制的に解体する
- グループや個人に対して過度な干渉や管理を行い、トラブルを未然に防止する
- 大人の価値観を押し付けて、個性や大切なものを否定する
- 子どもの気持ちに寄り添わず、力で抑制するなど一方的な指導を行う
子どもから仲間を奪ってしまうと、学ぶ機会を喪失させるだけでなく、子どもたちの安心感の欠如や自尊心の低下など、大きな心理的ダメージの原因となってしまいます。また、大人の価値観の一方的な押し付けは、以後の子どもとの円滑なコミュニケーションの妨げになる可能性があります。
小学校低学年では「大人の指示を守ることで、善悪を判断する力やルールを身に付ける」ことが指導の中心でした。しかしギャングエイジでは、「自分たちで考えて行動するなかで、自ら学びを得る」といった、心理的な成長に配慮した方針で指導することが重要です。
効果的な関わり方と声かけ
ギャングエイジの子どもたちを指導するときに、大切なことが2つあります。「子ども扱いをせず、一人の人間として扱うこと」と「自己肯定感を後押しするポジティブな声かけ」です。具体的には、以下の点を意識してみましょう。
- 対等な立場で対話する
意見や考えを尊重し、一方的に指示するのではなく、対話を心がけましょう。 - 自己決定の機会をつくる
選択肢を提示し、自分で考えて決める経験を積ませることで、責任感と自信を育みます。 - 失敗を成長の機会として扱う
失敗を叱るのではなく、次に活かせる学びとして一緒に振り返りましょう。 - 個性や強みに注目する
それぞれの長所や得意なことを見つけ、それを活かせる場面を作りましょう。 - 信頼関係を築く
約束は必ず守り、子どもの気持ちに寄り添います。
これらを踏まえ、次に効果的な声かけの具体例を挙げます。
▼自主性を尊重する声かけ
「どうやって進めていきたい? あなたのアイデアを聞かせてください」
「自分で考えた方法でやってみて。必要なサポートがあれば言ってね」
▼成長を認める声かけ
「前回よりも上手くなりましたね。一生懸命練習している成果が出ていますよ」
「難しい課題に挑戦する意欲がすばらしい!あなたの成長ぶりが先生も嬉しいです」
▼協力を促す声かけ
「みんなの力を合わせると、もっと良いものができそうですね。どんな方法があるかな?」
「それぞれの得意なことを活かして、チーム全体で目標に取り組んでみませんか?」
▼考える力を育てる声かけ
「なぜそう思ったのか、先生に教えてもらえるかな?」
「他にどんな方法があるか、一緒に考えてみましょう」
▼達成感を共有する声かけ
「最後まであきらめず、見事にやり遂げられましたね!」
「みんなで協力し合って完成させましたね。一人ひとりの貢献があってこその成果です」
子どもへの強制や否定的な対応は避け、一人の個人として尊重した関わり方を心がけましょう。
保護者との効果的な連携方法
ギャングエイジの子どもたちには、教師と保護者の連携による、この時期の特徴を理解したうえでの適切な見守りとサポートが必要です。ここでは、情報共有や協力体制づくりのポイントを説明します。
保護者との情報共有のポイント
子どもにギャングエイジ特有の言動が見られるようになったら、教師は保護者と、この時期の特性に配慮した情報共有を行いましょう。この時期の子どもたちは大人と距離を置きたがるので、様子が見えにくくなりがちだからです。とくに、保護者が子どもの変化に戸惑い不安にならないよう、ギャングエイジについての知識・理解の共有も大切です。
連絡帳やお便り
日常的なコミュニケーションには、連絡帳やお便りを活用します。
前述のように、ギャングエイジは保護者にとって、急に反発するような言動が増え、なんとなく距離をとり始めたわが子の変化に、戸惑いや心配を感じやすい時期です。
「クラスのレクリエーションでリーダーシップを発揮していました」「周りへの思いやりの気持ちが見られます」など、集団で過ごすなかでの良い変化やポジティブな様子を、教師が具体的かつ定期的に伝えると、保護者の安心材料になります。
家庭と密なやりとりをすることで、保護者が悩みを抱え込まず、教師に相談しやすい雰囲気がつくられていくのもメリットです。子どもにサポートすべき問題が起きている場合、深刻な事態になる前に気付けるきっかけになるでしょう。
個別面談
教師と保護者が落ち着いて話す時間を確保できる個別面談は、ギャングエイジの子どもたちを支えるうえで大切な機会です。この時期特有の話題として、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 集団内での立ち位置の変化
- 自己主張・反抗心の表現のしかた
- 家庭と学校での表情や言動の違い
- SNSや友人関係のトラブルの兆候
ギャングエイジの子どもたちは、自己と他者の境界を模索しています。保護者とともに、学校での集団生活と家庭での様子を丁寧に照らし合わせましょう。子どもたちの成長だけでなく小さな変化やSOSを見逃さないよう、学校・家庭の双方が協力して見守る体制を整えておけると安心です。
子どもを守る協力体制の作り方
学校と家庭の協力体制において、とくに大切なことは以下の3つです。
- 子どもにトラブルが起きたときの対応方法や、どこから大人が介入すべきかというポイントを事前に決めておくなど、指導・支援の方針を一緒に考え共有する。
- すぐに変化に気付けるよう継続的に様子を見守りつつ、過敏に反応し合わず、冷静におおらかに構える。
- 急に距離が生じたことで保護者が子どもを過度に心配しないよう、教師から学校での努力や成長の様子などポジティブな要素を伝える。
ギャングエイジは成長に必要な過程であるという理解・知識を、保護者と共有しましょう。
そのうえで、いつでも子どもを支援できる連携体制を整えておきましょう。
教師と保護者の双方がギャングエイジを適切に理解し、密な情報の共有で連携体制を整えておくことは、この時期を乗り越えるための最善策と言えます。
ギャングエイジにおける子どもの成長を支えよう
この記事では、ギャングエイジの子どもに見られる特徴的な行動や、教師としての適切な対応、保護者との効果的な連携方法などについて説明してきました。
ただし昨今、時代・環境の変化により、ギャングエイジの特性が現れない子どもが増えていると言われています。それだけに、特徴が顕著な子を前にして、教師が対応に苦慮する場面もあるかもしれません。
とはいえ、ギャングエイジは人間の発達段階の過程で起こる、自然で必要な変化です。自主性や責任感、アイデンティティの確立など、大人としての社会性の基礎をつくるきっかけともなります。過度に反応せず温かく見守り、必要なときに手を差し伸べることで、子どもの成長を支えていきましょう。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。