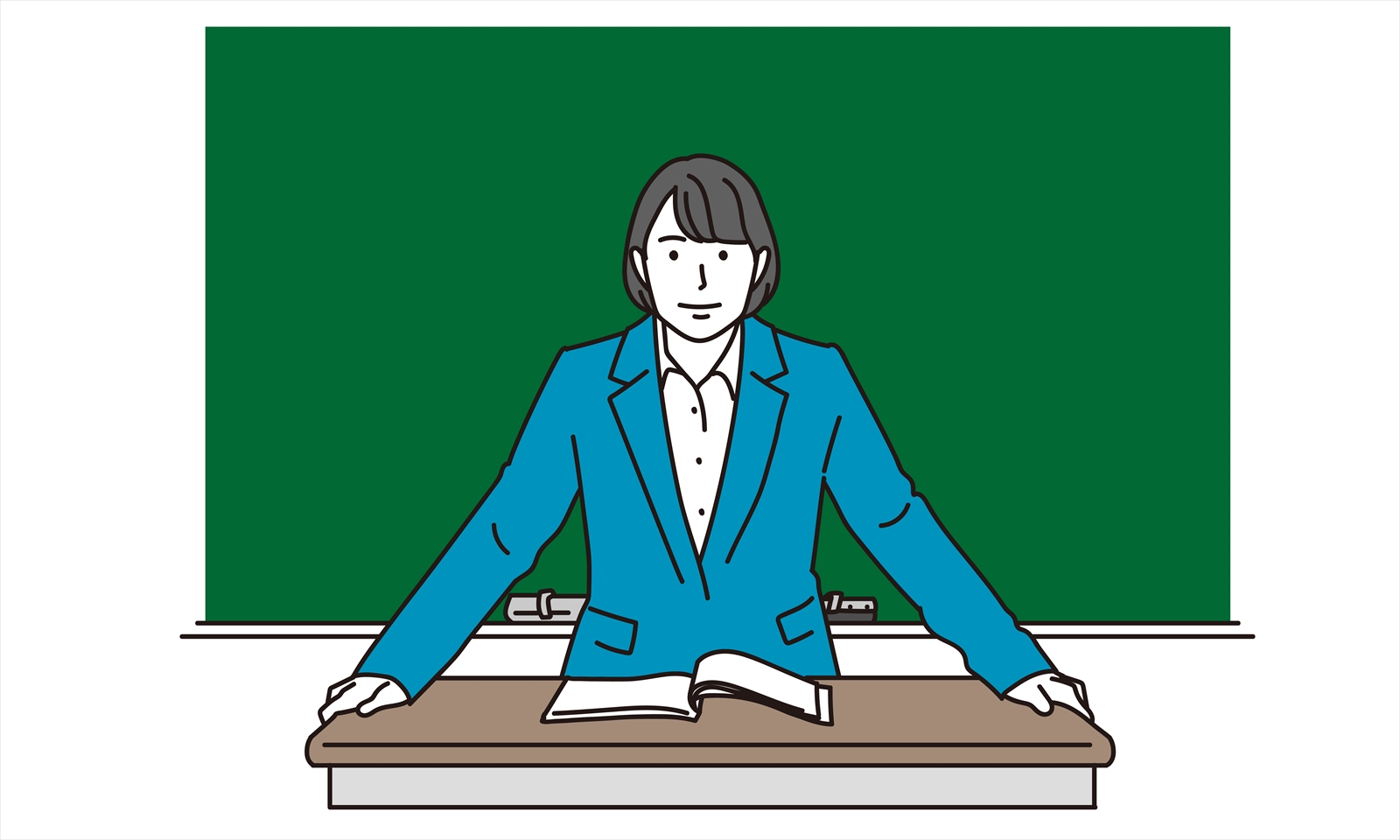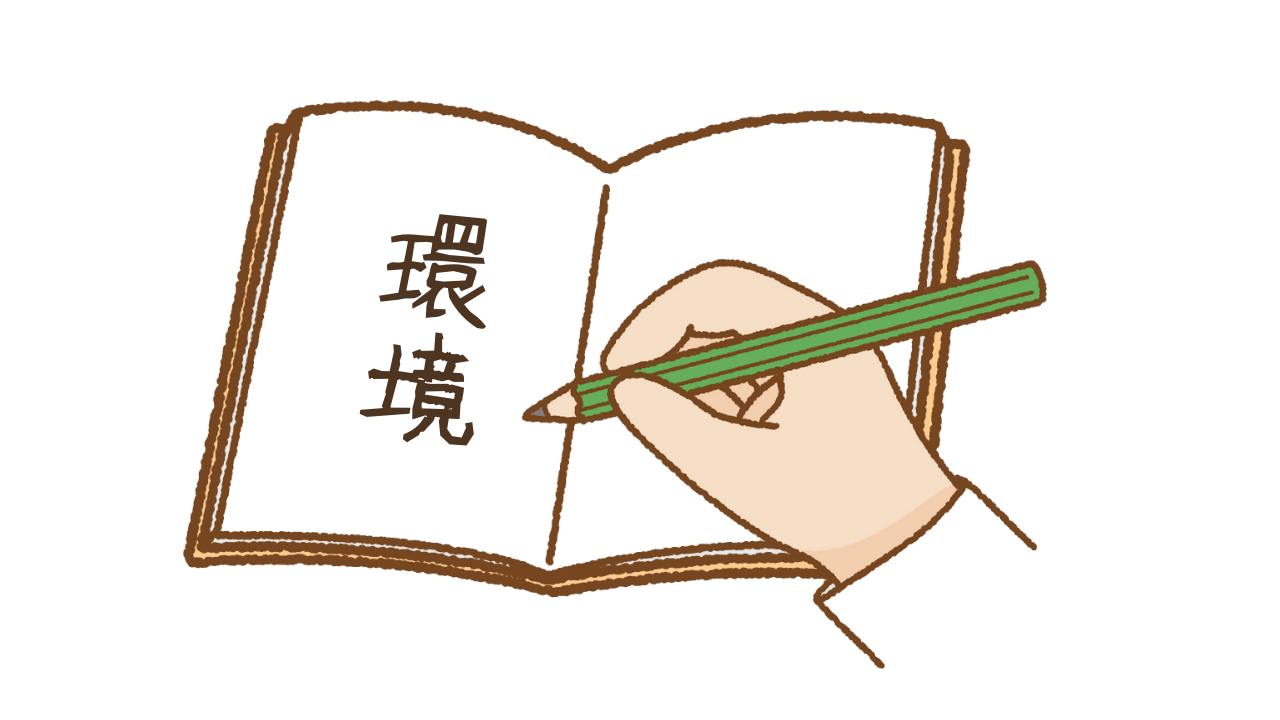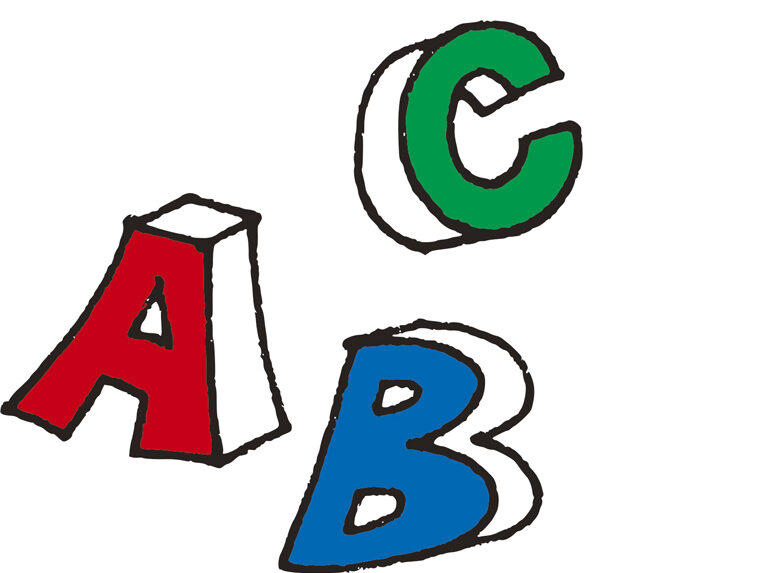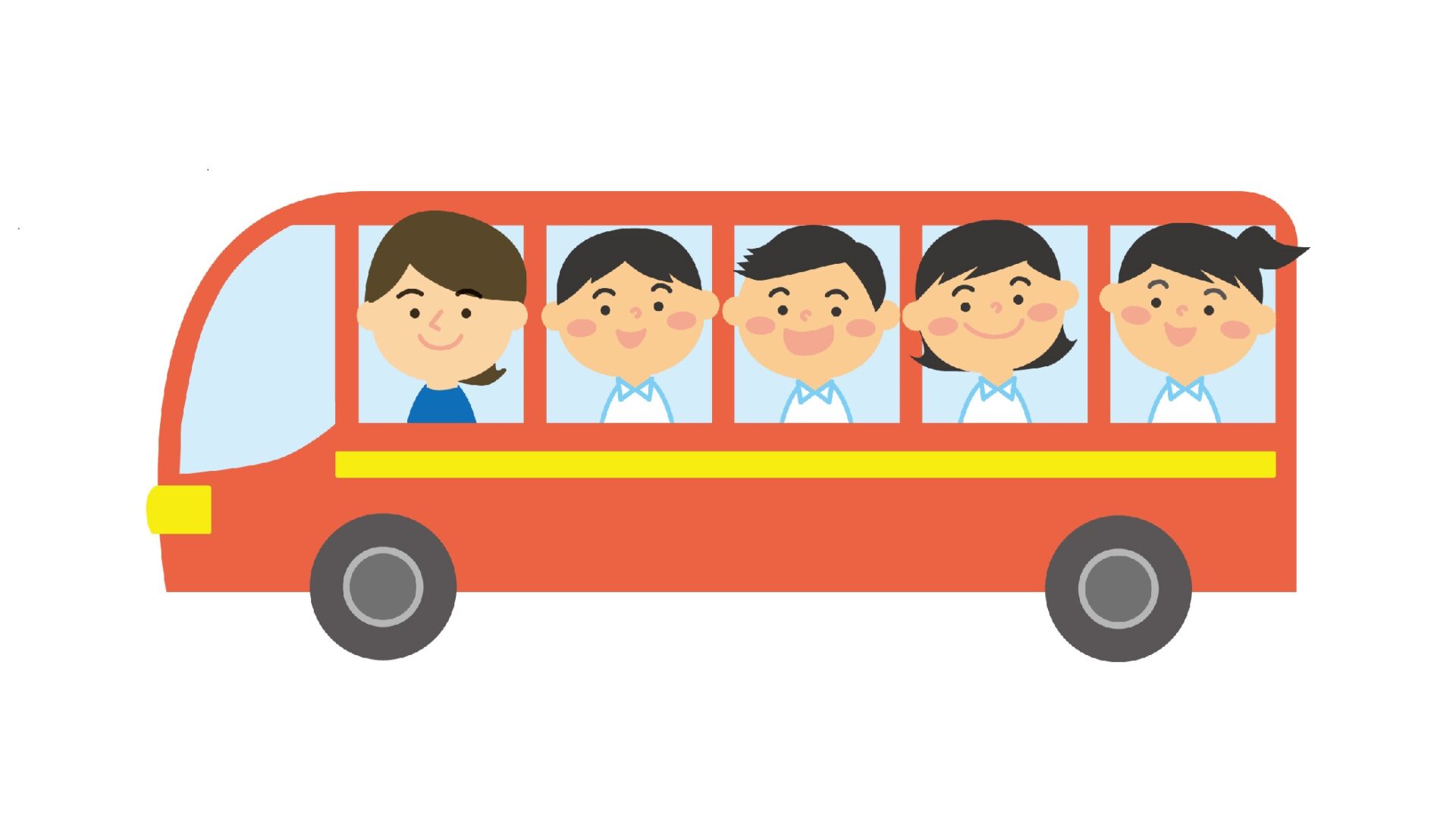目次
「発言する生徒が少なくて、授業がいまひとつ盛り上がらない」
「いつも教師ばかりが話していて、生徒にうまく発言の場をつくれない」
このように悩んでいる先生も、多いのではないでしょうか。
中学生は私たちが思っている以上に、まわりの目を気にしています。授業中に発言することに対して抵抗を感じやすい年頃です。しかし、できることなら生徒には、発言を増やし積極的に授業に参加してほしいですよね。
この記事では、中学生が授業で発言しない理由と、発言が増える授業づくりについて説明していきます。明日から使える「発言を引き出す工夫」も分かりやすく紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
中学生が授業で発言しない4つの理由
まずは、中学生が授業で発言しない理由を見ていきましょう。
授業で発言しない理由は、生徒によって異なります。どの理由があてはまるか、生徒を思い浮かべながら考えてみてください。
人前で話すことに苦手意識がある
生徒が発言をためらう理由として、まず、人前で話すことに苦手意識を持っていることが考えられます。自分に自信が持てず、発言そのものを避けたいと感じているのです。
特に中学生は、学力や精神面の変化が大きい傾向にあるため、まわりと自分を比較して差を感じやすく、劣等感を抱いてしまうことがあります。「自分の考えは、友達よりも劣っているかもしれない」と思い込み、人前に立ったり意見を言ったりすることに抵抗を感じてしまうのです。
こうした生徒にとって、人前で話すことは自分の弱さをさらけ出すことのように感じられて、忌避される場合もあります。
「間違った発言をしたくない」と考えている
「間違えたらどうしよう」と、発言をためらってしまう生徒もいます。自分の考えが先生の求めている正解かどうか、自信が持てず、発言に慎重になってしまうのです。
この背景には、「間違えたら成績が下がるかもしれない」「先生に悪い印象を与えたくない」という、評価を気にする気持ちが隠れていることがあります。先生に「きちんとできる自分」を見せたいという思いが強く、発言に消極的になってしまうのです。
同調圧力を感じている
人前で話すことに抵抗があるわけでも、先生からの評価を気にして慎重になっているわけでもないのに、生徒が発言をためらうことがあります。
その理由は、まわりの空気への敏感さです。中学生は、友人との関係や集団の中での立ち位置をとても気にする年頃です。「他の子が発言しないから、自分もやめておこう」「みんなと違うことを言って、浮いてしまったらどうしよう」といった気持ちから、空気を読んで、あえて発言しない選択をすることがあります。
このような同調圧力の中では、多数派の意見や行動に合わせようとする意識が強まり、目立つ言動はとらなくなります。そのため、本当は意見を持っていても発言しないという状況が生まれてしまうのです。
発言しにくい授業の雰囲気になっている
生徒自身の性格や心理だけでなく、授業の雰囲気や、発言しない授業への慣れが、発言をためらわせている原因の場合もあります。
たとえば、教師が中心となって進める講義形式の授業では、一方的に教師の話が続き、生徒の発言の機会が限られてしまうことがあります。そうなると、生徒が授業を他人事のように感じて、「発言しないのが当たり前」という空気が生まれてしまいます。
このような授業が頻発する環境では、「授業中に話すのは先生だけ」「答えを問われても、発言するのは決まった生徒」といった状態が定着しやすいでしょう。それで、いざ発言を求めても、誰も発言しようとしないという状況になるのです。
発言しない理由は、生徒や授業によって異なります。日々の生活の中で生徒の様子をよく見たり、時には個別に話を聞いたりしながら、発言しない理由を探っていきましょう。
授業で発言を増やすためには「心理的安全性」が大切
授業で発言しない原因は生徒によって異なり、さまざまな要因があることが分かりました。では、どうしたら生徒たちが安心して発言できるようになるのでしょうか。
ここで大切になるのが、「心理的安全性」という考え方です。
発言しやすいクラスになるために必要なのは「心理的安全性」
「心理的安全性」とは、ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授によって提唱された考え方です。「チームの心理的安全性」について、「対人関係においてリスクのある行動をしてもこのチームでは安全であるという、チームメンバーによって共有された考え」と定義しています。これを学校や塾におけるクラスに置き換えると、教室の中で生徒が気兼ねなく、安心して発言できる状態を指します。
心理的安全性が保証された環境では、たとえ失敗したり、答えが間違ったりしても、否定されることはありません。みんなと違う意見であっても、「それも一つの考え方だね」と受け入れてもらえるのです。
そのような環境を教室でつくることができれば、生徒は自分の思いや考えを、安心して口にすることができるようになるでしょう。
「心理的安全性」を高め、安心して発言できる場をつくる方法
では、生徒が安心して発言できる環境をつくるために、教師ができる対応や指導方法を考えていきましょう。
まず意識したいのは、どんな意見も否定せずに受けとめる姿勢です。たとえば、ある意見に対して「そういう見方もあるね」「おもしろい視点だね」といった返し方をするだけで、生徒は「話してよかった」と感じるようになります。
また、クラス全体で「他の人の意見を笑わない」「最後まできちんと聞く」といったルールを共有しておくことも大切です。そして、先生がそのルールを一貫して守る姿を見せることで、生徒同士の中でも自然とその姿勢が育っていきます。
発言を求める前に、生徒に少し考える時間を用意することも効果的です。「急に当てられても答えられないので、当てられたくない」という不安をやわらげ、発言へのハードルを下げることができるでしょう。
こうした日々の積み重ねが、生徒が「発言しても大丈夫」と思える授業づくりにつながっていきます。
「心理的安全性」を高めるために、まずは先生が率先して行動していきましょう。
生徒の発言が増える授業づくりのコツ6選
ここからは、「心理的安全性」をつくり出し、生徒の発言を増やす授業を行うコツを6つご紹介します。ぜひ、日々の授業に取り入れてみてください。
発言に対するハードルを下げる
生徒にとって「これなら言えそう」「なんとなく分かるかも」と感じられる問いかけは、発言へのハードルをぐっと下げてくれます。ちょっとした問いの工夫で、生徒が発言しやすくなる場面をつくり出すことができるのです。
ここでは、発問のねらいや内容に応じて使い分けたい、2つの問い方の工夫をご紹介します。
シンプルに解答できる問い方にする
問いがシンプルであればあるほど、生徒は考えすぎる必要がなく、反応しやすくなります。
たとえば、
- 「AとB、どちらだと思う?」
- 「これはYes? No?」
- 「この中から選ぶとしたら、どれですか?」
このように、選択式の問いにすると答えやすいでしょう。
こうしたシンプルな問いは、授業の導入やウォーミングアップ、確認問題など、正解が明確な場面で使うと効果的です。
生徒の考えを聞く問題にする
一方で、しっかりと考えて答えてもらいたいときには、生徒の考えを問う問題がよいでしょう。
たとえば、
- 「この資料を見て気づいたことは?」
- 「どうして、そう考えたの?」
- 「他には、どんな見方があるかな?」
といった問い方は、正解がいくつも考えられ、人によって異なる回答の仕方になるため、「間違えたくない」と感じている生徒に発言させるには効果的です。
こうした問い方は、考えを深めたい場面や、さまざまな意見を共有したい場面で取り入れると、学びが広がりやすくなります。
ペアトークやディスカッションを行う
「みんなの前で、いきなり発言するのは不安」と感じている生徒も多くいます。そんなときは、ペアやグループで話す時間を設けてみましょう。
たとえば、このような流れが効果的です。
- 教師が問いを提示する(例:「登場人物の気持ちは、どうだったと思う?」)
- ペアやグループで1~2分間、話し合う
- その中で出た意見を、グループの代表がクラス全体に発表する
このように、少人数で話してからみんなの前で発表するという流れをつくることで、いきなり個人に挙手させるよりも、生徒が発言しやすくなります。
また、グループ内でまとめた意見をクラスで共有するという目的の発表であれば、自分一人の考えではないことから自信を持って発表することができ、発言へのハードルはさらに下がります。
適切な声かけで生徒に自信を持たせる
生徒が安心して発言できるようにするためには、教師の声かけがとても大きな役割を果たします。
たとえば、発言のあとに「その意見、素晴らしいね」「いい気づきだね」といったポジティブな言葉をかけるだけでも、生徒は「ちゃんと聞いてもらえた」「認められた」と感じ、自信を持つことができるでしょう。
たとえ答えが間違っていた場合でも、できるだけ肯定的な言葉をかけるように心がけましょう。「惜しい!でも、考え方は合ってるよ」「方向性はすごくいいね、あと一歩だね」といった声かけをすることで、失敗を恐れずに挑戦する姿勢を後押しできます。
どんな発言であっても受けとめてもらい、良いところを褒められることで、生徒の中に「また発言してみようかな」という気持ちが少しずつ生まれていくのです。
指名の仕方を工夫する
発問の内容や授業のねらいに合わせて、指名の仕方を工夫することも、生徒の発言を引き出すポイントになります。
ここでは、4つの指名の仕方を紹介します。
座席の列ごとに順番に当てる
「次の授業では、この列の人から順番に答えてもらうよ」などと、あらかじめ生徒に伝えておきます。明確に自分の番が分かるので、十分な心構えができます。
くじやルーレットを使う
「次は自分かもしれない」という緊張感の中でも、楽しみながら授業に参加できる方法です。当てられてもすぐに解答できるような、シンプルな問題を出題したときに有効です。
割りばしの先に出席番号を書いたくじを用意しておくと、繰り返し使えて便利です!
生徒同士で指名する
「発言した生徒自身が、次に発言する人を指名する」というスタイルです。生徒の考えを述べてもらうような問題のときに試してみましょう。慣れてくると、自然に発言の輪が広がります。
ノートを確認して指名する
授業では発言しない生徒でも、ノートやワークシートにはしっかりと考えを書いている場合があります。机間指導中に、「この考え、すごくいいね。みんなにも紹介してくれる?」とあらかじめ声をかけて、そのうえで指名しましょう。先生からお墨付きをもらえたことで解答に自信を持てるので、安心して発言ができます。
「話す力」を育てる
ふだんから生徒の「話す力」を育てる指導を行うことも、発言を増やすためには効果的です。
たとえば、発言の際に意識するとよいポイントとして、次のようなものがあります。
- 要点を絞って話す
- 短く、簡潔に伝える
こうしたポイントを、繰り返し指導したり、教室内に掲示したりすると、生徒も少しずつ意識できるようになります。
そして、生徒が実際に発言した場合は、たとえうまくいかなかったとしても、みんなに伝えようと頑張った姿勢と意欲を認めてあげましょう。成功体験を重ねて話し方に自信がついてくると、自然と「発言してみようかな」と思える機会が増えていきます。
聴く力を育てる
発言しやすいクラスをつくるには、「話す力」だけでなく「聴く力」を育てることも欠かせません。
他の生徒が発言しているときに、クラス全体が真剣に耳を傾けることで、話す生徒は「聴いてもらえている」という安心感と自信を得ることができます。
また、発言のあとにうなずいたり、「なるほど」といったポジティブなあいづちを返したりするように促すと、相手の意見を尊重する空気が少しずつ育っていきます。
先生が率先してうなずいて反応したり、「いい聴き方ができているね」と声をかけたりすることで、「聴く姿勢」を大事にするクラスの雰囲気がつくられていくでしょう。
生徒が「話す力」を身につけて自信を持って発言できるように、サポートしていきましょう。
特定の生徒しか発言しない?クラス全体の発言を増やす方法
「いつも同じ生徒ばかりが発言しているから、他の生徒にも発言させたい」と考えている先生も少なくないでしょう。
そこでここでは、特定の生徒だけでなく、クラス全体の発言を増やす方法を紹介していきます。
挙手だけじゃない、発言が増える授業参加の方法
発言の多い授業というと、つい誰かが挙手して答えるという場面ばかりをイメージしがちです。
でも、本当に大切なのは、それぞれの生徒が主体的に授業に参加し、自分の考えを持っているかどうかです。挙手して発言する以外にも、意見や考えを表す方法はいろいろあります。
たとえば、以下のような方法です。
- 付箋に意見を書いて、黒板や模造紙に貼って掲示する
- ホワイトボードに解き方や考え方を書く
- タブレットなどの端末や電子黒板といったICTを使って、意見を共有する
こうした方法を取り入れることで、生徒が自分の考えを他の生徒に伝えるハードルを下げることができます。さらには、クラスみんなの考えを視覚的に共有してまとめられるので、学習効果も期待できます。
グループ発表で発言の機会をつくる
「一人で発表するのはちょっと苦手」という生徒にとって、グループ発表は発言へのハードルを下げる手助けになります。
複数人で協力して発表内容をまとめたり、誰がどの部分を話すか分担したりすることで、「一人だけの意見じゃないから大丈夫」という安心感が生まれ、発言に自信を持つことができます。
注目されるのが苦手な生徒でも、「グループの一員として仲間と一緒に発表する」という形式なら、話しやすくなるでしょう。
発言しない生徒への個別対応と声かけ
とはいえ、さまざまな工夫をしても、発言が増えない生徒もいるでしょう。そういった場合は、まず「話したくない」のか「話せない」のかを見極めることが大切です。理由によって、声かけや支援の方法は大きく異なります。
たとえば「話したくない」と感じている生徒には、無理に発言させようとするのではなく、安心して話せる環境を少しずつ整えていくことが効果的です。
一方で、場面緘黙(かんもく)や吃音といった発話に関わる特別な事情がある場合には、本人に無理をさせないことが第一です。こうしたケースでは、担任だけで抱え込まず、他の教員や保護者、カウンセラーなどと連携して対応することが大切になります。
発言が多すぎる生徒への対応
授業中、いつも積極的に手を挙げてくれる生徒の存在は、とてもありがたいものです。しかし、その生徒ばかりが頻繁に発言することで、「発言=その子の役目」になってしまうこともあります。
そんなときは、その生徒の意欲をしっかり認めたうえで、他の生徒の発言も聴きたいという意図を伝えることが大切です。
たとえば、
- 「あなたの意見は、最後にじっくり聞きたいな」
- 「他の人の意見も聞いてみたいな」
といった声かけをすることで、その生徒の意見を尊重しながらも、クラス全体の参加を促すことができます。
こうした対応によって、「一人の意見だけでなく、いろんな考えがあるから授業が深まる」という姿勢をクラス全体に広げていくことができるでしょう。
挙手を促すだけでなく、自分の考えを伝える方法を変えたり、個別に声かけをしたりすることで、クラス全員がまんべんなく発言できる機会をつくっていきましょう。
授業中に発言が増えるとどうなる?生徒の学びとクラスの変化
授業中に生徒の発言が増えると、多角的な視点や自分とは異なる見方・考えを知ることで、生徒の思考が深まり、学びがより主体的になります。だれかが発言するたびに、他の生徒も「自分なら、どう考えるかな?」と頭を動かし、自然と考える時間がクラス全体に生まれていくでしょう。
また、さまざまな意見が飛び交うことで、「違う考えを聞くのもおもしろい」「自分の意見も言ってみようかな」と、生徒たちの間で発言することに対する前向きな雰囲気が広がっていきます。
授業中の発言が増えることで、クラスの一体感や、生徒の主体性が自然と育っていきます。
今日からできる!授業で発言を増やすための実践リスト
ここまでご紹介してきた工夫の中から、すぐに授業に取り入れられるポイントを、実践リストとしてまとめました。
- まずは「どんな意見でもOK」と伝える
- クラスで話を聞くときのルール(傾聴の姿勢、ポジティブな反応)をつくる
- 授業内で発言しやすい質問や問題を増やす
- 挙手発言以外の方法(付箋・ホワイトボード・タブレットの活用)を試す
- ペアトークやグループディスカッションで「少人数のなかで話す」機会をつくる
- 生徒のノートやワークシートをチェックして、指名する
日々の授業でできるちょっとした工夫で、少しずつ発言の多い授業を目指していきましょう。
「授業での発言が多いクラス」は、先生の工夫で実現できる
授業中に発言しない生徒がいても、一概に「意見がない」「やる気がない」ことが理由ではありません。環境や状況が整えば、少しずつ発言できるようになる子はたくさんいます。
先生のちょっとした声かけや、問い方の工夫、クラスの雰囲気づくりといった積み重ねが、生徒の「発言しよう」という気持ちを引き出し、少しずつクラス全体も変化していきます。
生徒が安心して自分の考えを伝えられるようになると、授業の雰囲気はどんどん良い方向へと変わっていきます。発言の多い活発な授業は、先生の手でつくることができるのです。
できることから一つずつ、発言を増やす工夫を取り入れてみてください。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。