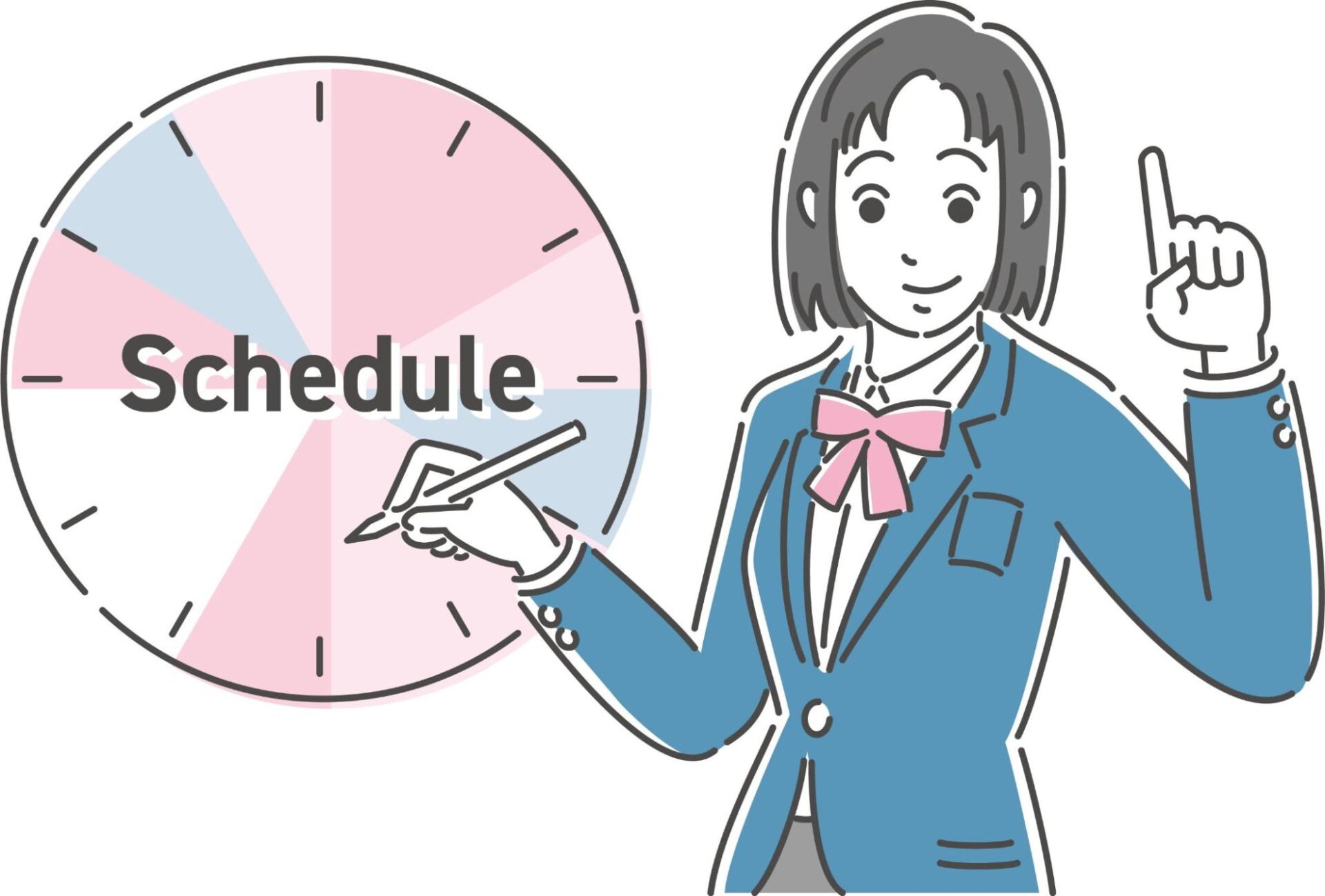目次
「成績がなかなか上がらない…もっと夜遅くまで勉強した方がいいのかな?」
「睡眠時間を削ってもいいから、もっと問題を解きたい!」
「眠っている時間がもったいないと感じてしまう…」
受験勉強が始まると、生徒からこのような声を聞くことが多くなるのではないでしょうか。実際に、睡眠時間を削ってしまい昼間眠くて勉強に集中できていない、という生徒は大勢います。
この記事では、受験生に必要な睡眠時間と、効果的な学習を両立させるためのポイントをご紹介します。体調が万全な状態で受験に臨めるように、生徒たちをサポートしていきましょう。
受験生に必要な睡眠時間とは?
まずは、受験生に必要な睡眠時間を確認しましょう。一般的には、高校受験生は8時間以上、大学受験生は6時間以上必要といわれています。
勉強が大事な時期とはいえ、睡眠時間を削ってまで勉強することは体調を崩す原因になります。ここでは、年齢に応じた必要な睡眠時間の詳細と、睡眠が大切な理由を説明します。
必要とされる睡眠時間
厚生労働省が策定した「健康づくりのための睡眠ガイド2023」によると、小学生は9~12時間、中学・高校生は8~10時間の睡眠時間を確保することを推奨されています。ちなみに、成人の場合は6時間以上が推奨されています。
このように、成長するにつれ、健康の保持に必要な睡眠時間は短くなっていきますが、成長期である高校生までは成人よりも長い睡眠時間が必要です。
とはいえ、これはあくまで指針であり、実際に必要な睡眠時間には個人差があります。推奨されている時間を目安にしつつ、個々に自分が「睡眠で休養がとれている感覚(睡眠休養感)」が持てる時間を確保することが大切です。
※参考:「健康づくりのための睡眠ガイド2023」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/001305530.pdf
健康のために必要とされている睡眠時間を目安にして、自分に合った適切な時間を確保しましょう。
良質な睡眠が学習効果を高める仕組み
良質な睡眠とは、途中で覚醒することなく熟睡できて、起きたときにスッキリしている睡眠のことです。量・質ともに良い睡眠は、学習効果を高めるために不可欠です。
睡眠は、学習・記憶に関して以下のような重要な役割を果たしています。
- 記憶の定着・整理ができる
- 集中力・判断力が増す
- ストレスを解消する効果がある
それぞれの仕組みについて、詳しく説明します。
記憶の定着・整理ができる
良質な睡眠は、学習により記憶した内容の定着を強固にする役割を果たします。暗記で習得した内容も、睡眠時に整理されて、長期記憶として脳に定着するのです。
人間は睡眠中、レム睡眠とノンレム睡眠を交互に繰り返しながら寝ています。
- レム睡眠=体は休んでいるが、脳の活動は起きている状態に近い
- ノンレム睡眠=脳も体も休んでいる
レム睡眠中に、脳は日中の記憶を整理して定着させます。記憶の定着プロセスを十分に機能させるためには、適切な睡眠時間を確保することが重要です。睡眠時間が短すぎると、レム睡眠とノンレム睡眠のサイクルが十分に繰り返されません。とくに、レム睡眠の質と量が低下することで、記憶の定着が不完全になってしまいます。
そのため、暗記を多く含む学習をした日は、しっかりと寝ることが重要です。学習した内容が十分な睡眠を通して記憶にしっかり定着することで、試験問題で出た際に、必要な情報としてすぐに取り出せるようになるのです。
集中力や判断力が向上する
十分な良い睡眠には、集中力と判断力を高める効果もあります。いずれも学習の能率UPに影響するので、睡眠の質を高める工夫をしましょう。
集中力がアップすると、ケアレスミスの防止や試験における正答率の向上につながります。たとえば、長文読解や難解な問題に取り組む際などに、解答に至るまでのスピードやひらめきといったかたちで効果を実感できるはずです。ケアレスミスが減り、点数アップが期待できるでしょう。
ストレスを解消する効果がある
質の高い睡眠は心身をリラックスさせるので、不安感の軽減やストレスの解消が期待できます。逆に、睡眠で休養がとれている感覚(睡眠休養感)が低い人ほど、抑うつの度合いが強いといわれています。
ストレスが溜まっていると、ちょっとしたことで苛立ったり落ち込んだりと、感情コントロールがうまくできず疲れてしまいます。学習にも集中しづらくなり、それによって悩みが増加し、またストレスが増えるという悪循環が起こります。
良質な睡眠をしっかりとって、体も心も回復した状態で勉強に打ち込めるよう心がけましょう。
睡眠中の脳の仕組みを活かして、学習効果を高めるために有効な睡眠を心がけましょう。
受験生のための睡眠の質向上テクニック
生活習慣と質の良い睡眠には、密接な関係があります。睡眠の質を向上させるためには、とくに就寝の時間帯や睡眠をとる環境、寝る前の行動が大切です。具体的には次のような点に注意して、生活習慣の見直し・改善をしてみましょう。
就寝時間と起床時間に気をつける
就寝時間と起床時間は、毎日同じ時間に決めておくのがよいでしょう。休日だからといって夜遅くまで起きていたり、昼近くまで寝ていたりするのは、習慣的な睡眠の質の維持のためにもよくありません。いつもと同じ時刻にアラームを設定する、朝から予定を入れるなどして、休日も早寝早起きの習慣作りを心がけましょう。
早めに就寝するためには、保護者の協力も不可欠です。たとえば塾の講義が遅くまである日は、終了後できるだけすぐに帰宅し、早めに就寝できるようなルール作りや声がけをお願いしておきましょう。また、保護者の就寝時間が遅いと、食事や入浴等の時間が全体的に遅くなり、子どもの就寝時間も遅くなる傾向があります。子ども本人だけでなく、家族みんなの活動時間も同時に見直してみるのがおすすめです。
睡眠環境を整える
睡眠時の環境は睡眠の質に影響を与えるため、つねに整えておきましょう。
睡眠をとる室内ではエアコンや加湿器などを利用して、温度・湿度を快適に保つのがおすすめです。厚生労働省が策定した「健康づくりのための睡眠指針2014」によると、室温の許容範囲は13〜29℃で、寝具内の身体付近の温度は33℃前後がよいとされています。また、室内の湿度は40〜60%を保ちましょう。
さらに、人は寝ている間も汗をかくので、パジャマや肌に触れる寝具類は汗を吸いやすい素材(綿や麻・シルクなど)のものを使うと、心地よく眠れます。
カーテンは遮光機能や遮音機能があるものを利用すると、睡眠の質を高めるのに効果的です。真っ暗な環境で寝るのが不安なら、明るすぎない豆電球や常夜灯などを利用して調整しましょう。また、静かな環境を保てるように、稼働時に音が出てしまう電化製品などは電源をオフにするなどの対策をしましょう。
このように、一人ひとりに合った就寝環境を整え、快適に眠れるような工夫をすることも大切です。
※参考:「健康づくりのための睡眠指針2014」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000047221.pdf
夜更かしを防ぐ工夫をする
睡眠時間の確保と質向上のためには、夜更かしは避けましょう。夜更かしは、習慣になってしまっていることが多いので、就寝の1時間前からは明るすぎる照明を避け、光量を落とした空間で過ごす、(次に詳しく取り上げますが)就寝前にはスマートフォンやPCなどを見ない、といった対策をとるようにしましょう。
就寝前のカフェインの摂取にも注意が必要です。個人差はありますが、体内でのカフェインの効果は平均して4時間程度で薄れるとされています。覚醒作用を考慮すると、コーヒーやエナジードリンク、玉露などのカフェイン含有量が多い飲み物を飲むのは、就寝の4時間前くらいまでにしたほうが、夜更かしを防げるでしょう。
また、適度な疲労は睡眠導入を促すため、日中に軽い運動をするのも効果的です。ただし、寝る直前の運動は入眠を妨げてしまうため、避けるようにしてください。
スマートフォンとの付き合い方を考える
生活に欠かせない存在となっているスマートフォンとの付き合い方も、見直してみましょう。
スマートフォンで閲覧するコンテンツや情報により、頭が冴えてしまい、眠れなくなることもあるでしょう。とくに、見ていた情報が不安や心配ごとにつながると、精神的なストレスになり、睡眠に悪影響を及ぼします。夜は通知をオフにする時間を設定し、就寝の1~2時間前から使用を控えるのがおすすめです。
また、睡眠を促すホルモンであるメラトニンは、就寝の約2時間前から分泌されますが、照明やスマートフォンの画面のような強い光を見るとメラトニンの分泌が抑制され、睡眠への導入を妨げるといわれています。
夜間のスマートフォン使用は控えるとともに、どうしても使用する必要がある場合は、夜モードで画面の光量を調整したり、ブルーライトカット効果のあるフィルムを着けたりして、影響の軽減を工夫することをおすすめします。
「枕元にスマホを置いておくと、ついつい見てしまう」という生徒には、寝ている場所から少し離れた位置にスマートフォンを置いて就寝するよう伝えてみてください。
日頃の心がけ次第で、睡眠の質を高めることは可能です。生活習慣を見直してみましょう!
睡眠時間を確保しつつ勉強を進めるコツ
勉強時間を確保するために睡眠時間を削るのは、効率的ではありません。受験生にとっては健康管理が最も大切だからです。ここでは、健康のために必要な睡眠時間を十分に確保しながら、起きている時間を有効活用して勉強を進めていくコツを紹介します。
日単位・週単位の学習計画を立てる
睡眠時間をしっかりと確保するためには、まず日単位や週単位で大枠の勉強計画を立てましょう。試験日までに学び終えたい学習範囲の進捗状況などを確認しながら、1日ごとに取り組む内容を決めていくと、焦りから睡眠時間を削ってまで勉強をすることも減っていきます。
学習計画の遂行には、毎日の予定と進度の確認に役立つ以下のようなグッズを用意しておくと便利です。
- 書き込みのできるカレンダーやスケジュール帳
- 大きめの付箋
- チェックリスト式のメモ帳
カレンダーやスケジュール帳には、試験の日程や週単位の大まかな学習範囲を記入し、残りの日程と学習科目の配分を調整します。細かなタスクは付箋やチェックリストなどを使って分けておき、完了したらチェックを付けると達成感が得られます。
先生は、生徒が作成した学習計画通りに進められているか、定期的に確認してください。無理のある学習計画を立ててしまうことも睡眠時間を削ってしまう一因となりますから、その生徒の学習スピードやモチベーションにあった計画になっているか、相談に乗ってあげられると良いですね。
優先順位を考えながら時間管理をする
効率よく勉強を進めるコツの一つは、1日の中でもしっかりと時間管理をすることです。日中だらだらと無駄な時間を過ごしてしまわないよう、その日に進める学習範囲の中でも優先順位をつけて勉強を進めましょう。絶対に学習したい内容は日中の早めの時間帯に取り組んでおくと、夜遅くなってから慌てる必要がなくなります。
1日の学習スケジュールは、科目などで時間を区切って立てると、有効な時間管理がしやすくなります。集中力を維持するために、休憩も適度に設定しましょう。
集中力が高い時間帯を効果的に使う
効率よく勉強を進めるためには、集中力が高い時間帯の活用も大切です。1日の中には、集中力が持続しやすい時間帯と、集中しにくい時間帯があります。集中しやすいタイミングとしては、以下を参考にしてみてください。
- 脳も体も疲れていない午前中(起床後2〜5時間)
- 軽い運動後(疲れない程度)
- 仮眠後(30分以内)
とくに重要な内容や苦手科目の学習は、集中力が高い時間帯に取り組むことで能率アップをはかりましょう。
適度な休憩をとる
メリハリをつけて効率よく学習を進めるために、休憩はしっかりとりましょう。一般的に、小学校では1コマ45分、中学校や高校では50分で授業が実施されています。学校の授業時間を目安として、個々の学習も45〜50分ごとに10分程度休憩すると、集中力を維持しやすいでしょう。
また、長時間座ったまま勉強し続けていると、肩こりや頭痛の原因になります。休憩中は深呼吸をしてリラックスしたり、軽い運動やストレッチで体をほぐしたりするのも、効率の良い学習のために有効です。
睡眠時間をしっかり確保するために、一日単位のタスクを効率よく進めましょう!
睡眠についての悩み別対処法
寝つきが悪くて眠りにつくまで時間がかかる、眠りが浅くてすぐ目が覚めてしまう、早寝早起きのリズムに変えたいなど、一言で睡眠に関する悩みといっても、その内容は人により異なります。ここでは、悩みの内容別の対処法を紹介します。
よりよい睡眠で学力アップを目指せるよう、受験生の悩みに寄り添って、一緒に解決策を見つけていきましょう。
寝つきが悪い場合
布団に入ってもなかなか眠りにつけないという場合は、就寝前に血行を良くしたり、リラックスした状態で入眠できるような工夫をしてみましょう。
温かい飲み物を飲む
就寝前に温かい飲み物を飲むと、体が温まり血行が促進されます。体の深部の熱が手足に伝わった後に、ゆっくりと体全体の体温が下がることで、眠りに入る準備ができます。飲み物としてはホットココア、ハーブティー、白湯などがおすすめです。
湯船に浸かって温まる
就寝の1~3時間前に湯船に浸かると、手足の血管を拡張させて血行が良くなり、寝つくまでにかかる時間が短くなります。シャワーだけでなく、湯船につかってリラックスするとよいでしょう。
ヨガやストレッチをする
ヨガやストレッチなどリラックスできる体操をすると、自律神経が整い、寝つきがよくなります。
就寝前は暖色系の照明にする
白色の蛍光灯は、睡眠を促進するホルモンであるメラトニンの分泌を妨げます。就寝前は、暖色の蛍光灯をつけるか間接照明を利用するなどして、光の色や強さを調整すると寝つきがよくなるでしょう。
夜中に目が覚める場合
夜中に目が覚めてしまう理由には、以下のようなものがあります。
- 精神的なストレス(不安や緊張、心配ごと)
- 光や音による刺激
- 尿意
- 寝心地が悪い
- 室温が適切でない
目が覚める原因が部屋の外からの音や光であれば、遮光性や遮音性の高いカーテンを利用したり、寝る位置を調整したりして、快適に眠れる環境をつくることが大切です。
夜中にトイレに行きたくなって目が覚めてしまう人は、就寝前の水分摂取量を控えめにしましょう。前述のようにカフェインを多く含む飲み物には利尿作用があるので、コーヒーや玉露、濃い紅茶などは控え、水や白湯を飲む習慣をつけてみてください。
また、精神的なストレス(不安や緊張、心配ごと)が原因で目が覚める人は、リラックスできるように深い呼吸を心がけます。就寝前に5分間、以下の呼吸法を試してみてください。
- 寝る体勢で、ゆっくりと口から、4秒かけて息を吐きます。
- すべて吐ききったら、次は鼻から、4秒かけてゆっくりと息を吸います。
- このとき、息を吐きながらお腹が凹み、吸いながらお腹が膨らむ「腹式呼吸」を意識します。
- これを1セットとして10回繰り返します。
呼吸法を習慣として取り入れることで、自律神経のバランスを整えられるでしょう。
夜型から朝型の生活に切り替えたい場合
これまで夜型だった人が朝型の生活に切り替えたい場合は、以下のような対策が有効です。
- 少しずつ就寝時間を早める
- 朝日を浴びる習慣をつける
- 夜は徐々に照明を暗くする
生活リズムを一気に変えようとすると、不眠の原因になってしまいます。リズムを変える際には、少しずつ段階を踏みましょう。
また、起床後 2時間以上室内にいると、太陽の光による体内時計のリセットができず、その影響で寝つける時刻が遅れていってしまうという指摘もあります。起きたらすぐにカーテンを開けて太陽の光を浴び、外へ出る習慣をつけましょう。
テスト前の緊張による不眠への対応
テスト前は、緊張やプレッシャーでなかなか眠れないという生徒もいるでしょう。試験に対する不安感が強いと緊張感が高まってしまうので、「これまでがんばってきた自分の努力を信じよう」「今持っている力でベストを尽くせば、大丈夫!」と、日頃の積み重ねを信頼するよう励ましましょう。
一人で不安を抱え込まず、友人や先生、家族などに話して気持ちを共有してもらうことも、心の負担軽減にはおすすめです。具体的に心配な点や思い悩むことがありそうなら、先生への相談を促してみましょう。アドバイスをもらうことで勇気づけられ、緊張の原因解消につながるかもしれません。
睡眠の悩みの裏には、生活習慣や心理的な原因があることが多いもの。生徒に寄り添い、一緒に対策を考えましょう。
自分に合った睡眠管理で受験を乗り切ろう
学習の効果を高めるためには、生徒一人ひとりに合った適切な睡眠が不可欠です。良質な睡眠をとることで、記憶力や集中力をアップさせられます。就寝前はリラックスできるように過ごし、就寝時の環境にも気を配れるような生活リズム、習慣づくりを促していきたいですね。必要な睡眠時間と睡眠休養感には個人差もありますので、生徒に寄り添ったアドバイスを心がけましょう。
睡眠の効果を最大限に活かし、生徒たちが精神的にも身体的にもベストコンディションで受験に臨めるように、睡眠の大切さを伝えていきましょう。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。