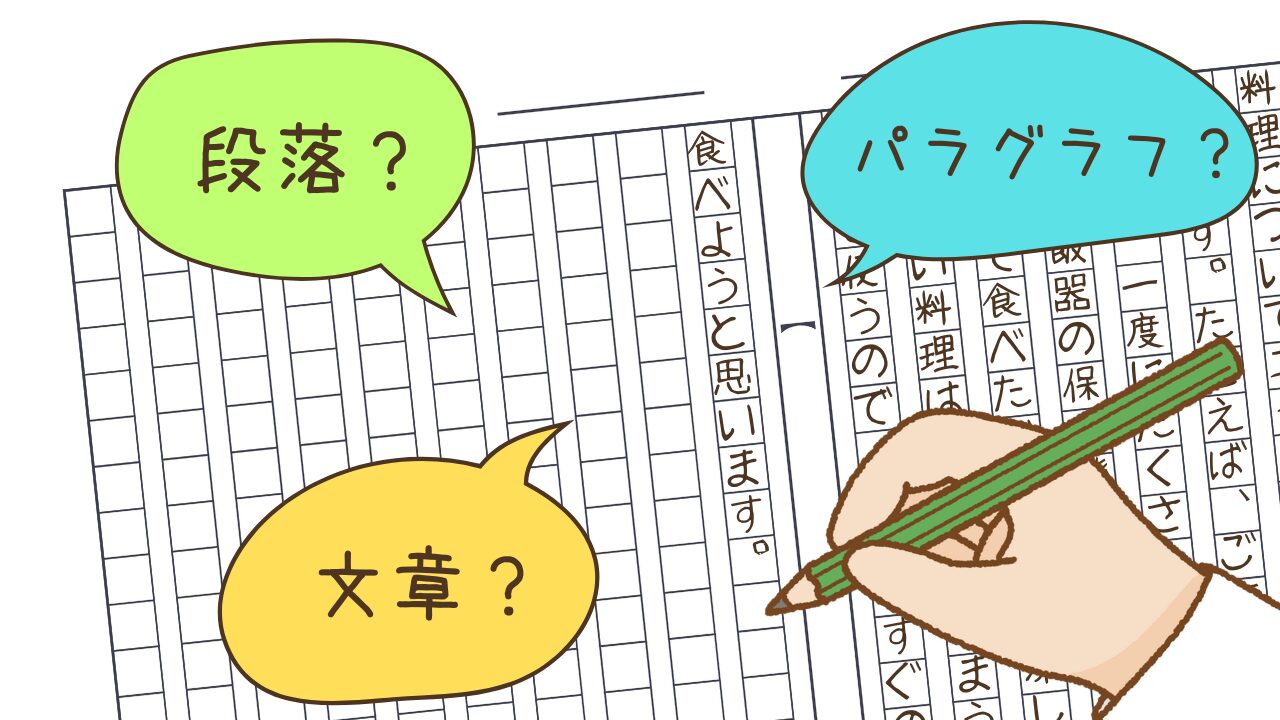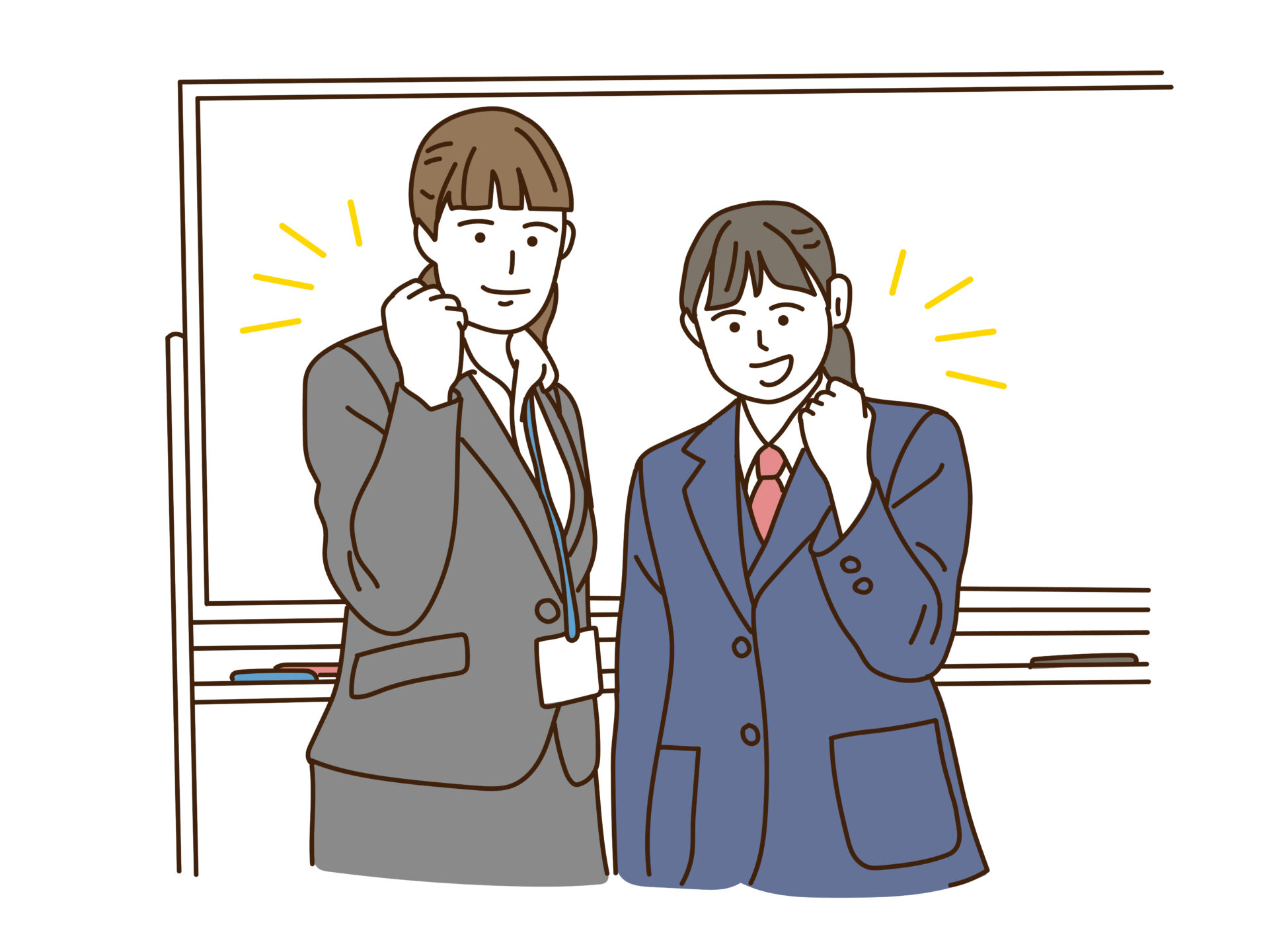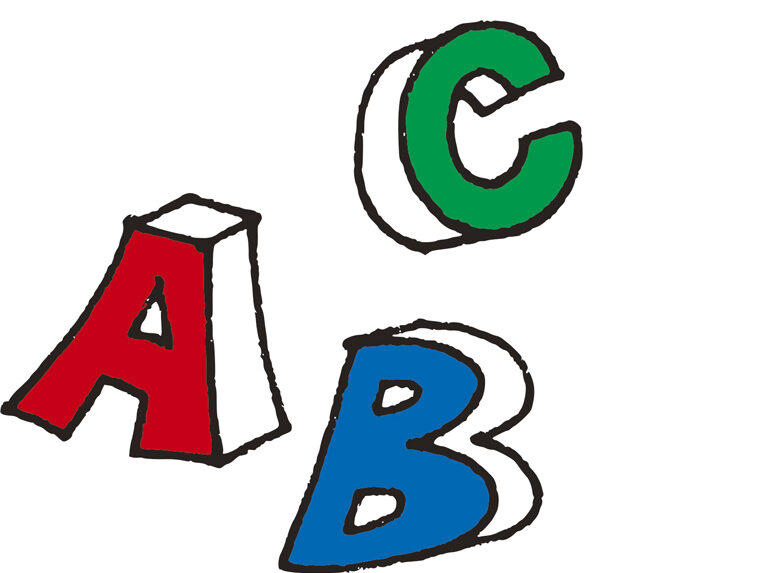目次
「詩の授業、どう進めたらいいのかわからない…」
「子どもたちに詩の書き方を、どのように指導したらいいのだろう?」
このようにお悩みの先生も、いるのではありませんか?
詩は自由な表現が可能だからこそ、児童にとっても「何を、どう書けばいいの?」と戸惑いやすい単元です。
この記事では、言語という形・約束事の中で児童の自由な感性・発想を引き出す指導の工夫や、指導例を交えた授業づくりのヒントを具体的に紹介します。
小学生に詩の書き方を教える授業のねらい
小学校3年生からの国語科での詩の学習は、ただ創作を楽しむための活動ではありません。言葉を通して五感と思考を結びつけ、自分の気持ちや感じ方、考えを表現する力を育てる重要な学びの機会です。教師が詩の授業のねらいを明確に理解しておくことで、児童の言語感覚や表現力を効果的に伸ばす指導が可能になります。
国語科で詩を教える意味と授業の目的
小学生の詩の学習は、思考力や想像力、言語感覚を養い、国語に対する関心を高める学びとして、国語科に位置づけられています。詩の構成や表現技法を学び、鑑賞したり音読したりしながら詩を解釈し、理解力や感想を伝える力を養います。
そして詩の創作は、国語科の目標である「国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力」の育成にも通じます。技法や形式を意識しながら自分の感じたことや思い浮かんだ事柄を言葉で表現することで、それらの力が身に付きます。
児童は、言葉の響きやリズム、表現の工夫に親しみながら、言葉の持つ力、面白さや美しさを実感して国語への関心を高め、言語感覚を養うことも期待されます。
※文部科学省「小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 国語編」を元に執筆
詩の学習で育てたい言語感覚と表現力
詩の学習で育てたい言語感覚と表現力は、以下の通りです。
- 語彙力
- 気持ちの表現
- 比喩的思考
- 創造力
- 音やリズムの感覚
- 他者の表現に共感する力
詩を読み、書くことを通して、児童は豊かな言葉に触れ、表現の幅を広げます。自分の感情や感覚を言葉にすることで自己表現力が高まり、比喩や象徴といった技法を通して、抽象的な事象を具体的に表す力が育ちます。そして、自由な発想による詩作は創造性を引き出し、リズムや音の響きへの意識で音韻感覚を養います。
さらに、他者の詩を読む経験は、多様な感じ方や表現への理解・共感を深めるきっかけになります。
このように、詩の学習は子どもたちにとって、言葉の力をぐんと伸ばしてくれる機会となるでしょう。
中学年と高学年で変わる指導ポイント
児童の発達段階に応じた指導内容やテーマ選びを工夫することは、詩の学習においても重要です。
中学年(3・4年生)では、低学年(1・2年生)で行った詩を読むことを通じて言葉の響きやリズムを楽しみ、詩に親しむ活動を発展させます。感じたことや思ったことを詩に表す創作活動を通じて、言葉で表現する力を育てます。
身近な出来事や自然の様子など、感じたことを素直な言葉で表現することを重視しましょう。
高学年(5・6年生)では、比喩や象徴を用いて、より深い感情や風景、抽象的な概念を表現する力を育てます。詩の構成やリズム、言葉の選び方など、表現技法に焦点を当てた指導を行いましょう。
児童の発達段階に応じた詩の授業を通して、言語能力を効果的に育成することができるでしょう。
大切なのは、詩の学習を通して、日本語による表現の豊かさが児童に伝わること。自分の思いや感性を言葉で表現できる力につなげましょう。
小学生に伝わる!詩の書き方と指導ポイント
詩は、自由な表現の場です。児童には、形式にとらわれずに、自分の内なる思いを言葉で紡ぐ喜びを感じてもらうことがポイントです。
導入として多様な詩に触れ、その表現や韻のリズムを実感させましょう。身近な事柄や感情をテーマにすると、児童は無理なく表現への第一歩を踏み出せます。
「詩は自由」という前提を共有する
「詩は自由」であること、正解のない表現活動であることを、学習のはじめにしっかり伝えましょう。
「上手に書かなきゃ」というプレッシャーから解放されたとき、児童は初めて「自分の思いを、自由に書いていいのだ」と感じられます。この安心感こそが、児童の心の奥底にある思いや創造性を解き放つのです。そして「自分」を正直に表現することを後押しし、そこから言葉による豊かな表現力が育っていくでしょう。
まずは「読む・聞く」ことから始める
詩を書く前に、まずは詩を読んだり音読を聞いたりして、表現や雰囲気などの「詩の世界」に触れさせましょう。
子どもたちは、音のリズムを体で楽しんだり、言葉の響きを耳で楽しんだり、情景が目に浮かぶ様子を想像したりして、イメージが膨らむ感覚を体験できます。そうした積み重ねのなかで、詩的な感覚が自然と身についていきます。「詩って面白い」と感じ、自分でも書いてみたくなるでしょう。
テーマの選び方次第で書きやすくなる
詩のテーマは、季節の出来事や風景、日常生活での体験や心の動きなど、児童が日々感じていることや身近な題材がおすすめです。
心に残っている出来事・うれしかったこと・悲しかったことなど、感情と結びついたテーマにすると、自然に言葉が出てきやすく、詩を書くハードルが下がります。自由度が高く共感しやすいテーマであれば、自然に言葉が湧き出し、自分らしい表現へとつながるでしょう。
詩は自由度が高い「表現の場」だからこそ、児童が安心して書き始められるような導入やテーマ設定が大切です。
授業にそのまま使える!詩の書き方5ステップ
児童が創作の流れをつかみやすい授業をするための具体的な進行方法を、5ステップで紹介します。ぜひご活用ください。
ステップ①テーマを決める
まずは、自分が感じたことや印象に残ったことなどを思い出し、詩のテーマを見つけます。うれしかったこと、不思議に感じたことなど、連想しやすい問いかけをし、クラスで言葉を出し合っていきます。児童の発言を黒板に書き、その中から1つ選んで詩を書くことにすれば、自分でテーマを決めるのが難しい子でも、出された案の中から選びやすくなります。
中学年は、五感・経験・身近な自然・感情に素直に反応できるテーマを選定しましょう。たとえば、好きな〇〇、雨の日の音、ランドセルの中、ドキドキしたこと、などです。
高学年は、感情・風景・時間の流れ・比喩的な表現にも挑戦できるようなテーマにします。たとえば、未来の自分、あのとき言えなかったこと、鳥になったら、空、などです。
ステップ②思いつく言葉をたくさん出して、発想と表現の幅を広げる
テーマが決まったら、それに関連する言葉を自由に、できるだけたくさんノートに書き出します。自分の中のイメージや五感に残る印象を連想できる言葉を挙げていくのがポイントです。質より量を重視し、批判や評価はしません。この作業を連想ゲームのように広げていくと、予期しなかった発想が生まれることもあります。
連想マップや五感シートを使うと、言葉が広がりやすくなります。ここで出てきた言葉が詩の材料になります。
ステップ③印象的な言葉を組み合わせていく
②で出した言葉の中から特に気に入ったものを選び、それらを組み合わせて詩にしていきます。作文のような文章(散文)でなくてよいので、感じたままに、印象や言葉の響きを大切にして並べます。
語尾をそろえる、間を空ける、繰り返すなど、リズムや印象を意識した並べ方を紹介すると効果的です。比喩(たとえ)や擬音語などの表現技法にも、このタイミングで触れると、児童の言葉がより豊かになります。
ステップ④「詩」としての形を整え、思いが伝わるようにする
仕上げとして、並べた言葉の配置を整えます。③で形にした内容を声に出して読んでみて、全体の流れや一つ一つの語の印象、言葉の響きやリズムが自分にとってしっくりくるか、自分の気持ちを表せているかを考えながら見直します。
改行の位置やリズム、強調したい言葉の配置などを工夫すると、表現がより引き立ちます。朗読して聴いてもらうことを意識において、より伝わりやすく魅力的な詩に整えます。
ステップ⑤読み合って表現を深める活動へ
最後に、できあがった詩をクラスのみんなで読み合います。友だちの詩を読むことで新たな気づきや共感が生まれ、自分の詩への感想を聞くことは、表現することに自信がもてるようになります。「○○なので、ここが好き」「この表現が面白い」など、感想は肯定的で具体的に伝えるルールにしておくと、安心して発表し合える環境になります。
自分の気持ちが誰かに伝わったという体験から、子どもたちは表現することの楽しさや、自分の内側から湧き出る言葉の力を実感します。この実感がさらに豊かな表現へと向かう強い動機となるのです。
小学生が使いやすい!表現の幅を広げる詩の書き方テクニック

ここでは、児童の言葉をより魅力的にするための表現の工夫を紹介します。子どもらしい発想による表現をさらに豊かにし、詩の授業を楽しく取り組むヒントを見つけてください。
擬音語・擬態語を活用する
ドキドキ・ふわふわ・ザワザワなど、オノマトペ(擬音語、擬態語)は、児童が音や感触を直感的に表せる言葉です。活用すると、詩に感覚的な豊かさや臨場感を加えられます。
身近な経験から自然と表現が引き出されるため、詩づくりの導入にも適しています。たとえば、先生が以下のように使い方の例を示すと、児童の発想をさらに広げられるでしょう。
- シンシンと白が降りてくる
- サクサクのクッキー しあわせの音
- こたつはぬくぬく うとうとの昼下がり
比喩(たとえ)でイメージを広げる
「〇〇みたい」「まるで〇〇のよう」とたとえると、目に見えない気持ちや様子もイメージが広がり、伝えやすくなります。
比喩は、想像を言葉に変える力を育てる表現技法です。大切なのは、上手さよりも、自分なりの感じ方や自由な発想を、そのまま言葉にすることです。自由でのびのびとした表現を引き出すために、感じたままを大切にしましょう。
繰り返しや音のリズムで”詩らしさ”を出す
同じ言葉や音の響きを繰り返すと、詩に音楽的なリズムが生まれます。短いフレーズでも、行の並びや改行の工夫によって、音読したときの聞こえ方や雰囲気が大きく変わり、詩らしさが増します。
声に出して読むと、心地よい言葉の流れを感じ取れるでしょう。音読を通して、音とリズムに対する感覚が自然と育っていきます。
詩ならではの表現技法を取り入れると、子どもたちの言葉はより豊かで魅力的になります。
先生の声かけ例|自分らしい表現を引き出す言葉かけ
詩の授業では、児童が安心して自分の言葉を紡ぎ出せるような声かけが大切です。
「うまく書かなくてもいいんだよ。思ったことを言葉にしてみよう!」
「それって、言葉にするとどんな感じかな?」
「気持ちが伝わってきたよ!」
書けない…という児童には、「じゃあ、感じたことをひとつだけ言葉にしてみようか」と、焦らず寄り添う姿勢がポイントです。
正解を求めずに思考やイメージを広げる問いかけや、出てきた言葉を肯定するやりとりが、児童の安心感や挑戦する気持ちを育てます。先生の言葉が詩に向き合うきっかけとなり、ときには心の支えになるのです。
子どもたちの自由な発想は、すべてが正解。肯定的に寄り添う姿勢が大切です。
小学生の詩の授業で効果的な導入と活動アイデア
詩の授業では、導入や活動の工夫が児童の興味を引き出します。詩への親しみを育て、書く意欲を高めるために、授業ですぐ実践できる導入とワークアイデアを紹介します。
導入での詩の読み聞かせで魅力を伝える
授業の導入で詩を読む・聞く活動からスタートすると、児童は詩の世界に自然と入っていけます。童謡や短い詩、イメージが広がる詩を選ぶと「なんか面白い」と感じやすく、自分が表現することへのハードルも下がります。
詩の単元中は、授業の冒頭に詩の読み聞かせを取り入れ、言葉の世界の楽しさを共有しましょう。児童の詩への親しみや関心が、自然に高まっていくでしょう。
身近なテーマを選ぶ
「好きな食べ物」「雨の日」「季節の音」など、身近に感じやすいテーマを設定すると、児童は自分の経験や感情を詩にしやすくなります。言葉が自然に浮かびやすくなり、自分の思いや経験とつなげて考えると表現も深まっていきます。
グループで言葉を出し合い、語彙や表現の引き出しを増やす
テーマに沿ってグループで言葉を出し合うと、語彙や表現のバリエーションが増えます。周りの意見がヒントとなり、表現に悩む児童も思いやイメージを膨らませやすいでしょう。助け合いながら言葉を共有すると、想像力が刺激され、詩を作る楽しさもより深まります。
連詩やグループでの詩作に挑戦する
一人一行ずつバトンのようにつなげていく連詩や、テーマに沿ってグループで詩を作る活動は、ゲーム感覚で楽しめます。テーマやリズム、語数などをあらかじめ決めておくと進めやすく、言葉のやりとりの中で表現の面白さにも気づけます。個人では思いつかないような表現力豊かな詩が生まれ、完成した作品をみんなで朗読すれば、大きな達成感と一体感が得られるでしょう。
作品を学級便りや校内掲示で紹介すると、達成感や自信にもつながります。さらに、授業をきっかけに詩作に意欲的になった児童には、小学生対象の詩のコンクールへの応募や、新聞・雑誌への投稿などを勧めてみるのもいいでしょう。
詩の書き方で大切なのは「上手さ」よりも「言葉を楽しむ」こと
詩の授業では、児童が「うまく書く」ことにとらわれず、言葉による表現を自由に楽しめることを大事にしましょう。自己表現の喜びを大切にする活動により、言葉による表現力は自然に伸びていきます。
正解のない表現活動だからこそ、自分の言葉で思いを綴る経験は、児童にとって何より貴重です。詩の魅力である、自由に表現できる安心感と楽しさを、ぜひ引き出してあげてくださいね。
ここでは、詩の授業づくりのヒントについて紹介しました。小学生の国語の指導については、以下の記事も参考になります。
・作文が苦手な原因と指導法
・読みやすい文章を書くコツ|一つひとつの文を意識しよう
・読みやすい文章を書くコツ|パラグラフ・ライティングを活用しよう
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。