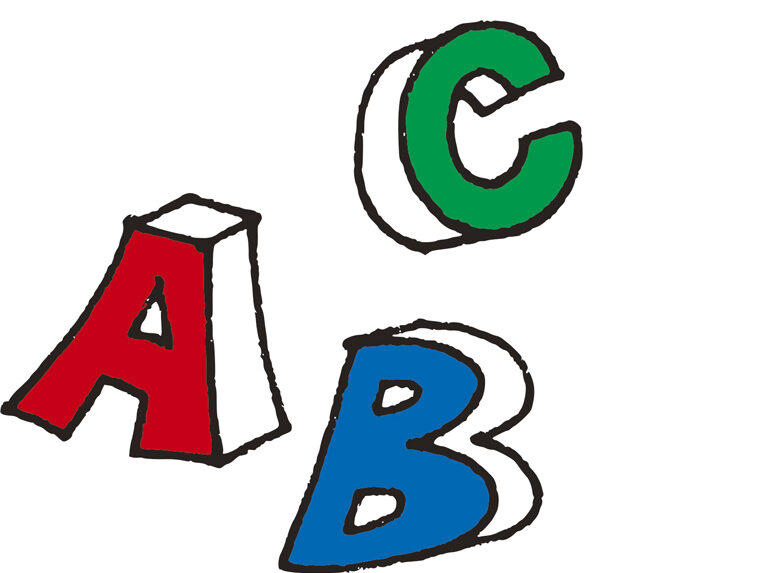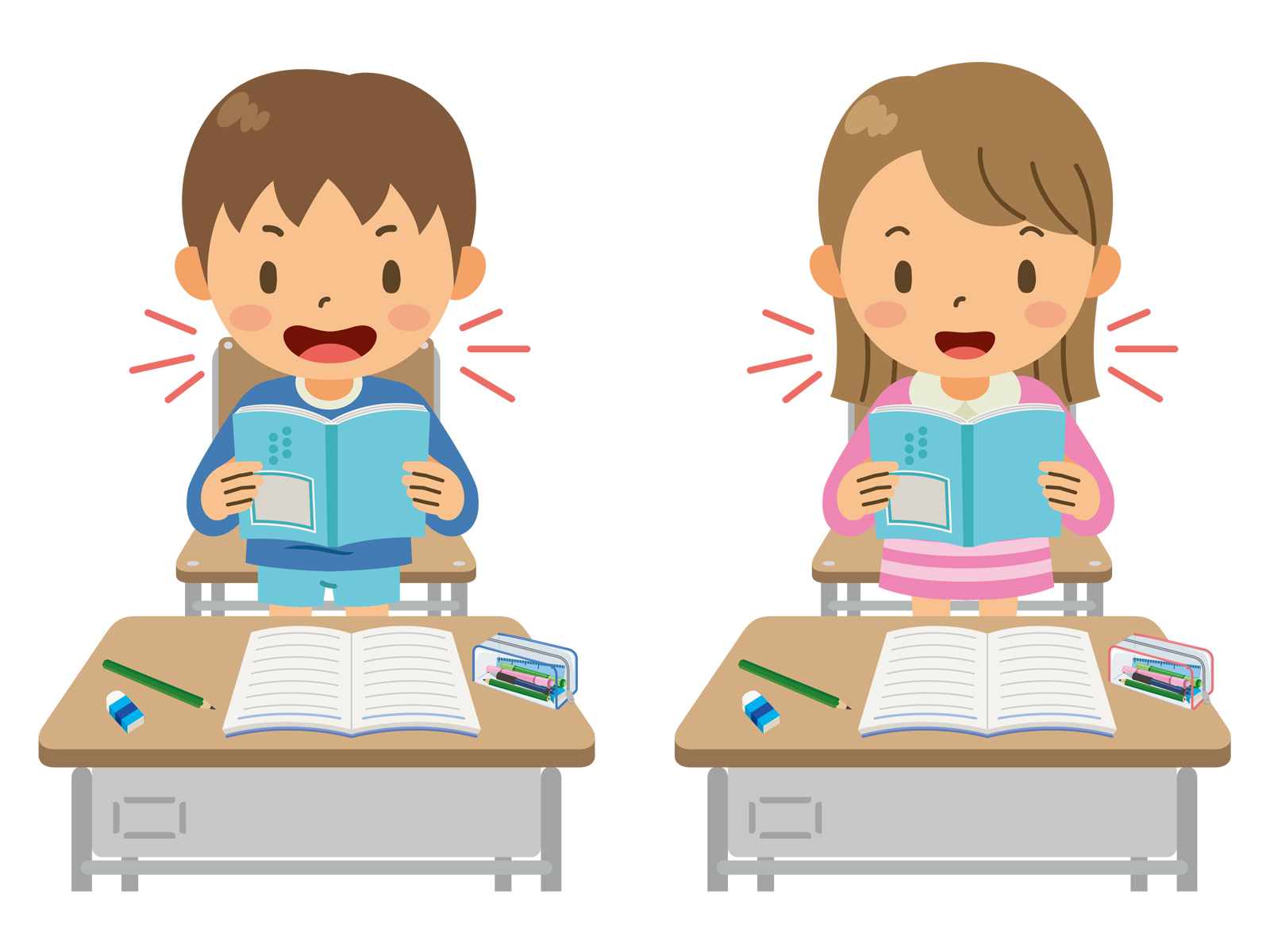
目次
小学校の国語の授業や宿題では、日々の学習の一部として音読が取り入れられています。また文部科学省でも、音読は国語科における重要な学習活動のひとつとして位置づけられています。
とはいえ「音読って、実際にどんな力がつくの?」と聞かれたとき、その効果をあらためて言葉にするのは意外と難しい、と感じている先生も多いのではないでしょうか。
実は音読には、語彙力・読解力の向上をはじめ、脳や心のはたらきにも良い影響があることが、研究や実践から明らかになっています。
そこでこの記事では、国語科における音読の効果と、より効果的な指導のコツについて、わかりやすく解説します。自信を持って音読指導ができるよう、一緒に整理していきましょう。
音読とは?国語科で重視される理由をわかりやすく解説
文部科学省の報告書『国語力を身に付けるための国語教育の在り方』のなかで、学校における国語科教育では、「情緒力」「論理的思考力」「思考そのものを支えていく語彙力」の育成を重視していくことが必要であり、特に「情緒力」を身につけるためには「読む」ことを重視し、授業内で継続的に組み込むことが大切であると述べられています。
そして、音読については、次のように述べられています。
音読によって,国語力や独創力とかかわる脳の場所が特に活性化するという脳科学の知見もあることから,積極的に音読を取り入れていくことが大切である。また,音読することによって,漢字の読みを覚えたり,文章の内容を確実に理解したりできる。
出典:国語力を身に付けるための国語教育の在り方|文部科学省
(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/04020301/007.htm#top)
つまり音読は、語彙や漢字の定着のみでなく、文章の理解といった言語能力の基盤を育てる手段として、国語教育の中で重視されているのです。
国語科の授業では長年にわたり音読が取り入れられており、国語力の土台を育む学びとしての役割を果たしています。音読は単なる「読み」の練習ではなく、国語力全般の育成を支える重要な活動といえるでしょう。
音読は、日本人に必要な国語力を身につけるための大切な学習活動です。授業や宿題などに積極的に取り入れていきましょう。
音読の効果とは?小学生に身につく3つの力
音読は、日本語を読む練習にとどまらず、子どもたちのさまざまな力を伸ばしてくれる大切な学習活動です。特に小学生の時期の音読は、「学力」「脳の働き」「心の成長」の3つの面で効果があるといわれています。
ここでは、それぞれの側面から、音読のもたらす効果を見ていきましょう。
【学力への効果】語彙力・読解力が伸びる
前述したように、音読によって、子どもたちの語彙力を高め、文章の内容をしっかり理解する力を育てることができます。
難しい文章であっても音読をくり返すことで、語句の意味の理解が深まり、文章全体の構成や流れもつかめるようになります。段落のつながりや展開に目が向くようになり、内容を深く読み取る読解力が少しずつ育っていくのです。
音読を含む「読む活動」を毎日積み重ねることで、子どもたちの学力の基盤がつくられていくでしょう。
【脳への効果】集中力や思考力が高まる
近年の脳科学研究では、音読を行うことで脳の前頭前野が活性化することが、明らかになっています。
前頭前野は、集中力・思考力・判断力などをつかさどる重要な領域で、学習に欠かせない「考える力」の司令塔のような役割を持っています。
東北大学の川島隆太教授の研究によれば、文章をすらすらと音読しているときには、脳の血流が増えて神経細胞が活性化し、脳の働きが高まるそうです。特に前頭前野が活発に働くことで、子どもは自然と集中しやすくなり、学習に取り組む姿勢が整いやすくなるでしょう。また、学習した内容をわかりやすく整理する力や、的確な判断力が高まることも期待できます。
このように、学習を始める前に音読を取り入れることは、頭のウォーミングアップとしても有効だと考えられます。
【心への効果】自信や自己肯定感が育つ
音読は、子どもたちの「心」にも良い影響を与えます。「うまく読めた」「最後まで読めた」といった達成感を積み重ねることで、少しずつ自信が育っていくのです。
毎日の習慣として音読に取り組むと、「できた!」という小さな成功体験をくり返し感じられるポジティブな機会となります。「前よりも、すらすらと上手に読めるようになった」というような実感が生まれると、それが自己肯定感の芽生えにつながっていくでしょう。
また、授業や学級活動の中で音読を発表する機会があると、人前で読む経験の積み重ねができ、授業で発言することへの抵抗感を減らしていく効果も期待できます。
音読は脳を活性化させ、子どもたちの国語力の基礎を育てる大切な学習活動です。自信や自己肯定感も育まれ、子どもたちの心と学びの支えになっていきます。
音読を授業や宿題に取り入れる理由
音読は、多くの小学校で、授業や宿題の一部として日常的に取り入れられています。
ここでは、音読を取り入れることの意味や効果について、3つの視点から整理していきます。
理由① 読解力がつき、すべての学習の土台になる
音読は、「読む力」を育てるための基本的な活動です。毎日くり返し声に出して読むことで、正しい日本語の使い方、漢字の読み方、言葉の意味、文の切れ目や抑揚のつけ方などが、自然と身についていきます。
大切なのは「声に出すこと」で、文字だけを追う「黙読」よりも、内容の理解が深まりやすいといわれています。文章の構造やリズムを身体的に感じながら読むことで、意味をより正確にとらえる力が育つのです。
こうした積み重ねは読解力の向上につながり、国語だけでなく、算数の文章題や社会・理科の教科書や資料を読み解く力など、他教科の学習にも大きく活かされます。
音読は、すべての学習の基礎となる「読む力」の土台をつくる、重要な役割を担っているのです。
理由② 家庭学習の習慣化につながる
音読は、短時間で取り組める手軽な学習活動です。だからこそ家庭でも続けやすく、特に低学年の子どもにとっては、学習習慣を身につけるきっかけになりやすいのです。これは、学校で音読を宿題に出す大きな理由の一つでもあります。
ただし、音読を宿題にする際には、そのねらいを保護者にどう伝えるかも大切なポイントです。中には「ただ読むだけで意味があるの?」と、疑問を持つ保護者もいるかもしれません。そんなときは「毎日のルーティーンとして取り組むことで、学習のリズムが整います」と説明すると、音読の価値が伝わりやすくなります。
また、子どもが音読に取り組む際は、保護者の声かけが大きな支えになります。「叱らずに見守り、前向きな言葉がけをしていただけると、やる気につながります」と伝えておくと、家庭でもよりよい学習環境が整いやすくなるでしょう。
理由③ 授業の集中力アップや学級の一体感づくりに役立つ
音読は、授業の導入や切り替えのタイミングにぴったりな活動です。声を出して読むことで気持ちが切り替わり、「これから学習に取り組むぞ」という空気が、教室内に自然と生まれます。また、脳の前頭前野も活性化し集中力が高まるので、子どもたちの学習へのスイッチを入れる助けにもなります。
特に、休み時間と授業中との気持ちの切り替えが難しい低学年では、授業の始まりに音読を取り入れると、そのあとの学習活動にスムーズに取り組めるでしょう。
また、クラス全体で同じ教材を音読することで、「みんなで取り組んでいる」という共通の感覚が生まれ、安心感や仲間意識が育まれます。このように音読は、学級の一体感づくりにも役立つ活動なのです。
音読のねらいや効果を整理し、「音読って本当に必要?」と聞かれたときにも、自信を持って答えられるようにしていきましょう。
「生徒を授業に集中させたい」と考えている方には、こちらの記事が参考になります。
生徒を授業に集中させる方法は?集中しない原因や、先生・生徒ができる対策を紹介
音読の効果を高める!効果的なやり方と指導のコツ
音読による効果をあげるためには、毎日しっかり取り組むことが大切です。せっかく音読しても、惰性的な形だけの取り組みになってしまうと、子どもたちの意欲も効果も下がってしまいます。
ここでは、音読の効果を引き出すために意識したい指導のポイントと、日々の実践に取り入れられるちょっとした工夫をご紹介します。
読み飛ばさず、ていねいに読むことを意識させよう
読む力を育てるには、ていねいに読むことが欠かせません。しかし、子どもたちは音読に慣れてくると「早く終わらせたい!」という気持ちから、読み飛ばしたり、意味を考えずに読んだりしてしまいがちです。
そんなときは、次のような声かけで、音読のポイントを意識づけしてみましょう。
- 「大きな声で、はっきり読もう」
- 「句読点でいったん止まって、意味を考えて読んでみよう」
読み方にクセがある子や読み飛ばしが目立つ子への指導には、モデル音読を取り入れるのも効果的です。先生の音読や朗読の教材などを真似させることで、子ども自身の読み方も変わっていきます。
音読の宿題は、子どもに合った教材を選ぼう
音読は、読んでいる文章の語句や内容に意識を向けることなく「ただ読むだけ」になってしまうと、効果が下がってしまいます。
宿題として音読を出すときは、学年や子どもの実態に合わせて、無理のない分量・難易度になっているかを確認することが大切です。家庭での取り組みやすさも意識しましょう。
教科書に載っている文章だけにこだわらず、子どもの学年・発達段階を考慮のうえ、興味関心を引きそうな題材の文章を選ぶのもよいでしょう。また、早口言葉や詩、昔話、古文など、教材にバリエーションをもたせるのも一つの方法です。いつもと違う音読に挑戦することで、新鮮さや楽しさが生まれます。
飽きずに毎日続けられる工夫をしよう
音読は、毎日こつこつ続けることで力になります。でも同じ教材を繰り返し読んでいると、「またこの文章か…」と子どもが飽きてしまうこともあります。
そんなときは、ちょっとした遊び心を取り入れて音読に楽しさをプラスしてみましょう。
- 「今日は登場人物になりきって読んでみよう」
- 「ロボットの声で読んでみよう」
- 「おじいちゃんの声で読んでみよう」
低学年の子どもたちには、こうした「なりきり音読」が効果的です。慣れてきたら、「この単元の好きな場面だけ読む」「自分が好きな本を選んで読む」といった選択肢を与えると、自分から進んで音読する姿勢が育ちやすくなります。
音読が「ただ読むだけ」にならないよう、日々のちょっとした工夫を取り入れ、子どもたちの興味関心や意欲をしっかり引き出していきましょう。
音読の効果を高めて、毎日の学びを深めていこう
音読は、毎日の積み重ねにより、生きていくうえで必要な国語力の基礎を育ててくれる、とても大切な学習活動です。シンプルな学習ですが、脳の働きを活性化し、学力向上につながる「読む力・考える力・学びに向かう力」を養うだけでなく、子どもの心にも良い影響を与えるなど、さまざまな効果が期待できます。
また、授業や家庭学習に取り入れやすく、学習の習慣づけやクラスの雰囲気づくりにもつながるのが音読の魅力です。「ていねいに読む」「意味を考えて読む」といった意識を子どもに持たせる工夫を加えるだけで、音読の効果はぐっと高まります。
先生自身も「どんな力を育てたいか」「どうすれば楽しく続けられるか」を意識しながら、音読をより意味のある学びにしていきましょう。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。