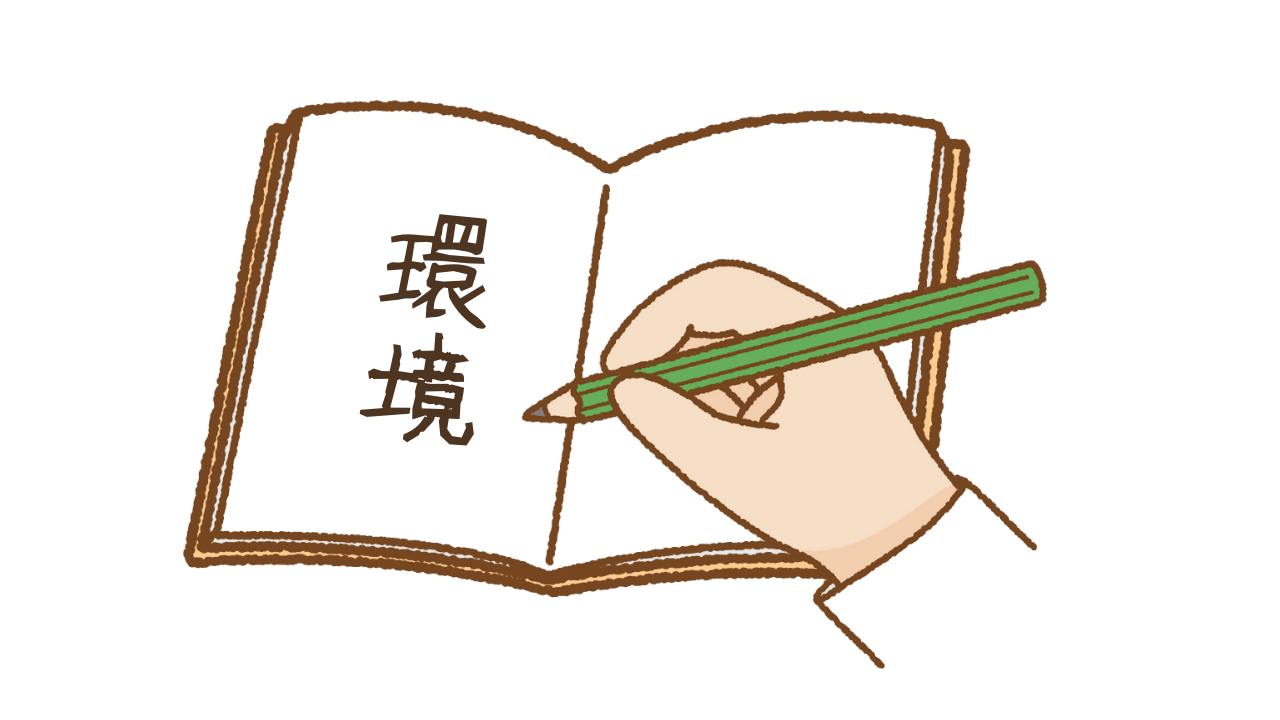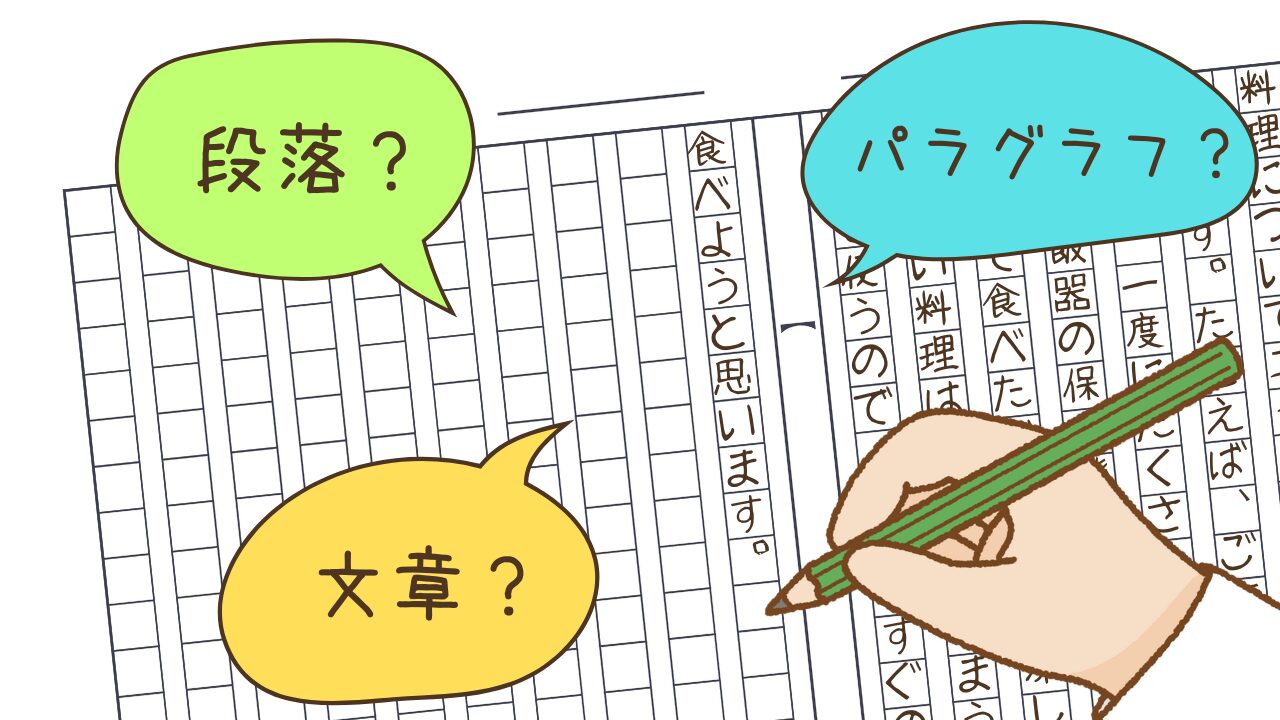目次
「生徒たちに、敬語への苦手意識を持たず、興味や理解を深めてもらうには?」
「どんな授業をすれば、児童が楽しみながら、正しい敬語を習得できるだろう…」
「そもそも、自分も敬語を適切に使えているだろうか?」
このように、児童・生徒が敬語をおもしろいと思える授業をするにはどうしたらよいのかと、悩んでしまう先生もいるでしょう。また、いざ敬語を教えようとしたときに、自分自身の知識が曖昧であることに気づく場合もあるかもしれません。
そこで本記事では、敬語の基本的な知識を復習しながら、児童・生徒が「おもしろい」と感じてくれるような敬語の指導法を紹介していきます。
大人も知っておきたい!敬語の知識
敬語とは、相手の立場を尊重する気持ちを表現する言葉です。相手や場面に応じて敬語を使い分けることによって相手への敬意の気持ちを表せます。
ここではまず、敬語の3つの種類、「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」について確認しましょう。
尊敬語
尊敬語とは、相手方または第三者の行為について高めて表現することで敬意を表す言葉です。尊敬語には、①特定の語形に変化するもの、②「お(ご)~なさる(される)」などの語形にするもの、③「~れる」「~られる」などの語形によって表されるものがあります。
たとえば「来る」という動詞は、尊敬語では「いらっしゃる」「お見えになる」「お越しになる」などに変化します。
①の例としては、他に以下のようなものがあります。
- 言う → おっしゃる
- する → なさる
- 食べる・飲む → 召し上がる
- 見る → ご覧になる
②の表現として、「お(ご)~なさる(される)」の他に、「お(ご)~くださる」「お(ご)~になる」などの語形があります。
例:
- 運転なさる(運転される)
- ご用意くださる
- お読みになる
③は、動詞に「れる」「られる」を付けて尊敬の気持ちを表します。
例:
- 読まれる
- 来られる
他にあげられるのは、名詞や形容詞に尊敬の接頭語である「お/ご」を付けて、尊敬語として使う方法です。「先生はお忙しい」「ご多忙のところ」「お客様のお名前」などのように使われます。
謙譲語
謙譲語は、自分の行為をへりくだって表現することで相手への敬意を表す言葉です。
謙譲語には、以下の2種類があり、文化庁の「敬語の指針」によれば、謙譲語Ⅰと謙譲語Ⅱに分類されます。
出典:「敬語の指針」(平成19年2月2日 文化審議会答申) (https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/sokai/sokai_6/pdf/keigo_tousin.pdf)(2025年3月3日に利用)
自分が受け手に対して行う行為・ものごとなどについて、相手を立てる表現(謙譲語Ⅰ)
自分から相手または第三者に向かう行為・ものごとなどについて、相手(受け手・対象)を目上・上位と見て、自らへりくだることで相手への敬意を表す言い方です。このタイプの謙譲語にも、①特定の語形に変化するものと、②「お(ご)~する(いたす)」といった語形を使うものがあります。
①の例として、たとえば「行く」の謙譲語は「伺う」です。他にも以下のような例があります。
- 言う → 申し上げる
- 会う → お目にかかる
- あげる → 差し上げる
- 聞く → 伺う
また、②の言い方の例としては、「ご案内する」「お預かりする」などがあげられます。
その他、名詞に使われる謙譲語には「先生へのご挨拶」「先生へのお手紙」などがあります。ただし、これが「先生からのご挨拶」「先生からのお手紙」のような表現になると、同じ名詞でもその動作を行う人を敬う尊敬語にあたります。いずれの使い方でも、相手を立てる表現であることには変わりありませんが、正しく認識しておきましょう。
自分側の行為を丁重に表現することで敬意を表す方法(謙譲語Ⅱ)
「私が参ります」「〇〇と申します」のように、自分側の行為等を丁重にへりくだって表現することで、相手への敬意を表します。この場合、謙譲語Ⅰと違うのは、敬意を払っている相手が行為の対象者ではなく、話の聞き手であるという点です。
名詞でも「小社」「拙著」など自分をへりくだる表現がありますが、これらは主に、手紙などの書き言葉で使われることが一般的です。
丁寧語
相手(聞き手)に対して、丁寧に述べることで、配慮を表す言葉です。丁寧語にも、細かく分けると「丁寧語」と「美化語」の2種類があります。
丁寧語
丁寧語の代表的なものは、文末に「です」「ます」を付けた表現です。丁寧な言葉遣いで相手(聞き手)への配慮を表し、誰に対しても使えます。
また、「です・ます」よりも丁寧度の高い表現に「(~で)ございます」があります。これは、語尾に付けることでフォーマルな印象が強まるため、ビジネスの場でも多く用いられる表現です。ただし、相手への尊敬を表すものではないので、使い方には注意が必要です。
▼よくある「ございます」の誤用例
誤:〇〇様でございますね。
正:〇〇様でいらっしゃいますね。
敬意を払うべき相手に対し、このように使うのは誤りで、尊敬語を使うべき場面です。これに対し、「担当者の〇〇でございます」のように、自己紹介や身内の紹介などに使うのは適切と言えます。
美化語
美しく品のある言葉遣いや、表現を和らげることにより、改まった印象や相手に寄り添うニュアンスなどを表します。尊敬の意味はありませんが、相手への配慮や丁寧さから敬語に準じる表現とされます。名詞に敬語の接頭語である「お」「ご」を付けて、より丁寧に表現した言葉を指します。
「お」や「ご」を美化語として使う場合、和語(日本固有の言葉)には「お」を、漢語(中国由来の言葉)には「ご」を付けて、丁寧さを表します。ただし、何でも「お」や「ご」を付ければいいというものではなく、過度な美化語はかえって不自然な印象を与えますので、気をつけましょう。
「お」と「ご」の使い分け方ですが、あとに続く名詞が訓読みであれば和語、音読みであれば漢語です。たとえば「お」を付ける例としては、お菓子、お祝い、お心遣いがありますし、「ご」を付ける例であれば、ご入学、ご参加、ご出席などがあげられます。
まずは、敬語の基本的な種類と正しい使い方を押さえましょう。
敬語の指導において押さえたいポイント2つ
授業で敬語を教えるときには、敬語の使い方や使う場面について知り、敬語について理解を深める必要があります。その上で、場や相手に適した言葉を選ぶ大切さを知り、日常生活で自然に敬語を使えるようになることが目標です。
そのためには、以下のようなポイントを押さえて授業を組み立てましょう。
1.日常生活と敬語を結びつける
そもそも敬語は、学校生活や日常生活の中で使われているものです。ふだん何気なく見聞きしている敬語に注意を向け、それを自分たちの日常のコミュニケーションと結びつけることで、敬語への理解が深まるきっかけになります。
たとえば学校生活では、先生に用件を伝えるときは敬語を使います。お客様がいらしたときにも敬語を使う機会があるでしょう。学校の外では、家での来客への対応やお店で買い物をするときなどに、敬語が使われます。
このように、ふだん自分たちが無意識に触れている敬語表現に気づけると、どのような場面でどのような敬語が使われているかがわかり、理解が深まります。
2.スモールステップで学ぶ
敬語は上記のように大きく3つに分類されますが、一番身近で使いやすい敬語といえば丁寧語でしょう。授業で敬語を取り上げる場合、丁寧語からスタートするとハードルが下がります。丁寧語が身についてきたら、身近な場面を例にしながら尊敬語へとつなげていくと、理解しやすくなります。
逆に、敬語の中で最も難易度が高いのが謙譲語です。謙譲語を教えるときには、なるべく具体的に身近な場面を想定し、実演を交えながら指導するのもよいでしょう。
日常生活における身近な場面と結びつけながら、実感として理解を深めてもらうのがポイントです。
つまずきやすい敬語と正しく使うためのポイント
敬語表現の中には、敬意や丁寧さを意識するあまり、知らないうちに不適切な使い方をしやすいものがあります。
ここでは、大人でも陥りやすい敬語表現の誤用と、正しく使うためのポイントを解説します。
二重敬語
二重敬語とは、1つの語に対して同種の敬語表現を二重に使用することを言います。
たとえば「お読みになられる」という表現は、読むの尊敬語表現「お読みになる」に、さらに尊敬語の表現である「~られる」を重ねた二重敬語です。この場合は「お読みになる」が正しい敬語で、これだけで十分に敬意を表します。
他にも、以下のような表現は、つい使いがちな二重敬語にあたります。
- 誤:ご覧になられる → 正:ご覧になる
- 誤:おっしゃられる → 正:おっしゃる
- 誤:承らせていただく → 正:承る
- 誤:拝見させていただく → 正:拝見する
いずれも、より丁寧に表現しようと考えた結果として起きるケースです。誤用を避けるポイントとしては、迷った場合は、よりシンプルな敬語表現を選ぶと適切である場合が多いでしょう。
謙譲語と尊敬語を重ねる
謙譲語と尊敬語を重ねてしまうのも、敬語を使用する際によく見られる誤りです。
たとえば「お伺いになる」という表現には、謙譲語と尊敬語が混在しています。この場合の「伺う」は謙譲語で、「お~になる」は尊敬語です。謙譲語として使う場合は「伺う」、尊敬語として使う場合は「お尋ねになる」「お聞きになる」などとするのが正解です。
行為者が誰なのかをきちんと把握し、誰(なに)に向けられた行為なのかも踏まえた上で表現を選ぶと、このような誤用を避けることに繋がります。
敬語の連結
敬語の連結とは、2つ以上の言葉をそれぞれ敬語にして、接続助詞の「て」でつなげた言葉です。「ご覧になっていらっしゃる」(「見る」の尊敬語「ご覧になる」+「いる」の尊敬語「いらっしゃる」)のような表現が該当します。敬語の連結は、それぞれの敬語の使い方が適切で、かつ敬語同士の結びつきに不合理がないかぎりは許容されており、誤りではありません。
しかし、二重敬語とは言わないまでも回りくどい印象を与え、使い方によっては過剰な表現と受け取られかねないので、注意が必要です。上の例の場合であれば、「ご覧になっている」とするのがよいでしょう。意図が伝わりやすいシンプルな敬語表現で、相手への配慮を示すことを心がけましょう。
大人もつまずきやすいポイントも多くあるので、再確認しておきましょう。
おもしろい敬語の授業づくりアイデア6選
敬語は学校生活だけでなく、児童・生徒たちがこれから成長していき、さまざまな立場の人たちとコミュニケーションを図るときに必須となる社会スキルの1つです。しかし、いざ授業で学ぶとなると、関心が持てなかったり、敬語のしくみを理解できなかったりする生徒もいるかもしれません。
ロールプレイングなどの実践形式やゲームを通して学ぶと、楽しみながら体験的に敬語を習得できます。また、視覚的な教材を使用することで、敬語の仕組みを理解しやすくなる子もいるでしょう。
ここでは、児童・生徒がおもしろいと感じられる敬語の授業づくりに適した、具体的なアイデアを6つ紹介します。
実践形式で学ぶ敬語学習2選
ロールプレイ
敬語は、年齢が上がるにつれて、ますます適切な使用が求められる大事な言葉です。実際に敬語が使われるさまざまな場面を取り上げて、ロールプレイングすることで実践的に学べます。
たとえば先生と生徒の設定、お客様と店員の設定など、敬語が使われるシチュエーションを想定して役割を分け、実際に会話をしてみるとよいでしょう。
実演することで、どのような相手にどのような目線に立って敬語を使えば、よいコミュニケーションが成立するのかを考える機会になります。可能であれば、ロールプレイングしている様子を動画で撮影して後から見返すと、適切な敬語の使い方について議論する題材にもなります。
インタビュー
実践的に敬語を学ぶ方法としては、身近な大人へのインタビューを通して習得するのも一つの方法です。どんな言葉遣いをすれば、相手への敬意を伝えながら対話できるのかを学べます。
たとえば、校長先生にインタビューをしたり、学校に関わりのある校医の先生などにお願いして質問する機会を設けたりするのもよいでしょう。可能であれば、児童・生徒に人気の近くのお店や、地域の図書館などに出向いて、取材をするのもよいかもしれません。
実際の会話を録音して皆で後から聴いてみると、敬語の使い方を楽しく習得できます。大人とのコミュニケーションは、児童・生徒にとって自信にもつながるでしょう。
ゲーム形式で楽しく学べる敬語学習2選
敬語神経衰弱
トランプの神経衰弱と同じルールで、敬語を使った日本語カードでゲームをします。
用意するのは、日本語の動詞や名詞を一枚にひとつずつ書いたカードと、それらを敬語にした日本語のカードです。まず、すべてのカードを裏返しにして並べます。参加者同士、じゃんけんなどで順番を決めて、早い人から順にカードを2枚めくり、普通の言葉と同じ意味の敬語のペアを作っていきます。同じ意味の普通の言葉と敬語を選べたら、その2枚のカードを自分のものにできます。2枚のカードの意味が揃わなかったら、元の裏返しの状態に戻します。こうしてカードがなくなるまで繰り返し、一番多くのカードを取った人が勝ちです。
2枚揃えられたカードの敬語を使って短文を作ったりすると、さらに理解が深まるでしょう。
敬語すごろく
敬語を使ったすごろくのゲームを通して、敬語の表現を学びながらゴールを目指します。
ゲームのルールは、通常のすごろくと同様です。サイコロを振って出た目の数に応じて進み、止まったマスに書かれた指示に従います。マスにはそれぞれ異なる場面設定が書いてあり、そのシチュエーションに応じた敬語を使って会話をするルールです。
ゲームの指示に応じて答えた敬語が間違った使い方でも、勝敗には関係ないので、敬語が苦手な児童でも楽しく参加できるでしょう。誤った使い方をした児童には、その場で先生が正してあげることになりますが、試験ではないので注意や叱るような言い方は避けましょう。
視覚的な教材で学ぶ敬語学習2選
敬語変換カード
視覚的にわかりやすく学ぶ方法として、敬語変換カードを使う方法もおすすめです。カードに、普通の言葉、または誤った敬語表現を書いておきます。それを児童に見せて、普通の言葉は敬語に直し、誤った敬語は正しい表現に直します。
▼カード活用の例
- グループワーク形式
各グループにカードセットを配布し、協力して敬語に変換・修正させる活動ができます。 - 一斉授業での活用
黒板やモニターにカードの内容を提示し、クラス全体に問いかけて答えさせる形式も効果的です。磁石付きのカードを使って黒板に貼り、移動させながら説明することもできます。 - 個別学習
各生徒に小さなカードセットを配布し、自分のペースで学習させることもできます。特に復習や発展学習として活用できます。
カードを使うメリットは、ゲーム感覚で実施できる手軽さです。カードの裏に正解を書いておくことですぐに答えを確認できるため、授業の導入にも活用できます。
最初は単語から始めて、慣れてきたら文章を提示するなどしてレベルを上げていくとよいでしょう。
場面連想
イラストや写真から場面を連想して、敬語を学ぶ方法もあります。
これは、写真などが撮られた場面で話されている会話を敬語で再現することで、さまざまな立場での敬語表現を考える学習方法です。たとえば、学校生活や地域での活動、日常のワンシーンなどのイラストや写真を用意します。
いきなり会話を連想することが難しい場合、以下のような段階的な指導がおすすめです。
- 先生による会話例の提示
まず先生が場面に合った「敬語になっていない基本的な会話例」を提示します。 - 敬語変換ワーク
提示された会話を児童が敬語に直す練習をします。 - 役割分担
イラストの中の「店員と客」「先生と児童」など、役割を明確にして、立場による敬語の使い分けを学びます。 - 発展
慣れてきたら、自分で会話を考えてみましょう。
イラストや写真を使用することで、授業で習ったことと実際に敬語を使う場面との結びつけがしやすくなります。
楽しみながら実践的に敬語を学べる工夫をしていきましょう。
おもしろい授業で敬語を楽しく学ぼう
この記事では、敬語についての基本的な知識や、大人でも誤りやすいポイントを解説し、児童・生徒の敬語習得を助ける、楽しく実践的な授業のアイデアを紹介しました。
もっとも大切なポイントは、以下の3つです。
- 日常生活と結びつけて学ぶことで、自然に敬語の特性を理解できるようになる
- 段階的な学習により、ハードルが高いと感じさせず、無理のない習得をめざす
- 実際の場面を想定した学習法や、実践的な活動を通じて、楽しみながら身につけていく
敬語の正しい使用は、大人になればできて当然のマナーや良識とみなされます。児童・生徒の将来にも大きく影響するスキルですので、今回紹介した内容を参考に、児童・生徒が楽しく学べる敬語の授業に取り組んでいきましょう。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。