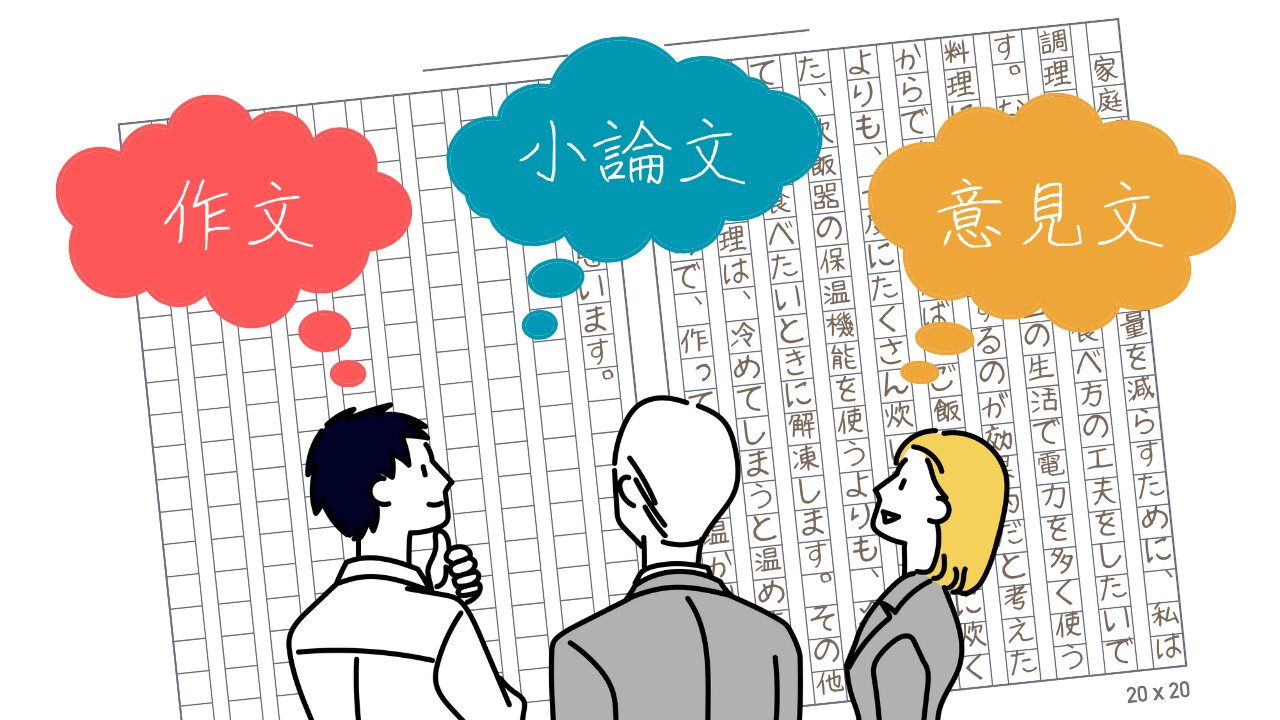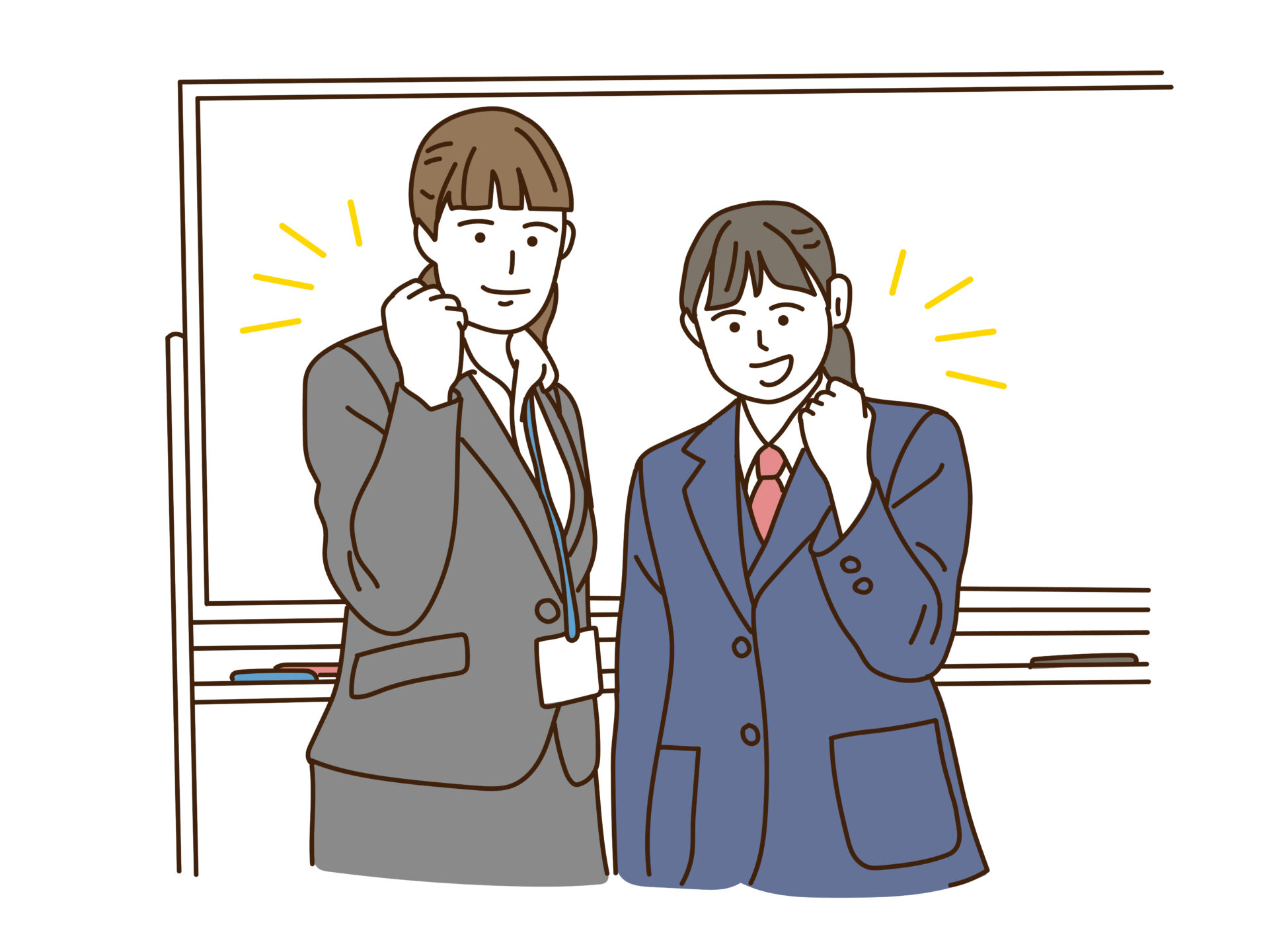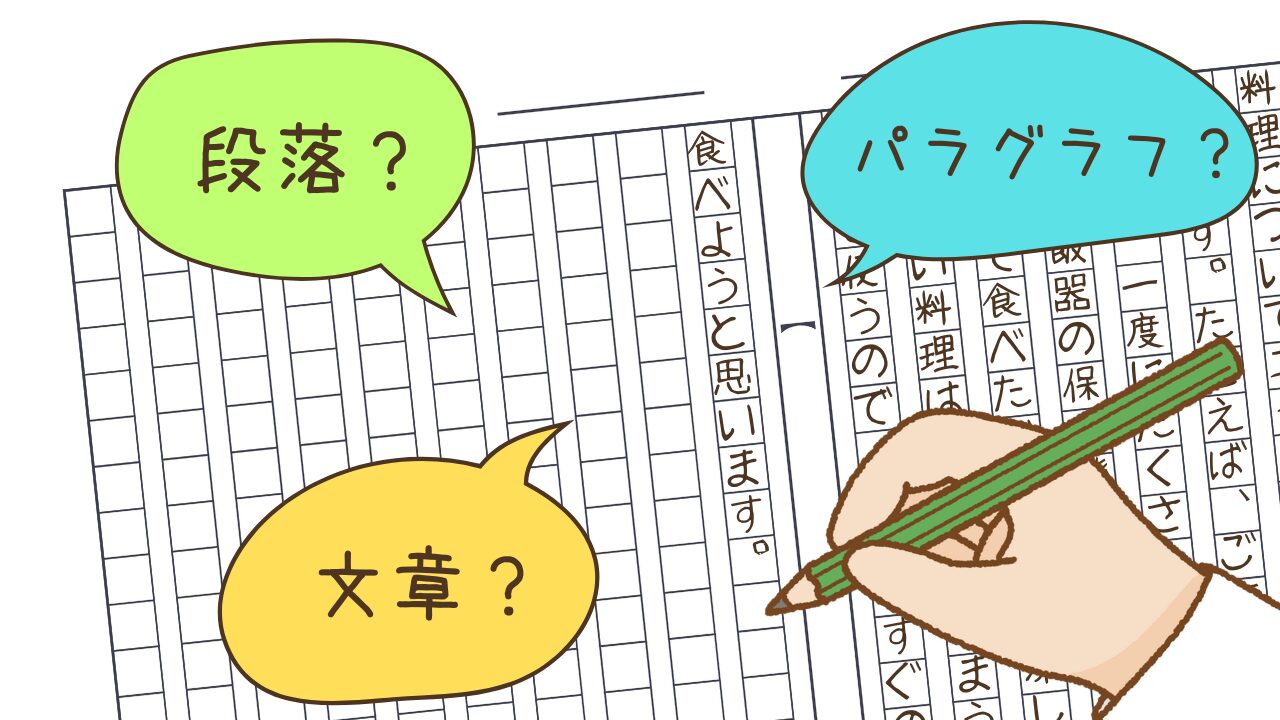目次
「中学生への先取り学習を取り入れた方がいいのか、迷っている」
「先取り学習って、どんな効果があるのかな」
このように感じている塾講師の方も、多いのではないでしょうか。
学校の授業よりも早く学習内容を進めることで、学力アップや受験対策につながる一方で、生徒の理解度やモチベーションへの影響を懸念する声もよく聞かれます。
そこでこの記事では、塾で先取り学習を導入するメリットや注意点、実践ステップを具体的に紹介します。生徒にも講師にも無理のない形で、効果的に先取り学習を導入するためのヒントとして、ぜひご活用ください。
塾で中学生の先取り学習を導入するねらいと背景
現在、大手の進学塾を中心に、中学生向けに先取り学習を取り入れているケースが多く見られます。その背景にあるのが、高校入試の傾向の変化と、それに対応した準備の早期化です。
中学3年生になると、一般的に、多くの生徒が夏頃から本格的に受験勉強を始めます。しかし、近年の入試では、「自分の考えを表現する力」や「複数の情報をもとに答えを導く力」など、単なる知識を問うだけではなく、深い理解や思考力を問われる問題が増えています。
そのため、中3の夏から受験対策の勉強を始めても、十分とは言えない場合もあります。特に英語や数学のような積み上げ型の教科では、中1・中2の内容があいまいなままだと、応用問題に対応するのは難しいでしょう。
こうした状況を受けて、早い段階で基礎を固め、余裕を持って受験期を迎えられるようにカリキュラムを設計する塾が増えています。
知識だけでなく思考力や表現力が問われる入試へと、傾向が変化してきたなかで、早い段階からの計画的な入試対策が、ますます重要になっています。
塾で中学生の先取り学習を導入するメリットと課題
実際に、塾で先取り学習を取り入れることで、生徒にはどのようなメリットがあるのでしょうか。導入を検討する際には、メリットだけでなく、注意すべき点にも目を向けておくことが大切です。
ここでは、生徒にとっての先取り学習のメリットと課題の両面を、整理して確認していきましょう。
メリット1:学校の授業が復習になり、余裕と自信が生まれる
塾で先取り学習を行うことによって、学校で扱う内容をあらかじめ学んでおくことができ、学校の授業が「初めての学び」ではなく「復習」のような位置づけになります。その結果、内容の理解がスムーズになり、気持ちにも余裕が生まれやすくなります。
さらに、学校の授業中に「わかる」「できる」と感じられる場面が増えることで、自信を持って学習に臨めるようになります。こうした小さな成功体験の積み重ねは、意欲の向上にもつながっていきます。
メリット2:基礎を早めに固めることで、入試対策に向けた時間を確保できる
先に述べた通り、先取り学習の大きなメリットのひとつは、入試対策のスタートを早められることです。特に英語や数学のように、前に習った内容がそのまま土台となる「積み上げ型」の教科では、この効果がより顕著にあらわれます。
学習指導要領で定められている中1・中2の学習内容は、応用問題もありますが、どちらかというと基礎力の積み上げが重視されています。この段階で学習の土台を整えておくことが、後の応用的な学習や入試対策をスムーズに進めるための重要な土台になります。
あらかじめ学習の土台ができていれば、それだけ応用問題や過去問演習などに時間をかけやすくなり、受験に向けた学習に余裕を持って取り組めるでしょう。
課題1:生徒によっては、先取り学習の進度についていけないことがある
一方で、すべての生徒が先取り学習のスピードについていけるとは限りません。特に、自分のペースで理解を深めたい生徒や、学校の授業についていけていない生徒、学校の授業で習うことで十分な内容理解ができている生徒にとっては、塾での先取り学習が負担になりやすく、つまずきの原因になることもあります。
先取り学習を行う際は、各生徒の理解度をこまめに確認しつつ、無理のない進め方を心がけることが大切です。
課題2:理解が不十分なまま進み、「わかったつもり」になりやすい
先取り学習をすることで「とりあえず、習ったから大丈夫」と安心してしまい、実際には知識の定着が不十分なこともあります。内容の理解が浅いまま次の単元に進んでしまう子も少なくない点には、注意しなければなりません。
その場合は、学校の授業も復習として機能せず「わかったつもり」で進んでしまう可能性があるため、塾での先取りの際には、確認テストや再演習、振り返りの時間をしっかり設けることが必要です。
先取り学習の効果を引き出すためには、生徒たちの理解度の確認やフォロー体制も含めて、丁寧に行うことが必要です。
【教科別】先取り学習の効果
先取り学習の効果は、教科ごとに異なります。
ここでは英語・数学・理科・社会・国語の5教科について、先取り学習が生徒にとってどのようにプラスに働くのかを整理していきます。
英語|単語や文法の知識を土台に、長文読解やリスニングの力を伸ばせる
英語は、単語や文法といった知識を土台に、読解・リスニング・英作文などの技能を伸ばしていく教科です。
先取り学習によって、単語や文法などの基礎知識を早期に定着させておけば、長文演習・リスニング対策などに割ける時間を増やすことができます。また、長文読解問題やリスニングを解くためには、そもそも文法や単語の知識があることが前提条件となるため、基礎を固めることは、入試の得点アップに直結します。入試では長文問題の配点が高くなっていますので、早期の基礎定着は入試本番でも大きな強みとなるでしょう。
数学|基礎の定着を早め、演習問題を解く時間を多く確保できる
数学は、先取り学習の効果が特に出やすい教科です。
「正負の計算」や「文字式」で習った内容を「方程式」や「関数」で使うように、数学は、前の単元で習った内容を次の単元で活用することが多い教科です。単元同士が積み重なる構造になっているため、基礎単元を早めに学習しておくことで、後の学習をスムーズに進めやすくなります。
さらに、数学では「理解したあとに、どれだけ演習を積むか」が得点力を左右します。そのため、学校の授業までに基本的な学習内容の理解を終わらせておき、定期テスト前や入試前に演習の時間をしっかり確保することが重要になります。
理科|知識が定着し、実験や観察の思考が深まる
理科は、内容の抽象度が高く、初めて聞く専門用語や現象にとっつきにくさを感じる生徒も少なくありません。だからこそ、学校の授業よりも先に塾で基本的な知識を頭に入れておくことで、授業での理解のハードルを大きく下げることができます。
たとえば「化学変化」「電流」「圧力」などの単元は、事前知識なしだとすぐに理解することが難しく、生徒がつまずきやすい内容です。しかし、先取りで用語や基本原理を押さえておくことで、学校の授業が復習の位置づけになるので、理解が深まりやすくなります。
また、実験や観察の授業にも、基礎的な理解ができた状態なので、余裕を持って取り組めます。「なぜこうなるのか」と自分の視点で考える余裕が生じ、理科を「暗記科目」ではなく「考える教科」として深く学ぶことで、知識が定着しやすくなるでしょう。
社会|全体像をつかむことで、授業が整理の時間になり理解が深まる
社会は、事前の基礎知識の有無によって、理解度が大きく変わる教科の一つです。学校の授業では、出来事や現象、制度などを一つひとつ取り上げて解説していくため、時系列的な流れや全体像がつかめていないと、それぞれが点と点の知識になりやすいという特徴があります。
特に歴史や地理は、暗記だけでなく「流れ」や「因果関係」の把握が重要です。あらかじめ、塾で学習領域の全体像や基本用語を押さえておくと、何が重要で、何と何がどのようにつながっているのかを意識しながら学校の授業に参加できるので、理解度・定着度がアップします。
受験を見据えた学習計画としても、塾で先に知識をインプットしておくことで、「時事問題との関連づけ」や「思考問題への対応」といった視点で、授業を入試対策につなげやすくなります。早めのインプットが、社会の得点力アップの土台になるのです。
国語|語彙や文法の基盤を早めに固めて、読解力・記述力をじっくり伸ばせる
国語では、文章の読解・記述の基盤となる力を早めに育てておくことが、読解力や記述力の伸びにつながります。
日本語の「語彙」や「文法」「記述の型」などの基礎的な知識を習得し、それらの知識を用いて読解問題や作文問題に取り組みます。さらに、「説明文」「物語文」「論説文」などの文章構造の理解や、設問のパターン別アプローチ(傍線部の理由・言いかえ・抜き出しなど)などの読解練習を重ねることも大切になります。
先取り学習で、早い段階から基礎知識の習得に取り組んでおくことで、読解練習や演習問題に時間を割くことができ、得点アップにつながります。
そして、定期テストや受験を見据えると、「記述」や「古文・漢文」を伸ばすことでライバルとの差別化が可能です。これらも早めに塾で型や知識をインプットしておくことで、時間をかけて練習でき、他教科と同様に、十分に力を伸ばせる教科となります。
教科によって、先取り学習の効果の出方やねらいは異なります。実施の際は「どの力を伸ばしたいから、どのタイミングで取り入れるのか」という視点で、効果を引き出しましょう。
先取り学習を塾で導入するための3ステップ
先取り学習は、単に学習の進度を早めるだけではなく、生徒の理解度や自信にも大きく関わる取り組みです。だからこそ、導入の際には、目的や進め方を丁寧に検討することが欠かせません。
ここでは、塾で効果的に先取り学習を導入するための、3つのステップを紹介します。
ステップ1:導入の目的と実施の対象を明確にする
まず大切なのは、「誰に・何のために」先取り学習を実施するのかという、導入の目的と対象を明確にすることです。
たとえば、
- 受験を見据えて、演習問題を解く時間や解説の時間を確保したい
- 数学が得意な生徒が多いクラスで、先の単元の内容を早めに習得させたい
というように、クラスの状況や学力層に応じて目的や内容を設定することで、より成果につながりやすくなります。
また、生徒一人ひとりの理解度を見極めることも重要です。苦手な単元を無理に先取りすると、かえってつまずきの原因を増やしてしまうこともあります。正答率が落ちがちな単元は、生徒の理解度に合わせて丁寧に教え、それ以外の単元から始めるなど、適切な先取りのための工夫も必要でしょう。
ステップ2:カリキュラム・進度の調整をする
目的が定まったら、次は実際の進め方を設計していきます。このときに十分意識したいのは、学校の授業との進度や単元のズレを把握することです。学校の教科書やカリキュラムと照らし合わせながら、無理のないスケジュールを立てましょう。
また、先取り学習は「一度学んだら終わり」ではありません。演習や確認テスト、振り返りの時間も含めた学習設計が重要です。
たとえば、以下のように段階を分けて繰り返すことで、知識の定着を図ることができます。
- 先取り授業:学校の1〜2週間前を目安に、新単元を解説
- 学校の授業直前:理解度の確認テストを実施
- 学校の授業後:演習問題で理解をさらに深める
- 定期テスト前:単元全体のふり返りと弱点補強を行う
このように同じ内容を複数回取り扱うことで、「学習したのに忘れてしまった」という事態を防ぎ、定着しやすくなります。
ステップ3:生徒・保護者への説明とフォロー体制を整える
先取り学習は、塾の取り組み方によっては、生徒に負担やプレッシャーを与えてしまうこともあります。そのため、導入前に「なぜ先取りをするのか」「どのように進めるのか」を生徒・保護者に丁寧に伝え、不安を生じさせないための配慮・工夫が欠かせません。
たとえば、
- わからないときは、いつでも戻って復習できる
- 定着の確認を行うので、「わかったつもり」にはなりにくい
- 質問のための時間をしっかり確保する
といったプランの説明を加えることで、生徒自身が納得しながら取り組める学習スタイルに移行しやすくなるでしょう。
また、保護者への十分な説明と信頼関係の維持も、先取り導入を成功させるために大切にしたいポイントです。「このような理由で先取りを始めます」「この範囲を、この時期までに進める予定です」など、具体的な見通しやフォロー体制を、保護者にも伝えることで、塾への信頼感と安心感につながります。
先取り学習導入を、生徒だけでなく保護者の理解を得たうえでスタートすることは、成果をあげるための大前提。塾としての取り組みを、保護者との連携で軌道に乗せる気持ちで、先取りのためのフォロー体制を整えていきましょう。
目的に応じた設計で、先取り学習を効果的に活かそう
中学生の先取り学習は、生徒の理解度やモチベーション、教科ごとの特性に配慮しながら進めることで、大きな成果につながる可能性を秘めています。
特に英語や数学といった積み上げ型の教科では、先取りによって早めに基礎を固めることで、応用力や入試対策へのスムーズな移行が期待できるでしょう。
大切なのは、先取りを「誰に・何のために行うのか」という視点を持ち、生徒一人ひとりの特性やクラスの状況に合わせて、柔軟にカリキュラムを設計することです。そのうえで、つねに丁寧なフォローを心がけ、生徒と保護者に安心感を与えることで、先取り学習の効果をより高められるでしょう。
「よくわかった」「できた」という自信につながる実感を生徒が積み重ねられるよう、自塾の方針に合わせて、効果的な先取り学習の導入をご検討ください。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。