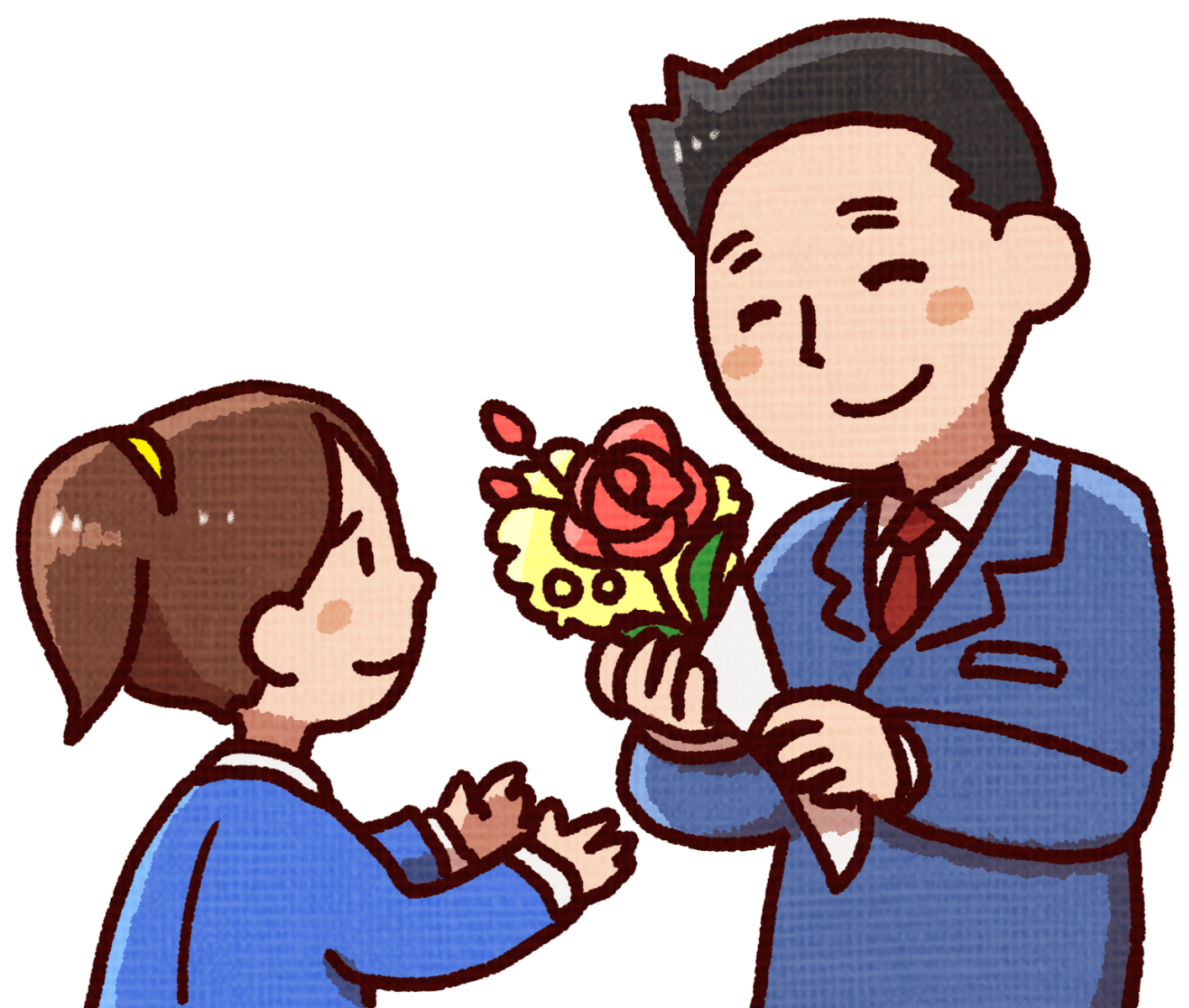目次
「高校受験を控えた生徒がやる気を出せるよう、メンタルケアをしたい」
「余計なことを言って逆効果になるのが怖い」
「他の先生方がどのように声かけしているかを知りたい」
受験生を受け持っている先生や、これから受け持つ先生の中には、このようにお悩みの方もいらっしゃることでしょう。高校受験は生徒にとって、人生を大きく左右する一大イベントです。不安やプレッシャーから感情が不安定になることも、少なくありません。
そこでこの記事では、受験生が抱えがちなストレスや心情の変化を解説し、効果的なメンタルケアのコツを紹介します。重要なポイントとともに、具体的な声かけの例を解説しますので、高校受験を控える生徒への接し方の参考にしてください。
受験期の生徒が抱えがちなストレスとは?
まずは、受験生がストレスを抱える主な原因を解説します。生徒のメンタルケアをするためにはまず、なぜストレスを抱えているのかを知る必要があるからです。
日頃から、生徒の様子を観察したり話を聞いたりしながら状況を推測して、適切な声かけを行いましょう。
試験の成績
試験の成績がストレスの原因となる受験生は、少なくありません。とくに模試では、志望校の合格可能性や順位が数値で示されます。その結果、目標に届かない焦りや、他人との比較による劣等感が生じやすくなってしまいます。また、努力したにもかかわらず結果に結びつかなかった場合、落ち込みやモチベーションの低下につながることもあります。
しかし模試の結果は、生徒の当日のコンディションや、出題内容の得意不得意によって変動することも少なくありません。試験の成績が原因でストレスを感じていそうな場合は、試験結果はあくまで参考程度である点を伝え、前向きな言葉で励ましましょう。
声かけの具体例:
- 「模試を受けるのは結果に一喜一憂するためではないよ。苦手分野を把握して、対策するためのものだからね」
- 「模試の結果は、あくまでも現時点での到達度の参考と捉えて。入試本番までまだ時間があるから、ここから挽回していこう」
一方で、本番までの残り期間を考慮して成績が低すぎる場合は、志望校や学習方法の変更を提案したほうが良いケースもあります。高すぎる目標設定は過度なプレッシャーとなり、かえって実力を発揮できない原因になりかねないからです。
声かけの具体例:
- 「次回の試験に向けて、学習方法を少し変えてみるのはどうかな?効果的なやり方を一緒に考えてみよう」
各生徒の状況を踏まえ、一人ひとりに合った声かけを心がけてください。
家庭環境
教育の現場で見落とされがちなのが、家庭環境に起因するストレスです。
たとえば、親から過度な期待を寄せられていたり、兄弟姉妹と比較されたりしたことが、心理的な負担や落ち込みにつながっているケースが当てはまります。本人は十分に努力しているのに、家族に認めてもらえないと感じてしまい、葛藤することもあるでしょう。休憩中に「勉強しなさい」と言われたり、ことあるごとに「頑張れ」と繰り返されたりすることも、受験生にとってはプレッシャーになります。
さらに、家庭の経済的不安がストレスの原因になることもあります。参考書を買うための費用や通塾などにかかる費用に不安があったり、本人は私立を志望しているのに学費面で公立を受験せざるを得ないケースなどが考えられるでしょう。
家族との関係に悩む受験生には、たとえば以下のように声をかけてみてはいかがでしょうか。
生徒への声かけの具体例:
- 「親御さんの期待に応えたいという気持ちも大切だけど、まずは自分のペースを大事にしよう。君の頑張りは、私もしっかり見ているよ」
- 「家でのやり取りで悩んでいることがあれば、いつでも相談してね。場合によっては、一緒に保護者の方とお話しすることもできるよ」
- 「行きたい高校をあきらめる前に、奨学金制度などについて調べてみよう。先生も情報を集めて協力するよ」
また、高校受験という重大な人生の岐路を前にすると、生徒だけでなく保護者も不安や心配事を抱えてメンタルが不安定になることがあります。そのストレスの矛先が受験生に向かってしまうと、生徒の心理的負担や学習意欲の低下につながるだけではなく、家族間に亀裂が生じることにもなりかねません。日々の関わりや三者面談などのタイミングでは、保護者の変化も見逃さないよう心がけましょう。
保護者への声かけの具体例:
- 「受験はマラソンのようなもので、本人が息切れしないためのペース配分が大切です。勉強と休息、オンオフの切り替えで、うまくメンタル面のバランスを取る必要があるんです。そのためには、我々からの指導と、ご家庭でのサポートの両方とも重要ですから、ともに協力していきましょう」
- 「お母様の不安なお気持ちもよく理解できますが、〇〇さんは決めた目標に向かってどう努力すればいいか、自分で考えて頑張れる子ですよ。お子さんを信じて一緒に見守っていきましょう」
ストレスの原因が家庭環境にある場合、生徒のメンタルケアだけでは解決が難しいことがあります。三者面談などを通じて、保護者の心配事や意向を聞いたり、受験生本人の頑張りを伝えたりして、円満な状況改善を図りましょう。
時間管理
時間管理がうまくできず、もどかしさや焦りを感じる受験生も多くいます。とくに部活などで忙しい生徒にとっては、勉強のための時間確保が難しく、ストレスを感じることもあるでしょう。
中には、スケジュールを無理にこなそうとして睡眠時間を削り、体調を崩してしまう生徒もいます。このような状況に陥ると、学習効率が落ちてしまい、逆に勉強の成果が出にくくなってしまいます。
そんな生徒には、思うようにスケジュールをこなせない自分を責めずに、まずは簡単な習慣付けから始めるように提案してみましょう。
声かけの具体例:
- 「まずは、決まった時間に机に向かうことから始めてみよう」
- 「勉強時間を確保する難しさは多くの人が感じているから、自分を責めないようにね。❝少しずつでも毎日❞ を心がけよう」
受験で本来の実力を発揮するためには、日頃からの心身の健康維持が大切です。受験生が焦って無理をしないよう、睡眠時間や体調管理に配慮しつつアドバイスをしていきましょう。
人間関係
高校受験を控える生徒にとっては、同年代のライバルとの人間関係もストレスの原因になります。周囲との競争意識は向上心を刺激するという良い面もありますが、過度にならないように注意も必要です。他人の状況に気を取られすぎると、焦りや不安から自分のペースで学習ができず、集中力が妨げられてしまうこともあるでしょう。
また、SNSでの友人関係も受験生の心理に大きく影響します。たとえば、「友達グループが勉強会をしている写真を見て、自分だけ誘われていないとモヤモヤする」「友人からのメッセージにすぐ返信しなければと気になって、なかなか勉強に集中できない」といった状況は、昨今の中学生にはよくある悩みと言えます。さらには、LINEグループへの返信やInstagramのストーリーのチェックなど、SNS上のコミュニケーションに時間を取られて勉強時間が確保できない、という問題も生じています。
このような悩みを抱える受験生への声かけで大切なのは、意識を他人、外部ではなく自分自身に向けさせること。またSNSに関しては、学習の妨げになるほど生活の多くを占めないよう、一日の中でアクセスする時間を決める、通知をオフにする、などの提案をしてみましょう。
声かけの具体例:
- 「SNSより、目の前の勉強や自分の時間を優先していいんだよ。すぐに返事ができなくても、本当の友達なら離れていかないから無理しないで」
- 「人それぞれのペースがあるから、比較するなら、友達より過去の自分と比べよう。苦手教科も、こんなに点数が上がっているよ」
人間関係に悩みや不安を抱えながらも、先生や親に相談するのをためらってしまう受験生もいます。相談を受けた場合は親身に話を聞き、適切なアドバイスで軌道修正を促しながら、本人と一緒に解決策を見つけましょう。
生徒一人ひとりの悩みに寄り添い、個々の状況に合ったメンタルケアを心がけましょう。
受験生のメンタルの通年変化を理解しよう
ここからは、高校受験を控えた中学3年生のメンタルの変化を、1学期、夏休み前後、2学期、直前期に分け、時系列に沿って解説します。
受験生の悩みは、時期により大きく変わります。各時期における効果的なサポート方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1学期(目標設定期)の特徴と対応
▼心理的特徴
- 受験への漠然とした不安
- 目標設定に伴うプレッシャー
- 現状の学力と目標のギャップによるモチベーション低下
▼サポートのポイント
- 実現可能な目標設定のサポート
- 学習計画の立て方のアドバイス
- モチベーション維持のための定期的な面談
中学3年生の1学期は、受験を意識しつつも、まだどのように対策を進めるべきか分からず、漠然とした不安を持つ生徒が多い時期です。実現可能な目標を設定し、進むべき方向を明確にすることが不安解消のカギとなります。「志望校合格」という大きな目標を掲げる一方で、まずは成長を実感しやすい小さな目標クリアを積み重ねていけるように、生徒と一緒に考えましょう。
定期的な面談やカウンセリングを通じて、学習計画の立て方について助言するのも効果的です。受験は長期戦なので、1学期から無理な頑張りで息切れしてしまわないよう、モチベーションの維持を意識したサポートを心がけてください。
夏休み前後の焦りと不安
▼心理的特徴
- 計画と現実のズレによる焦り
- 模試の結果による自信喪失
- 他者との比較による不安
▼サポートのポイント
- 学習計画の軌道修正をサポート
- 夏期講習での学習習慣の立て直し
- 具体的な弱点克服プランの提案
受験において、自由時間が増える夏休みは勝負の時期です。時間が増える分、学習計画の重要性が増し、自己管理がうまくできずに焦る受験生も出てくるでしょう。さらに、夏休み前後の模試結果が自信を失わせ、焦りや不安を増加させる原因となる場合もあります。
この時期のサポートは、学習計画の見直し・改善から始めましょう。焦りが強まりやすい時期だからこそ、軌道修正や無理のないスケジュールを意識することが重要です。
具体的な弱点克服プランを提案すると、学力アップを実感しやすい効果的な学習ができ、精神面・心理面の安定にもつながりやすいでしょう。また、夏期講習を活用して日々の学習習慣の改善・立て直しをするのも効果的です。講習を通じて毎日の勉強が習慣化できれば、自分の勉強ペースをつかみ維持しやすくなります。
また、部活動の引退を迎え、受験が近づいていることを実感する生徒も多い時期です。生徒が気持ちを切り替え、受験に向けた心構えを本格的に整えるためのサポートを行いましょう。
2学期(追い込み期)の心理変化
▼心理的特徴
- 志望校合格への不安の具体化
- 進路変更の検討による迷い
- 学習の行き詰まりによる停滞感
▼サポートのポイント
- 定期的な進路相談の実施
- 具体的な受験対策の提示
- 学習方法の見直しと改善
2学期で受験生のメンタルがとくに不安定になりやすいのが、内申点が確定する11~12月の時期です。内申点が確定すると、志望校に対する不安が具体的になるうえに、目標に届かない場合は進路変更の検討も求められます。学習面でも、本格的な受験勉強を開始して半年という区切りで息切れしてしまい、停滞感を感じる受験生も少なくありません。
この時期には定期的な進路相談を行い、受験生自身が納得できる結論を出せるようにサポートしましょう。また、停滞感を取り除くために学習方法の見直しを行ったり、具体的な受験対策を提示したりするのも大切です。
直前期の緊張とストレス
▼心理的特徴
- 試験への強い緊張と不安
- 体調管理への不安
- 家族関係のストレス
▼サポートのポイント
- ストレス解消法の具体的アドバイス
- 体調管理や生活リズムの調整に役立つアドバイス
- 試験当日の具体的なイメージトレーニング
直前期は、多くの受験生にとって、ストレスが最も高まる時期と言えるでしょう。入試そのものへの緊張や不安感のほか、体調不良で受験できなくなることへの不安から、体調や衛生面に対して過敏になる生徒もいます。また、受験に際して不安になりやすいのは受験生の家族も同じです。プレッシャーや不安が家庭での摩擦を引き起こす場合もあるため、面談の際には家族関係にも気を配りましょう。
直前期には、受験生がリラックスできる環境作りが重要です。無理をして試験当日に悪影響が出ないように、生活リズムを整えるためのアドバイスをしましょう。規則正しい生活を送ることは、体調面だけでなく、精神的な安定にもつながります。また、深呼吸や軽い運動などの具体的なストレス解消法を提案し、リフレッシュの時間を確保できるよう促すのもおすすめです。
さらに、試験当日のイメージトレーニングを事前に行っておくと、受験生が安心して試験に臨めるでしょう。試験会場の雰囲気や当日の流れを具体的にシミュレーションすることで、当日の緊張を和らげられます。
年間を通じたメンタルの傾向を知って、受験生の心情に寄り添った対応を目指しましょう。
周りの教師・保護者と情報共有をしよう
高校受験生のメンタルケアは、他の先生や保護者と連携しながら行うことが大切です。受験生の悩みは一人ひとり異なるため、対応や声かけも個々の生徒に応じたものが求められます。保護者や他の先生方と情報共有を行うことで、より適切できめ細やかなサポートができるでしょう。
ここからは、受験生のメンタルケアに役立つ情報共有の内容を解説します。
チームを組んで成功事例を共有し合う
受験生への対応は、複数の教師や講師がチームとなって行うことが大切です。先生同士が日頃から情報共有を行っていれば、生徒一人ひとりが抱える不安を多角的に認識・理解でき、より適切なサポートが可能になります。
たとえば生徒が不安を表に出したとき、その場に担任の先生がいるとは限りません。そんなとき、先生同士が個々の受験生の状況を共有していれば、居合わせた先生が適切に対応できます。情報の共有により先生たちの対応に一貫性が生まれるため、より安心感を与える声かけやサポートを生徒に行えるようになります。
また、生徒によって悩みを相談しやすい相手が異なるので、できるだけ多くの大人が関わるようにすると、生徒にとって相談相手が増えるという利点もあります。その際に効果的だった声かけや、改善が見られたサポート内容を共有してもらえば、他の受験生への対応にも応用できるでしょう。
保護者との連携がサポートのカギになる
受験生のメンタルケアには、保護者との連携も欠かせません。保護者からの情報で、生徒の家での学習状況や心理的な変化を把握できるほか、保護者も子どもの学校や塾での状況を知ることで、家庭でのサポートをしやすくなります。長年近くで見守ってきた保護者だからこそ、教師が気付きにくい些細な変化や、効果的なメンタルケアの方法を知っている場合もあるでしょう。
保護者との情報共有には、三者面談は格好の機会です。生徒本人を前に保護者の視点を交えて現状や課題、悩みについて話し合うことで、生徒との対面だけでは見えにくかった問題の原因や本質が明確になり、サポートしやすくなります。保護者には受験成功のためのメンタルケアの重要性を伝え、望ましい関わり方や声かけを提案するとよいでしょう。
先生同士、保護者など、周囲と連携し合って、生徒が前向きに受験勉強に取り組める環境を作りましょう。
揺らぎやすい受験生のメンタルに優しく寄り添おう
この記事では、受験生が抱えがちなストレスの原因や、受験生特有の心理面での通年変化、他の先生・保護者との協力体制でメンタルケアに向き合う重要性をお伝えしました。
高校受験は、生徒の今後の人生に大きな影響を与える一大イベントです。それだけに、今までになかった緊張感やプレッシャーに悩む中学生が大勢います。今回の内容を参考に、生徒たちが受験で本来の実力を発揮できるよう、一人ひとりに寄り添ったメンタルケアを目指してみてください。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。