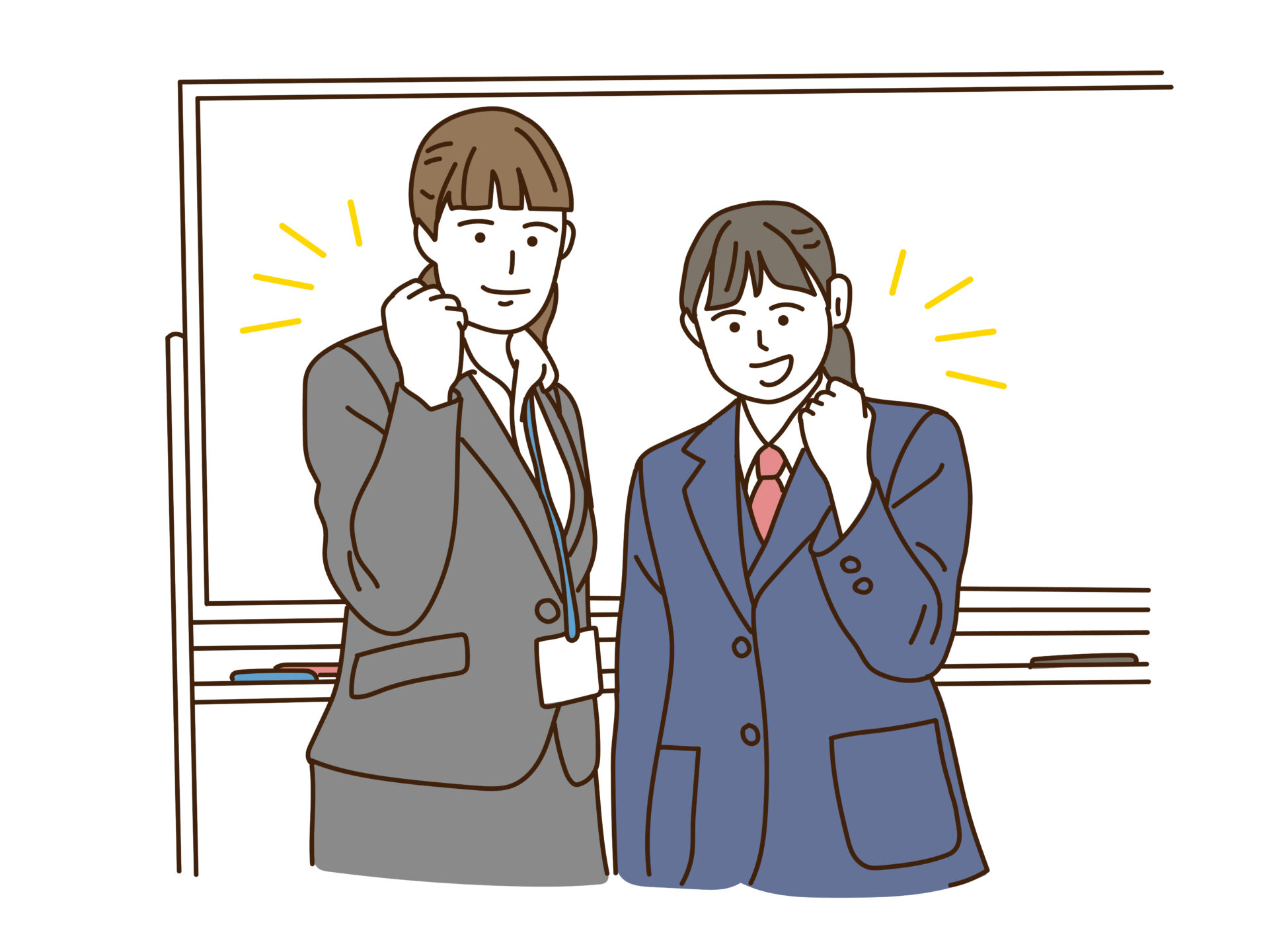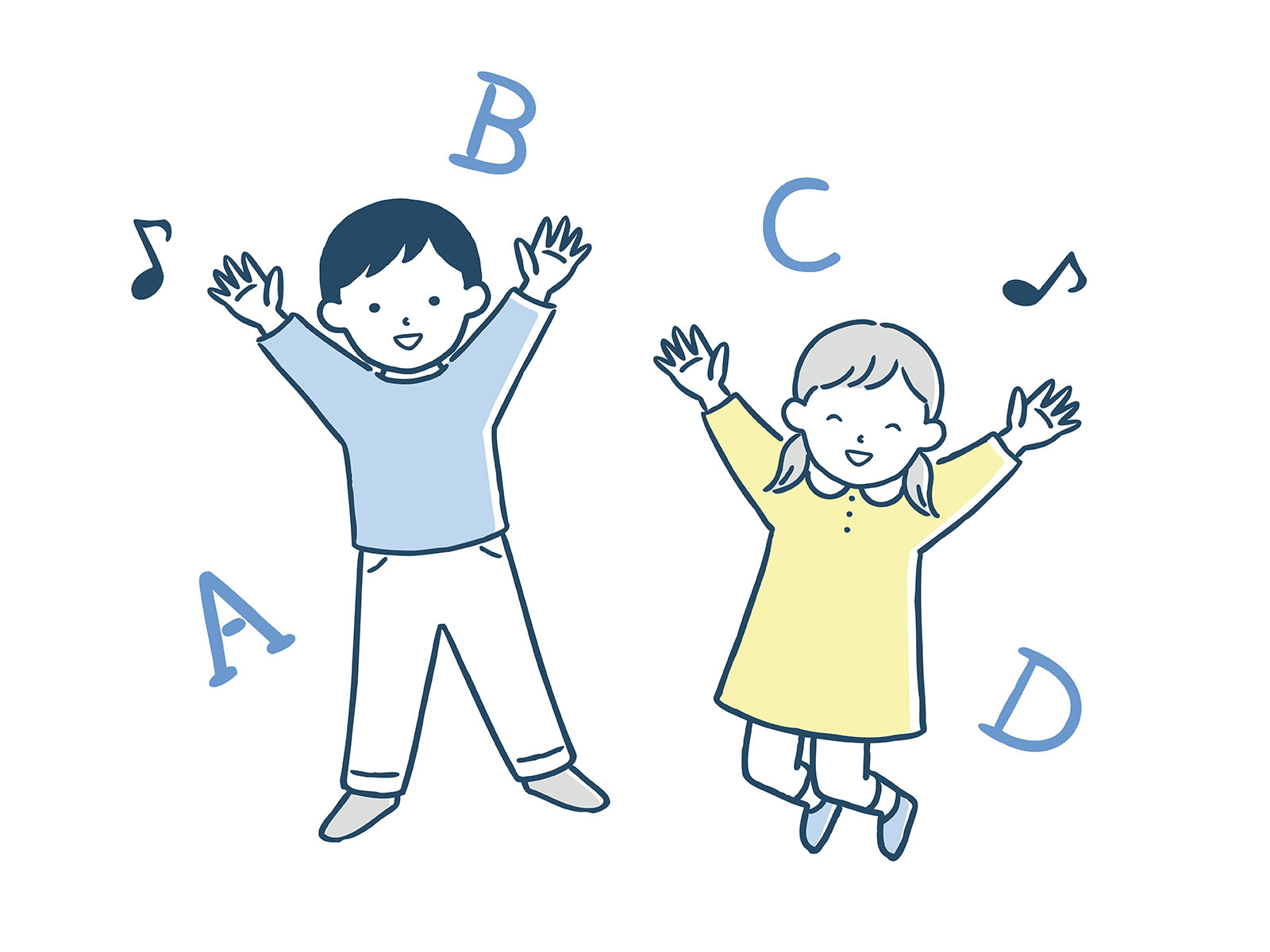「何度も練習しているのに、なかなか漢字が覚えられない」
「テスト前にあんなにがんばったのに、すぐに忘れてしまう」
そんな子どもたちを前に、「漢字をどう教えればいいのだろう?」と悩むことはありませんか?
小学校中学年ごろから、漢字への苦手意識をもつ児童が増えてきて、指導に困っている先生も多いと思います。しかし、漢字を覚えられないのにはちゃんと理由があります。そして、教師のちょっとした工夫や関わり方で、児童は自信をもって取り組めるようになるのです。
この記事では、漢字が覚えられない子どもたちの背景や苦手意識の原因を整理し、明日からの授業や指導に活かせる具体的な工夫や声かけのヒントをご紹介します。
漢字が覚えられないのは、なぜ?
一生懸命取り組んでいるのに、なかなか漢字が覚えられない児童には、いくつかの共通した背景やつまずきの傾向があります。
ここでは、児童が漢字につまずく主な理由を整理していきます。その子に合った指導のヒントを見つける手がかりにしていきましょう。
学年が上がるにつれて、習う漢字が難しくなる
小学校低学年で習うのは、画数が少なく、形や意味が直感的に理解しやすい漢字が中心です。しかし学年が上がるにつれて、画数が多く形が複雑な漢字や、抽象的な意味、複数の読み方をもつ漢字が増えていきます。
たとえば、1年生で習う「山」「木」などは、見た目も意味もわかりやすく、覚えやすい漢字です。ところが3年生になると、「様」「感」「発」のような形も意味もより複雑な漢字が出てきます。そのため、「難しい」「覚えにくい」と感じる児童が増えていくのです。
これまでは数回書けば漢字を覚えられていた児童も、3年生以降は「書いたのに覚えられない」「すぐ忘れてしまう」という経験をするようになります。
こうしたつまずきは、漢字の難易度が上がることで起こる自然な反応のひとつです。努力が足りないのではなく、「これまでとは違う難しさ」に戸惑っているサインとして捉え、丁寧に支援していくことが大切です。
「書くこと」そのものが苦手である
漢字を覚えられない児童のなかには、「書くこと」自体に苦手意識をもっている子もいます。
たとえば、鉛筆の持ち方が安定せず、うまく文字の形が整わない子や、手先の不器用さから文字を書くことそのものに大きな負担を感じている子もいます。また、筆圧が弱くて字が薄くなってしまい、見返したときに自分の書いた字が読みづらいというケースも見られます。
こうした児童は、何度書いてもうまく書けない経験が続くことで、「書くのが嫌い」「書きたくない」と、苦手意識を強めてしまいがちです。
文字を書くことそのものがつらいと感じている状態では、「覚える」ことに集中するのは難しくなってしまいます。やみくもに練習量を増やしても、学習の効果は出にくいでしょう。
まずは、書くという行為自体がその子にとって負担になっていないか、日頃の書字の様子をよく観察し、必要に応じて支援や声かけの工夫をしていくことが大切です。
短期記憶(ワーキングメモリ)が弱い
漢字を覚えるためには、「形」「意味」「音(読み方)」「使い方」といった複数の情報を同時に処理・記憶する力が必要です。そのため、ワーキングメモリが弱いタイプの子どもにとっては、負担が大きくなりやすい学習でもあります。
- 書いている途中で字の形がわからなくなる
- 何度も練習しているのに、すぐ忘れてしまう
というように、たくさんの情報を頭の中にとどめておくことが難しいのです。
努力しているのに結果につながらない経験を重ねると、「どうせ覚えられない」といったあきらめの気持ちが強くなってしまいます。
発達の特性が関係しているケースも
漢字学習がどうしても苦手な児童のなかには、発達の特性が関係しているケースもあります。その場合、努力しても成果につながりにくく、本人が自信をなくしてしまっていることも少なくありません。
このようなケースでは、本人の努力だけでは改善が難しいため、その子に合った教育的支援の必要性を視野に入れることが大切です。担任の先生だけで抱え込まず、学年の先生や支援担当の先生、管理職と連携しながら、できるサポートを考えていけるとよいでしょう。
漢字学習でつまずく原因は、児童によって異なります。日頃の学習の様子を観察したり、アンケートをとったりして、個別の理由を探りましょう。
かえって逆効果になりやすい漢字指導法
漢字の学習では、良かれと思って取り入れられている指導法が、児童によっては苦手意識や漢字嫌いを助長し逆効果になることもあります。
ここでは、つまずきや苦手意識につながりやすい指導の例をお伝えします。
作業的にくり返し書かせる
漢字を何度もくり返し書くことで覚えやすいという児童もいますが、すべての児童にとって、この方法が効果的とは限りません。
書くことが、意味を理解せずにただ手を動かすだけの作業になってしまい、記憶に残らない児童もいるのです。字形を正確に捉えられずに誤った漢字を何度も書くことで、間違ったまま覚えてしまうリスクもあります。
また、書くこと自体が苦手な児童にとっては、ただ時間がかかるばかりで効果のない作業になってしまうこともあります。そうすると「がんばってもできない」という感覚が残り、漢字への苦手意識を強めることになりかねません。
さらに、面白みのない単純作業は、創造性や自主性の強い子にとってはストレスになり、本来高まるはずの漢字への好奇心や学習意欲の低下につながることもあるでしょう。
書くこと自体に苦手意識がある児童には、回数よりも質を意識した練習が有効です。単純作業的に延々と何度も書くより、漢字の形や書き順を意識して3~5回書く方が、集中できて記憶に残りやすくなります。
厳しい添削
「とめ・はね・はらい」を丁寧に教えることは、漢字学習において欠かせないポイントのひとつです。しかし、細かすぎる添削が、かえって児童の「覚えた!」という自信を奪ってしまうこともあります。
特に、もともと漢字に苦手意識のある児童には「また間違えた」「何度も注意されてつらい」と感じさせてしまい、やる気の低下を招いてしまうでしょう。
気になる点を一気に全部直そうとするのではなく、まずは「全体の形が整ってきたね」「前よりずっと読みやすくなったよ」と、頑張りの成果を認めるポジティブな声かけを意識しましょう。
そして、一度に注意するポイントはなるべく少なくしましょう。複数の点を一気に注意するよりも、一つか二つずつ課題をクリアさせるほうが、子どもは前向きに取り組めるようになります。
正確な漢字習得のための添削や指導法が、逆に漢字学習への興味や意欲を低下させてしまうこともあります。児童の様子を見ながら、前向きに取り組めるような指導や声かけを工夫していきましょう。
漢字が覚えられない子のための具体的な教え方
漢字をなかなか覚えられない子には、「どこでつまずいているのか」を見極めたうえで、学びやすい方法を取り入れていくことが大切です。
ここでは、苦手意識を抱える児童にも効果的な、実践しやすい教え方の工夫を紹介します。
「読み方」をしっかり覚えよう
読み方は知っているつもりでも、実際に書こうとすると漢字が出てこないことがあります。たとえば、「重い」という漢字を覚えていても、「体重」や「重要」といった言葉になると正しい漢字が思い出せないというケースです。これは、「重=じゅう」という読みがあいまいなまま漢字練習をしているサインともいえます。
ただ漢字や単語を書く練習をくり返すよりも、初めに読みを定着させ、漢字の読みと意味が自分の中で確実につながることが大切です。確実に読めるようになると、単語における漢字の使い方や意味もあわせて理解しやすくなり、書くときの記憶の手がかりが増えていくのです。
実際に漢字が使われている例文や文脈のなかで、読みを確認しながら書く練習を行うと、「読む」と「書く」がつながり、より記憶に残りやすくなるでしょう。
漢字の成り立ちから意味を理解しよう
漢字を単に形として覚えようとすると、どうしても暗記に頼ることになるので、画数が多くなるほど記憶に定着しにくくなります。しかし、成り立ちや部首の意味を知ると「この漢字は、なぜこの形なのか」がわかり、漢字の意味と字形がつながって記憶に残りやすくなります。
たとえば「休」は、人が木に寄りかかって休んでいる様子を表します。また「明」は、左右ともに光を放つ日(太陽)と月が並んで「明るい」ことを意味します。
このように、漢字が生まれた由来や、その形に込められた意味を知ることで、単なる暗記ではなく意味を深く理解しながら覚えることができ、記憶に残りやすくなるのです。
また、部首を理解していると、新しい漢字に出合ったときにも、「にんべんは人を意味するから、人に関する漢字かな」「くさかんむりが付いているから、植物に関係する漢字だろう」といった気づきが生まれやすくなります。
このように、字形と意味のつながりがわかっていると、難しい漢字も覚えやすくなるでしょう。
五感を使って覚えよう
漢字を学習するときは、複数の感覚を使った方法を取り入れると、より記憶に残りやすくなります。
たとえば、「書く」という視覚と手の動きによる方法だけでなく、声に出して漢字を読むことで、「口で言う」「耳で聴く」という感覚も加わり、より確実な定着につながります。ノートに漢字を書く練習をする前に、漢字や熟語を目で確認しながら声に出して読みあげる、といった活動を取り入れるのもよいでしょう。
あるいは、空中で手を大きく動かして漢字を書く「空書き」も効果的です。ノートに書く前に、空書きで漢字の形や書き順を確認することで、正しく丁寧に書く意識が高まります。空書きは、人差し指とは限らず、小指やグー、手全体などを使って変化をつけることで、楽しみながら取り組めます。
このような体感をともなう学習法によって、漢字学習は面白くないという先入観がやわらぎ、漢字がより身近に感じられていくでしょう。
生活のなかで漢字に親しむ機会を増やそう
漢字が苦手な児童にとって、生活のなかで自然に漢字にふれる機会を増やすことは、学習へのハードルを下げるうえでも効果的です。
たとえば、教室の掲示物や配付プリントには意識的に習った漢字を取り入れ、目にする機会を増やしてみましょう。
授業のちょっとした時間や雨の日の休み時間には、「漢字探しゲーム」や「漢字しりとり」といった活動もおすすめです。こうした活動を取り入れることで、楽しみながら漢字にふれる時間をつくることができます。
また、授業以外の時間や家でも、日記を書く習慣や、手書きのメッセージや手紙を書くことを提案したり、本を読むように働きかけたりすると、子どもたちが無理なく漢字と接する場面が増えていきます。
このように「勉強」としてだけではなく、日常生活のなかで漢字に親しむ時間を積み重ねていくことで、自然と読む力・書く力の基礎が育っていくでしょう。
デジタル教材も活用しよう
漢字の学習にもデジタル教材をうまく取り入れることで、子どもの学習意欲や漢字への興味を引き出すことが期待できます。
特に、紙と鉛筆の学習に苦手意識がある子どもにとっては、タブレットを使うことで漢字学習へのハードルが下がり、前向きに取り組みやすくなる場合もあります。
大切なのは、デジタル教材の使用を「楽しい」だけで終わらせず、漢字の読み・書き・意味の理解といった学習目標につながるように活用することです。紙の学習と組み合わせながら、それぞれの児童に合った学び方を見つけていきましょう。
漢字への興味や知る楽しさが生まれると、学習意欲につながります。個々の子どもの特性に合った学習法が見つかるように、多角的なアイデアを活かした指導を工夫しましょう。
漢字が覚えられない子への指導のコツ
漢字をなかなか覚えられない児童には、学習内容だけでなく、日々の関わり方や声かけも状況の好転に役立ちます。
ここでは、なかなか漢字が覚えられず困っている児童への声かけや関わり方のポイントを、お伝えしていきます。
小さな成功体験を積み重ねよう
漢字を覚えられない児童にとって、「できた!」という体験は何よりの自信になり、苦手意識の払拭に役立ちます。
最初から完璧に書けるようになることを目指すだけが、良いわけではありません。読み方を正しく答えられたことや、例文中で漢字を適切に使えたことなども、「がんばったね」と励ますきっかけになります。
まずは、「前より字の形が整ってきたね。この調子!」「今日は、新しい漢字もよく読めたね」など、少しでもポジティブな変化や努力を見つけて褒めてあげましょう。小さな成功による自信や嬉しさを積み重ねることで、「自分も漢字を覚えられるんだ」という気持ちが育ち、学習に前向きに取り組めるようになります。
状況に合わせて学習量や方法を調整しよう
みんなと同じように漢字を学習するなかでつまずきを感じている児童は、「自分には難しくて、周りの子と同じようにできない」と感じて、自信を失うことがあります。その場合は、その子にとって無理なく取り組めるような工夫をすることが大切です。
たとえば、
- 書き取り練習の量を減らす
- 新しい漢字は、なぞり書きできるような教材を使う
- 飽きないように、取り組む時間を短くして集中できるよう工夫する
といった方法があります。
「3回だけ集中して書く」「今日習った漢字の中で、この文字だけは確実に覚える」など、小さな目標を設定してクリアしていくと、達成感を得やすくなり本人が進歩を実感できます。難なくこなせるようになってきたら、少しずつ設定量を増やすなど調整してあげましょう。
児童のペースに合った方法・進度で確実に覚えていくことができれば、学習を負担に感じることはなくなります。その子に合った学習量で苦手意識をやわらげ、漢字学習への前向きな気持ちを育てていきましょう。
児童の特性に応じて柔軟に学習法を変えよう
児童によっては、漢字の形を覚えることや書くことが、どうしても難しい場合があります。それは、努力が足りないからではなく、記憶の仕方や見え方、感じ方など、その子ならではの特性によるものかもしれません。
授業での指導がどうしても功を奏さないときには、その子の認知特性に合った学び方を一緒に探していくことが大切です。一人で対応するのが難しい場合は、学年の先生や支援担当と相談しながら、最適な指導方法を見つけていきましょう。
児童一人ひとりのペースや特性の違いに配慮し、その子に合った「できる方法」を一緒に見つけていきましょう。
漢字が覚えられない子には、必ず理由がある
漢字が覚えられないのは、やる気がないからでも、集中していないからでもありません。学年が上がり、学ぶ漢字の量や難しさが増していくなかで、つまずいてしまう児童たちは、それぞれ違った理由で苦手意識を感じているのです。
だからこそ、その子に合った教え方・学び方を見つけることが大切です。無理のない方法で小さな目標を設定し、少しずつ「できた」「覚えられた」という実感を積み重ねていけば、苦手意識もやわらいでいきます。
本来、漢字にはそれぞれの歴史、成り立ちがあり、知的好奇心を引き出すに十分な奥行きのある面白さを秘めています。先生の関わり方ひとつで、子どもの持つ漢字へのイメージが大きく変わることもあり得ます。一人ひとりのつまずきに寄り添いながら、その原因を探り、前向きに学べるような学習法を工夫していきましょう。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。