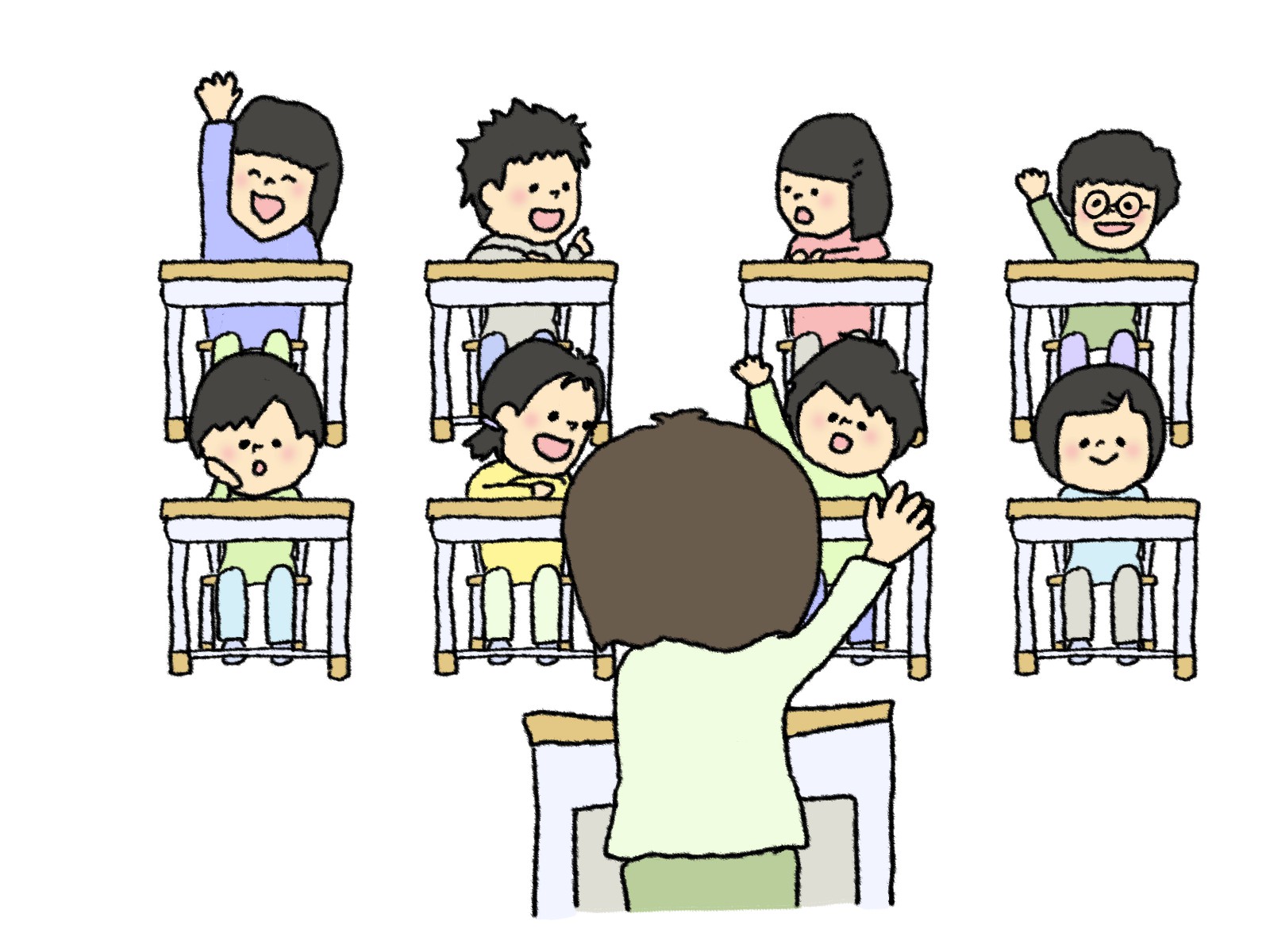
目次
「次の席替えは、ちょっと面白い方法でやってみたい」
「席替えが、子どもたちの学校生活にとって、ポジティブな出来事になるような工夫をしたい」
このように考えている先生に向けて、この記事では、子どもたちと一緒に楽しめる席替えの方法を紹介します。
くじ引きやトランプなどを使った定番のアイデアに加えて、子ども同士の会話が生まれやすくなる工夫や、特別感があって楽しめる演出など、すぐに取り入れやすい席替えの方法を11個まとめました。
子どもたちにとって教室の座席は、毎日の授業で積極的に学び、楽しい学校生活を送るうえで、とても重要です。席替えを楽しめるだけでなく、席替えによるトラブルを防ぐための配慮についても解説します。
この記事を参考にして、子どもたちがワクワクする席替えを実践してみてくださいね。
ランダムに決める席替えアイデア
偶然に任せる席替え方法は、手軽に実施しやすく、子どもたちもゲーム感覚で楽しめます。くじを引くときのドキドキ感や、その場のリアクションで、毎回違った盛り上がりが生まれるのも魅力です。
ここでは、ランダムに選んで決める席替えのアイデアを5つ紹介します。
くじ引き席替え
【準備するもの】
座席番号を書いたくじ(紙片・カード・割り箸など)、くじを入れる箱や袋
【手順】
- 座席にあらかじめ番号を振っておく(黒板や大きな紙に書く)
- 座席と同じ番号を書いたくじを用意し、1人ずつくじを引かせる
- 引いた番号に対応する席に座る
【ポイント】
くじを引く瞬間は、教師がリアクションを入れたり、ちょっとした声かけをしたりすると、盛り上がります。手軽でシンプルですが、毎回子どもたちをドキドキさせられる方法です。
トランプ席替え
【準備するもの】
子どもたちが引くための人数分のトランプカード、座席に貼る用のトランプカード
【手順】
- 各座席にトランプカードを貼っておく
- 子どもに1枚ずつトランプカードを引かせる
- 引いたカードと同じ席に座る
【ポイント】
「ハートはほっとする席」「スペードは集中席」など、マークに意味を持たせるとさらに楽しくなります。また、ジョーカーやエースを「先生のすぐ近く」などの特別席に設定、といったアレンジを加えると盛り上がります。引くためのカードは事前に子どもの前でシャッフルして、公平感を演出しましょう。
サイコロ席替え
【準備するもの】
サイコロ、列番号のくじ(必要に応じて)
【手順】
- くじをひいて、それぞれが座る「列」を決める
- 各列の席に、一番前から順に1、2…と番号をつけていく
- 同じ列になったメンバー同士がじゃんけんをして、サイコロを振る順番を決める
- 順番にサイコロを振り、出た目の番号の席に座る(例:3が出たら前から三番目の席)
- すでに出た目の席が決まっていた場合は、再度サイコロを振る
【ポイント】
何が出るかわからない楽しさがあり、サイコロを振るたびに盛り上がります。なお、席を離したい事情のある子同士がいる場合、座る列を、くじではなく先生が決めれば配慮がしやすくなります。列ではなく、座席の位置でグループに分けるというアレンジも可能です。
あみだくじ席替え
【準備するもの】
黒板や模造紙、チョークまたはペン
【手順】
- すべての座席に番号を振る
- 人数分の縦線に対し、ランダムに横線を加えてあみだくじを完成させる
- 子どもにスタート位置を選ばせ、たどった先の番号の席に座る
【ポイント】
あみだくじの縦線は、事前に先生が書いておくと進行がスムーズです。「横線は1人1本」などのルールを決めて、子どもたちに線を追加させても盛り上がります。ただし、混線しないように注意しましょう。あみだくじを男女別に作成することで、男女固定の席にすることも可能です。
スムーズに席替えを進められるよう、あらかじめくじやカードの準備、ルールの確認など、しっかりと準備しておきましょう。
自分で席を選べる席替えアイデア
席替えのワクワク感を高めたいときには、子ども自身が席を選べる形式もおすすめです。
ここでは、選ぶ順番だけをランダムにすることで、平等性を保ちながら自由度もある3つのアイデアを紹介します。
くじ引き指名席替え
【準備するもの】
出席番号を書いたくじ、黒板に書いた空欄の座席表(があるとスムーズ)
【手順】
- 最初の1人は、先生がくじを引いてランダムに選ぶ
- 選ばれた子が好きな席を1つ選び、次の人を決めるくじを引く
- くじで指名された子が座席を決め、さらに次の人を決めるくじを引く
- これを繰り返す
【ポイント】
「誰が次に呼ばれるのか?」というドキドキ感があり、全体の雰囲気が自然と盛り上がります。男女で席を分けたい場合などは、あらかじめ列やエリアを色分けした座席表を提示しておくとスムーズです。
ビンゴ席替え
【準備するもの】
ビンゴカード(空欄のマス付き)、筆記用具、ビンゴマシンなど
【手順】
- 子どもに1〜75の中から好きな数字を選ばせ、ビンゴカードに記入させる
- ビンゴマシンで数字を発表していく
- ビンゴが完成した順に、空いている好きな席を選ばせる
【ポイント】
自分で数字を選んでビンゴカードを作ることで、ビンゴのワクワク感がさらに増します。複数人が同時にビンゴになった場合や、最後までビンゴが完成しなかった子が複数いる場合は、じゃんけんなどで席を選ぶ順番を決めましょう。制限時間をあらかじめ伝えておけば、席選びに時間がかかりすぎる心配もなくなります。
じゃんけん席替え
【準備するもの】
特になし(黒板に空欄の座席表が書いてあるとスムーズ)
【手順】
- 先生と全員でじゃんけんを行い、「勝ち」「あいこ」「負け」の3グループに分ける
- 各グループ内でじゃんけんを繰り返し、順位を決める
- 「勝ち」「あいこ」「負け」グループの順で、さらに各グループ内の順位の高い子から、好きな席を選ばせていく
【ポイント】
シンプルな方法ですが、じゃんけんで勝ち残ろうと気合を入れる声や応援の声が飛び交い、教室が盛り上がります。すべての席を自由に選ばせる方法だけでなく、たとえば「勝ち」グループは窓側、「あいこ」は中央、「負け」は通路側といったブロック分けをして、その中で席を選ばせる工夫もできます。
完全なランダムではなく、どの席に座るかを自分で選べる要素もあることで、子どもたちは主体的な活動として楽しめます。
考える楽しさがある席替えアイデア
席替えをゲーム感覚で楽しむだけでなく、子どもたちの「考える力」や「知的好奇心」をくすぐる要素を取り入れることで、学級活動にもつながる時間になります。
ここでは、知的なやりとりが楽しめる席替えのアイデアを紹介します。
クイズ席替え
【準備するもの】
クイズの問題、正解数を記録する表
【手順】
- あらかじめ数問のクイズを用意し、子どもたちに出題する
- 正解数が多い順に、好きな席を選ぶ
- 同点の場合は、じゃんけんやくじなどで順番を決めて席を選ぶ
【ポイント】
知識量に偏りが出ないように、出題のジャンルを幅広く工夫すると、誰でも楽しみやすくなります。
たとえば、「学校行事に関する問題」や「なぞなぞ」「簡単な計算問題」など、子どもたちの日常に関連した内容を取り入れるのもおすすめです。
クイズ席替えでは、問題をチーム戦にして取り組むようにさせても、協力する楽しさが生まれ、学級づくりにもつながります。
コミュニケーションが生まれる席替えアイデア
新しい座席でも、すぐに周りの子と自然に会話が生まれるような仕掛けを席替えに取り入れることで、クラスの雰囲気がやわらぎ、人間関係の広がりにもつながります。
ここでは、新しい席の周りの子たちとの関わりを深めやすい、2つのアイデアをご紹介します。
ペアカード席替え
【準備するもの】
ペアになる2枚セットのカードを人数分(同じマークや数字、絵柄など)、座席表(黒板や模造紙など)
【手順】
- 同じ種類のカードを2枚1組にして、人数分のカードセットを用意する
- 子どもたちにカードを1枚ずつ引かせ、同じ種類のカードを引いた子同士がペアを組む
- ペアで相談しながら、座席表を見て2人で隣り合う席を選ぶ
【ポイント】
カードのデザインは動物や食べ物など、親しみやすいデザインのカードを使うと、和やかな雰囲気になります。座席を選ぶ方法は、自由選択だけでなく、ペアごとにくじを引いて決める方法など、さまざまにアレンジできます。
相性チェック席替え
【準備するもの】
選択式の質問、座席表
【手順】
- 「好きな季節」「好きな科目」「ドラえもんの道具で欲しいもの」など、選択式の質問を用意
- 同じ答えを選んだ子どもたちをグループに分ける
- 教師がグループごとに座席のエリアを指定する
- グループ内でくじを引くなどして、指定エリアのどの席に誰が座るかを決める
【ポイント】
この方法で席を決めると、同じ好みや興味を持っている子同士が近い席になります。そうすると、会話が生まれやすく、クラス内での新たな交流の輪も広がります。人数に偏りが出た場合は、グループの組み替えや席の配置を柔軟に調整しましょう。
どんな共通点のある子ども同士を近くの席にしたいのか、考えながら質問内容を工夫していきましょう。
スムーズなコミュニケーションを意識した席替えは、あまり話したことのない子同士の自然な会話のきっかけを作ることができます。
特別感のある席替えアイデア
いつもの席替えに、ちょっとした演出を加えるだけで、子どもたちにとって特別な時間になります。
ここでは、そんなちょっとした工夫で盛り上がる席替えアイデアを紹介します。
プレゼントボックスでくじ引き席替え
【準備するもの】
座席番号を書いたカード、カードを包む折り紙、見た目のきれいな箱や袋
【手順】
- 座席番号を記入したカードを折り紙などでプレゼント風に包み、箱や袋に入れる
- 子どもたちに1人ずつ引かせて、出た番号の席に座らせる
【ポイント】
通常のくじ引きと同じルールですが、見た目の演出を変えるだけでワクワク感が増します。季節のイベント(クリスマス・バレンタイン・七夕など)に合わせてラッピングを変えると、より楽しい雰囲気になりますよ。
「今日はスペシャルな席替えだよ」といった声かけをするだけでも、子どもたちの気持ちは高まります。
席替えを成功させるために気をつけたい3つのこと
楽しいはずの席替えも、進め方によっては決め方に不満が出たり、新たな座席が毎日の学校生活上の支障やトラブルにつながったりすることもあります。
ここでは、席替えをスムーズに行い、子どもたち全員が新しい座席に納得して前向きな気持ちで過ごすための、ポイントを紹介していきます。
人間関係への配慮でトラブルを未然に防ぐ
クラスの人間関係や個別の配慮が十分でないと、思わぬトラブルが起きることがあります。
視力・聴力・発達特性など、席の位置に配慮が必要な子には事前に確認するのはもちろん、以下のようなポイントも事前におさえておくことが大切です。
- 対人関係で不安を抱えやすい子
- 特定の子との関係にストレスを感じている様子がある子
このように、座席の位置に配慮が必要な子や、席を近くにするのは避けるべき子同士を、日頃から把握しておきましょう。
ランダムに決める形式であっても、近くの席同士にならないようにするなどの配慮が必要な子どもには、くじに細工をする、あらかじめ一部の席を決めておくといった、先生主導での事前の工夫が必要です。
席を決めるうえで公平性が前提であるのはもちろんですが、全員が「安心して過ごせること」を優先した配慮は、当人だけでなく、クラス全体の安定につながります。
偏りを防ぐ!公平な席替えの工夫
「仲が良いわけじゃないのに、また同じメンバーの近くになった」「あの子はいつも窓側ばかり」など、座席の位置の偏りは、小さな不満のもとになります。不満につながる偏りや不公平感を減らすためには、次のようなことを意識しましょう。
まずは、過去の座席の配置を記録しておくことです。それにより、いつも同じ席になっていないか事前にチェックすることができます。
また、いつも同じ方法ではなく、ランダム形式と選択形式を交互に行うとよいでしょう。時には、「窓側・中央・通路側の3つにブロック分けをしてからくじを引く」というように、一定のエリアを指定した自由すぎないくじ引きにするのも一案です。
子どもが納得できる声かけの工夫
どんな方法で席を決めるにしても、子どもたちの「納得感」を大切にすることが、スムーズな席替えと、その後の良好なクラスの雰囲気には欠かせません。
あらかじめ「今回は、こんなルールでやるよ」「前回はランダム形式だったから、今回は自分で選べる方法にしますね」など、決め方のルールや意図を伝えるようにしましょう。
声かけの工夫次第で、同じ席替えでも子どもたちの受けとめ方が変わります。もし不満が出たときには、「でも、後ろの席も意外と落ち着くよ」「その席は黒板が見やすくて人気なんだよ」など、前向きな声かけをすると、気持ちの切り替えもしやすくなります。
席替えですべての子どもの希望をかなえるのは難しいですが、先生が配慮してくれていることが伝われば、子どもたちも納得してくれるでしょう。
面白い席替えでクラスの雰囲気をもっとよくしよう
席替えは、ただ座席の場所を変えるだけの活動ではありません。クラス全体の雰囲気や人間関係に大きく関わるだけでなく、子ども1人ひとりの毎日の学習や学校生活の充実度に影響する重要なイベントです。
同じ「席替え」でも、どんな方法で進めるか、どんな声かけをするかによって、子どもたちの受けとめ方は大きく変わります。今回は、ゲーム性のあるもの、考える楽しさがあるもの、コミュニケーションを後押しするものなど、さまざまな工夫を取り入れた席替えのアイデアを紹介しました。
どれも席替えをポジティブにとらえられるよう、子どもたちの「楽しい」「おもしろい」という気持ちを引き出しながら、クラスのまとまりづくりにも役立つ方法ばかりです。
もちろん、すべての子どもが安心して学校生活を送れるよう、先生による事前の配慮は必要です。日頃から子どもたちの様子を観察し、人間関係のトラブルを生まないような工夫や、席の位置に特別な考慮が必要な子への対応が必要になることもあるでしょう。
そのうえで、「楽しい」と「納得感」の両方を意識しながら、次の席替えを、子どもたちにとって前向きな学校生活につながる時間にしていきましょう。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。













