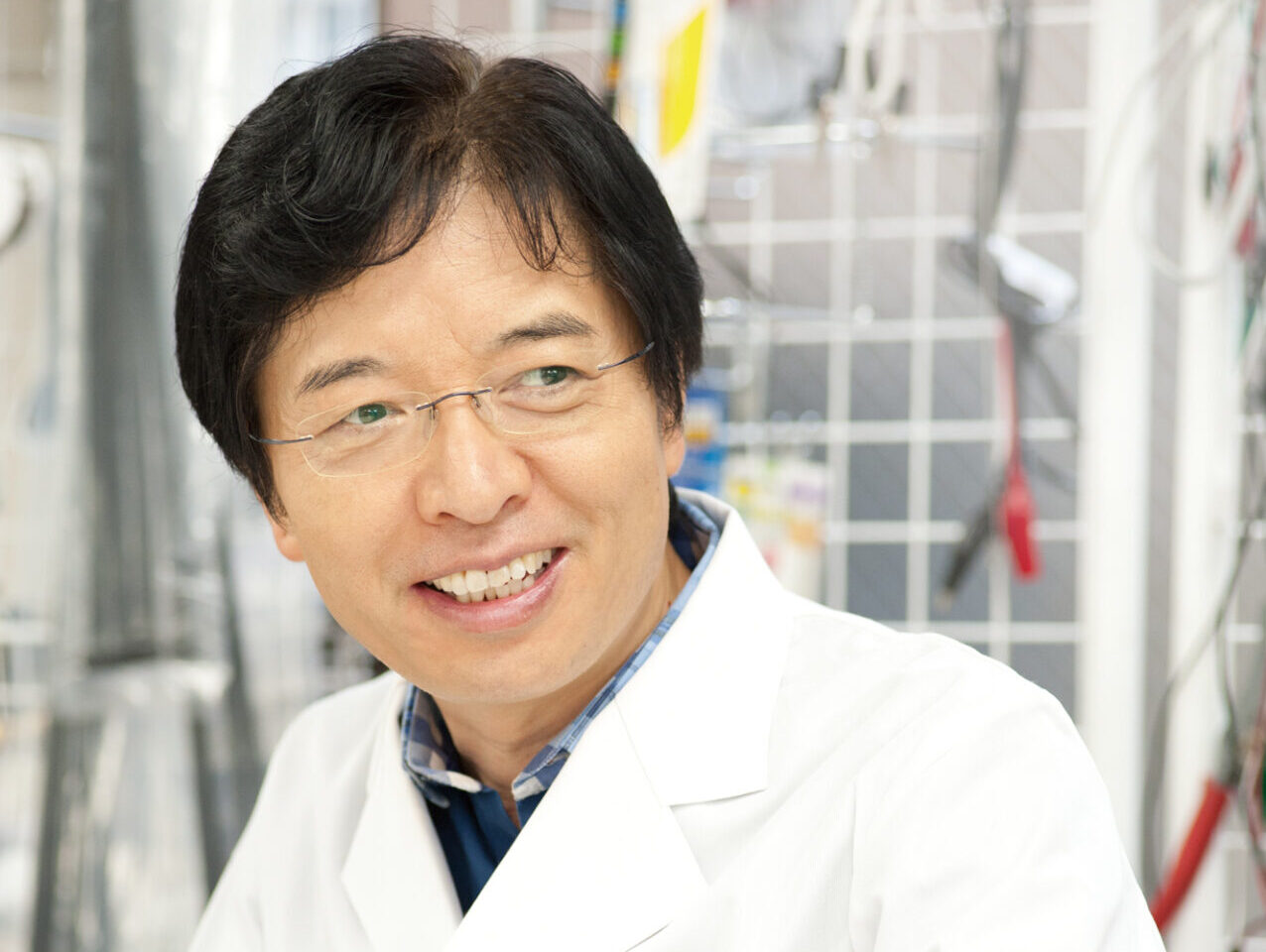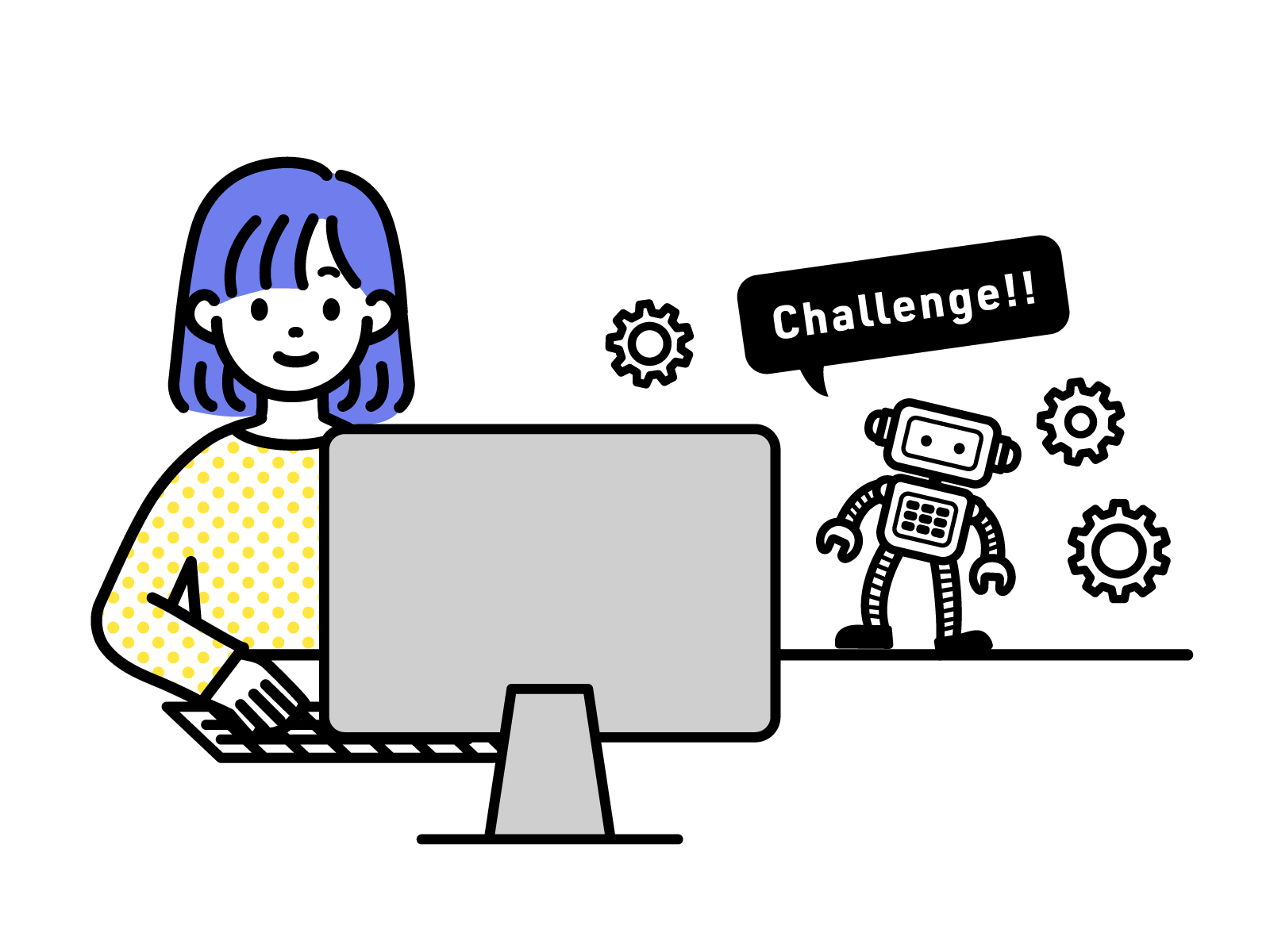
目次
「STEAM教育のSTEAMって、どういう意味?」
「STEAM教育が、実際に現場で活用された事例を知りたい」
「STEAM教育を授業に取り入れるには、どうすればいいの?」
このようにお悩みの先生方も、いらっしゃることでしょう。
STEAM教育とは、科学技術が高度に発達し浸透した新時代において、実社会での課題解決に必要な能力を育成する教育手法です。
この記事では、STEAM教育の概要や注目される理由、具体例を詳しく解説し、授業に取り入れるコツも紹介します。ポイントを押さえて、子どもたちが楽しみながら学べる授業を考えましょう!
STEAM教育とは?
まず「STEAM」とは、Science・Technology・Engineering・Art・Mathematicsの5つの英単語の頭文字を組み合わせた造語です。
STEAM教育は、近い未来に到来する新時代に適応するために必要な能力・スキルを身につけるための取り組みです。日本政府が「目指すべき未来社会の姿」と策定した超スマート社会、AI技術が高度に発達・浸透した「Society5.0」時代に必要とされる、理数的問題解決能力や、人間性に根ざした創造力を育むことを目的としています。
そして、実際にSTEAM教育では、その語源となっている科学、技術、工学、芸術、数学の5分野を教科横断的に扱います。
▼STEAM教育を構成する分野
- S:科学(Science)
- T:技術(Technology)
- E:工学(Engineering)
- A:芸術(Art)
- M:数学(Mathematics)
以下、STEAM教育を構成する5分野それぞれについて、詳しく解説していきます。
S「科学」
「科学(Science)」では、理科系分野全般の学習を通して、数理的思考の土台となる、課題や法則に気付く力を養います。対応教科としては、物理、化学、生物学、地学などがこの分野に含まれます。
STEAM教育の目的の一つは、「課題を発見し、解決策を導き出せる能力」です。身の回りの「なぜ?」を発見し、自ら仮説を立てて検証する科学的思考は、課題を見つけ問題解決する力を養う、よい訓練になります。
知識の暗記にとどまることなく、子どもたちが観察や実験を通して法則を見つけるプロセスを体験することが、この領域の学びには大切です。授業への主体的・積極的な参加によって、自分を取り巻く社会における課題に気付き、解決策を導き出せる能力が身に付くことでしょう。
T「技術」
「技術(Technology)」では、プログラミングなどの学習を通じて、論理的思考力や問題解決能力を養います。
小学校では2020年度、中学校では2021年度に、プログラミング教育が必修化されました。これは、コンピュータ活用のための技能習得以上に、より高度な情報化社会の到来やグローバル化といった、大きな社会的変化に対応できる人材に必要な「プログラミング的思考」を身につけることを目的としています。授業では、コード入力のようなプログラミングの専門知識がなくても、子どもたちが絵や図形を動かして直感的に楽しく操作できる「ビジュアルプログラミング言語」と呼ばれる言語を使用します。
プログラミング的思考とは、どうすれば自分の意図する動きを実現できるか、指示を細分化して論理的に考えることのできる能力です。さらに、動きをより効率的にするために、一度考えた指示の組み合わせを改善する能力も含まれます。
プログラミング的思考を習慣づけることで、問題解決に至るための「分解」「順序立て」「分析」「抽象化」「一般化」という5つの力が身につくとされています。子どもたちがプログラミング的思考を身につけられるよう、技能の習得よりも、考えるプロセスそのものに重きをおいて指導することが大切です。
E「工学」
「工学(Engineering)」では、ものづくりの経験を通じて、生産力や空間的把握能力を育みます。 技術と異なる点は、実際に現実世界で動くものを作るという点です。論理上は間違いがないように見えても、実際に動かすと思ったような動きをしないことは、ものづくりではよくあります。 工学を学ぶことで、物理法則などを考慮に入れながら、実用的なものを設計する練習ができるでしょう。
例えば、技術の学習で得た知識を活かしたロボットプログラミングや電子工作などが、代表的な実践例として挙げられます。子どもたちがものづくりの難しさに挫折しないよう、前向きに試行錯誤する楽しさも伝えられるとよいでしょう。
A「芸術」
「芸術(Art)」は、進歩した科学技術を正しく取り扱うことのできる人間性や倫理観、新しい価値を生み出す発想力・創造力を培うことを目的としています。
STEAM教育の原型は1990年代に米国で始まった「STEM教育」で、「A」は後から追加されました。その理由は、科学技術を適切に使いこなすためには、知識だけでなく、自由な発想力や人間力も必要になるためです。
そのため、図工や音楽といった芸術系科目だけでなく、経済や政治、倫理といった要素もこれに含まれます。さらに、既存の枠組みにとらわれない自由な視点や生き方の基盤となる「リベラルアーツ」の学びも含みます。これは、古代ギリシアで生まれた概念で、基礎的な教養と思考力を養い、人間としての総合力を育てることを目的としています。
AIの普及拡大が予想されるSociety5.0時代ですが、社会の方向性を正しく決めるのは人間である、という点に変わりはありません。革新的な発想や、美観だけでなく使う人への配慮がなされたデザインも、人間が得意とする分野です。
子どもたちが、それぞれ独自の発想を尊重し合いながら、学びの成果を得られるようなサポートをしていきましょう。
M「数学」
「数学(Mathematics)」では、計算や図形などの問題を通じて公式や法則といった根拠に基づく考え方を習得し、論理的思考力を養います。数学を学ぶことは、既知の情報をもとに正しい結論を導き出すトレーニングになります。
これは、先に紹介した科学、技術、工学の基盤となる能力なので、他分野と組み合わせた学習がしやすいのも特徴です。たとえば小学5年生の授業では、多角形を描く実習にプログラミングを活用し、体験学習的に、その便利さを実感してもらいます。
これまでの理数教育の課題を踏まえ、子どもたちが算数・数学への苦手意識を持たないよう、学ぶプロセスでの楽しさを意識した指導が求められるでしょう。
科学技術への興味や学ぶ楽しさを引き出せる理数教育の実現が大切です!
STEAM教育が注目されている理由とは?
STEAM教育は、新しい時代に適応するための取り組みとして、国内外で注目されています。ここでは、STEAM教育が重視されている理由を、詳しく解説します。
今までの教育とSTEAM教育の違い
STEAM教育が今までの教育と異なるのは、各教科を縦割りに学ぶのではなく、全分野を横断的に学ぶ点です。
従来の教育では、国語や算数といった「教科」を別々に学ぶのが一般的でした。それに対して、STEAM教育では、教科の垣根を超えてS・T・E・A・Mの「分野」で学びます。
後述する「Society5.0」に向けた教育の課題の一つに「文理分断」があります。これは、従来の日本の学校教育では、高校生の多くが文系・理系にクラス分けされることにより、特定の科目を十分に学ばず卒業するという問題です。とくに、文系クラスで理系科目を履修しない学生が多いことは深刻な問題です。
▼文理分断による問題
(Society 5.0 に向けた人材育成~社会が変わる、学びが変わる~ (概要)より)
- 日本の四年制大学の学生は、人・社系5割、理工系2割、保健系1割、教育・芸術系等2割
(諸外国は、理工系にドイツ約4割、フィンランド・韓国等約3割) - 高校の普通科全体のうち「物理」履修者は2割
政府はAI研究の人材不足を懸念し、STEAM教育の導入によって文理分断が解消されることを期待しています。
Society5.0時代におけるSTEAM教育の意義
Society5.0とは「仮想空間と現実空間を高度に融合させた社会」です。内閣府の第5期科学技術基本計画において、「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」として提唱されています。それに対し、現代はSociety4.0(情報社会)と位置づけられており、地域格差や情報収集の負担といった社会的課題があります。それらの課題がAIやIoTによって解決され、誰もが生きやすくなった社会が「Society5.0」です。
Society5.0の実現に向けて、日本の教育も大きな転換期を迎えています。テクノロジーの急速な発展に向けて、単なる知識の習得だけでなく、創造につながる豊かな発想と柔軟な思考ができる人材の育成が必要です。
STEAM教育は、来るSociety5.0時代に必要とされる、以下のような能力・スキルを育むことを目指しています。
▼Society5.0時代に必要な能力
- デジタル技術を活用した創造力
- 分野横断的な問題解決能力
- イノベーションを生み出す発想力
- データサイエンスの基礎的な理解力
- 新しい価値を創造する統合的な思考力
技術革新は日進月歩で、現在も加速・発展を続けているため、その変化に柔軟に適応しつつ新しい価値を創造できる力が必要となります。そのような非認知能力の育成を目指した取り組みとして、STEAM教育は注目されているのです。
Society5.0時代の到来に向けてSTEAM教育を取り入れ、必要な能力・スキルを養いましょう!
STEAM教育の実践例
STEAM教育は、すでに国内外のさまざまな現場に取り入れられています。ここでは、日本と海外における具体的な実践例を見ていきましょう。
日本の事例
兵庫県では2020~2022年度の3年間、「STEAM教育実践モデル校事業」というプロジェクトが実施されました。これは、兵庫県教育委員会が県立高校3校を実践モデル校に指定し、学校ごとの特色を反映した文理融合型のカリキュラム開発を目標としたものです。
▼実践モデル校の取り組み例
- ビッグデータを活用したプロジェクト型授業・探究活動
- ロボットプログラミングと芸術的自己表現の融合カリキュラムの開発
目的は文理融合型カリキュラムの開発であり、将来的な目標として、兵庫全県での展開とSTEAM学科の設置が掲げられました。
海外の事例
アメリカでは、2013年にオバマ政権が「STEM教育5ヵ年計画」を発表しました。具体的には、次の3つを含む国家目標が設定され、年間30億ドルの予算が投入されています。
▼STEM教育5ヵ年計画
- 2020年までに、初等・中等教育のSTEM分野の優秀な教員を10万人増員する
- 高校卒業時までにSTEM分野を経験した若者を毎年50%増加させるための支援
- 今後10年間で、STEMの学位取得者を100万人増加させる
2015年にはSTEM教育法が成立し、STEM教育の定義の幅が広がり、国家戦略として積極的な支援策が取られています。2017年には、新たに「芸術(Art)」分野が追加され、STEAM教育法となりました。
さらに、カリフォルニア州には画期的な取り組みを行うチャータースクール「High Tech High」があります。授業料無料で、教科書や成績表はなく、「課題解決型学習」による非認知能力の育成を重視した教育施設です。
課題解決型学習では、生徒自らが興味のある題材を選んでプロジェクトを立ち上げます。最終的には実社会に貢献する成果を出すことが求められており、学校外との連携が多い点も特徴です。
紹介した事例を参考にして、STEAM教育の考え方を授業に取り入れてみましょう!
STEAM教育を始めるときのコツ
ここでは、STEAM教育を実践する際の準備や心構えを解説します。
STEAM教育の授業プランのつくり方
STEAM教育の授業では、各分野の要素をバランスよく含めつつ、子どもたちが興味を持ちやすい身近な課題を選びましょう。また、正解が一つに定まらない柔軟な課題設定を行うことも大切です。
▼授業プランで意識すべきポイント
- 身近な課題をテーマに選ぶ
- 各分野の要素をバランスよく含める
- 子どもたちが主体的に取り組めるよう、オープンエンドな課題設定をする
プラン作成時に役立つのが、経済産業省が開発した「STEAMライブラリー」です。子どもたちの興味に応じた教材を検索し、ダウンロードできます。日本国内での豊富な実践事例も掲載されているので、授業を行う際の参考にもなります。
▼「STEAMライブラリー」コンテンツ例
- 桃太郎のフシギを科学的に考えよう!
- 音のバリアフリー~音で健康と福祉をもたらす社会づくり~
- 「身の回りのものができるまで」~何からできている?どんなふうにできている?~
※ 出典:STEAMライブラリー未来の教室
先生に求められる役割と心構え
STEAM教育では、正しい知識を教えるよりも、子どもたちの主体性や考える力を伸ばすことが重視されます。そのため、先生には「教える」ことよりも「学びをサポートする」ことが求められます。
子どもたちが自主的に学習を進められるよう、自分で結論を出すまでの過程を見守りましょう。とくに「芸術」分野のような明確な答えのない課題に関しては、子ども同士でお互いのものの見方・捉え方、発想や表現法を尊重し合えるようなサポートを心がけてみてください。授業の進行が止まらないよう、先生として必要な舵取りと適切なアドバイスをしながら、自主的に「自分の答え」にたどり着いてもらうことを重視しましょう。
STEAM教育にぴったりの学習環境づくり
STEAM教育の授業では、座学だけにとどまらず、グループワークや実験などを伴うことが一般的です。さらに、子どもたちの自主性や興味に合わせて、授業の方向性を柔軟に変える必要があります。
さまざまな実習内容に対応できるよう、教室レイアウトの工夫や、必要になりそうな道具の準備などを行いましょう。
▼STEAM学習のための環境づくりのポイント
- グループワークがしやすい教室レイアウト
- 実験や制作に必要な道具の準備
- 失敗を恐れずチャレンジできる雰囲気づくり
子どもたちが失敗に対してネガティブな印象を持たないための雰囲気づくりも、とくにSTEAM学習においては先生の重要な役割です。失敗を恐れて挑戦しないよりも、諦めずに試行錯誤する姿勢が大切であることを伝えましょう。
子どもたちの主体性を大事にした授業進行を心がけ、先生はサポートに回ることが大切です
STEAM教育が開く新しい教育の形
この記事では、STEAM教育の意義や注目されている理由、国内外の実践例、実際に始める際のコツをお伝えしました。
STEAM教育は、「Society5.0」時代を生き抜くうえで必要な、問題解決能力や創造力の育成を目指した取り組みです。今回ご紹介した内容を参考に、子どもたちが楽しく主体的に取り組める授業づくりをしてみてください。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。