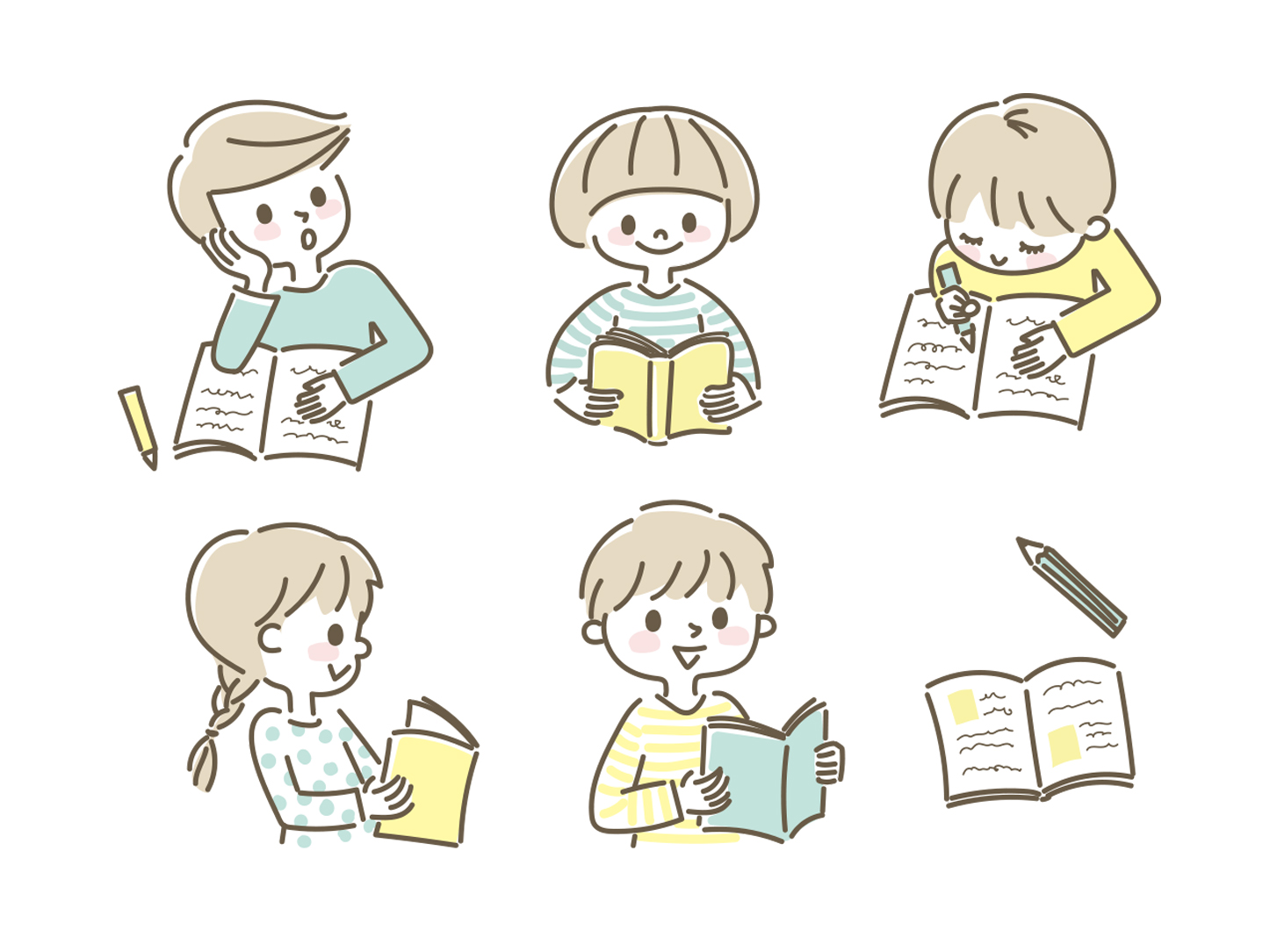目次
教員にとって、毎日の授業に加え、校務分掌による担当業務も、学校の運営を支えるための大切な役割です。
でも、新任や若手の先生方の中には、
「校務分掌って、具体的にはどんなことを指すの?」
「研究部の担当になったけれど、どう動けばいいのか分からない」
といった不安を感じる方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、この記事では、
- 小学校でよくある校務分掌(業務分担)の種類と、それぞれの仕事内容
- 若手の先生が任されやすい校務
- 校務分掌による担当業務をスムーズに進めるためのポイント
について、分かりやすく解説します。
分掌による校務の担当が初めての先生でも、安心して取り組むためのヒントがきっと見つかるはずです。
校務分掌とは?種類や仕事内容を分かりやすく解説
「校務分掌(こうむぶんしょう)」とは、学校内のさまざまな業務(校務)を、先生同士で分担して受け持つ仕組みのことです。「分掌」という言葉には、「仕事を分け合って、それぞれが担当する」という意味があります。
小学校では、行事の運営、生活指導や健康指導の計画、校内研究、情報発信、備品の管理など、授業以外にも多くの校務があります。こうした多岐にわたる業務を一人で抱えることが、難しいのは明白です。そのため、分掌により校務の種類別に担当を決め、先生たちが各自、役割を務めることで協力して学校を支えていくのです。
校務分掌による学校組織の部門構成、設置数や校務の分け方などは、各学校の実情によって異なります。ここでは、一般的な校務分掌の例として、以下のような区分による部門を紹介していきます。
- 教務部:学校運営の中心
- 指導部:生活・学習・安全・保健・進路指導
- 研究部:校内研修・授業改善の推進
- 管理部:校内運営と庶務・設備管理
- 渉外部:広報・地域連携など
では、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
教務部(学校運営の中心)
教務部は、学校の教育活動全般を円滑に進めるために、授業・学習に関わる業務を幅広く担当します。教育機関である学校運営の根幹を担う仕事が多く、大きな責任をともなう業務といえます。
- 教育課程の編成
- 時間割・年間指導計画の作成や調整
- 児童の学籍関係書類の管理
- 通知表に関わる事務処理
教務部の仕事を担うには、学校全体のスケジュールを管理する力が求められます。教務主任をはじめ、教員としてある程度の実績がある先生が担当するのが一般的です。若手の先生が、印刷や資料の準備といった教務の一部を、補助的に担当することもあります。
指導部(学習・生活・安全・保健・進路指導)
指導部は、子どもたちの学習・生活・安全・健康などを支える業務全般を分掌します。「学習指導」「生活指導」「安全指導」「保健指導」「進路指導」などを担当し、それぞれ目的に応じた指導を行う役割があります。
学習指導
国語科、算数科といった教科ごとの運営や教材管理を行う学習指導は、教務主任や管理職を除くほとんどの教員が担当する校務です。若手の先生も例外ではなく、校務分掌により、必ず何らかの教科を受け持つのが一般的です。
教員数が多い学校では各教科を2人で分担しますが、少人数校では1人で複数の教科を受け持つ場合もあります。
- 教科ごとの教材や教具の管理
- 特別教室の整頓、管理
- 授業づくりに関する情報共有や研究、教材活用の工夫の共有など
学習指導は、授業と深く関わる校務なので、担当教科についての知見を増やす機会になるでしょう。
生活指導
子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、日々の生活面全般に配慮し、必要な指導や学校のルールの周知といった役割を担います。生徒指導とも呼ばれる校務です。
- 生活目標の設定・掲示
- 校内でのトラブルやいじめ発生時の対応・記録・共有
- 長期休業中の過ごし方についての注意喚起
生活指導担当の先生が作成した目標や指針は、担任の先生がクラスの子どもたちに伝え、日々の生活の中で実践していくことになります。
安全指導
避難訓練や防犯対策など、学校内外での子どもたちの身の安全を守るための、指導や計画を担います。いざ危険に直面した時に子どもたちが適切な行動をとれるよう、日頃からの指導の積み重ねや、学校・教師側の備えが重要になります。
- 交通安全指導の企画と実施(横断指導、登下校指導など)
- 防犯訓練・不審者対応訓練の企画と実施
- 地震・火災などの避難訓練の年間計画と運営
- 通学路や校内設備の安全点検・危険箇所の把握
防犯訓練や避難訓練では、警察署や消防署など地域の関係機関と連携する場面も多くあります。また、登下校の見守り活動では、地域ボランティアや保護者との協力を軸にした関わりが生まれやすいのも特徴です。
保健指導
子どもたちの健康や衛生面に関わる業務を、養護教諭と連携しながら行います。
- 保健目標の掲示や啓発資料の準備
- 感染症対策の情報共有
- 応急処置や体調不良児童の対応時の支援
保健指導を担当する場合、養護教諭との連携は欠かせません。また、児童の委員会活動で保健委員会を担当するのが一般的です。
進路指導
小学校における進路指導は、児童に職業についての基礎知識を身につけさせ、将来の進路を選択するための能力を養う「キャリア教育」を軸とします。子どもたちが将来の生き方を見つけていける力を育てる取り組みを担います。
- 「キャリア・パスポート」の内容の提案
- 職業調べ、地域の方の講話など、児童の将来の進路選択につながる企画推進やサポート
学校によっては、中学受験に関する進路指導やサポートを担うこともあります。
キャリア・パスポートとは、児童生徒が成長をふり返りながら現在の自分を自己評価し、生き方や将来の進路に活かしていけるよう、小・中・高を通して継続的に学習や活動の内容を記録していくポートフォリオ(個人資料)のことです。2019年4月~2020年4月に全国で導入されました。
研究部(校内研修・授業改善の推進)
研究部は、教員同士が学び合う機会や、授業の質向上のための取り組みを企画・運営する、教員の学び・成長のための部門です。学校全体での授業研究や校内研修を通して、教育の質を高める役割を担っています。
- 校内研究のテーマ設定と年間計画の作成
- 公開授業・研究授業の企画と調整
- 講師依頼や研究資料の準備
- 校内研修や分科会の運営
- 学力向上や授業改善の取り組みに関する共有
近年は、学校全体として若手の先生の割合が増えています。こうした背景から、従来の校内研究に加えて、若手の先生を対象とした研修や支援体制を設ける学校も多くなっています。
さらに、その若手向け研修の運営を、当事者である若手の先生自身が担うケースも見られるようになっています。
管理部(校内運営と庶務・設備管理)
管理部は、日常の庶務や備品の管理、施設整備などを通して、学校が円滑に機能するよう支える部門です。学校によっては「総務部」や「庶務部」と呼ばれることもあります。
- 備品・消耗品の発注・管理
- 校内掲示板やプリンタ・コピー機などの共用設備の整理
- 行事用の物品チェックや配布物の取りまとめ
- 校内環境の点検・改善(照明、机・椅子など)
備品や消耗品の管理は、各教科の担当に応じて分担されるのが一般的です。たとえば、算数の担当ならコンパスや分度器、国語の担当なら書写用具というように、必要な備品をそれぞれの教科担当者が管理します。このような役割は、初任者の先生でも取り組みやすい校務です。
渉外部(広報・地域連携など)
渉外部は、学校と保護者・地域・外部機関をつなぐ役割を担う部門です。保護者や地域の方との連携・協働活動の下地となる信頼関係を築き、学校の教育活動への理解と協力を得るための大切な役割です。
- 学校だより・学年通信などの作成・発行
- 学校ホームページや広報掲示物の管理
- PTA活動や地域行事との連携、外部講師の調整
近年は、ICT活用に関わる業務も校務分掌の一つとして扱われることが増えています。タブレットやプロジェクターなどのICT機器の管理や、授業での活用支援、トラブル対応などを担当する「ICT担当」を設けている学校もあり、これは若手の先生が任されることも多い役割です。
校務分掌により、若手や新任の先生の担当になりやすい役割
はじめて校務分掌で特定の部門の業務を任されると、責任の大きさに不安を感じる先生も少なくないでしょう。ですが、多くの学校では、新任や若手の先生が無理なく分掌に対応できるよう、比較的負担の少ない校務や補助的な役割からスタートできるよう配慮されています。
以下に、若手の先生が任されることの多い具体的な役割の例を紹介します。
- 放送担当:朝会や行事での放送業務、音響機器の準備・操作など
- 掲示・環境整備:季節の掲示物づくりや校内の案内表示の作成など
- ICT担当:タブレットやプロジェクターの準備、授業中のICTサポートなど
自分にできることから少しずつ誠実に取り組んでいけば、大丈夫です。分からないことがあれば、周囲の先生に相談しながら、一歩ずつ進めていきましょう。
生活指導や研究部などの学校教育の中核を担う部門においても、若手の先生に補助的な役割が分担されることがあり、校務分掌は現場経験の浅い先生を育てるための仕組みとも受け取れます。一つひとつの校務に向き合う経験を「学びのチャンス」と捉えましょう。
校務分掌で任された役割をスムーズに進めるための3つのコツ
校務分掌で任される各役割の進め方には決まった型があるわけではないため、特に現場での経験が浅い先生にとっては、戸惑うことも多々あるかもしれません。
ここでは、校務分掌による担当業務をスムーズに進めていくための、3つのコツを紹介します。
年度初めに年間スケジュールを大まかに把握する
まずは、学校全体の年間行事予定を確認し、自分の担当する部門が関わる行事と時期を、大まかに把握しておきましょう。「いつ」「どのくらいの準備が必要か」が分かると、計画的に行動できます。
【例:安全指導の場合】
| 4月 | ・交通安全教室、登下校指導の計画 ・地域への依頼 |
| 5月 | ・避難訓練(地震) |
| 7月 | ・夏休み前の安全指導 |
| 10~11月 | ・防災、防犯週間に合わせた啓発 |
| 12月 | ・防犯訓練(不審者対応) |
また、これらの行事のうち「職員会議で提案が必要なものはどれか」を、事前に確認しておくことも大切です。
たとえば、12月の防犯訓練は、職員会議での提案が必要です。そのために、下記のようなスケジュールで準備を進めていきましょう。
- 9月:前年度の記録を見て下案を作成
- 10月:警察との日程調整、訓練内容の検討
- 11月:職員会議で実施計画を提案
このように、行事と職員会議の両方を見据えて、逆算してスケジュールを立てることで、スムーズな進行が可能になります。
前任者の記録や資料をチェックする
校務分掌による各部門の業務を進めるうえで、過去の担当者の記録はとても参考になります。共用のPCフォルダやファイル棚を確認し、役立ちそうな資料をピックアップしておきましょう。
【チェックしておくと安心な資料の例】
- 年間計画や行事記録(いつ・何を・誰と行ったか、など)
- 過去のプリントやおたよりのひな形
- 準備物の一覧や各種チェックリスト(忘れやすい備品の確認も)
ただし、前年度とまったく同じように進める必要はありません。前例を参考にしつつ、その都度、現状に合わせて調整・改善していく意識を持って進めましょう。
分からないことは、早めに前任者やベテランに相談する
過去の資料を見ても分からない部分は、遠慮せずに前任の先生に確認しましょう。もし、前任の先生が異動や退職などでいない場合は、疑問や曖昧さをそのままにせず、同じ部門担当のベテラン教員や、学年主任、教務主任に、必ず確認・相談してください。その姿勢が、未然にミスやトラブルを防ぐうえでも大切です。
また、実際に進めるなかで分からないことだけでなく、前年度のうまくいかなかった点や課題点も確認しておくと、校務の改善につながります。
「どうすればいいか分からない」と感じたときこそ、早めの「報・連・相」が大切です。相談することをためらわず、安心して自分の役割に取り組みましょう。
校務分掌の目的を理解し、ポジティブに学校運営に関わっていこう
校務分掌は、学校運営を円滑に進めるために必要な仕組みです。学校の教育目標実現のためには、校長先生をトップとする組織がスムーズに機能するよう、先生たちが自身の役割をしっかり務めることが大切です。
とはいえ、最初から完璧にこなそうと気負いすぎる必要はありません。また、苦手なこと、分からないことがあっても当然です。周囲に相談し協力し合いながら進めていく姿勢が、若手にとって何より大切なのです。
校務には、授業で教えるだけでは得られない仕事上の学びがあり、教員同士がチームとして取り組むことで生まれる達成感もあります。新しい業務経験が、自分の視野や興味を広げてくれることもあるでしょう。
少しずつ「できること」が増えていけば、学校組織の中で果たせる役割が大きくなっていき、より教員としての自信もついていきます。自分が担う役割の目的・意義を理解し、前向きに取り組んでいきましょう。
【関連記事】先生同士が支え合える雰囲気づくりにつながる仕組みとして「チーム学校」というあり方も広がっています。以下の記事も参考にしてみましょう。
・若手の先生こそ知っておきたい「チーム学校」の仕組み・関わり方・役割
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。