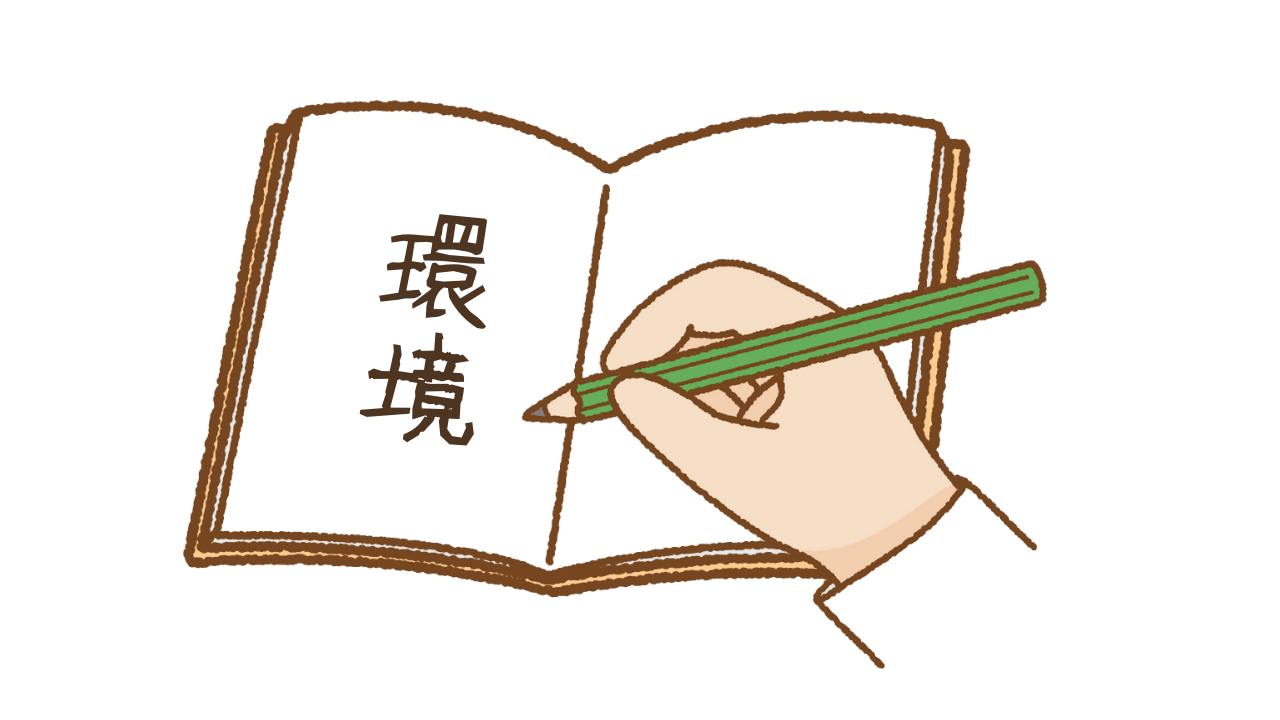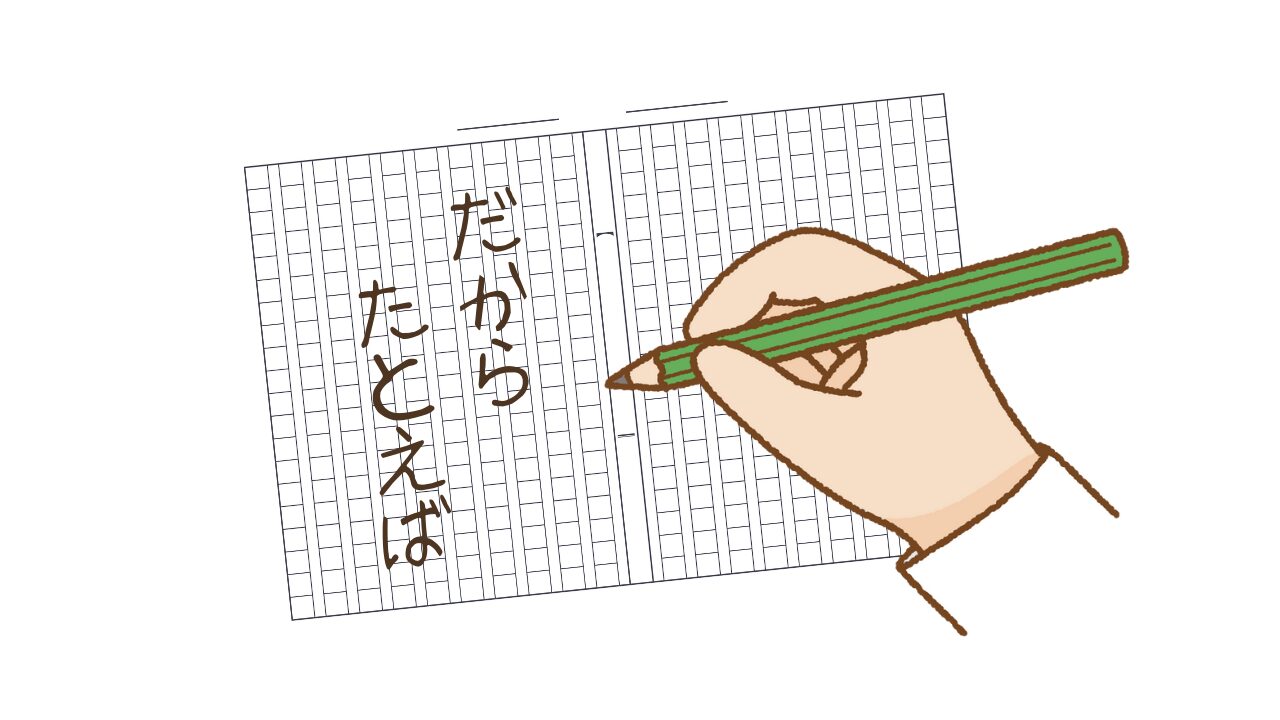目次
「生徒が文章問題の意味を理解できていない…」
「学年が上がると、教科書の文章が長く複雑になるため、内容を読み取れなくなる子が増えている」
このように、子どもたちの読解力の向上に課題を感じている先生は、多いのではないでしょうか。
読解力は、学習の基盤となる重要な能力であり、国語だけでなく全教科の学びや将来の社会生活においても不可欠です。この記事では、読解力の定義から現状、そして明日から使える具体的な指導法まで、教育現場ですぐに活かせる情報をお届けします。
読解力とは? 学校から社会へつながる能力
読解力は、単なる「文章を読む力」ではありません。あらゆる教科学習の基盤となるだけでなく、将来の社会生活においても欠かせない、生きるうえでの基礎的な能力です。ここでは、読解力の本質と重要性について見ていきましょう。
読解力とはどんな力?
OECD(経済協力開発機構)が実施する国際学習到達度調査(PISA)において、読解力は「自らの目標を達成し、自らの知識と可能性を発達させ、効果的に社会に参加するために、書かれたテキストを理解し、利用し、熟考する能力」と定義されています。
※参照:文部科学省「PISA調査における読解力の定義,特徴等」(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku/siryo/1379669.htm)
つまり読解力とは、単に文章の内容を正確に読み取れるだけではなく、以下のような力を含む総合的な能力なのです。
- 文章の内容を正確に理解する力
- 筆者の意図や主張を把握する力
- 文章から得た情報を自分の知識と結びつける力
- 情報を評価・分析し、活用する力
このように読解力は、学習において重要であるだけでなく、日常生活や将来の社会参加にも必要不可欠な、人間にとっての基礎能力であると言えます。
教科学習を支える読解力
読解力は、国語だけでなく、あらゆる教科の学習において重要な役割を果たします。
- 算数・数学:文章題の条件を正確に把握する/必要な情報を取り出す
- 理科:実験手順や観察記録を読み取る/科学的な説明文を理解する
- 社会:資料やデータを分析する/歴史的文脈を読み解く
- 英語:文章構造を把握する/文化的背景を捉える
どの教科においても、「読む」という行為は学習の入り口となります。そのため読解力が不足していると、教科書の内容や問題文を理解することが難しくなり、学習全般に影響を及ぼすことになるのです。
実生活と社会で活きる読解力
読解力は、学校での学びだけでなく、実生活や将来の社会参加においても重要な意味を持ちます。
- コミュニケーション:相手の意図を正確に読み取る
- 情報収集・選択:多様な情報源から必要な情報を見つけ出し、その信頼性を判断する
- 問題解決:状況を正確に把握し、適切な対応策を考える
情報があふれる現代社会では、さまざまな文章や情報を適切に理解し、有効に活用する力が、ますます求められています。つまり読解力を高めることは、子どもたちの将来の可能性を広げることにつながるのです。
読解力は、すべての人間活動の基盤となるスキルです。学校の学習だけでなく、社会生活での重要性も意識した指導を心がけましょう。
子どもたちの読解力の現状
読解力に関する国際的な調査結果や社会背景から、日本の子どもたちの読解力の現状を見ていきましょう。
現在の日本の子どもの読解力は?
OECDが実施する国際学習到達度調査・PISAによると、日本の子どもたちの読解力には大きな変動が見られます。2012年の調査では世界4位でしたが、2018年には15位まで順位が後退。その後回復し、2022年の調査では再び3位という好成績を収めています。
2022年調査で順位が回復した背景には、以下のような要因があるとされています。
- コロナ対応の差異:コロナ禍での休校期間が諸外国に比べて短く、学習機会が比較的維持されたこと
- ICT環境の整備と活用:ICTの活用能力が向上し、コンピューターを使ったPISA調査の形式にスムーズに対応できたこと
- 授業改善の進展:新学習指導要領において、言語能力が学習の基盤として明確に位置づけられ、授業改善が進んだこと
※参照:文部科学省・国⽴教育政策研究所「OECD生徒の学習到達度調査 PISA2022のポイント」(令和5年12⽉5⽇)(https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/2022/01_point_2.pdf)
ただ、日本の順位回復は外的要因(他国の低下)による部分も大きいと考えられるため、実質的な日本の子どもたちの読解力向上を示しているとは言い切れません。実際のところ、国内の教育現場では、依然として読解力に課題を感じる声も多く聞かれます。
子どもの読解力を低下させている要因とは
PISAの結果によると、日本の子どもたちの読解力は、2000年代に入ってから低下傾向を示しました。現在でも、教育関係者やメディアからは「文章をしっかり理解できない子どもが増えている」という指摘があります。
この背景には現代社会の急速な変化があり、それに起因する生活習慣の変化が深く関わっています。読解力低下の要因としては、次のような点が考えられます。
- SNSの普及:短文投稿やチャットが主流になったことによる、長文を読む機会の減少
- 情報環境の変化:幅広い多様な文章に触れる機会の減少(パーソナライズされた情報に触れる機会の増加)
- 読書習慣の変化:新聞購読率の低下や、時間をとってじっくり本を読む習慣の減少
社会的変化を背景とした生活上の多様な変化が、子どもの読解力にも大きな影響を与えており、教育現場での指導の重要性が、より高まっています。
国語の授業に盛り込もう!すぐに実践できる読解力アップ術
読解力の向上には、国語の授業での取り組みが特に重要です。ここでは、明日からでもすぐに実践できる具体的な指導法を紹介します。
子どもが夢中になる、語彙力を高める学習アイデア
語彙力は、読解力の土台となる重要な要素です。楽しみながら語彙を増やせる学習法を取り入れましょう。
辞書を使った言葉探しゲーム
辞書を活用したゲームで、子どもたちの言葉への興味を引き出しましょう。
- 先生がお題(例:「さんずいが入った漢字を使った熟語」「季節に関する言葉」)を出す。
- 制限時間(例:5分)内に、お題に当てはまる言葉を辞書の中から探す。ルールを設定し、ゲーム性をもたせる。
・先生が決めた目標数(例:5個)に挑戦
・時間内に見つけた数を競い合う など - 見つけた言葉をそれぞれ発表する。他の子の発表を聞いて面白い、珍しいと感じた言葉には拍手する。
- 見つけた言葉の中から各自一つ選んで、例文を作る。
付箋を使った辞書学習
付箋を使って記録をつけることで、辞書を使うことを習慣化しましょう。
- 辞書の適当なページを開く。
- ページ内で1つ知らない言葉を見つけ、その言葉を付箋に書いてページの上部に貼る。
- 週1回、月1回など定期的に付箋の言葉を見返して、意味がわかるようになっていたら付箋を取る。
その言葉を使った例文を書き留めたり、調べた言葉を発表し合ったりすると、日常的に使える語彙が豊かになっていくのでおすすめです。
このように、辞書を活用し扱いに慣れることで、語彙数が豊富になり、情報収集能力が高まります。言葉の世界への興味が広がるきっかけにもなるでしょう。
音読の習慣で読解力を伸ばす
音読は、文章を丁寧に読み込むことにつながり、内容への理解を深める効果的な方法です。国語の授業の始まりや終わりに、ぜひ音読を取り入れましょう。短時間でも継続的に行うことで、読解力が向上します。
▼おすすめの音読アイデア
- 交代読み
複数人で順番に交代で音読する方法です。自分が読む番でなくても次の文を予測しながら聞くため、集中力と理解力が高まります。文の区切りや句読点を意識する習慣が自然と身につき、文章理解の基礎力が向上します。 - スピード読み
通常の音読の倍の速度で、文章を声に出して読んでいく挑戦です。音読練習の最後に実施すると効果的で、語彙力や読解力の向上を実感できるでしょう。テンポよく先生の後に続いて読むことで、文章処理能力が鍛えられるので、長文読解にも役立ちます。特に、音読に苦手意識があった子にとっては、達成感や自信を育む効果もあるでしょう。 - 役割分担読み
登場人物やナレーターなど、役を決めて複数人で朗読劇のように読み分ける方法です。登場人物の立場や感情を想像しながら読むことで、文章の内容理解が深まります。会話文と地の文を意識して読み分けることで、文章構造への理解も促進されます。
音読を通じて、子どもたちは文章の持つリズムや構造を、体感的に理解できるようになります。また、漢字の正しい読み方を通じて表現や語彙の理解、多様な日本語の言い回しなどにも自然と親しむことができ、読解力の向上に効果的です。
読書習慣が自然と身につく環境づくり
読書量の増加は、語彙力や文章理解力の向上に直結します。子どもたちが自然と本に親しめる環境づくりを心がけましょう。
▼クラスでの取り組み例
- 教室内で「おすすめ本コーナー」として授業内で扱った題材と同じ作者の別作品や、授業で扱ったテーマに関連する本を紹介し、子どもたちの興味の幅を広げる。
- 朝の読書タイムや国語の授業の導入など、習慣的・定期的に全員が読書する時間を確保する。
また、国語の「話すこと・聞くこと」の学習と連携して、自分が読んだ本の感想を互いに共有し合う時間を設けると、読書の楽しさをより実感できるようになるでしょう。日常的に本を読む習慣が身につくことは、語彙力や理解力、表現力の向上だけでなく、想像力や思考力、創造性の育成にもつながります。
辞書に親しむ活動や音読の習慣、読書を楽しめる環境づくりなど、楽しみながら反復的・習慣化できるアイデアで、子どもたちの読解力と言葉への興味を自然に育みましょう。
国語の授業以外でも!各教科で取り組む読解力向上作戦
読解力は国語に限らず、全教科で必要な力です。ここでは、各教科の特性を活かした読解力向上のための取り組み例を紹介します。
算数の文章題をスッキリ解決!
算数の文章題は、読解力不足によって正しく理解できないケースが多く見られます。そこで、以下のような取り組みで、文章題を読み解く力を育てましょう。
▼指導のポイント
- 文章の構造化:問題文の数字や条件に線を引きながら、注意深く読む習慣をつける
- 視覚化:問題の状況を絵や図に表現する活動を取り入れる
- 言い換え練習:問題文を自分にとってわかりやすい言葉で言い換えてみる
算数でのこのような活動を通じて、子どもたちは文章から必要な情報を適切に取り出し、整理する力を身につけることができます。また、問題の構造を視覚的に捉えることで、複雑な文章題も理解しやすくなります。
理科で楽しく情報活用!
理科では、実験や観察の目的や、そのための視点・手順を理解したり、結果を分析したりする場面で、読解力が求められます。
▼指導のポイント
- 実験手順書を読み、手順を図解してみる
- 観察・実験の結果をグラフや図に整理・表現し、読み取れる情報を話し合う
- 科学的な資料を、重要な情報に印をつけるなどして、考察を深めながら読む習慣をつける
理科の学習を通じて、情報を視覚化する力や、データから意味を読み取る力が育ちます。子どもたちの科学的な見方・考え方を育むとともに、読解力・考察力の向上にも効果的です。
社会の資料を楽しく読み解こう!
社会科では、地図や統計資料、年表など、さまざまな形式の資料を読み解く力が必要です。
▼指導のポイント
- 複数の資料(地図とグラフなど)を関連づけて読み取る活動を取り入れる
- 資料から読み取れる事実と、そこから考えられることを区別する習慣をつける
- 「なぜ」「どのように」という問いを立て、資料から答えを探す活動を行う
社会科の活動を通じて、子どもたちは多様な情報を関連づけて考える力や、資料から事実を正確に読み取る力を身につけることができます。
算数の文章題や理科の実験手順、社会科の多様な資料といった各教科の特性を活かしながら、学習の基盤となる読解力を高めることが可能です。
明日からできる!子どもの読解力向上への第一歩
読解力は、国語に限らず算数、理科、社会など、全教科の学習に不可欠な能力です。また、コミュニケーション能力や、情報収集・活用力のほか、将来の可能性を広げる社会スキルの基盤となる重要な力です。
読解力を育むためには、教科学習を軸として、語彙力の向上や的確な文章理解力、読書習慣の定着につながるような、継続的かつ日常的な実践が必要です。
子どもたちの未来を支える「生きる力」につながる読解力を育む機会や習慣を、学校教育の現場で少しずつでも補えるような指導の工夫が大切です。子どもたちの読解力を育てるための新たな取り組みのきっかけとして、この記事がお役に立ちますよう願っています。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。