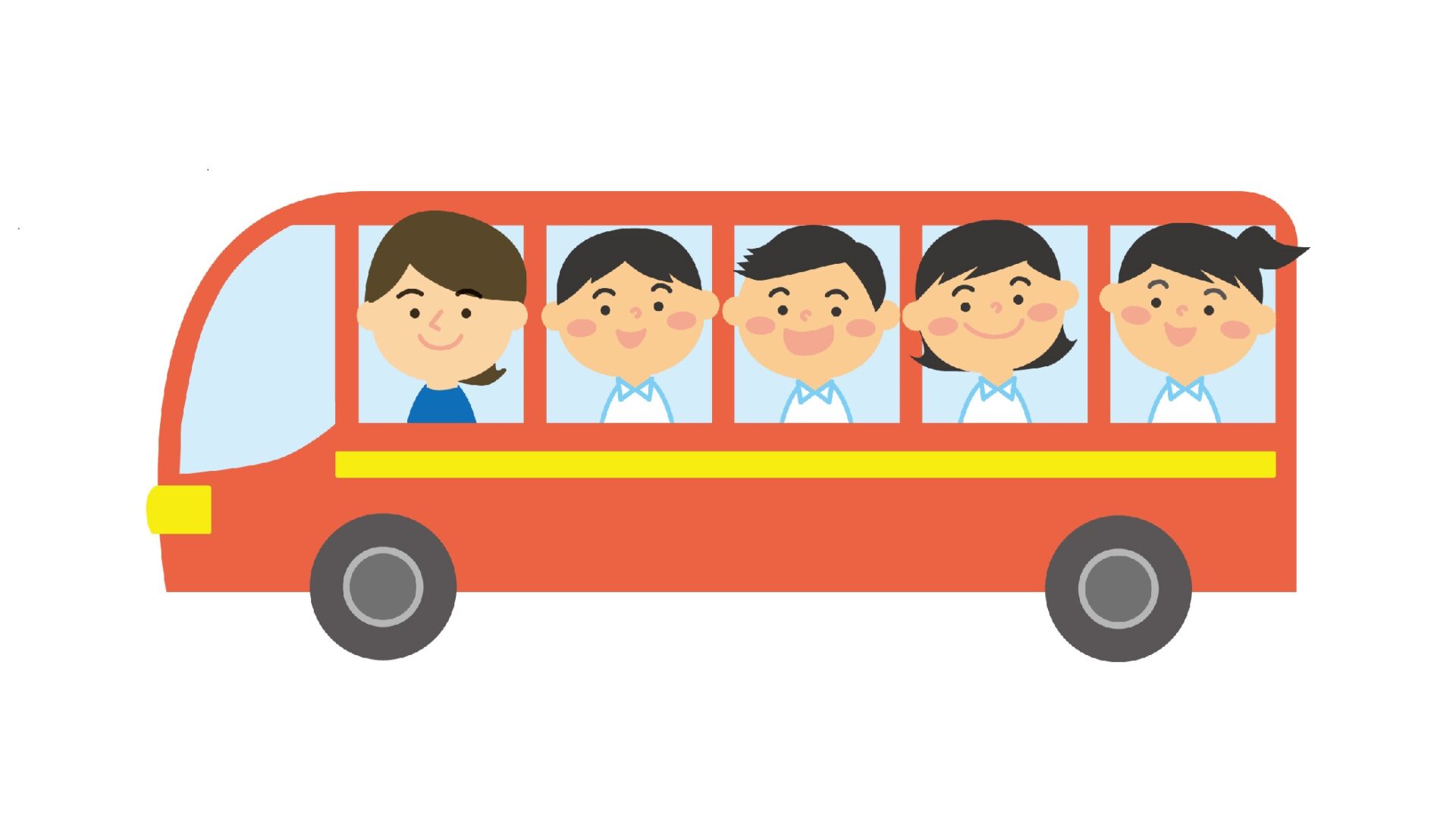目次
「毎日の朝の会で、他の学校やクラスではどんなことをしているの?」
「マンネリ化を避けたいけれど、朝の会で話すネタに日々悩んでいる」
「子どもたちが喜ぶような、楽しくて新鮮なアイデアを知りたい!」
このようにお悩みの先生方も、いらっしゃることでしょう。
朝の会の目的は、子どもたちの心身の状態を確認しつつ、学習に臨むための意識の切り替えを行うことです。うまく活用できれば、クラスの一体感を作ることにも役立ちます。
そこで、この記事では、小学校の朝の会で使えるネタを30種類、目的ごとに紹介します。毎日の登校が楽しみになるような、おもしろい朝の会を企画してみましょう。
コミュニケーション力を高めるアイデア6つ
まずは、コミュニケーション力の向上に役立つ朝の会のネタを6つ紹介します。
軽いスピーチや雑談を企画すれば、朝の会の短い時間でも、子どもたちが自己開示や会話のキャッチボールを行う練習になります。
今日の一言
クラス全員で共有する「その日のスタート」として、日直が一言で思いを表現します。長い話ではなく、その日の気持ちや決意を端的に伝えることで、クラス全体の雰囲気づくりを行います。
▼例
「今朝、登校中に桜が咲き始めているのを見つけました。春が来たなと思います」
「今日は算数のテストです。頑張ります!」
先生が短くコメントを返すことで、クラス全体でその日の気持ちを共有する時間となります。所要時間は1分程度です。
ペアトーク
隣の席の人と2分間、先生の指定したテーマについて話し合うワークです。クラス替えや席替えの直後であれば、まだあまり話す機会のなかった人と親交を深めるきっかけにもなるでしょう。
テーマは「休日の出来事」や「好きな食べもの」など、子どもたちが話しやすい内容にしましょう。話題が切れてしまっていないか、先生が見回って確認することも大切です。
全員一言リレー
先生がテーマを決め、クラス全員で会話のリレーをしてみましょう。テーマに沿って、1人1人順番に一言ずつ話をつなげていきます。
▼例:「今日の天気」をテーマとした場合
1番目の児童「今日は晴れだね」
2番目の児童「空が青いよ」
3番目の児童「散歩したくなるね」
順番が毎回変わるように、先頭になる人や回る順番を記録しながら変化させましょう。
朝の2分間スピーチ
特定のテーマについて、準備をして臨むスピーチ活動です。話す力、聞く力、構成力を育てることを目的とします。 事前に担当を決めておき、スピーチの準備をしておくように伝えましょう。クラスメイトからの質問時間を設けることで、双方向のコミュニケーション力も育ちます。
最初のうちは、先生が学年に合わせて話しやすいテーマを設定しましょう。子どもたちがスピーチに慣れてきたら、自分で好きなようにテーマを決めてもらうのもよいかもしれません。
▼スピーチのテーマ例
- 休日の過ごし方
- 好きな本や映画
- 将来の夢
- 最近挑戦したこと
- 家族との思い出
- お気に入りの場所
グループでのお題トーク
学級班または4~5人のグループで、先生が決めたテーマについて話し合います。テーマの選び方次第で、低学年から高学年まで応用できるアイデアです。
国語の授業で扱った小説をテーマに感想を述べ合ったり、直近のニュースに関する意見を語り合ったりすれば、学びにもつなげられます。低学年の場合は「もしも空を飛べたら」など、親しみやすい題材を選ぶとよいでしょう。
隣の人の良いところ探し
日頃のやりとりで感じている隣の席の人の良いところや、良かったと思う行動などを発表するワークです。
お互いに相手の具体的な行動や長所を褒め合うことで、隣同士の仲がよくなるきっかけとなり、クラス全体の雰囲気もよくなるでしょう。
▼良いところ探しの発言例
- 「〇〇さんは、いつもニコニコしているので、話していると楽しい気分になります」
- 「〇〇さんは、昨日の体育が終わったときに、自主的に用具を片付けていました」
- 「〇〇さんは、算数が苦手な私に、根気強く教えてくれます」
- 「〇〇さんは、係の仕事を黙々とていねいにこなしています」
上手にテーマを設定すれば話題がつながりやすくなり、クラスの親和度UPに役立ちます!
学習につながるアイデア6つ
次に、学習につながる朝の会のネタを6つ紹介します。
それまでに学んだ各教科の授業の復習も、工夫次第で楽しく朝の会に取り入れられます。これから学ぶ内容の予習をして、学習へのモチベーションアップにつなげるのもよいでしょう。
今日の言葉
1日1個、四字熟語やことわざを紹介します。まずは言葉だけを見せて、読み方や意味を当ててもらえば、その後の解説をより興味を持って聴いてもらえるでしょう。
その言葉が生まれた背景や、なぜそのような意味になるのかを説明すれば、一層子どもたちの記憶に残りやすくなります。
高学年なら「動物が出てくることわざ」「数字が入っている四字熟語」などのルールを決めて、知っている言葉を挙げてもらうのもおすすめです。
学びの発表スピーチ
日ごとに担当を決め、その日の学習内容に関連したテーマでスピーチを行います。
スピーチをするには、それまでに学んだ内容の理解が不可欠なので、理解度の確認にもなります。担当の子がプレッシャーを感じないよう、担当の人数や時間を調節したり、テンプレートを作ったりする工夫も必要です。
今日のクイズ
各教科について、とくに覚えておいてほしい内容のクイズを出題します。曜日ごとに教科を変えれば、得意科目がある日の登校意欲にもつながるでしょう。
選択肢式にすれば、クラス全員が参加できます。〇✕式にして、選択肢によって教室の左右に分かれてもらう方式も盛り上がるでしょう。
漢字の成り立ち紹介
1日に1文字ずつ、漢字の成り立ちを紹介します。学んだばかりの漢字を取り上げると、授業のおさらいにも役立ちます。
似ている形の漢字の意味を推測したり、共通点を見つけたりと、自主的に漢字を学ぶきっかけにもなるでしょう。
英語のフレーズ練習
簡単な英語のフレーズを全員で練習します。挨拶や日常会話など、覚えやすく汎用性の高い一言を中心に選びましょう。
可能であれば、フレーズを構成する英単語の意味も解説したほうが、記憶に定着しやすくなります。また、季節の行事や校内イベントにちなんだものを取り上げると、興味を持ってもらいやすいでしょう。
今日の計算チャレンジ
簡単な計算問題に挑戦するワークです。小テスト形式にすれば、クラス全員が参加できます。
▼計算チャレンジの実施例
- 計算問題の小テストを配布する
- 時間制限を決めて、解いてもらう
- 答え合わせをする
- 高得点が取れた人に挙手してもらい、クラス全員で拍手する
タイムアタック方式にして、得点を競うことでゲーム性を持たせれば「もっと高得点を取りたい!」という意欲につながります。
楽しみながら授業での学習内容につなげられるような、小さなワークにすることがポイントです。
心を育むアイデア6つ
子どもたちの心の成長につながる、朝の会のネタを6つ紹介します。一日の目標を決めたり、その日に嬉しかったことを探したりすることで、毎日の充実感につながるでしょう。
今日の目標宣言
その日の個人目標を宣言してもらいます。日替わりで当番を決めるか、クラス全員で一言ずつ話すかは、確保できる時間に合わせて調節しましょう。
目標は、努力次第で必ず達成できるような簡単な内容にしましょう。毎日目標を決めて達成するサイクルを回すことで、子どもたちの自己肯定感を育めます。
感謝の言葉交換
クラスメイトに対して、感謝の言葉を伝えるワークです。感謝を伝える側・受け取る側が特定の児童に偏らないよう、記録を取りながら進めるとよいでしょう。
感謝を伝えられた児童は自信を持てるだけでなく、良い言動を認めてもらえていることに気付き、充足感や自己肯定感を得られます。話すのが苦手な児童にとっても、クラスメイトに気持ちを伝えられる良い機会になるでしょう。
小さな日替わり当番
1〜2日単位で交代する当番を設け、クラスの仲間のために小さな役割を担います。明確な順番制(出席番号順や座席順など)で、できることから取り組むことで、自然と思いやりの心が育ちます。
▼当番の役割例
- お知らせ担当
朝の会や帰りの会で、連絡事項を確認する。「〇時間目は図工室です」「明日は体育着です」など、クラスの仲間に伝える。 - 教室見守り
移動教室の時に、忘れ物がないかさりげなくチェックする。「〇〇さん、筆箱が机に残っていますよ」など、声をかける。 - あいさつ当番
朝の挨拶や帰りの声かけをする。「おはようございます」「気をつけて帰ってね」など、温かい言葉を交わす。
ポイントは短い期間で交代することです。順番制にすることで、特定の児童への負担の集中を防ぐことができます。失敗を責めず、互いに助け合える雰囲気づくりを心がけましょう。
朝の読み聞かせ
短い物語や詩を朗読し、読み聞かせます。プリントを配布するなどして、子どもたちに音読してもらうのもおすすめです。
時間を確保できるのであれば、クラス内で感想を述べ合うと、より有意義な時間になります。自分と異なる意見・視点を知ることは、子どもたちの感性を刺激し、視野を広げることにつながります。
俳句や川柳を紹介した後に、季語などのテーマを設けて実際に作品作りをしてもらうのも盛り上がるでしょう。
グッドニュースの共有
身の回りのうれしい出来事や発見を共有するワークです。個人的な体験から社会的な出来事まで、子どもたちが「よかったな」「うれしいな」と感じたことを、グッドニュースとして発表します。
先生が見つけたグッドニュースを初めに話すと、子どもたちも発表しやすくなるでしょう。
▼グッドニュースの例
- 「近くの駅で、ツバメが巣を作っていました」
- 「休み時間にドッジボールをして、初めてキャッチができました」
- 「妹が一人で靴紐を結べるようになりました」
なお、テレビやネットで知ったニュースを題材にするのもよいでしょう。自分の身の回りの出来事に一喜一憂するだけでなく、関心を広く外に向けて、世の中の動きを自分事として捉えるレッスンになります。
毎日の「ありがとう」探し
前日に経験した「ありがとう」な出来事を共有します。学校内での出来事に限らず、家族や出会った誰かにしてもらって嬉しかったこと、感謝していることの発表が中心になります。
▼ありがとう探しの例
- 「帰り道、ランドセルのふたが空いて中身を全部、道に落として困っていたら、上級生が拾うのを手伝ってくれました」
- 「母が仕事帰りに、私の大好きなお菓子を買ってきてくれました」
- 「公園で、誰かがベンチに置いていったゴミを片付けてきれいにしてくれている人がいました」
日常の感謝を探す習慣をつければ、毎日を気持ちよく過ごせるだけでなく、自分たちもそのような行いを心がけたいと思うきっかけになるでしょう。
一人ひとりの小さな気づきや頑張りが、クラス全体の雰囲気を明るくしていきます。感謝の気持ちと互いを認め合う心で、温かいクラスを育てましょう。
学校生活に楽しさをプラスするアイデア6つ
朝の会を活用して、子どもたち一人一人が前向きな気持ちで一日を始められるアイデアを6つ紹介します。
とくに低学年の場合、学校を自分の居場所として感じられることが大切です。子どもたちが「今日も学校に来てよかった」と感じられる朝の時間を作りましょう。
今日のカラー
自然や季節、行事にちなんだ色を通して、子どもたちの感性や知識を育みます。一例として、暦などに基づく色図鑑のような書籍やサイトの情報をもとに、先生がその日、季節にふさわしい色を紹介します。
また、以下のような方法で子供たちが「色探し」や「今日のカラー選び」をするのも楽しいでしょう。
▼実施方法の例
- 季節の色を探そう
春:桜色、若葉色、菜の花色など
夏:空色、檸檬色、若苗色など
秋:茜色、柿色、栗色など
冬:銀灰色、雀茶色、煉瓦色など - みんなで選ぶ今日の色
① 日直が複数の色カードの中から1枚を選び、選んだ理由も合わせて発表する
② 誕生日の子どもが色を選ぶ(誕生日の子がいない日は日直が担当)
③ 季節の行事や特別な活動がある日は、それにちなんだ色を選ぶ
じゃんけん列車
体を動かしながら楽しむミニゲームです。金曜日や行事の前日など、特別な日に実施するのがおすすめです。5分程度で完了するので、朝の会の時間を大きく取られることなく、気軽に取り入れてクラスに活気を生み出せます。
▼じゃんけん列車の手順:
- 音楽をかけて、その間教室内を歩き回る
- 音楽が止まったら、近くの人とじゃんけんをする
- じゃんけんに負けた人は、勝った人の列の一番後ろにつく
- 1~3を、全員が一列になるまで繰り返す
- クラス全員が一列になったとき、先頭にいた人が優勝
じゃんけん列車のBGMは、次に紹介する「今日の一曲」で選んだ曲を使うのもよいでしょう。
今日の一曲
朝の会のBGMを選びます。先生が決めてもいいですが、児童に選んでもらえば、子どもたちの流行や関心を知ることができます。先生が選ぶ場合は、その曲が作られた背景や、自分が選んだ理由について、解説するとよいでしょう。
また週に1回、たとえば月曜日の朝の会の最後の5分間を使って、音楽に親しむ時間を設ける、といった運用もおすすめです。
朝のなぞなぞタイム
先生と子どもたちが、なぞなぞを出し合います。まずは例として先生が出題し、それに続いて、児童が考えたなぞなぞを挙手して出題してもらうとよいでしょう。
▼会話例
先生:「では、今日のなぞなぞタイムを始めます。今日は先生から出題です。『ポケットに入れると、すーっと消えてしまうものな〜んだ?』」
児童A:「ハンカチ!」
先生:「残念! もう一度考えてみましょう。ポケットに入れると…」
児童B:「あ! 手をポケットに入れると見えなくなる!」
先生:「正解です! では、今度は誰か出題してくれる人はいますか?」
ポイントは、簡単なものでよいということ。なぞなぞを解いたり考えたりすることは、言葉に関心を持つことにもつながります。
今日のチャレンジカード
朝の会の始めに、その日に取り組みたい具体的で前向きな言動が書かれた「チャレンジカード」を1枚引くメニューです。カードは1枚ずついろいろなバリエーションのチャレンジ内容を書いて、何枚も用意しておき、裏向きにして日直が1枚引いて選びます。
▼カードの例
- 「今日は、誰かに『ありがとう』を3回以上言ってみよう」
- 「休み時間に、好きな遊びを全力でしてみよう」
- 「授業で分からないことがあったら、勇気を出して質問してみよう」
- 「廊下は走らず、右側を静かに歩くことを意識してみよう」
「やってみたい人は挑戦してね」というニュアンスにし、強制にならないよう配慮しましょう。クラス全体のポジティブな雰囲気づくりにつながります。
言葉の面白さ発見タイム
週に1回程度、朝の会の最後の3分間を使って、言葉に親しむメニューに取り組みます。学年に応じた言葉遊びを通して語彙力を広げ、日本語の面白さに気づくきっかけを作りましょう。
▼実践例
- 今週の漢字で連想ゲーム
国語の授業で習った漢字を使って連想を広げる
例:「木」→「林」→「森」→「緑」→「葉」
漢字の成り立ちや意味の理解を深める - 季節の言葉でしりとりに挑戦
その季節に関連する言葉でしりとりをする
例:「さくら」→「ランドセル」→「ルール」
季節感と語彙を同時に学ぶ - 音数で遊ぼう(10回ゲーム)
同じ音の数の言葉を考える
例:3音「さくら」「つばめ」「はるか」
音節への意識を高める
その週の学習内容の定着や、桃の節句、お月見といった和の暦にもとづく季節感・行事への意識づけも自然に行える遊びです。間違いを責めない和やかな雰囲気で、子どもたちの教養を育てましょう。
子どもたちの1日の学びは、心の準備から。朝の会で前向きな気持ちにスイッチを入れましょう!
子どもたちの健康チェックを兼ねたアイデア6つ
子どもたちの心身の健康状態を把握するのは、朝の会の目的の1つです。そこで、楽しみながら健康チェックができるネタを6つ紹介します。
おもしろ健康観察
クラス全体で声を出し合って、互いの健康状態を共有する活動的な健康観察です。子どもたちにとっては、自分のコンディションを周りに伝えるトレーニングになります。実施する前に、あらかじめルールを伝えておきましょう。
▼おもしろ健康観察の例
- 「今の元気度を、声の大きさで表してください」
- 「今の気持ちを、表情で伝えてみてください」
なお、普段から声が小さいなど、状態の把握に注意が必要と思われる児童には、個別に健康状態をあらためて尋ねるなどの配慮を欠かさないようにしましょう。
朝のストレッチタイム
簡単なストレッチをクラス全員で行います。
長い時間座ったままで体が硬くなってしまうと、身体的なデメリットだけでなく、集中力の低下にもつながります。体を動かす授業のない日は、朝の会で軽い運動やストレッチをするのがおすすめです。
今日の気分メーター
自分と向き合い、心の状態を可視化するメニューです。その日の朝の気分を5段階で表現します。子どもたちにとって、気持ちをコントロールする練習になります。
▼実施方法
- 朝の会の始めに、各自が静かに自分の気分を振り返る時間を設ける
- 5段階(例:1=とても落ち込んでいる、3=普通、5=とても元気)で記録
- 個人用の記録カードに、日付と数値を記入
- 記録は強制せず、自主的な取り組みとする
朝の深呼吸タイム
クラス全員で深呼吸を行います。息を吐く時間と吸う時間を、先生がカウントしましょう。
深呼吸の最中は、無理にカウントに合わせようとせず、あくまで自然に呼吸するように、子どもたちに事前に伝えておきましょう。
挨拶と握手で元気度チェック
隣の席の子と挨拶や握手をして、声の調子や握力、手の感触などから、お互いの元気度を確認します。隣だけでなく周りの席の人たちと、順番に挨拶していってもよいでしょう。
簡単な挨拶を毎日クラスメートと繰り返すことで、他の場面でも周囲の人たちに目を配り、変化に気付けるようになるでしょう。
朝の表情チェック
先生の声がけによって笑顔、真顔、驚き顔などの表情を作り、周囲の児童とお互いの様子を確認し合います。
表情は大切なコミュニケーション手段です。表情を意識して作る機会を通して、感情表現の幅を広げ、他者の表情への関心を育てます。
▼実施方法
- 先生がお手本を見せながら声がけをする
「おはよう。今日は『うれしい』表情を作ってみましょう」
「隣の人と向き合って、お互いの表情を見せ合ってみましょう」 - 少しずつ表現の幅を広げていく
最初は表しやすい感情(うれしい、悲しい、びっくり、など)からスタートし、慣れてきたら複雑な感情(困惑、悩んでいる、など)も取り入れる。 - 「どんな時に、こんな気持ちになる?」と話し合う
余裕があれば、感情と表情のコミュニケーションについて話す時間を設ける。
ただし、実施前に以下の点は事前に伝えておきましょう。
- 無理をせず、できないときはしなくてもよいこと
- 個人の表現の違いを認め合うこと
遊び心のあるワークにすることで、人見知りな児童にとっても、周りの子とのコミュニケーションのきっかけになるでしょう。
朝は、子どもたちの健康状態や変化に気づきやすい時間です。先生が丁寧に見守りつつ、児童同士でもお互いの様子を気にかけ合えるクラスをめざしましょう!
朝の会についてのQ&A
最後に、朝の会を企画する際にありがちな疑問について、Q&A形式で解説します。ポイントを押さえて、子どもたちがその日の学校生活を楽しく始められるようにしましょう!
朝の会を成功させるコツはありますか?
10分程度を目安に、メリハリのある進行を心がけましょう。特に小学生の場合1つのことに集中できる時間は短いため、だらだらと長くならないよう注意が必要です。活動の切り替えを明確にすることで、集中力を保ちやすくなります。
本記事で紹介したアイデアでも触れているように、子どもたちに適切な役割を与えて自主性を育むことが重要です。自分で考え、選び、行動する機会を設けることで、子どもたちの学習意欲や前向きな姿勢を引き出すことができます。主体的な参加の積み重ねが、授業での学びの質を高めることにもつながるでしょう。
時間が足りない場合はどうすればよいですか?
朝の会に確保できる時間に合わせて、基本的な趣旨や流れを押さえ、無理のない範囲で実施しましょう。
あくまでも、学校生活のメインである授業や実習のためのウォーミングアップの時間として、柔軟に対応することが大切です。
取り入れるアイデアは、詰め込みすぎず1日に一つにしたり、所要時間を想定して指名の人数をあらかじめ決めておくなど、授業に支障の出ないような計画を立てておくことも大切です。
高学年でも楽しめるアイデアはありますか?
スピーチ系のアイデアや、ネタのお題・テーマ設定を工夫するなど、年齢相応の内容にすれば高学年でも十分楽しめます。年齢とともに児童の視野も広がっていくので、時事問題やその日話題になっているニュース、流行などに関するテーマを多く取り上げるのもよいでしょう。
▼高学年向けのテーマ例
- ここ1週間以内に、とくに興味を持ったニュースや情報を一つ取り上げ、それについての意見や感想を話す。
- 「今、ハマっているもの」についてプレゼンする。
年間を通じて、学校内でのイベントや教科学習の進度に合わせたテーマ設定をするのもよいでしょう。
子どもたちと一緒に朝の会を充実させよう
この記事では、朝の会で使えるネタ30選を紹介しました。
朝の会は、登校したばかりの子どもたちの様子を見ながら、学校での一日の始まりに、気持ちを学習モードへ切り替えてもらうための大切な時間です。また、短いながらも、授業とは違う先生と生徒の交流の場でもあります。今回ご紹介した内容を参考に、子どもたちの自主性やポジティブな学習姿勢につながる、楽しい朝の会を行いましょう。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。