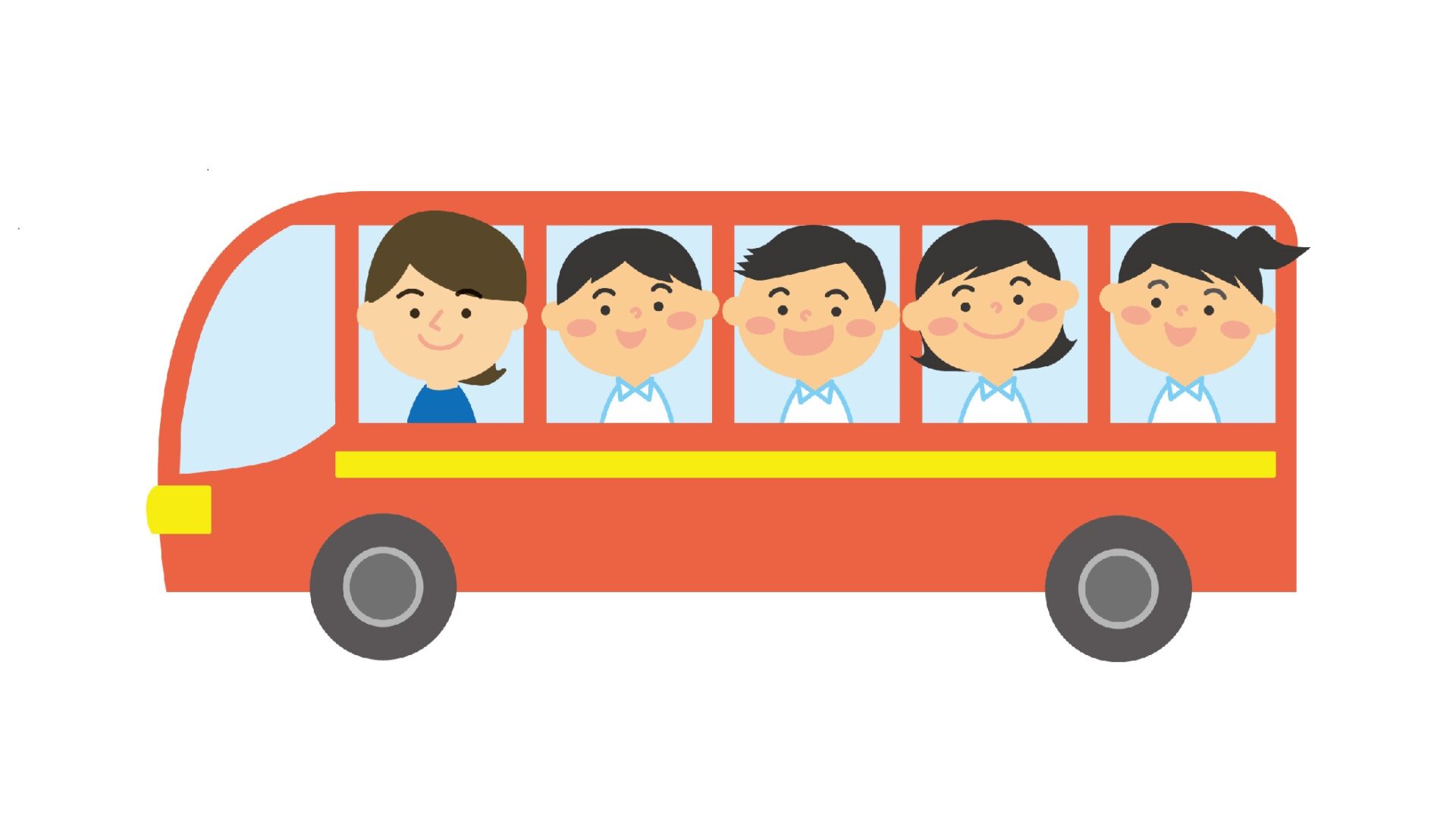目次
この記事では、「大阪・関西万博」の時事解説を小学校高学年~中学生にわかりやすく説明します。授業の合間に話すネタ、関連事項を解説する際の資料などとしてご活用ください。
大阪・関西万博がスタート
2025年4月13日、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)が開幕しました。
「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、10月13日までの184日間、大阪府・夢洲(ゆめしま)を会場に開催されます。日本で万博が開催されるのは、愛知県で開催された2005年日本国際博覧会(愛・地球博)以来20年ぶりですが、万博とはどのようなイベントなのでしょうか。
万博ってどのようなイベントなの?
万博とは国際博覧会条約に基づき、各国の政府が主催者となって開催する「国際博覧会(万国博覧会)」の通称で、「万国博」「EXPO(エキスポ)」などとも呼ばれます。
初めて開催された万博は1851年にイギリスで開催されたロンドン万博(第1回ロンドン万国博覧会)です。それ以前からヨーロッパ各国では、技術や物産の展示を目的とした国内博覧会が開催されていましたが、ロンドン万博はヴィクトリア女王の夫であるアルバート公らが中心となって、初の国際博覧会として開催されました。ロンドン万博でイギリスは圧倒的な工業力を世界に示して大成功を収め、その後、各国で万博が開催されるようになりました。
1928年には国際博覧会条約が成立し、条約にのっとって開催されるように監督する博覧会国際事務局(BIE)が設立されました。現在、万博とはBIEが承認し、条約に基づいて開催される国際博覧会を指し、「登録博覧会(登録博)」と「認定博覧会(認定博)」の2種類があります。登録博は5年に一度開催される大規模なもので、開催期間は6週間以上6か月以内です。今回の大阪・関西万博は、この登録博にあたります。前回、2020年にアラブ首長国連邦で開催予定だったドバイ国際博覧会は新型コロナウイルス感染症の影響で延期され、2021年10月から6か月間開催されました。また、認定博は登録博と次の登録博の間に1回だけ開催される期間の短い(3か月以内)博覧会です。
万博は、世界中から人や物が集まり、さまざまな技術や商品、芸術に関する流行などを世界に向けて発信する場となってきました。出品を機会に発展した工業技術などは数多くあり、生活の利便性を高めたり、新しい流行が広がるきっかけとなったりする役割を果たしてきました。現在では世界の共通課題に取り組む場ともなっています。
日本でこれまで開催された万博は?
日本と万博との関わりは1862年、ヨーロッパを歴訪中の江戸幕府の使節団(文久遣欧使節)が、第2回ロンドン万博を訪れたことから始まります。福澤諭吉も参加したこの使節団は、進んだ西洋文明を目の当たりとすることとなりました。日本が初めて参加したのは1867年のパリ万博で、このときは江戸幕府と薩摩藩、佐賀藩が出展しました。日本政府として初めて公式に参加・出展したのは1873年のウィーン万博でした。
日本では1940年に東京と神奈川県で紀元2600年記念日本万国博覧会の開催が決まっていましたが、日中戦争の激化などのため、同じ年に予定されていた東京オリンピックもろとも中止となりました。
日本で初めて実際に開催された万博は、1970年の大阪万博です。「人類の進歩と調和」をテーマに開催された大阪万博には77か国が参加。プロデューサーに起用された岡本太郎氏が制作したシンボル「太陽の塔」を中心とするテーマ館は来場者に強い感銘を与え、アポロ11号が持ち帰った「月の石」の展示や「動く歩道」、電気自動車なども話題となり、総入場者数が6400万人を超える大成功を収めました。
その後の日本では、登録博として2005年の愛・地球博が、認定博の前身である特別博として1975年の沖縄海洋博、1985年の科学万博、1990年の花の万博が開催されています。
筑波研究学園都市で開催された科学万博では、さまざまな科学技術や宇宙がビジュアル化され、日本に科学ブームを巻き起こしました。愛・地球博では自然の摂理から謙虚に学び、持続可能な社会を創生していく「自然の叡智」をテーマに、環境へ配慮した取り組みや省エネ技術が取り入れられ、気候変動など地球的課題に対する理解と行動を意識づける機会となりました。
なお、大阪・関西万博のあとの2027年には神奈川県でGREEN×EXPO2027(正式名「2027年国際園芸博覧会」)が開催予定です。認定博ですが、「大規模国際園芸博覧会」として認定されたため、6か月と1週間という長期にわたって開催されます。
| 正式名称 (略称・通称) | 期間 | 場所 | テーマ | 参加国 (日本を含む) | 総入場者数 |
| 日本万国博覧会 (大阪万博) | 1970年3月15日~9月13日 | 大阪府(千里丘陵) | 人類の進歩と調和 | 77か国・4国際機関 | 6422万人 |
| 沖縄国際海洋博覧会 (沖縄海洋博) | 1975年7月20日~1976年1月18日 | 沖縄県(国頭郡本部町) | 海-その望ましい未来 | 36か国・3国際機関 | 349万人 |
| 国際科学技術博覧会 (科学万博、つくば博) | 1985年3月17日~9月16日 | 茨城県(筑波研究学園都市) | 人間・住居・環境と科学技術 | 48か国・37国際機関 | 2033万人 |
| 国際花と緑の博覧会 (花の万博、花博) | 1990年4月1日~9月30日 | 大阪府(鶴見緑地) | 花と緑と生活の関わりを捉え21世紀に向けて潤いのある社会の創造を目指す | 83か国・37国際機関、18園芸関係等の国際団体 | 2312万人 |
| 2005年日本国際博覧会 (愛・地球博、愛知万博) | 2005年3月25日~9月25日 | 愛知県(瀬戸市南東部、豊田市、長久手町) | 自然の叡智 | 121か国・4国際機関(国連は33の国連関係機関含む) | 2205万人 |
万博開催でどのような影響や効果が期待できる?
万博は社会や経済に多くの影響を与えてきました。万博の開催に合わせてインフラが整備されたり、万博のレガシー(遺産)が活かされたりすることが、その後の地域社会・経済の発展につながっています。20年ぶりに日本で開催される大阪・関西万博でもその効果が期待されています。
大阪・関西万博はどんな万博なの?
大阪・関西万博は、大阪・関西地域、そして2020東京オリンピック・パラリンピック後の日本の成長を持続させる起爆剤にすることを目的に誘致されました。
大阪・関西万博では「いのち輝く未来社会のデザイン」をメインテーマに、「持続可能な開発目標(SDGs)達成への貢献」と「日本の国家戦略Society5.0の実現」を目指しています。SDGsとは国連加盟国が2030年までに達成すべき17の目標であり、Society5.0とはサイバー(仮想)空間と現実空間を高度に融合させたシステムによって、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会を指します。IoT(モノのインターネット:家電などのさまざまなものをインターネットとつなぐこと)やAI(人工知能)をはじめとする技術で地球規模の課題が解決されることは、SDGsの達成にもつながります。会場のシンボルとなるのは、「多様でありながら、ひとつ」という万博会場のコンセプトを象徴する世界最大級の木造建築物「大屋根リング」です。
大阪・関西万博には158の国・地域と7国際機関をはじめ、多くの企業や団体が出展しています。各国の特徴を伝えるパビリオンがつくられ、その国の技術や文化などを体験することができます。
日本からは「循環」をテーマの中心にすえた「日本館」や、医療や健康分野の先端技術や未来社会のモデルを提案していく「大阪ヘルスケアパビリオン」、8人のプロデューサーが企画した、リアルとバーチャルを取り混ぜた体験によって「いのち」について考えることができる「シグネチャーパビリオン」などが出展されています。
また、万博会場を未来社会のショーケースに見立てて先進技術や次世代技術を実装・実証する「未来社会ショーケース事業」が、多くの企業や大学・研究機関などが参加して、会場のさまざまな場所で実施されています。
●大阪・関西万博で実施されている「未来社会ショーケース事業」
| スマートモビリティ万博 | 水素と電気のハイブリッドで航行する水素燃料電池船 自動運転などの新技術が融合したEVバス 次世代ロボットの実装・実証(ロボットエクスペリエンス) 次世代の空の移動手段「空飛ぶクルマ」 など |
| デジタル万博 | AIによる来場者向けプラン提案や来場サポートアプリ 自動翻訳システム 主要施設間の次世代ネットワークによる接続 など |
| バーチャル万博 | アバターで参加できる大阪・関西万博のバーチャル会場 など |
| アート万博 | 場所や空間全体を作品として体験させるインスタレーション プロジェクションマッピング パブリックアート など |
| グリーン万博 | CO2(二酸化炭素)吸収路面素材、CO2の回収装置 水素発電、純水素型燃料電池、アンモニア発電、 リサイクルが難しかった紙の利用 万博閉会後に発生する建築物や建材などの資源の有効利用を目的としたリユースマッチング など |
| フューチャーライフ万博 | 未来都市、未来のくらし(食・文化・ヘルスケア)のバーチャル体験 など |
大阪・関西万博開催でどのような効果があるの?
大阪・関西万博は国内から2470万人、海外から350万人、計2820万人の来場者を見込んでおり、観光や地域経済に大きな効果をもたらすと考えられています。経済産業省は、建設投資や運営・イベント、来場者の消費による経済波及効果を約2.9兆円と試算しています。
また、世界から最先端技術が集まることで、新しいアイデアが創造発信されたり、技術革新が生まれるきっかけになったりすることや、投資の拡大、地域の世界的な認知度の向上や交通インフラの整備によって、万博終了後も世界から人が集まる活力のある地域となる効果が期待されています。
1970年の大阪万博で導入された「動く歩道」や、愛・地球博で万博では初めて導入されたICチップ入り入場券がその後の普及につながったように、「未来社会ショーケース事業」で実装・実証されている先進的な技術やシステムが普及し、未来の社会の利便性を高めることにつながっていくことが望まれています。
ポイントを確認しよう
大阪・関西万博は、建設費の増額や海外パビリオンの建設の遅れ、前売券の販売状況が目標を大きく下回っていることなど不安要素を抱えながらの開幕となりました。大成功だった1970年の大阪万博や2005年の愛・地球博のときとは社会情勢が異なり、万博は時代遅れとの意見もあります。
しかし、世界各国の最新技術や英知が集結する国際イベントが国内で開催されるのは数十年に一度のことです。万博会場には未来につながる技術や現代社会の課題、世界の国々を知るきっかけが詰まっており、それは自分が何かを創造していく種となるかもしれません。会場に足を運べなくてもバーチャル体験できるものもあるので、期間中に万博に目を向けてみてはいかがでしょうか。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。