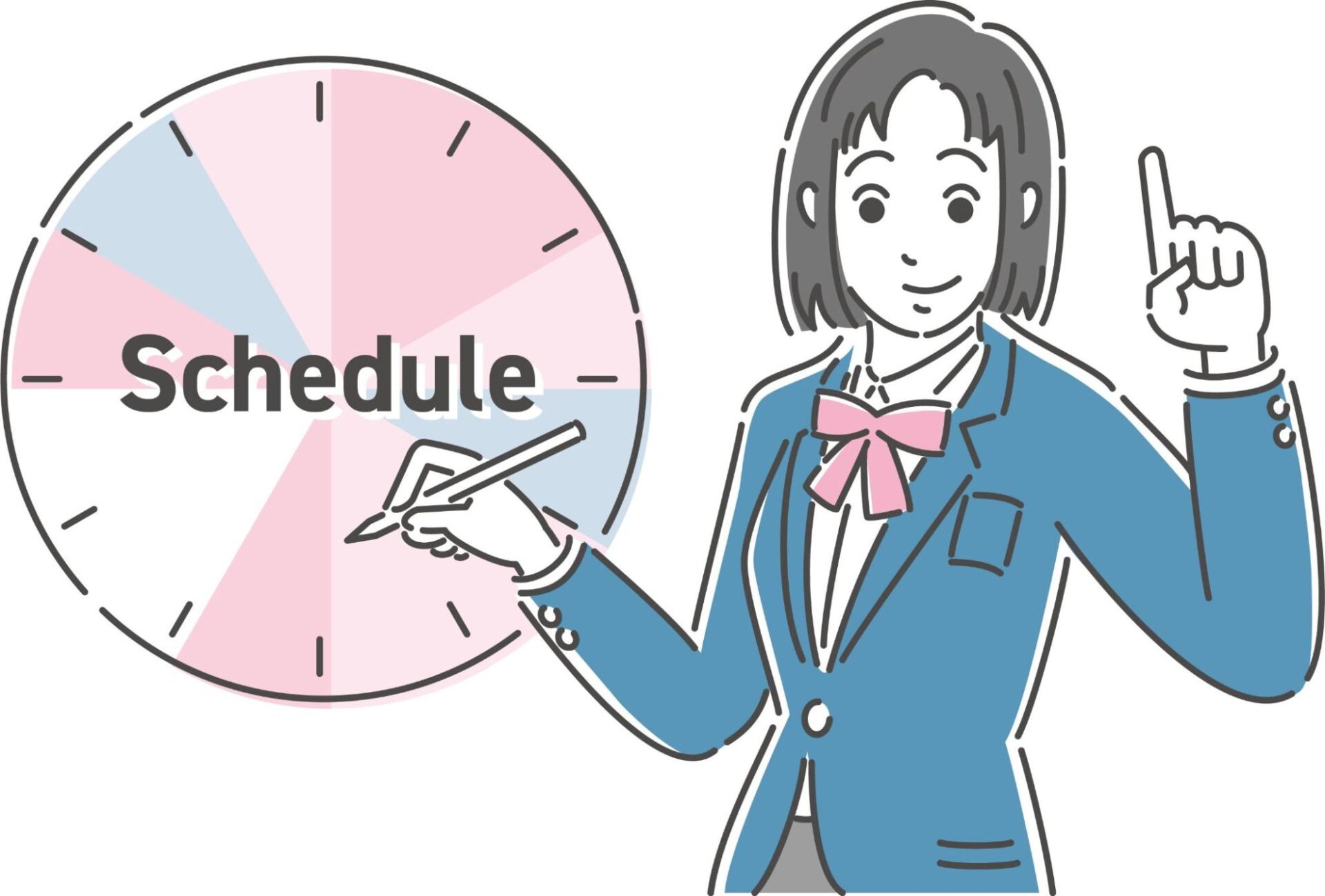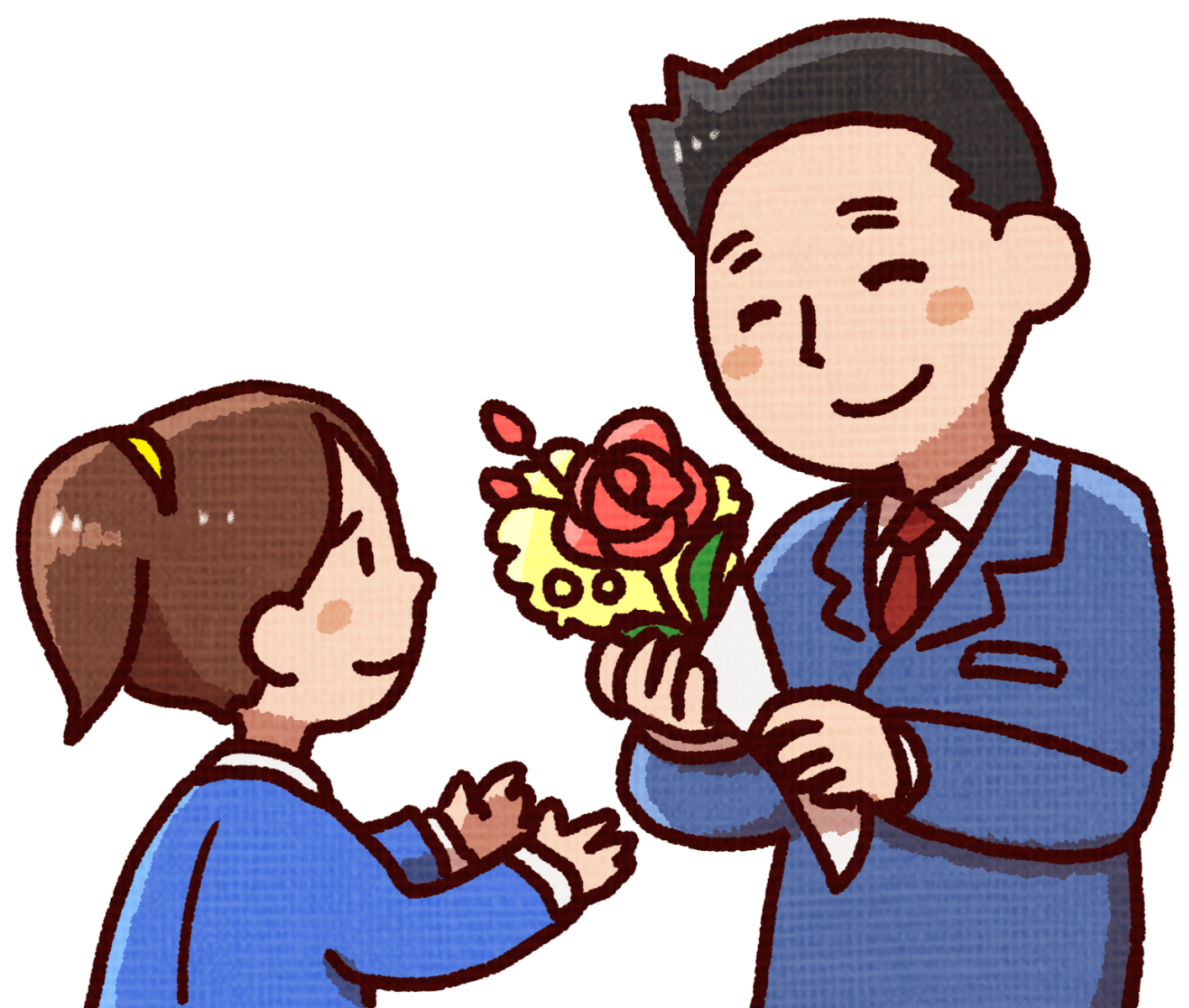
目次
「離任式の挨拶では、どんな話をすればよいのだろう。具体例が知りたい」
「生徒たちの記憶に残る挨拶にしたい」
「離任の挨拶をする際の、注意点やうまく話すコツを知りたい」
このようにお悩みの先生方も、いらっしゃることでしょう。
離任式は、新任校や新たな場へ進む教師にとって節目となる大切な学校行事です。
この記事では、「心に残る離任式の挨拶」の具体的な例文や、必要な事前準備、注意事項などについて解説していきます。日々を共に過ごしてきた児童・生徒や教職員に感謝を伝え、前向きなお別れの場にするための挨拶文を作りましょう。
離任式の基本を知ろう
離任式は、教職員が学校を異動・退職するにあたって行われる学校行事です。学校や自治体によって差はありますが、3月末の修了式と同日か4月中に行われることがほとんどです。
式は全校集会の形式で行われることが多く、体育館などで実施されます。全校児童・生徒と教職員が集まって行われますが、学校によっては保護者も呼ばれたり、学年ごとに分けて実施されたりする場合もあります。
🟨離任式の流れの一例🟩
- 校長からの紹介
- 離任者のスピーチ
- 児童・生徒代表からの感謝の言葉
- 花束贈呈セレモニー
- 退場時の見送り(拍手や校歌演奏など)
離任式の挨拶の目的とは?
離任式の挨拶の主な目的は3つです。それぞれについて、1つずつ掘り下げて解説します。
🟨これまでの感謝を伝える🟩
児童・生徒や同僚の教師、保護者など、教育活動に協力してくれた人たちに感謝を直接伝えられる貴重な機会です。日々の忙しさの中では十分に伝えられなかった感謝の気持ちを、この機会に言葉にして表現しましょう。
🟨教育活動において一つの区切りをつける🟩
今日までの思い出を振り返り、自身や受け持った児童・生徒の成長を改めて見直すことで、教育活動に区切りをつけます。児童・生徒たちにとっても、お世話になった先生との関係性に一つの区切りをつけることで、新年度のスタートへの心の準備ができるでしょう。
🟨前向きなお別れをする🟩
多くの時間や出来事を共有してきた児童・生徒と教師が、エールを送り合い前向きに別れることで、お互いにステップアップに向けた新たな一歩を踏み出す後押しとなるでしょう。別れは寂しいものですが、それを乗り越えて成長していくことの大切さを学べる場でもあります。
「事前準備チェックリスト」を作っておこう
離任式に臨むときには、事前準備をしておくと心に余裕ができ、より聴く人にわかりやすく思いを伝えられます。以下、具体的な準備の流れを時系列でまとめていきます。
1週間前までにすること
- 思い出を整理する
- 挨拶で話す内容の骨子を考える
- 伝えたいメッセージをまとめる
着任から今日までの思い出を整理し、話す時間の長さに合わせて骨子を作成します。児童・生徒に伝えたいメッセージは、当日言い忘れの無いようにまとめ、原稿を作成しておきましょう。
3日前までにすること
- 挨拶の原稿を完成させる
- 話す時間を計測し、内容を調整する
- 当日着る服装を準備する
事前にまとめておいた原稿を推敲・清書して、完成させます。完成した挨拶原稿をもとに、話す時間を計りながらスピーチを練習し、さらに内容の調整までしておけると安心です。また、当日着る服装一式を用意して、早めに整えておきましょう。
前日までにすること
- 挨拶原稿の最終確認をする
- 離任式の流れ・段取りを確認しておく
- 必要な持ち物を準備・確認する
原稿の最終確認を行い、式の流れや挨拶の順番など、段取りを確認します。また、当日も慌てることなくスムーズに対応できるよう、原稿やハンカチなどの持ち物の準備・確認をして、万全の体制で式当日を迎えましょう。
思い残すことなく、かつ皆の心に残る挨拶にするためにも、余裕をもって準備を進めておけるといいですね。
早めに挨拶の準備をしておけば、当日焦らずに「自分の言葉」で気持ちを伝えられるでしょう。
心に残る「離任式の挨拶」の構成の3つの柱
心に残る離任式の挨拶にするために、以下の3つの柱を意識して挨拶文の構成を練ってみましょう。これらのポイントを踏まえた構成にすることで、気持ちが伝わる離任式のスピーチになるでしょう。
1.感謝を伝える
共に過ごした児童・生徒や、お世話になった先生方、学校への感謝の気持ちを伝えます。児童・生徒たちには成長を見せてくれたことや日々の関わりへの感謝、先生方には惜しみない協力や支援への感謝、学校にはサポートに対する感謝を述べると良いでしょう。
具体的なエピソードを盛り込むと、聞き手の心に響く挨拶になります。
2.思い出を共有する
日常の出来事や学校行事などを振り返ります。具体的なエピソードを交えると思い出を共有でき、温かい挨拶になるでしょう。
児童・生徒の成長を感じた瞬間のエピソードなども、聞き手の共感を引き出し、お互いが共に過ごした時間の大切さを再確認できそうです。
3.未来へのメッセージ
児童・生徒たちへの応援や励ましの言葉を伝えます。これからの学校生活やそれぞれの将来に向けて、後押しとなるようなメッセージで締めくくれば、別れの寂しさを和らげ、未来への希望に変えることができます。
先生方や学校に対しては、今後の発展への期待や教育活動へのエールを伝えるとよいでしょう。
惜別の気持ちより楽しかった思い出を共有して、明るく温かな雰囲気でお別れできるように心がけましょう。
相手別「離任式の挨拶」の例文
ここからは、離任式の挨拶の例文をご紹介していきます。例文を参考にしながら、実際の校風や自身の思いと重ね合わせてアレンジしてみてください。
全校児童・生徒に向けた挨拶
全校児童・生徒に向けた挨拶は、限られた時間で全学年に話をするため、簡潔で皆にわかりやすい言葉選びを心がけます。最後は、お互いの未来へ向けた明るいメッセージで締めくくりましょう。
🟦例1
みなさん、こんにちは。◯◯です。このたび◯◯学校を離れることになりました。この学校には〇年間在籍し、その一員として、皆さんと共に学び、成長することができたことは私の宝物です。
これからも、皆さん一人ひとりが夢に向かって努力する気持ちを心から応援しています。新しい環境でも、皆さんの笑顔を思い出しながら頑張ります。本当にありがとうございました。
🟦例2
こんにちは。◯◯です。◯◯学校を離任することになりました。この学校で皆さんと過ごした時間は、私にとって本当にかけがえのないものです。授業や学校行事、部活動など、皆さんが一生懸命に取り組む姿を見て、私もたくさんの力をもらいました。
皆さんに伝えたいのは、これからも「自分を信じて進んでください。」ということです。学校生活は楽しいことばかりではなく、ときには悩んだり、つまずいたりするかもしれません。でも、そんなときこそ、自分の可能性を信じて、挑戦を続けてください。
私も新しい場所で挑戦を続けます。またいつか、どこかで、成長した皆さんに会えることを楽しみにしています。
担当学年・担当クラスに向けた挨拶
担当学年や担当クラスなど、密にかかわった児童・生徒たちへの挨拶は、行事の思い出や日頃の様子など、共に過ごした日々を思い起こすエピソードを交えると、より深く想いが伝わります。
🟦例1
◯年の皆さん、このたび私は、◯年間在籍した◯◯学校を離れることになりました。皆さんと過ごした時間は、私にとってかけがえのない宝物です。
この学年は、とにかく明るくて元気なクラスばかりでした。授業でのやりとりや、皆さんの部活動での生き生きした表情、学校行事に真剣に取り組む姿など、思い出してみると、いつも私のほうが元気をもらっていました。〇〇学校で最後に受け持った学年が皆さんでよかったです。
これからも、自分の夢や目標に向かって努力し続けてください。新しい場所でも、皆さんのことをずっと応援しています。本当にありがとうございました。
🟦例2
◯年◯組の皆さん、私はこの◯月でこの学校を去ることになりました。皆さんと過ごした時間は本当に楽しく、毎日が学びと感動の連続でした。特に校内◯◯大会では、優勝したいという熱い思いを抱き、協力し合って突き進む、皆さんの団結力とあきらめない姿に胸を打たれました。
学校生活は楽しいことばかりではなく、つらいことや悩むこともあるかもしれません。でも、どんなときも一人ではないことを忘れないでください。自分を信じ、仲間を信じ、前を向いて進んでいってください。
皆さんの未来が輝かしいものであることを願っています。今まで、本当にありがとうございました。
教職員に向けた挨拶
教職員に向けた挨拶では、これまでお世話になったことへの感謝の気持ちを伝えましょう。それに加え、学校の今後の成功や発展を願う言葉を添えると、前向きな別れの挨拶になります。
🟦例1
本日をもって、◯◯学校を離れることとなりました。未熟な私を温かく迎え入れていただき、成長する機会を与えてくださったことに、心から感謝申し上げます。
この学校で過ごした◯年間、本当に多くのことを学ばせていただきました。特に同学年担任の先生方には多くの場面で助けていただき、本当にお世話になりました。教師として、子どもたちと共に成長する貴重な機会を得られたことに、心から感謝しております。
日々の指導の心得や行事への関わり方、学級運営の仕方など、教師としての基本をご指導いただきましたことは、私にとってかけがえのない財産です。
今後の◯◯学校の益々のご発展と、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。〇年間、本当にありがとうございました。
🟦例2
このたび、◯年間在籍した◯◯学校を離れることとなりました。振り返れば諸先生方には、つねに本当にお世話になり、わが身の至らなさが悔やまれることばかりです。
初めて担任を受けもったときの緊張感、魅力ある授業づくりの難しさ、行事の成功に向けた教師としての努力や工夫、学校教育のすべての場面で皆様と共に学び、成長できましたことに、深く感謝しております。
特に◯◯先生には、いつも未熟な私をおおらかに見守っていただき、チャレンジにもご理解ある後押しを賜りました。あらためて、心よりお礼申し上げます。
新しい環境でも、ここで学んだことを活かしながら、日々精進してまいります。どうか今後とも、よろしくお願い申し上げます。本当にありがとうございました。
挨拶をする相手と自分との関係性を踏まえ、思いを共有できるメッセージを心がけましょう。
「離任式の挨拶」の話すときのコツ
同じ挨拶の内容でも、ちょっとした話し方の工夫で、相手の聞きやすさは変わってくるものです。ここでは、児童・生徒に思いが伝わりやすくなるための話し方のテクニックや、落ち着いて話すための感情コントロールの方法について、具体的なコツをお伝えします。
話し方のテクニック
離任式の挨拶では、内容だけでなく話し方も重要です。とくに体育館などの広い空間で話す場合は、普段の授業とは違った話し方をすることで、より一層想いが伝わりやすくなります。大切な言葉が伝えたい相手にきちんと届くよう、基本的なテクニックを見直して本番に臨みましょう。
🟨発音・発声🟩
後方の人まで届くように、言葉をはっきりと発音して話しましょう。とくに第一声を意識的に大きくすると、聞き手を引きつけやすく、声もこもらずに済みます。
🟨話すスピード🟩
一語ずつ、丁寧に話すことで内容が伝わりやすくなります。人が話す標準的な速度は1分に300文字程度といわれているので、原稿を考える際にも長くなり過ぎないよう意識し、早口にならないよう注意しましょう。
🟨アイコンタクト🟩
一人ひとりに話しかけるように、会場全体へ視線を送ります。聞き手の反応を見ながら話しましょう。
🟨抑揚や間(ま)の工夫🟩
話し方に抑揚のない単調な挨拶は、聞き手に退屈な印象を与えてしまいます。声のトーンや大きさに抑揚をつけたり、とくに重要な部分の前後に間を取ったりすると、話にメリハリが生まれて聞きやすくなります。
感情のコントロール
次に、挨拶中に涙が出そうなときや緊張を抑えられないときなどに役立つ、感情コントロールの方法についてご紹介します。登壇の直前でもすぐにできるので、覚えておくと便利です。
🟨身体を使う方法🟩
- 深呼吸をして気持ちを落ち着かせる
- 口角を上げて、笑顔を作る
- 足のつま先や両手を動かして、気持ちをそらす
🟨持っておきたいマインド🟩
- 大勢の前で緊張するのは当たり前だと認める
- 上手く話せなくても失敗ではない、大切なのは気持ちを伝えることだと考える
- 聞いている人たちは皆、自分の味方だと思う
離任式の挨拶は、在籍してきた学校での「最後の授業」とも言えます。発声や話し方の工夫次第で、より一層、気持ちの届く挨拶になるでしょう。
「離任式の挨拶」でよくある質問
ここでは、離任式の挨拶に関して、よくある質問に回答します。離任式に向けた不安を少しでも減らしておきましょう。
Q1. 原稿を見ても大丈夫?
離任式で原稿を見ながら話しても、まったく問題ありません。むしろ、緊張する場面で大切なメッセージを確実に伝えるためには、原稿やメモを活用することをお勧めします。
ただし、原稿に頼りきりになってしまうと、棒読みになってしまったり、気持ちが伝えきれなかったりする場合もあります。原稿を読み上げたり、丸暗記するのではなく、スピーチ内容の骨子や、伝えたいメッセージを話し忘れないための補助として、原稿やメモを手元に置いておきましょう。
ここからは、スピーチの際に見やすい原稿と活用の仕方のポイントをご紹介します。
🟨紙質と形状🟩
上質な紙や和紙など、しっかりとした紙を選びましょう。スピーチの際にしっかりと持っていられるように、手に持ったときに曲がらない厚みがある紙質が理想的です。
🟨文字の大きさと余白🟩
緊張すると視野が狭くなるものです。書いた本人も読みにくいような走り書きのメモではなく、読みやすいはっきりした大きめの文字で書き、行間や余白を十分に取りましょう。また、ポイントとなる部分は蛍光ペンでマークをつけたり、文字の色を変えたりしておくと、緊張してもすぐ目に入りやすく安心できます。
🟨大切なことをわかりやすく🟩
前述した通り、原稿は重要な話や絶対に伝えたいメッセージを目立たせて、すぐ目に入るように書いておきましょう。また、伝えたいメッセージやエピソードのみをメモして挨拶に臨む場合は、話の展開をすぐに思い出せるような構成で記しておくのがポイントです。当日緊張しても、伝えたい内容を漏らさずに伝えきることができます。
🟨スピーチ中の視線の動かし方🟩
手元の原稿とスピーチを聞いている人たちの間で、視線を交互に、適切に移動させることが重要です。とくに、段落の始まりと終わり、感謝の言葉や大切なメッセージを伝える際には、必ず顔を上げて聞き手全体と目を合わせるように視線を送りましょう。これによって、心からのメッセージであることが聞き手に伝わります。
原稿を見ながらであっても、つねに聞き手に語りかけるような話し方を意識してください。そのためにも、事前に何度か練習して、原稿を見るタイミングと視線を上げるタイミングのバランスを身につけておくとよいでしょう。
Q2. 何を着ていけばいいのかわからない
一般的に、式典は略礼装で臨むのが好ましいとされています。
男性の先生なら黒やネイビー、グレーなど落ち着いた色のスーツを選べば問題ないでしょう。ネクタイはダークカラーやシルバー以外に、上品なライトグレーやライトブルー系などのパステル調もおすすめです。
女性のスーツも同様ですが、淡いグレーやベージュなどの明るい色のスーツや、アンサンブルでもOKです。ジャケットの下には、カッターシャツ以外のボウタイやフリルカラー、襟なしのブラウスなどを着る先生もいます。ジャケットを羽織れば正装になりますので、ワンピースでもよいでしょう。ジャケットは、素材・デザインにフォーマル感があれば襟なしでも構いません。
ただ、学校によっては、独自のドレスコードを設けているケースもあるかもしれません。気になる場合は、勤続年数の長い先生に確認しましょう。そして、服装で一番大切なのは清潔感です。しわや汚れがないか確認し、気持ちを込めて身だしなみを整えましょう。
Q3. 時間配分の目安はありますか?
離任式での挨拶の理想的な時間は、基本的には3分程度です。この時間内であれば、聞き手の集中力が続きますし、伝えたい内容を簡潔に伝えられます。導入から始まり、本題で印象的なエピソードや感謝の言葉を述べて、最後に未来へ向けたメッセージで締めくくる構成であれば、3分という時間でも十分に心のこもった挨拶ができるでしょう。
ただし、この時間はあくまでも一般的な目安です。実際の状況によっても適切な長さは変わってきます。とくに考慮すべき点としては、以下のような状況があります。
🟨離任者の人数🟩
一度に多くの教職員が離任する場合は、一人あたりの時間を短くする必要があります。たとえば10人以上の職員が離任するような大規模校では、3分ずつ話していくと合計30分になり、聞く人が飽きてしまい、気持ちが伝わりづらくなってしまう可能性があります。このような場合は、一人あたり1〜2分程度に短縮することも事前に相談しておきましょう。
🟨学校の伝統や慣例🟩
各学校には、独自の慣行がある場合があります。前年度の離任式の様子や、学校側から時間の指定がないかなど、事前に必ず確認しておきましょう。
🟨対象となる児童・生徒の年齢🟩
たとえば低学年の児童が相手の場合は、挨拶を短く簡潔にしたほうが集中して話を聞いてもらえ、伝えたいメッセージが伝わりやすくなります。このように、聞き手の年齢層によって、効果的な話す時間や話し方を考慮し変えたほうが良い場合もあります。
🟨立場や在籍期間🟩
学校での役職や在籍期間によっても、適切な時間は変わってくるでしょう。長年勤務した先生と、1年間だけ勤務した先生では、伝えたい内容の量が違って当然です。実際の時間配分については、離任する教職員同士で事前に相談し、全体のバランスを考慮することをおすすめします。
場にふさわしい装いや適切な時間配分で、感謝の気持ちがより伝わりやすくなるでしょう。
「離任式の挨拶」で想いを届けよう
離任式の挨拶は、これまで日々を共にしてきた人たちへの感謝を伝え、思い出を共有し、未来へのエールを送る、大切な機会です。限られた時間の中で、聞く人の心に残るメッセージを届けるためには、「感謝」「思い出」「未来へのエール」という構成を意識しましょう。事前に原稿を準備し、練習を重ねることで、本番での緊張も軽減できます。
当日は、声のトーンや大きさ、抑揚に気を配り、児童・生徒たちとアイコンタクトをとりながら話すことで、より相手の心に響く挨拶になるでしょう。離任式が、お互いの新たな一歩を祝福し合う場、思い出に残る時間となることを願っています。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。