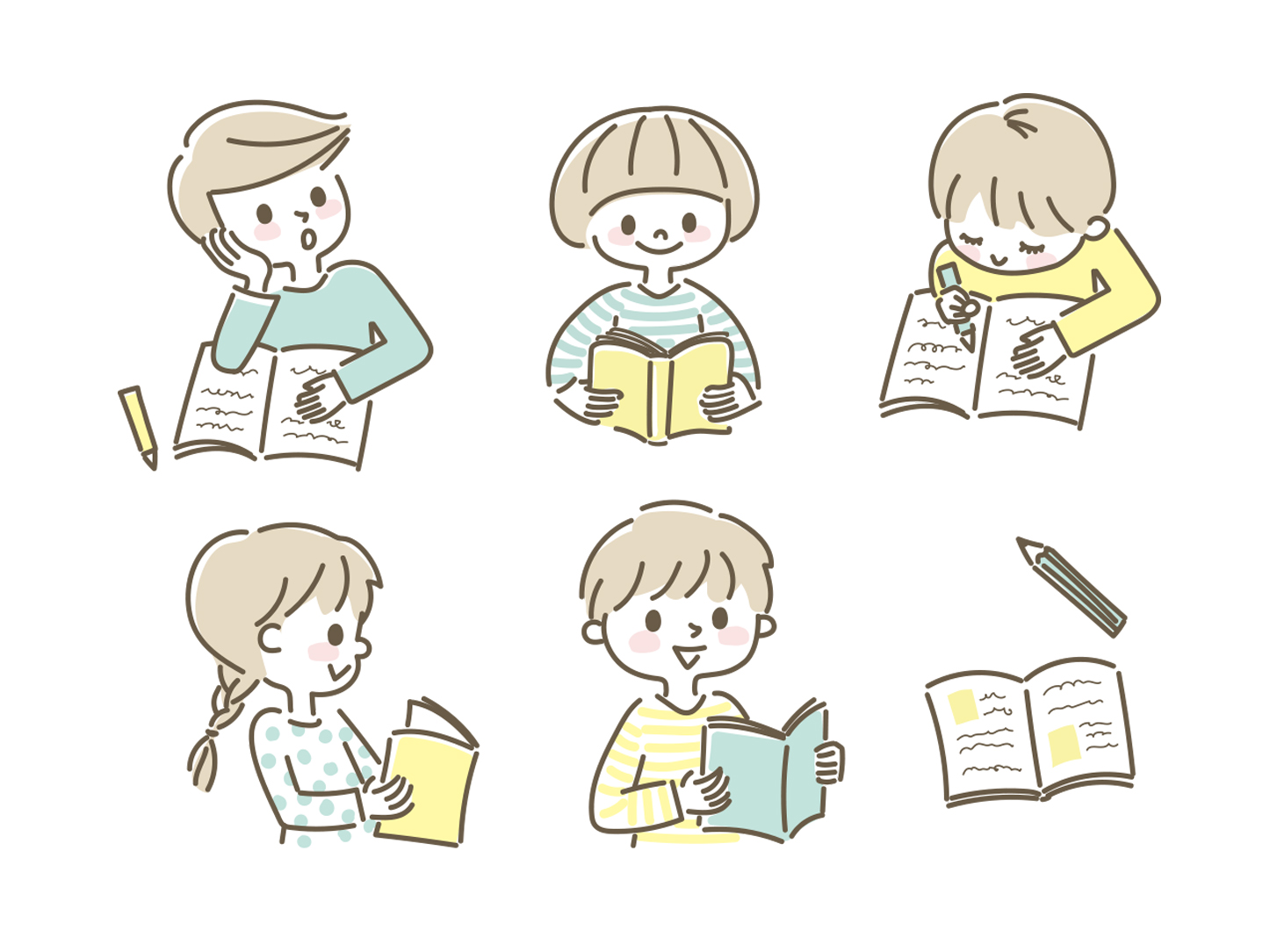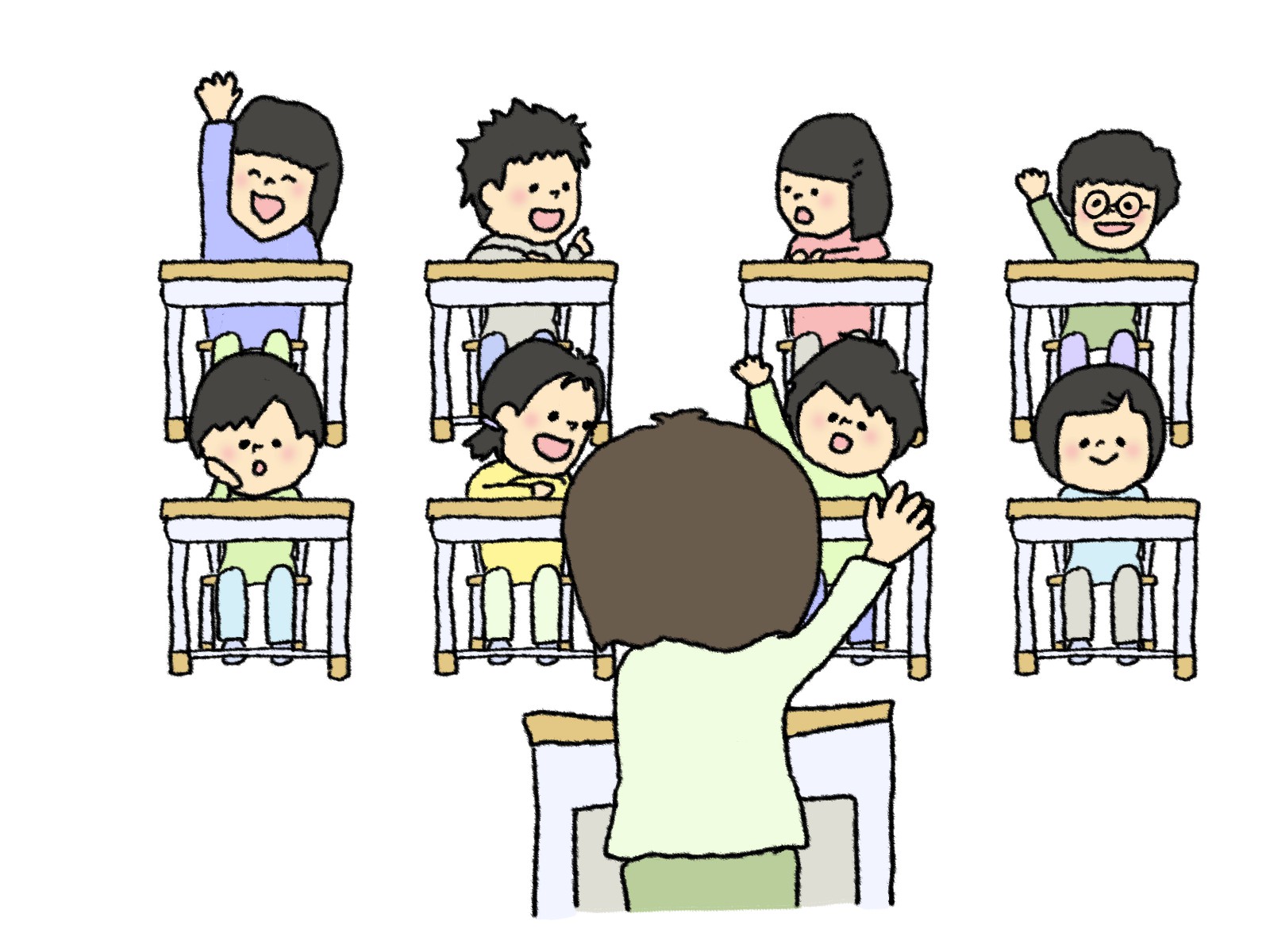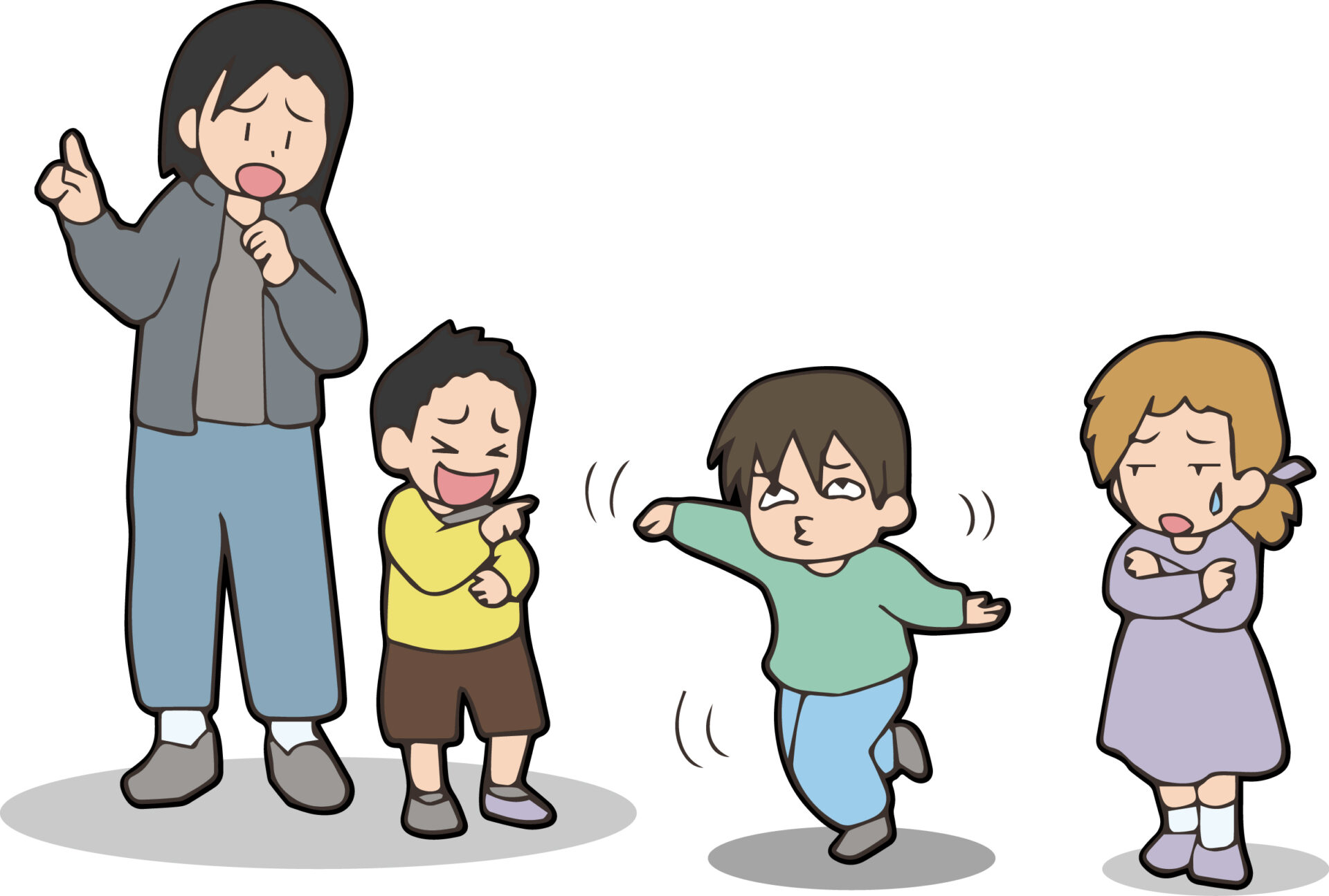
目次
「学級崩壊は何が原因で起こるの?」
「クラスがどんな状態になったら、学級崩壊にあたるのだろう?」
「学級崩壊が起きてしまったら、どんな対処法をとったらいいの?」
このように、学級崩壊の原因は何なのか、どう対応したらよいのかとお悩みの先生もいらっしゃることでしょう。
学級崩壊とは、学級全体の秩序が失われ、通常の授業や学級活動の実施が困難な状態を指します。学級崩壊の原因は一つではなく、さまざまな要因が複合的に絡み合って発生する場合がほとんどです。
この記事では、学級崩壊の原因や予防法、実際に起きてしまったときの対処法について解説します。学級崩壊の原因や有効な対処法を知り、学級崩壊が起こらないよう備えていきましょう。
学級崩壊とは?
学級崩壊とは、学級全体の秩序が失われ、学級がうまく機能しない状況のことです。
文部科学省によると「子どもたちが教室内で勝手な行動をして教師の指導に従わず、授業が成立しないなど、集団教育という学校の機能が成立しない学級の状態が一定期間継続し、学級担任による通常の手法では問題解決ができない状態に立ち至っている場合」と定義されています。
つまり、児童・生徒が教師の指導に従わず、授業や学級活動を行うことが困難な状態が一定期間続いている場合には、学級崩壊と言えるでしょう。
出典:文部科学省『学級経営の充実に関する調査研究』(中間まとめ)の概要(https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/25/1222198_014.pdf)
学級崩壊と言われる状態の具体例
学級崩壊と言われる状態の具体的な例は、以下の通りです。
- 授業中、多くの児童・生徒が勝手な行動をとり、教師の指示に従わない
- 学級内で暴力行為や暴言が頻発する
- 特定の児童・生徒がいじめの対象となり、クラス全体が不安定になる
- 教師の言葉かけや指導が、まったく響かなくなる
学級崩壊が起きると、児童・生徒が教師の指導に従わないため授業が成立しない、児童・生徒の暴力行為や暴言などで教室に落ち着きがない、などの混乱状態に陥ります。
学級崩壊が起こるのはなぜ?
学級崩壊が起きる原因はさまざまです。学級崩壊は、一つの原因で起きるわけではなく、いくつかの要因が複雑に絡み合って発生する場合がほとんどです。
ここでは、学級崩壊を招く原因について詳しく解説していきます。
児童・生徒側の原因
児童・生徒の中には、他人と向き合えなかったり、親の前でだけいい子に振る舞ったりするなど、社会性が未熟でコミュニケーション能力が不足している子どもも見受けられます。
また、自己肯定感が低く自分に自信がもてないことから、子どもが自暴自棄になったり他の人への暴力行為に結びついたりするケースもあります。
その背景には、核家族化が一般化した社会での共働き家庭やひとり親家庭の増加、近所付き合いの減少、インターネットが普及しSNSが発達したことによるリアルの人間関係の希薄化などがあります。周囲の大人との関わりが減ったことにより、家庭内で必要なしつけを受けられなかったり、十分な愛情を受けられなかったりすることがあり、その結果、子どもに問題行動が見られるようになることがあります。
教師側の原因
教師側の指導力や経験不足が、学級崩壊の一因になる場合もあります。授業の進め方、指示の出し方、問題行動への対処方法など、学級経営全般における指導力不足によるものです。
教師としての経験が浅いために適切な接し方ができなかったり、子どもの実態に合わせずに自身の指導法を押し通してしまったりすることで起きやすくなります。
また、教師に過度のストレスがかかり疲労が蓄積することで、学級崩壊の兆候となる生徒の変化や問題行動を見逃し、対応が遅れてしまう場合も少なくありません。実際に学級崩壊が起きてしまうと、そのことがストレスになり、さらに追い詰められてしまいます。
学校・社会環境の原因
学校全体で校内の問題に対応するための連携・協力体制が確立されていないと、学級担任の孤立化が起きやすく、学級崩壊につながる問題の早期発見や適切な対応を妨げる原因になってしまいます。このような状況では、学級だけでなく学校全体の規律も乱れやすいので、生徒への悪影響は避けられません。
また、社会の価値観の多様化により個人の考え方や価値観が尊重されるようになったのは良いことですが、その半面、以下のような集団生活の中で重んじるべき価値観を確立・共有しにくいという新たな課題が生じています。
- 他の生徒の発言や意見に耳を傾ける
- 自分と異なる考えを持つ人に対しても敬意を払う
- 共有スペースや教材を大切に扱い、次に使う人のことを考える
- 自分の行動が周囲にどのような影響を与えるかを考慮する
このような価値観が共有されないまま集団生活を送るようになると、教師の指示に従わない子や、自分勝手な行動に出る子が出てきてしまうと考えられます。
学級崩壊は、さまざまな要因が複雑に絡み合って起こる場合がほとんどです。
学級崩壊を予防するための取り組み
学級崩壊が起こってからクラスを立て直すのは、とても困難をともなうため、学級崩壊の要因になりそうな状況は事前に改善しましょう。ここでは、学級崩壊を予防するために日頃からできる取り組みについて解説します。
学習環境の整備と過ごしやすい雰囲気づくり
学級崩壊を防ぐためには、まず学習環境を整えることが大切です。
皆で使う共有物は置く位置を固定し、時間割や行事予定表などの掲示物も掲示場所を一か所にまとめ、使いやすく、情報がわかりやすい教室空間を目指しましょう。また、机やロッカーの中を定期的に整えるなど、整理整頓された清潔な教室づくりに努めましょう。
これにより、「自分だけでなく他の人への思いやり」や「共同体のルールを尊重する意識」を育み、結果として学級の規律を守る土台となります。
さらに、皆が過ごしやすい学校生活を送るためのルールを明確にしましょう。
ルールを決める際には、その理由や意義、なぜルールを守ることが大切なのかも丁寧に説明し、学校生活が周囲への配慮・思いやりの上に成り立つものだということを再確認する機会にします。
ルールは、明確・シンプルな表現で分かりやすく、子どもたちが納得できるものであること、そして教師自身もルールに反するような行動をせず、一貫した指導を行うことが大切です。
児童・生徒への理解を深めるコミュニケーション
教師には、日常的な関わりを通して、児童・生徒の悩みや不満の有無に気づく観察力や洞察力が求められます。
より深く状況を理解するために、必要に応じて個人面談を行うのもよいでしょう。そして、児童・生徒の話を聞くときには、「傾聴」の姿勢も大切です。否定的な言葉で応じず、気持ちに寄り添いつつ客観的に事実を捉え、適切な声かけやアドバイスで信頼関係を築くように努めます。
また、教師が児童・生徒の話にきちんと耳を傾けることは、子どもたちがお互いの良さを認め合い、自分の意見を言い合える、過ごしやすいクラスの雰囲気づくりの基本です。一人ひとりの個性の違いや失敗にもポジティブな言葉かけを行い、日頃から児童・生徒が安心して生活できる基盤をつくりましょう。
なお、学校で問題行動を起こす児童・生徒の中には、家庭環境などに問題を抱えている場合もあります。子どもたちの言動の背景にも目を向けて、問題の早期発見・対応に努めましょう。
保護者との信頼関係を築く
保護者との信頼関係を構築していくことも、学級崩壊を防ぐためには大切です。
子どもの成長や課題について、普段から保護者と連絡帳などを通してやりとりしたり、学級通信の定期的な発行でクラスの様子を共有したりしましょう。また、学級の経営方針や子どもたちの詳しい状況については、保護者会などで改めて丁寧に説明するなど、理解を得るための機会を設けるようにします。
このように、保護者とはつねに児童・生徒の成長について情報を共有し、問題の芽が見つかったときには早い段階で相談できる基盤を整えておくとよいでしょう。
教師自身の自己管理
学級崩壊を起こさないためには、教師自身の自己研鑽や自己管理も必要です。
教師は、児童・生徒、保護者など、多くの人たちの感情に触れる機会が多い仕事です。また、仕事の特性から、努力に対して期待しただけの達成感などが得られなかったときに、燃え尽きた感覚(バーンアウト)におちいってしまいがちです。
自分でも気づかないうちに疲労やストレスを溜め込んで、突然キャパオーバーしないように、自分自身をなおざりにせず、心身のヘルスケアに気を配りましょう。
また、子どもたちが授業の内容や方法に不満をもっていると、学級崩壊の引き金になりかねません。児童・生徒の実態に合わせた分かりやすい授業を行えているか、実際の反応を見ながら確認してください。指導法の改善・工夫を繰り返し、児童・生徒の満足度の高い授業にできるように努めましょう。
学級崩壊を防ぐためにも、日頃から学習環境を整えて、児童・生徒の理解に努めましょう。
学級崩壊への対処案
学級崩壊が起きてしまった場合には、学級担任だけでなく、学校全体で教員同士が連携し、根気よく取り組む必要があります。学級担任、学年主任をはじめとし、校長など学校管理職や、関係職員、スクールカウンセラーなどの専門家も交えてケース会議を開き、早急に具体的な支援計画を策定します。また、必要に応じて保護者に協力をあおぐことも視野に入れましょう。
ここでは、主な原因ごとに対応策を解説していきます。
児童・生徒への対応
問題行動の根底にある児童・生徒の心情を理解する
学級崩壊は、児童・生徒が抱える不満や問題行動への対応の遅れが原因で、起こる場合があります。
問題を抱える児童・生徒の学級での行動だけに焦点を当てず、その背景にも目を向けましょう。児童・生徒の声に丁寧に耳を傾けて、どんな感情を抱えているのかを共感的に受けとめます。
担任と児童生徒が1対1できちんと向き合う時間をつくるのも大切です。定期的な個別面談を実施し、お互いに認め合える関係を再構築していきましょう。必要に応じてスクールカウンセラーとの連携も視野に入れて心理的な支援を行いましょう。
また、保護者に子どもの様子を知らせて、どのような対応をするか共有し、家庭での協力を依頼するのもおすすめです。
個々の児童・生徒に応じた具体的な支援計画
学級崩壊の予防や事態の改善のためには、一人ひとりの児童・生徒の性質や課題を的確に把握したうえで、個別の支援計画を立てることが必要です。特に、学習面で困難を抱える児童・生徒、コミュニケーションに課題がある児童・生徒、情緒の安定に配慮が必要な児童・生徒などには、その特性に合わせた具体的な支援方法を考え、実践していきましょう。
また、すべての児童・生徒がクラスの一員として「必要とされている」と感じられるよう、一人ひとりの資質を活かした役割を与えましょう。
たとえば、絵が得意な子には掲示物の作成や配布物のイラストの担当を、計算が得意な子には行事の際の買い物や会計係を、植物が好きな子には学級園の管理係を任せるなど、それぞれの得意分野や興味・関心に合った役割を務めてもらいます。役割を通して自分を活かせる機会を得ること、周囲からの肯定的な反応があることは、児童・生徒にとって自信や自己肯定感につながります。
なお、学級活動への参加が困難な児童・生徒には、初めから他の子と足並みを揃えることを求めず、段階的なアプローチをすることが大切です。得意な内容だけ学級全体の活動に参加するなど、部分的な参加から始めることも効果的です。主体的に活動できる場面をつくりながら、無理のないペースで徐々に学級の一員として活動に参加できるようになるための支援をしていきましょう。
教職員や学校の運営体制
教職員の負担や能力を考慮した組織的な運営体制の見直し
教員の指導力不足や経験不足が学級崩壊の主な原因となっている場合は、管理職に速やかに報告し、児童・生徒の支援体制を確立していきましょう。
このような場合にはとくに、チーム・ティーチングなどによる指導体制の整備が必要となります。どのような点が学級崩壊につながったのかを意識しながら、これまでの授業方法を見直し、児童生徒にとって分かりやすく、興味・関心をもって参加できる授業を行えるように、柔軟な視点で改善していきましょう。
そして学年主任や生徒指導主事らとも協力し、抱えている業務量の見直し、業務の優先順位を整理するなど、一人の教師に過度な負担がかかりすぎないように調整をはかります。教職員同士が助け合って指導していく学校運営を目指し、一部の教員に負担が偏らないような組織的配慮を行いましょう。
教職員のメンタルヘルスケア
学級崩壊が起きる要因として、担任の教師が一人で問題を抱え込み疲弊している場合があります。
個人がメンタル面で追い込まれるのを防ぐために、メンタルヘルスケアの一環としても、チームで学級崩壊の問題に向き合う基盤づくりは急務です。ストレスマネジメント研修の実施など、日頃から職務上必要な知識として、誰もがストレスへの対処方法を知っておくことが大切です。
それでも学級崩壊が発生してしまった後は、担任の教師には特別な対処が必要になることも多いです。当事者は自責感や無力感を抱きやすく、精神的ダメージが深刻なケースも少なくありません。このような状況では事態を軽視せず、周りからも以下のような対応を促してください。
1.専門家によるカウンセリングの活用
学校カウンセラーや外部の臨床心理士など、専門家による個別カウンセリングを受けましょう。教師が安心して感情を吐露できる場を確保することで、心理的負担の軽減につながります。重度のストレス反応が見られる場合は、さらに専門医への受診も検討してください。
2.業務量の調整と休養の確保
学級崩壊への対応はエネルギーが必要なため、学校全体の問題として、担当教師の校務を一時的に軽減し、他の教員に割り振るなどの対応を検討しましょう。また、精神的ダメージが深刻な場合は、長期休養が必要になるケースもあります。本人は適正な判断が出来ない可能性もあるため、必要に応じて特別休暇の取得を促すなど、回復のための学校側の配慮も大切です。
学校・地域との協働
学校内外での支援体制の確立
ここまで繰り返し述べてきたように、学級崩壊に対しては、学校全体で組織的に取り組むことが大切です。さらに、教職員が指導方針を共有し学年・学校内で統一された指導を行うだけでなく、問題をオープンにして外部の知恵・サポートを求めることも時には必要となります。
たとえば、教育委員会との連携を強化し、解決に向けた対応策を協議することで、学校内だけでは進展のなかった問題解決の糸口が見つかる場合があります。さらには、児童・生徒のメンタルヘルスケアの一環として、地域のボランティアの活用を検討してみるのもよいかもしれません。
また、保護者との協力も欠かせません。日頃、一人ひとりの子どもたちに誰よりも密に向き合っているのは保護者です。保護者会を開催し、クラスでの子どもたちの現状や対応策を共有・協議しながら、教職員と保護者全員で協力して解決に努めましょう。
専門機関との連携
学校だけでは対応しきれない場合、より良い解決に向けた的確で具体的な方針・対応策を見出すためには、躊躇せずに専門機関との連携を行うことも必要です。とくに学級崩壊の現場で深刻ないじめや暴力行為が行われている場合は、警察への相談や児童相談所との連携を行いましょう。
状況に応じて外部の専門家と連携しつつ、一日も早い事態の改善・終息に努めましょう。
学級崩壊といっても、ケースごとに効果的な対応は異なります。原因を見極め、必要に応じて学校外にも協力を依頼しましょう。
学級崩壊の原因を知り、最適な対応ができるようにしておこう
学級崩壊とは、学級全体の秩序が失われ、通常の授業や学級活動が困難になった状態です。学級崩壊が起こる原因は一つではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合って起こります。
学級崩壊を防ぐには、普段から学習環境を整備し、児童・生徒の言動の底にある心情の理解に努めることが大切です。また、保護者や他の教員とも情報を共有して信頼関係を構築しておくことや、教師自身の指導力を高める努力を積み重ねていくことも必要でしょう。
もし学級崩壊が起きてしまったときには、自分を責めたり一人で抱え込んだりせず、すぐに周囲に相談し学校や地域全体で問題に向き合うことが大切です。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。