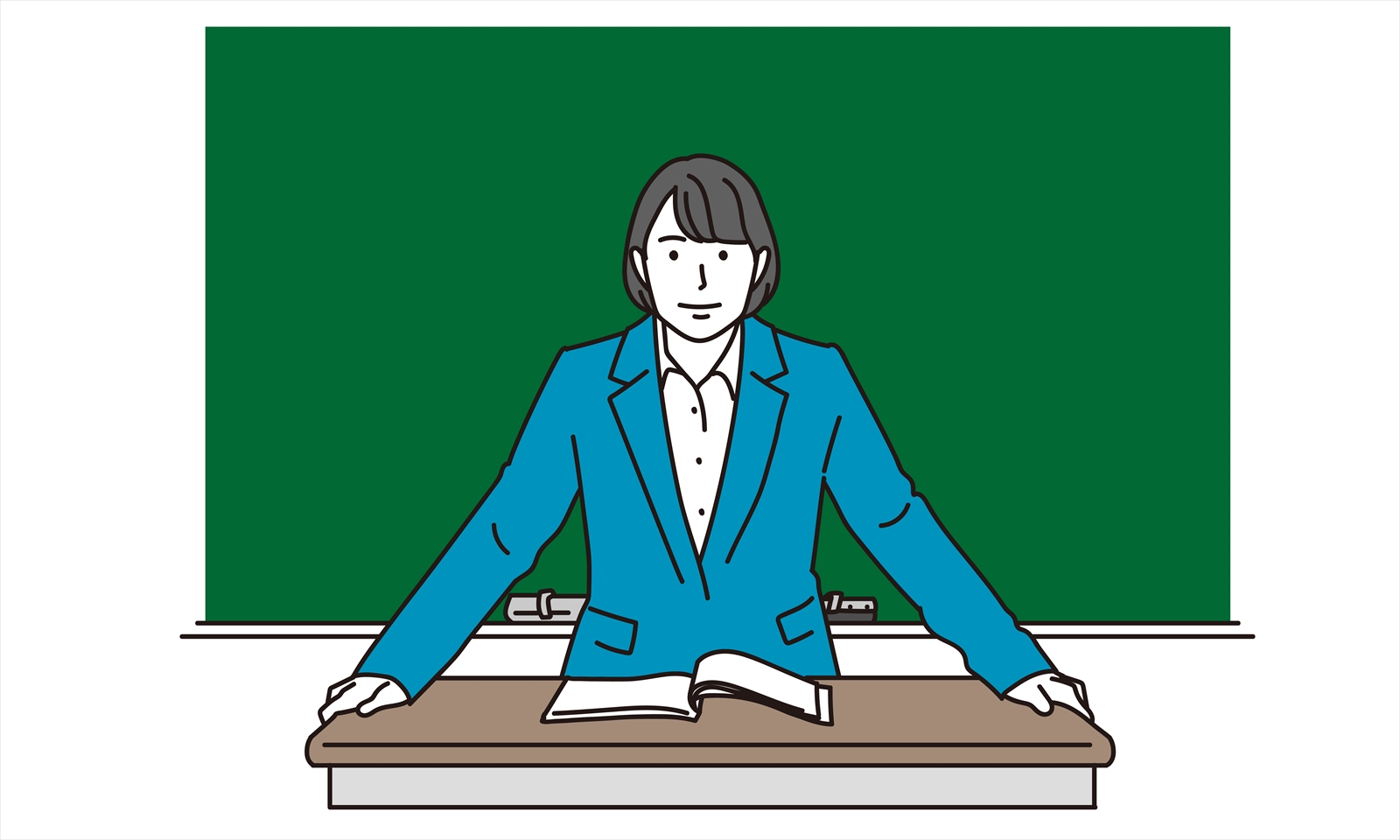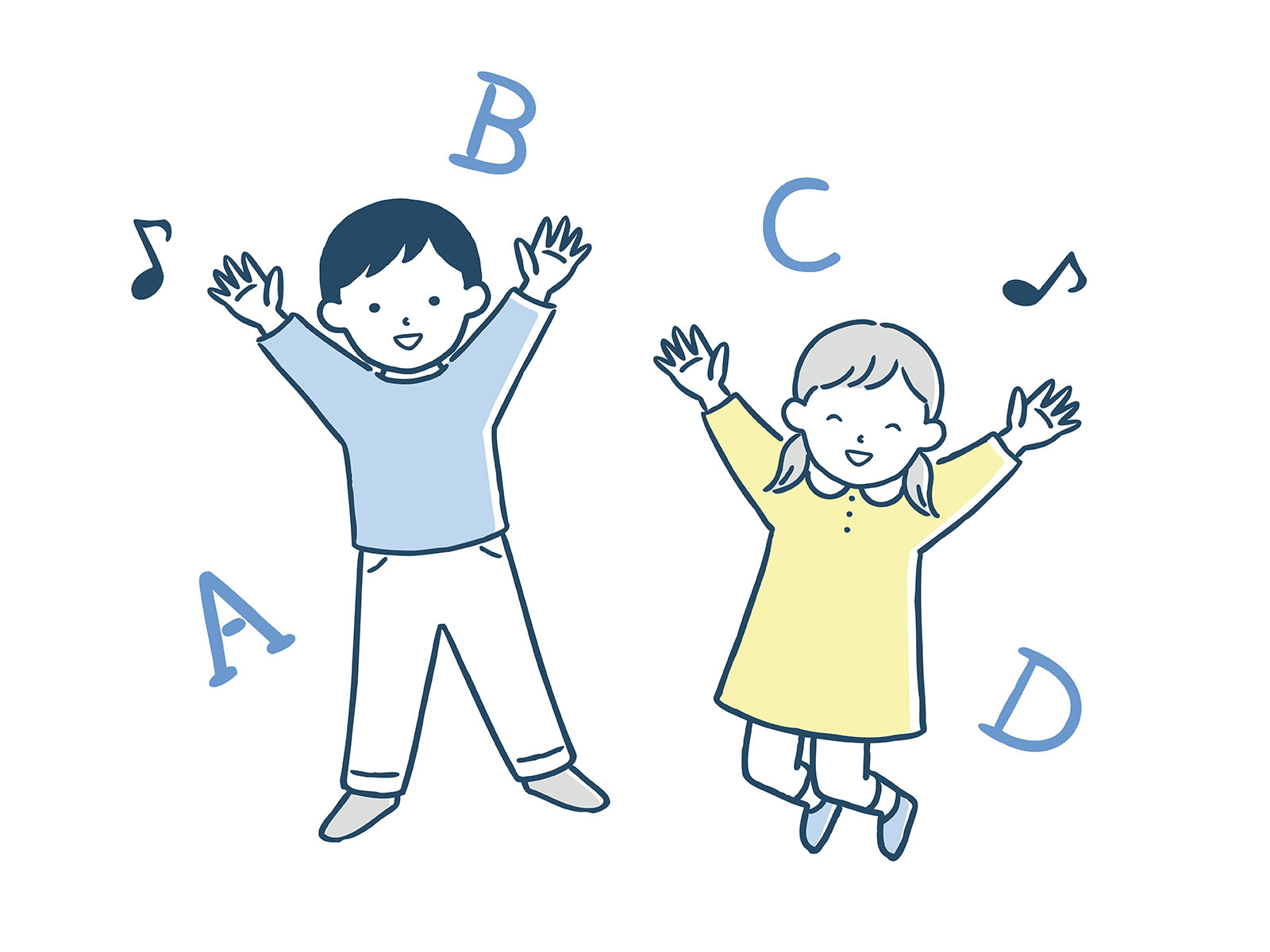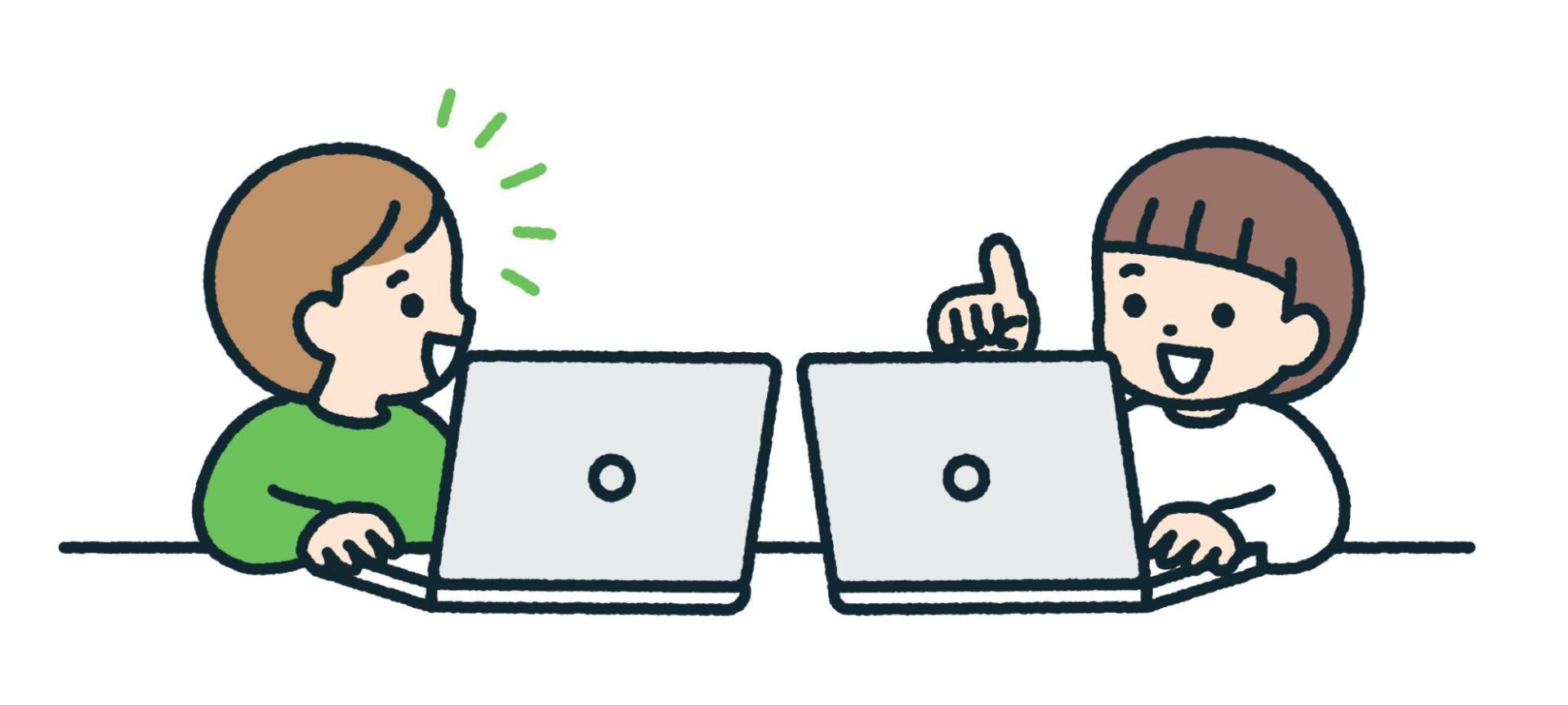
目次
「調べ学習を授業で取り入れたいけれど、どう進めればいいのか分からない」
「児童が興味を持てるようなテーマ設定が、うまくいかない」
「子どもたちが活動の仕方で迷わないように、もっと適切なサポートをしたい」
こんなふうに感じている先生も、多いのではないでしょうか。
調べ学習は、小学生の主体的に学ぶ力を育てる大切な学習活動のひとつです。だからこそ、子どもたちが安心して取り組み、学びを深められるような、教師の関わり方が重要になります。
そこで、この記事では小学生の調べ学習について、基本的な進め方や効果的なテーマの決め方、情報収集やまとめ方のコツを丁寧に解説していきます。
子どもたちの学びを深める調べ学習について、一緒に考えていきましょう。
教師が知っておきたい「調べ学習で育つ力」
調べ学習とは、子どもたちが提示されたテーマや課題に対して疑問をもち、自ら情報を集めて整理し、自分の言葉でまとめて発表するまでの一連の学習活動を指します。
この活動を通して、子どもたちのこれからの学びを支え、将来につながる、以下のような重要な力が育っていきます。
- 情報活用力(必要な情報を見つけ、整理して、目的や状況に合わせて適切に使う力)
- 問題解決能力(問題の原因や課題を分析・整理し、解決に向けて自ら考え行動できる力)
- 主体性・探究心・実践力(自ら問いをもち、考察や理解により学びを深め、活用につなげようとする力)
- 論理的思考力(物事を筋道立てて考え、結論を導き出せる力)
- 表現力(伝えたい情報や自分の意見や考えを、わかりやすく表現して伝える力)
これらは、単元や教科を越えて活かされる「学びの基盤」となります。調べ学習の指導では、活動の結果だけでなく、このような力の育成をめざす学習なのだと意識することが大切です。
調べ学習を行うときは、学習活動を通じて「どんな力を育てたいのか」を意識した指導をしていきましょう。
自ら問いを立てて主体的に学ぶ力を育む「探究学習」については、こちらの記事が参考になります。
探究学習とは?基本とテーマの決め方|授業の進め方とポイント
調べ学習の基本的な進め方
ここでは、小学生の調べ学習を進める際の、基本的な5つのステップを紹介します。授業の流れをイメージしながら、どの場面でどんなサポートが必要なのかをつかんでいきましょう。
STEP1. 課題・テーマの設定
調べ学習では、教員がテーマを設定します。その際に大切なのは、子どもたちが興味や関心をもてるテーマにすることです。
授業中に出た疑問や、日常生活の中で子どもたちに生じた「なぜ?」からテーマを見つけると、主体的な学びにつながります。
STEP2. 予想・仮説を立てる
テーマが決まったら、それぞれ自分の予想や仮説を立てます。子どもたちが知っていることや授業で学んだ内容をもとに、「きっとこうだ」「もしかすると、こうかも?」と自分で考える力を引き出しましょう。
仮説は1つだけに絞らず、多角的な視点で考えられるよう、グループワークで意見を出し合うのも効果的です。このステップを丁寧に行うことで、次の「何を、どう調べるか」が明確になり、情報収集の質が高まります。
STEP3. 情報収集
次に、予想や仮説をもとに、必要な情報を調べ、集めていきます。
このとき大切なのは、1つの情報源に頼らず、複数の資料・情報ソースを活用することです。図鑑や本、インターネット、インタビューなど、さまざまな手段を使って情報収集できるようにしましょう。そうすることで、情報を見極める力も育ちます。誰がいつ書いた情報なのか、明確な根拠はあるかなど、信頼できる情報かどうかという視点で判断するようサポートすると、必要な情報を選ぶ力が身についていきます。
そして、メモをとるときは要点を簡潔に、後で見て分かりやすいようキーワードを中心に書いていくことをアドバイスするとよいでしょう。
STEP4. 整理・まとめ
集めた情報は、そのまま書き写すのではなく、自分なりに整理してまとめていくことが大切です。
情報を内容ごとに分類したり、複数の情報の共通点や違いを見つけたりしながら、自分が伝えたいことをまとめやすく整理できるようサポートしていきましょう。整理した情報は、表や図を使ってまとめると、視覚的にも分かりやすくなります。
「調べて分かったこと」だけでなく、「学習を通じて気づいたこと」や「自分の考え」も盛り込むことを大事にできると、その子らしいまとめ方につながります。
STEP5. 発表・ふり返り
最後は、まとめた内容をクラス皆の前で発表することで、学びを広げていきましょう。
模造紙やスライドなど、発表の方法を自分たちで選べると、表現の幅が広がります。 発表を聴く側には、事前に配った質問カードや感想カードに思ったことを書いてもらうといった工夫をするのもおすすめです。全体で学び合う雰囲気が生まれやすくなり、発表した児童の学習へのモチベーションにもつながります。
発表後には、必ず「振り返りの時間」を取りましょう。楽しかったこと、難しかったこと、次に調べてみたいことなどをていねいに振り返ることで、次の学びに活かせます。
調べ学習の課題・テーマ|決め方の工夫と例
調べ学習をスムーズに進めるためには、最初のテーマ設定がとても大切です。
ここでは、児童の「知りたい!」という気持ちを引き出すテーマの決め方と、小学生におすすめのテーマ例をご紹介します。
児童の「知りたい」を引き出すテーマの決め方
テーマを決めるときは、子ども自身が「もっと知りたい」と感じられる内容なら、学びへの意欲が高まりやすくなります。日頃から、授業中のちょっとした疑問や、日常生活の中での「なぜ?」をメモしておくなど、子どもたちの声を拾い上げてテーマにつなげてみましょう。
テーマは、「自動車について」というような広いテーマだと、範囲が広すぎて調べにくくなってしまいます。「自動車の作り方」「自動車の種類」「未来の自動車」など、ある程度内容を絞ったほうがよいでしょう。
また「~について調べよう」よりも「○○って、どうなっているの?」というように、テーマを問いの形にすると、探究心が刺激されやすくなります。
子どもたちの日々のちょっとしたつぶやきや関心ごとに耳を傾けながら、調べたくなるテーマを見つけていきましょう。
小学生におすすめのテーマ例
ここでは、より具体的にテーマの例を紹介していきます。
子どもたちが教科学習や生活の中で抱いた疑問の中から、自分と身近な関わりがあると思えるテーマを選ぶことがポイントです。
- 各都道府県の名産品や、地域に根づいたイベント(社会科)
例:「自分の県には、どんな名産品がある?」「自分の県には、どんなお祭りがある?」 - 日本とアメリカの学校の違い(外国語活動)
例:「アメリカの給食はどんなメニュー?」「教室のつくりは、日本と違うの?」 - 食品ロスを減らすためにできること(給食の時間)
例:「日頃から食事の食べ残しを減らすためには、どんな工夫ができる?」
このように、身近にある問題や日々の暮らしとつながるテーマにすることで、子どもたちが自分のこととして調べやすくなります。
テーマ選びのポイントは、「自分のこと」として考えられるかどうかです。子どもたちが「知りたい」と思えるテーマを、身近なところから探しましょう。
調べ学習で使える情報収集の方法と注意点
調べ学習では、どのように情報を集めるかが、学びの質を大きく左右します。
ここでは、小学生におすすめの情報収集の方法と、特に活用機会の多いインターネットを使う際の注意点についてご紹介します。
小学生におすすめの情報収集の方法
小学生の調べ学習では、次のような方法を組み合わせて情報を集めるとよいでしょう。
- インターネット
- 百科事典・図鑑
- 図書室や図書館の本
- インタビュー(家族や地域の人など)
ひとつの情報源だけに頼ると、視点がかたよりやすくなります。いくつかの方法を組み合わせて多角的に調べ、情報の有効性や真偽を見極める力を育てていきましょう。
インターネットによる情報収集の注意点
学校では1人1台のタブレットが整備され、インターネットで調べものをする機会が増えてきています。インターネットは便利ですが、情報の信頼性を見極めることが重要です。
たとえば、情報検索の際、その分野の専門家が発信している情報や、公的な機関のホームページなどを中心に、確かな情報を探すよう促しましょう。また「誰が書いたものなのか」「いつの情報か」といった視点も一緒に確認していきましょう。
情報の信頼性を見極める方法は丁寧に指導しましょう。文章や図などを引用する場合は、どのサイトや資料を使ったのかを記録しておくことも大切です。
児童が表現しやすくなるまとめ方
調べたことを自分の言葉でまとめ、分かりやすく伝えることは、調べ学習の大切なゴールの1つです。
ここでは、児童が自分らしく表現するための「まとめ方の種類」と、「型を提示しながら自由にまとめる工夫」についてご紹介します。
まとめ方の種類と使い分け
調べた内容をまとめる方法は、児童の学年や個人差、テーマや取り組み方の実態に合わせて、取り組みやすいよう選ぶことが大切です。
ここでは、代表的なまとめ方を4つご紹介します。
ポスター・模造紙
大きな紙に調べた内容をまとめる方法です。文字だけでなく、写真やイラストを配置しながら整理できるので、発表のときにも伝わりやすくなります。グループで協力してまとめるのに適しているのも、ポスターや模造紙の大きな特長です。
ただし、物理的にスペースに限りがあるため、載せる情報はよく選ぶ必要があります。「何を伝えたいか」を整理しながらまとめていくと、見やすく分かりやすい発表資料になるでしょう。
ノート
自分のノートに、調べた内容をまとめる方法です。ノートは、手軽に書き込めて、自分のペースで考えながら自由に書けるのが特長です。特に、ひとりでじっくり整理したい子にとっては、取り組みやすいスタイルといえます。
ただしノートは小さいので、発表の際には他の子が見やすくなる工夫が必要です。たとえばノートをスクリーンに映したり、模造紙やスライドに発表用としてまとめ直したりするといった方法が考えられます。まとめの方法と合わせて発表方法にも目を向け、まとめ方を選びましょう。
スライド(PowerPointやGoogleスライド)
タブレットを使ってまとめる方法です。スライドは、文字だけでなく、写真やイラスト、動画なども入れてまとめられるため、表現の幅がぐっと広がります。発表資料としても見やすく、プレゼンテーションに適した形式です。
一方で、ツールの操作に慣れていない児童にとっては、作成に時間がかかることもあります。最初は、スライドの基本的な使い方を確認しながら進めることも必要です。
新聞形式
新聞のように、見出しと本文、写真や図などで構成するまとめ方です。情報を文章で整理しながら表現するので、文章力が育ちます。
ただし、情報の整理や構成の仕方にやや難しさがあるため、中学年の場合は個別の支援が必要になることもあります。見出しの立て方や段落の組み立て方など、あらかじめ簡単な見本を示しておくと、安心して取り組みやすくなるでしょう。
自由なまとめ方ができる「型」の提示
まとめ方を自由に選べるようにすると、自分らしい表現につながり、児童の主体性も引き出しやすくなります。しかし「自由にまとめていいよ」と言われると、かえってどうすればいいか分からず、手が止まってしまう子もいます。
そんなときは、まとめ方の「型」を提示するのがおすすめです。たとえば、「はじめ(テーマに対する予想や仮説)→なか(調べ方・調べて分かったこと)→おわり(自分の考えや感想)」という三部構成で型を作ると、一連の流れが整理され、この形に沿ってまとめやすくなります。
まとめの中身が引用ばかりにならないよう、自分の考えを述べるように指導しましょう。
調べ学習を成功させるには?主体性を引き出すコツ
調べ学習では「自分で調べて、自分の言葉でまとめる」という経験を通して、子どもたちの「主体的に学ぶ力」を育むことができます。子どもたちの主体性を高めるためには、先生がすぐに答えを教えるのではなく、子ども自身の「気づき」を促す関わり方が大切です。
たとえば、模造紙を使ってまとめているときに、文字ばかりになっている児童がいたら、「見やすいまとめにするには、どんな工夫ができるかな?」と問いかけてみましょう。一緒に離れた所から模造紙を眺めてみると、「ここに絵や図があるといいかも!」と、子ども自身が気づくことがあります。
また、情報収集の場面では、「これは、どういう意味だろうね?」「他の資料にも同じことが書いてあるかな?」などと声をかけることで、さらに深く広く調べてみようという意欲や興味が引き出されます。
児童の内側から生まれる小さな気づきや疑問を大切にしながら、自発的な学びを後押しするような関わり方を心がけていきましょう。
教師の問いかけひとつで、子どもたちに新たな視点が生まれ、主体性が高まるきっかけになります。
調べ学習を通じて児童の「学ぶ意欲」を引き出そう
調べ学習は、子どもたちが自らテーマに興味をもち、主体的に学びを深めていくことを促す学習活動です。一人ひとりの「知りたい」という気持ちを大切にしながら授業を進めていくことで、子どもたちが学ぶことの楽しさを実感するきっかけになります。
先生はすべてを教えようとするのではなく、子どもが自ら問いをもち、自分の力で調べ、考える姿を見守ることを心がけましょう。必要なときにさりげなくサポートできることが大切です。
完璧なまとめや立派な発表を目指すよりも、「このテーマについて、もっと知りたい!」という気持ちが育つことが、何よりの成果です。「学ぶって楽しい」と感じられる時間を、調べ学習を通して子どもたちに届けていきましょう。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。