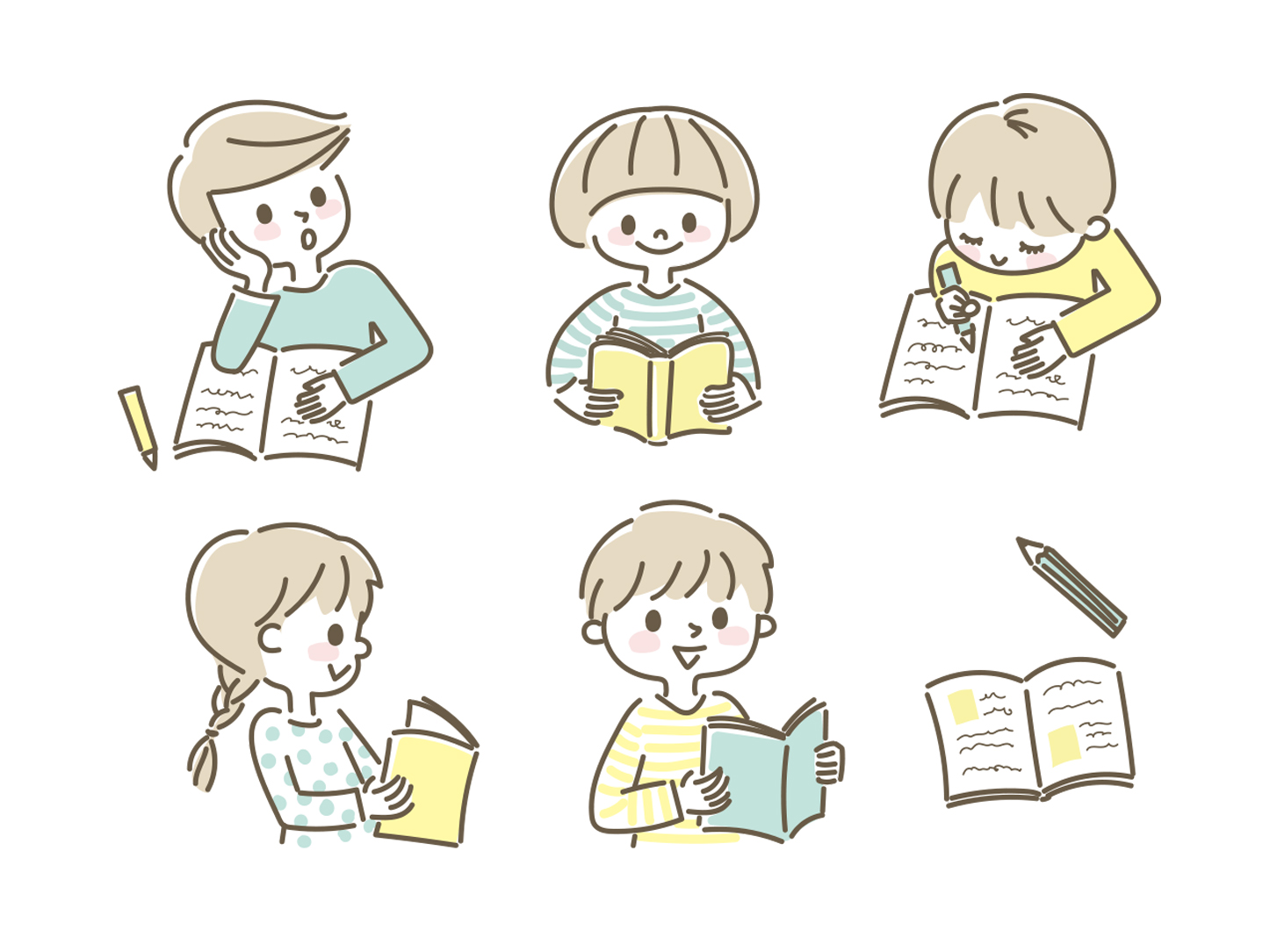目次
「通知表の所見は、どのように書けばいいの?」
「所見を書くときに気をつけるポイントが知りたい」
このような悩みを抱える先生も多いのではないでしょうか。
通知表の所見は、保護者に子どもの学校生活の様子を伝える手段であり、子どもの成長を記録する役割もあります。また、所見をていねいに書くことで、保護者との信頼が深まり、今後の指導や支援にも活かせます。
この記事では、通知表の所見の書き方・学年別の文例・効率的に充実した所見を書くコツを解説します。所見の書き方に不安がある先生や、所見をスムーズに書けるようになりたい先生は、ぜひ最後までお読みください。
通知表の所見は何のために書くの?
通知表の所見は、子どもの学校生活での取り組みや成長の様子を保護者に伝えるための重要なメッセージです。また、次年度以降の指導につながる資料としても活用できます。
ここでは「通知表の所見を何のために書くのか?」について、3つの視点から解説します。
保護者と子ども自身に「がんばり」や「成長」を伝えるため
通知表の所見は、子どもの努力や成長の様子を、保護者と子ども自身に伝えるために書きます。先生の視点で言葉にすると、学校での小さな変化や行動を、正確に保護者に伝えることができます。
▼例
- 音読が苦手だった子どもが、毎朝の練習を重ねて大きな声でスラスラと読めるようになった。
- 自主学習ノートに毎日まじめに取り組み、学習内容の振り返りができるようになってきた。
このように通知表の所見は、子どもの努力と成果を保護者に伝え、子どもの成長を実感してもらうことができます。さらに子ども自身にも、がんばりを認識していること、評価していることを先生の言葉で伝えて、自信をつけさせるための大切な手段です。
保護者と教育上の連携を深めるため
通知表の所見は、子どもの成長を学校と家庭の両方で支えていくための、大切な連携のきっかけになります。授業中の取り組みや日常生活での変化を保護者へ具体的に伝えると、家庭でも声かけやサポートがしやすくなります。
▼保護者との支援連携につながる内容の例
- 集中力が続きにくい子どもに、時間を設定して学習に取り組ませると効果があった。
- 持ち物チェックカードで忘れ物が減り、毎朝の準備がスムーズになった。
所見により、担任の目を通して子どもの様子を具体的に伝えると、保護者との連携が深まり、家庭での支援に役立ちます。
次年度の指導や支援に活かすため
通知表の所見は、次年度担任する先生が子どもの様子を知るための大事な資料にもなります。これまでの成長の様子や、効果のあった支援方法などを記録しておくと、学年が変わっても、その子に合った支援内容をスムーズに引き継ぐことができるでしょう。
▼次年度への引き継ぎに効果的な支援内容の例
- 言葉だけでは学習内容の理解が難しい場面もあったが、図解を取り入れることで内容をつかみやすくなり、定着につながった。
- 自分の気持ちを言葉にするのが苦手な子だったが、「メッセージカード」の活用により、思いや考えを少しずつ表現できるようになってきた。
このように、その子に合った関わり方を残しておくことで、新しい担任にも有効な支援方法がわかります。
通知表の所見は、児童のがんばりや成長を伝えるだけでなく、保護者との信頼関係の構築や次年度の支援につなげる役割もあります。
通知表の所見を書くために必要な準備
通知表の所見を具体的な内容にするためには、日々の児童の観察記録や成長の変化のまとめなど、事前の準備が必要です。ここでは、所見を書く上での柱となる準備を、3つに分けて紹介します。
観察記録や日常の出来事、変化をメモしておく
日常の観察で得た児童の情報を、その都度記録しておくと、所見作成時に具体的なエピソードが書きやすくなります。クラス全員の日々の行動や変化の詳細を、記録せずに後から思い出すのは難しいため、以下のように一人ずつの記録を残しておきましょう。
▼観察記録の例
| 学習面 | ・国語の音読のときに、はっきりとした声でスムーズに、自信をもって読めるようになった。 ・漢字の書き取りテストの正解率が高くなった。 |
| 生活面 | ・持ち物チェックリストの効果で、忘れ物が少なくなった。 ・いつも教室の隅までていねいに掃き掃除をしている。 |
| 人間関係 | ・グループ活動で友達の意見をよく聞けるようになった。 ・発表の準備に困っている友達に、さりげなく声をかけていた。 |
毎日の出来事で心に留まったことをメモしておく習慣で、子どもの成長を的確に伝える所見が書けます。
評価の観点別にポイントを確認する
通知表の評価観点に沿って児童の情報を整理すると、バランスの良い所見になります。評価の三観点「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」に基づいた視点で、情報の記録を心がけると、学校の評価方針と一致した所見が書けます。
▼評価の観点に合わせた記録の例(2年算数かけ算)
| 知識・技能 | 【9月】かけ算の基本概念を理解できており、かけ算の式の形で数量を表せるようになった。 【10月】同じ数字が繰り返される場合はかけ算を使うことを理解し、効率よく問題に取り組むことができる。 |
| 思考・判断・表現 | 【9月】「どの数が何回くり返されているか」に着眼し、数の「何倍」という考え方を自分なりの言葉で説明ができる。 【10月】問題の意図を理解したうえで適切な式を立て、その根拠・理由を踏まえた具体的な説明ができた。 |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 【9月】日常生活の中で出合う、かけ算で表せる数の事例を積極的に探し出せる。 【10月】たし算やひき算が含まれたかけ算の問題にも意欲的に取り組み、解法を理解できている。 |
このように、整理した記録の内容に具体性があると、より信頼性のある所見になります。
子どもの成長や変化を時系列に沿ってまとめる
新年度スタート時からの成長の様子を時系列に沿って整理して、変化をわかりやすくまとめておきましょう。「子どもの成長」が見える所見は印象に残り、家庭での声かけや支援にも役立つからです。
▼行動の変化の例
| 4月 | 忘れ物が多く、毎日声かけが必要 |
| 5月 | 日々の声をかけの効果が現れ、忘れ物が減り始めた |
| 6月 | 持ち物チェック表で、自主的に確認し始めた |
| 7月 | 毎朝、自分で持ち物チェックをして、忘れ物がほぼなくなった |
このように子どもの成長や良い変化を、所見欄で保護者に伝えられると、通知表の内容が前向きな印象となります。
通知表の所見を書くには、日々の記録と情報整理の習慣づけが大切です。児童の成長や変化は具体的に記録しておきましょう。
通知表の所見の書き方5ステップ
ここでは、通知表の所見の書き方を5つのステップで紹介します。ステップに沿って書き進めると、子どもの成長や努力が伝わる具体的な所見が仕上がりますよ。
STEP1 所見の型を確認する
まずは、学校や学年で決まっている「所見の型」を確認しましょう。
所見の型に沿って書くと、文章がすっきりまとまり、保護者にも内容が伝わりやすくなります。
▼所見の型の例
| ①書き出し(全体の様子) | 子どもの学校生活全般での雰囲気 |
| ②学習面の様子 | 各教科の取り組みの様子 |
| ③生活面の様子 | あいさつや掃除・係活動・人間関係 |
| ④今後の期待 | 今後に向けた目標や期待 |
STEP2 書き出しで学校生活全般の雰囲気を伝える
書き出し部分では、子どもの学校生活全般における雰囲気や取り組みの姿勢を、簡潔にまとめましょう。「学校ではどんな子なのか」が保護者に伝わるように、印象と様子を具体的に書きます。
▼書き出しの例
- 友達との関わりを大切にしながら、いつも穏やかな様子で学校生活を送っています。
- クラスの中心的な存在として友達をまとめながら、さまざまな活動に積極的に取り組んでいます。
書き出し部分では特に、子どものよさや成長が伝わるような「前向きな表現」にするのがポイントです。
STEP3 学習の様子を書く
次に、教科での取り組みや成長の様子を書きましょう。すべての教科ではなく、特にがんばりや成長が見られた教科・場面に焦点を当てて書くようにします。
小学校高学年では教科担任制が導入されている学校も多いですが、その場合は、所見を書く際に各教科の先生方とも連携をとりながら、児童の学習面での努力や変化を具体的に書きましょう。
▼学習の様子の例
- 音楽の授業では、リコーダーの練習に意欲的に取り組み、息の出し方や音のつなぎ方を工夫して、上手に演奏していました。
- 国語の「意見文を書く」の授業では、グループで話し合いながら意見を整理し、自信を持って発表する姿が見られました。
学習の様子では、どの教科に、どんな努力や成長、才能が見られたのかを、教科担任と情報共有しながら具体的に書くのがポイントです。
STEP4 生活面での様子を書く
生活面では、学級活動や係活動、人間関係など、学校生活での様子を書きましょう。行動の変化や人間関係での成長が伝わると、保護者にも安心感を与えられます。
▼生活面の様子の例
- 図書委員の当番活動に責任を持って取り組み、本を借りに来た友達にも落ち着いてやさしく接する姿に、高学年らしい成長が感じられました。
- 特に給食当番では、配膳の順番や量に気を配りながら手際良く進め、「これくらいで大丈夫?」とやさしく声をかけるなど、安心して任せられる頼もしい存在でした。
日々の言動や周囲との関わりの中で見せる様子を、具体的に書くのがポイントです。
STEP5 これからの目標や期待を書く
所見の最後には、今後に向けた期待や、教師から見た次の目標を書きましょう。文章の最後に励ましを込めた表現をすると、所見が前向きに締まります。
▼今後の期待の例
- これまでに身につけた整理整頓の習慣をこれからも続け、クラスの中で、ますます周りによい影響を与えられる存在になることを期待しています。
- 自分で学習計画を立てて取り組む姿勢が身についてきているので、宿題や予習復習だけでなく、自主的に進める力をさらに伸ばしてほしいです。
これまでの成長を認めながら、これからの伸びしろを前向きに伝えるのがポイントです。
5つのステップに沿って具体的に書くと、子どもの様子・状況が明瞭に伝わり、温かみのある所見に仕上がります。
小学校の通知表の所見【学年別文例集】
小学校1~6年生の通知表の所見文例を、学年別にまとめました。所見作成の参考にしてください。
小学校1年生の文例
| 書き出し | 入学して間もない頃は、初めてのことばかりで緊張している様子もありましたが、今では笑顔で過ごす時間が増え、安心した様子で学校生活を送れるようになってきました。 |
| 学習面 | ひらがなの練習では、「ね」や「ぬ」など難しい文字の形を何度も書き直しながら、ていねいに書こうとする姿が見られました。 |
| 生活面 | 登校後は、ランドセルを自分で素早く片付け、時間を確認しながら必要な学習用具を準備する姿が見られます。帰りの支度の際も、机の周りを整えるなど、落ち着いて行動できるようになってきました。 |
| 今後の期待 | これからも「自分でできた!」という前向きな体験を積み重ねながら、日々の生活を送ってほしいと願っています。 |
小学校2年生の文例
| 書き出し | 毎日の授業に落ち着いて取り組み、わからないことがあれば自分から質問するなど、前向きに学ぼうとする姿が見られます。 |
| 学習面 | 九九の暗唱に取り組む際には、友達と交代で出題し合い、「7×8は?」などと声をかけ合って、楽しみながら練習する姿が見られました。 |
| 生活面 | 友達に鉛筆を貸してもらったときに「ありがとう」と伝える、自分が順番を間違えたときには「ごめんね」と素直に謝るなど、気持ちを言葉でしっかり伝えられている姿が見られました。 |
| 今後の期待 | これからも、人の話をしっかり聞ける面を大事にしながら、自分の思い、望みや問いも落ち着いて伝えていけるようになりましょう。 |
小学校3年生の文例
| 書き出し | 新しい教科や学習内容にも積極的に取り組み、わからないことは進んで質問するなど、自分から学ぼうとする姿が見られます。 |
| 学習面 | 理科の授業では、モンシロチョウの成長の様子を観察する中で、「どうしてこんなふうになるの?」と疑問を持ち、図鑑で詳しく調べる姿が見られました。 |
| 生活面 | 給食当番では、配膳の準備を時間を見ながら手際よく行い、友達にも「これくらいでいい?」と声をかける姿が見られました。 |
| 今後の期待 | 今後も、日々の学習や係の活動などを通して、持ち前の探求心を活かし、さらに自分で考えて行動する力を伸ばせるよう願っています。 |
小学校4年生の文例
| 書き出し | 高学年に向けて、自分で時間を見ながら行動したり、目標を立てて努力したりする姿が増えてきました。 |
| 学習面 | 算数の授業では、折れ線グラフの学習で「どの時点で大きく変化しているか」などに注目しながら、グラフを読み取り、自分の言葉で説明できていました。 |
| 生活面 | グループ活動の話し合いの中で、相手の意見にはうなずきながらしっかり耳を傾け、「ぼくはこう思うな」と自分の考えを整理し、落ち着いて伝える姿が見られました。 |
| 今後の期待 | これからも、自分の意見を大切にしながら、コミュニケーション力を活かし、友達と協力して活動に取り組んでいけることを期待しています。 |
小学校5年生の文例
| 書き出し | 日々の学習や活動に意欲を持って取り組み、「やってみよう」というチャレンジ精神がしっかりと育っています。 |
| 学習面 | 音楽の「茶色のこびん」のリコーダー演奏では、音のつながりや強弱を意識しながら、集中して繰り返し練習する姿が見られました。 |
| 生活面 | 放送委員会では、声の大きさや話す速度を意識してアナウンスするなど、聞き手に伝わりやすい工夫をする姿が見られました。 |
| 今後の期待 | これからも学習や委員会活動を通して、自分で考えて工夫・努力ができる才能をさらに伸ばしながら、高学年として周囲を引っ張っていける存在へと成長していってほしいと願っています。 |
小学校6年生の文例
| 書き出し | 最高学年としてリーダーの自覚を持って、学校やクラスの行事、委員会活動などにも責任を持って取り組んでいます。 |
| 学習面 | 図工では「未来のわたし」をテーマにした作品づくりで、構想の段階からスケッチに時間をかけ、細部までこだわって表現する姿が見られました。 |
| 生活面 | 掃除活動では、砂ぼこりのたまりやすい場所にも気づき、自分から雑巾を取りに行ってきれいにするなど、自主的に動ける姿が見られました。 |
| 今後の期待 | 卒業後も、自分の感性やアイデアを表現し形にする力や、人のために行動しようとする姿勢を大切にしながら、新しい環境でも前向きに歩んでいってほしいと願っています。 |
通知表の所見を書く際の注意点
通知表の所見は、保護者にとってわかりやすく、子どもの成長が前向きに伝わるように書くことが大切です。ここでは、所見を書く際に気をつけたい4つのポイントについて紹介します。
ネガティブではなくポジティブな視点で書く
通知表の所見は、子どもの成長や努力を前向きに伝えられるよう、改善の様子や良くなってきた点に着目しましょう。
たとえば、「忘れ物が多かった」というネガティブな表現ではなく、「自分で持ち物を確認する習慣が身についてきた」などのポジティブな表現にする、といった感じです。
ポジティブな言葉選びや表現の工夫を心がけてみてください。
抽象的ではなく具体的な内容を書く
通知表の所見を書く際は、「どの教科を」「どんな場面で」「どのようにがんばっていたのか」という点を具体的に書きましょう。
たとえば、「算数の文章題では、登場人物の動きを図に整理して、自分の考えをノートに書き出しながら答えにたどり着こうとする姿が見られました。」というように、取り組みの様子が伝わる表現が効果的です。
学習面・生活面の両方をバランス良く書く
通知表の所見では、学習面と生活面の両方について、バランス良く書くことが大切です。どちらか一方にかたよると、学校生活全体での子どもの成長が十分に保護者に伝わらない可能性があるからです。
▼バランスのとれた記述の例
| 学習面 | 算数では「割合」の単元で、図や表を使って考えを整理しながら、問題の意味を的確にとらえようと工夫する姿が見られました。 |
| 生活面 | 掃除の時間には、自分の担当場所を黙々と掃除し、誰よりも早く準備や片付けを行うなど、責任感ある行動が印象的でした。 |
教科学習と日常生活の両面から、多角的に具体的な成長の様子を伝えましょう。
保護者と子どもが理解しやすい言葉で書く
通知表の所見は保護者だけでなく、子ども自身にも向けたメッセージです。専門的な用語や難しい表現はできるだけ使わないようにしましょう。
▼専門用語と伝わりやすい表現の比較
| 専門用語を用いた表現 | 伝わりやすい表現 |
| コミュニケーションを通じて多様な視点を取り入れながら、思考を深め、自身の見解を伝えることができています。 | いろいろな考えを聞きながら、自分の考えを持ち、意見を伝えられるようになりました。 |
| 他者と協働して活動に取り組んでいます。 | 友達と協力して、いっしょに活動を進めています。 |
上記のポイントを意識して所見を書くと、子どもの成長がより伝わりやすく、保護者との信頼関係を強めることにもつながります。
効率的に充実した所見を書くコツ
通知表の所見の締切で慌てないためには、日頃の準備と作業の進め方がポイントです。ここでは、新任の先生でもスムーズに所見が書けるようになる3つのコツを紹介します。
「メモ」や「記録」を習慣化する
通知表の所見をスムーズに書くためには、子どもたちの様子を日頃から記録しておきましょう。日頃から記録しておくことで、日が経っても子どもの努力や成長の様子を具体的に書けるからです。
▼「メモ」や「記録」の例
| 4月21日 | Aさん | 計算ドリルで間違えた問題を、休み時間に自分で解いていた。 |
| Bさん | 国語の発表で緊張しながらも、自信を持って発言できていた。 | |
| 4月22日 | Aさん | 掃除の時間に、黙々と集中して取り組んでいた。 |
日ごろから「メモ帳」と「ペン」を持って記録することを習慣づけると、所見内容が説得力のあるものになります。
AIやツールを活用する
所見作成には、AI(ChatGPTやGeminiなど)や文章作成支援ツール(PRUVやENNOなど)を活用すると、文章の校正や言い回しの変更・修正ができます。
▼AIやツールの活用例
- 誤字脱字のチェックをする
- 伝わりやすい文章の案を出してもらい、推敲に役立てる
- 長くなりすぎた文章を読みやすく整える
AIやツールをこのように活用すると、効率的に通知表の所見が作成できます。ただし、名前や学校名などの個人情報の取り扱いには、十分に注意して使用しましょう。
早めに取りかかる
基本的なことではありますが、通知表の所見を書く作業には、早めに取りかかり、時間に余裕を持って進めましょう。特に年度末は忙しい時期なので、締切への焦りから誤字・脱字などのミスをしないよう、適切なスケジュール管理で準備を心がけてください。
▼スケジュールの例
| 日付 | 内容 |
| 2月1日 | 下書き開始(記録の見返し、構成の確認) |
| 2月20日~25日 | 清書&修正(全体の読み返しと推敲、誤字脱字の確認など) |
| 3月1日 | 所見提出(校内締切) |
子どもたちの日頃の様子をメモする習慣や、AI・ツールの活用で作業の質を高め、余裕のあるスケジュールで計画的に作成しましょう。
所見の書き方のポイントを押さえて通知表作成をスムーズに!
この記事では、通知表の所見を書く目的や必要な準備、具体的な書き方、そしてより良い所見を書くうえでの工夫について紹介しました。所見は、子どもの成長を保護者に伝えるための大切な記録であり、次年度の支援にもつながる大事な情報です。
日頃から子どもたちの様子の観察・記録を習慣づけ、評価の観点や学年ごとの特徴を踏まえながら情報を整理しておきましょう。そうした工夫で、執筆の際になって焦ることなく、保護者に伝わりやすい所見に仕上がります。初めは書き方に悩むこともあるでしょうが、ポイントを押さえて、ポジティブで具体的な所見を作成しましょう。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。