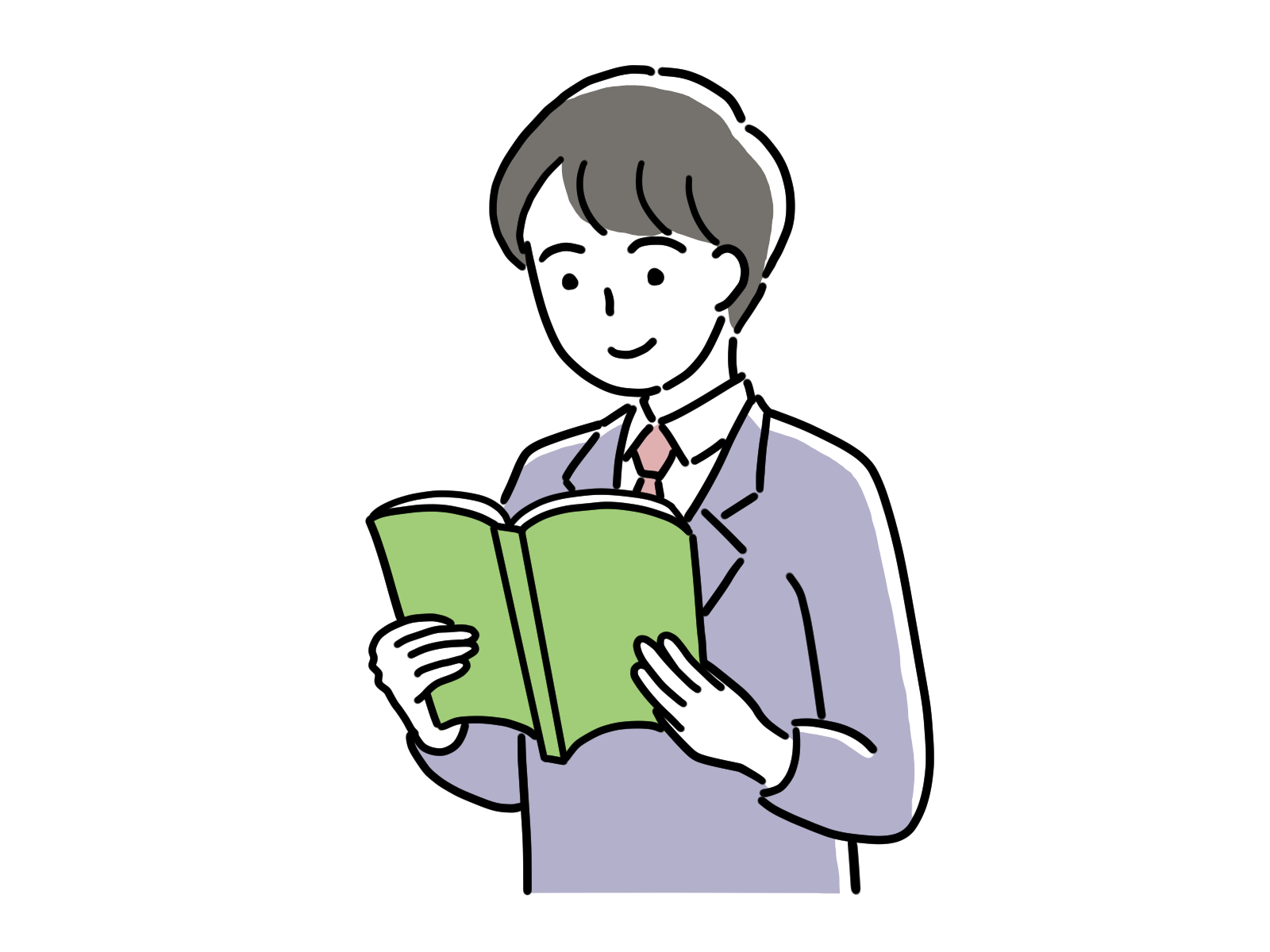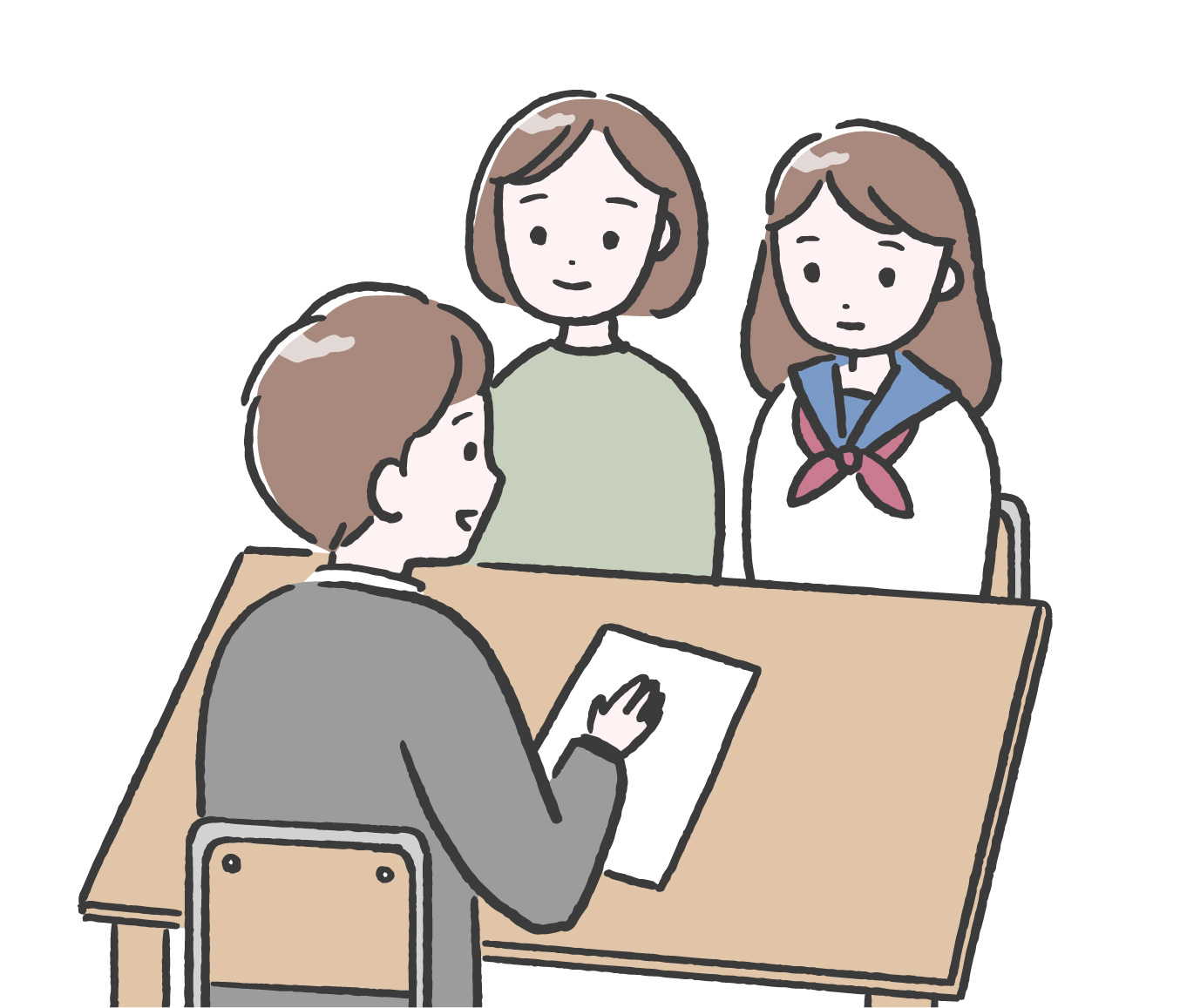
目次
「進路相談のときに、どうアドバイスをすればいいか、いつも迷う」
「生徒の気持ちに寄り添えているのか不安だ」
「保護者との面談では、なにを重視して話せばいいのかわからない」
このような悩みを持つ先生は、多いのではないでしょうか。
中学生を教える先生方にとっても、進路相談は生徒たちの将来を左右する重要なイベントです。生徒の顔を思い浮かべては、真摯に頭を悩ます方も多いと思います。限られた相談時間の中で、生徒にどのようなサポートができるでしょうか。
今回は(高校)進学についての進路相談に注目し、進路相談をより効果的なものにするためのコツ、注意点をご紹介していきます。
進路相談の目的とは?
進路相談は、単に卒業後の生徒の進学先・身の振り方を決めるだけの場ではありません。生徒の、この先の人生の方向性を一緒に考える大切な機会です。まずは、進路相談をなぜ行うのか、その主な目的をあらためて一緒に考えてみましょう。
生徒の自己理解と将来設計をサポートする
義務教育である小中学校と違い、中学卒業と同時に、生徒たちは自分で人生の進路を選択していかなければなりません。けれど、自分の将来について、まだ漠然としたイメージしか持っていない生徒も多いものです。考え出すと不安や迷いが生じることも多いでしょう。
生徒との面談では、「休日の過ごし方」「夢中になれる活動」「学校生活で感じるやりがい」などの具体的な質問を通して、生徒の興味や価値観を引き出していきましょう。また、生徒が語る経験や想いに対して、「その活動は、将来につながるかもしれないね」「そういう考え方は△△の分野で活かせそうだね」といった形で、大人の視点から可能性を提示することも効果的です。自己理解を深めることが、生徒のよりよい進路選択につながっていきます。
対話の中で、一人ひとりの気づきのペースに合わせて気持ちに寄り添い、その子らしい将来設計ができるよう後押ししていきましょう。
社会について知る機会を提供する
この先の人生に思いを馳せて自分の進路を考えることは、生徒たちにとって、視野が広がり、社会の成り立ちや多種多様な職業について知る機会でもあります。「こんな仕事があるなんて知らなかった!」「この仕事は、こんなふうに社会の役に立っているんだ」「自分の好きなこと、得意なことが、こんな仕事につながるかもしれない」という発見を、生徒たちと一緒に分かち合える機会にしたいものですね。そのために必要な幅広い職業についての最新知識、刻一刻と進展する社会のニーズの動向など、日頃から情報収集を心がけて伝えられるようにしておきましょう。
なお、進路相談だけでなく、授業や課外活動の一環として、生徒たちが社会を生きた形で知ることのできる機会をつくるのもおすすめです。
▼進路指導につながる活動の例
- 地域の特色ある企業(例:伝統工芸品の製作所、ベンチャー企業のオフィス)での職場見学
- さまざまな分野の第一線で活躍する社会人(例:宇宙開発技術者、国際協力NGO職員、地域活性化に取り組む起業家)を招いての講演会
- 生徒自身による業界研究プロジェクト(例:SDGsの観点から各業界の取り組みを調査)
- 卒業生との交流会(例:様々な進路を選択した先輩の経験談を聞く)
子どもたちが広い社会や新たな価値観・視点に触れて視野を広げることは、将来の可能性を広げることにもつながります。
学習意欲の向上につなげる
進路相談は、「なんのために勉強をするの?」という生徒たちの疑問に一緒に向き合い、答えを見つけるチャンスでもあります。将来の夢の方向性や、具体的な目標が見えてくると、今の学習の積み重ねが「自分の未来に、どうつながっていくのか」を感じとれるようになるものです。
たとえば「看護師になりたい」という生徒には、理科や数学、国語の学習が将来どう仕事に生きるのかを伝えるなど、日々の学習と将来の夢をつなぐサポートをしていきましょう。
進路相談は、生徒の人生の可能性を広げる大切な機会です。目前の進学先の決定だけでなく、その子らしい未来への道筋づくりが一緒にできたらいいですね。
【中学生を教える先生向け】進路相談のポイント
進路相談の際には、生徒一人ひとりの性格や状況、悩みの内容などにより、対応方法を十分考慮する必要があります。先生が対応のポイントを押さえることで、生徒たちは自信を持って、将来を見据えた進路選択ができるようになるでしょう。たとえば、以下のような配慮を行ってみてください。
生徒の状況に寄り添い、個別性あるサポートを心がける
生徒の数だけ、状況も抱える悩みの質も、思い描く夢も、実に様々で一つとして同じものはありません。だからこそ、指導法に最適解、定型化した最善のアプローチ法は無いと考えましょう。類型化することなく、一人ひとりの生徒個人と向き合い、その子の可能性や資質が活きる先導、後押しを心がけてください。
とはいえ、どう寄り添えばいいのか悩むこともあるでしょう。まずは、「聴く力」を意識してみてください。自分がなにをどう話すかを考える前に、生徒の話にじっくりと耳を傾けてみましょう。中には自分の思いや考えを言葉で表現するのが苦手な子、悩みを伝えることに躊躇する子もいるでしょうが、辛抱強く、真摯に言葉を待ちましょう。また、言葉にしがたい思いもあるはずですので、表情の動きや仕草、態度からも、生徒の気持ちを読み取ってみてください。
全員が後悔のない進路を選択できるよう、親身なサポートをしていきたいですね。
適切な情報共有を行う
進路選択で大切なのは、生徒、保護者との正確でタイムリーな情報共有です。たとえば、以下のような重要性の高い実務的な情報は、必ず正確に伝えましょう。
- 入試制度の変更点
- 各高校の選抜方法や受験科目
- 願書の提出期限
- 調査書の記載内容など
これらの情報は、進路指導部で確認・整理し、学年団で共有した上で、生徒と保護者に伝えていくことが望ましいでしょう。
特に重要な情報は、学級担任から生徒に直接伝えるとともに、進路だよりやプリントで保護者にも確実に届くようにします。また、保護者会では、入試の全体的な流れや各高校について説明する機会を設けましょう。
進路選択に必要な基本情報を踏まえ、進路相談では生徒の成績状況や志望校の選択について、具体的なデータを示しながら話し合えるよう準備しておくことが大切です。
保護者と連携する
進路選択は、生徒と保護者が一体となって取り組む重要な課題です。特に中学生の場合、進学に関する最終的な判断や責任、経済的な面も含めて保護者の役割は大きく、まさに親子で乗り越えていく人生の重要な節目といえます。保護者と信頼しあえる良好な関係を築き、生徒の未来を一緒に考えていきましょう。
ここでは、三者面談を効果的に進めるためのポイントをご紹介します。
▼事前準備
・生徒の学習状況、成績推移、模試結果などのデータを整理する
・志望校の情報(偏差値、学費、通学時間など)を収集する
・生徒との事前面談で希望進路の確認と不安点の把握する
▼面談の進め方
・まず生徒の現状と頑張りを具体的に説明し、保護者の安心感につなげる
・志望校検討では、第一志望校と併願校の組み合わせを提示する
・家庭学習の方法や学習計画について、アドバイスを行う
・経済的な面も考慮し、奨学金制度などの情報も適宜提供する
▼フォローアップ
・面談後の生徒の変化を観察し、必要に応じて個別フォローする
・次回の面談までの目標設定と確認方法を明確にする
・保護者との連絡手段(電話、メール等)の確保する
先生は生徒と保護者の橋渡し役として、両者の思いに寄り添いながら、具体的な道筋を示していくことが大切です。不安や迷いが生じやすい時期だからこそ、きめ細かなサポートを心がけましょう。
保護者との連携を大切にしながら、一人ひとりの生徒に向き合い、個別性のある丁寧なサポートを心がけましょう。
【中学校の先生向け】生徒の悩みに向き合うコツ
中学生の進路に関する悩みは、生徒の性格や状況によりさまざまです。そのため、個々の生徒への対応には、細心の注意と深い理解が必要です。以下では、生徒の悩みを受け止めつつ、個別性に配慮した効果的なサポートをするためのコツをご紹介します。
生徒の話を傾聴し、相談しやすい味方になろう
中学生の進路に関する悩みには、発達段階特有の特徴があります。たとえば、「成績が伸び悩んでいるが、志望校をあきらめたくない」「部活を続けたいが、勉強との両立に自信がない」「私立高校に行きたいが、家庭の経済状況が気になる」など、理想と現実の間で揺れ動く場面もあるでしょう。また「友だちと同じ高校に行きたい」「親や先生の期待に応えなければ」といった、周囲の評価を過度に気にする傾向も中学生ならではの特徴です。
こうした悩みに対しては、まず生徒の気持ちに寄り添い、話を傾聴することを心がけましょう。その上で、「今の成績でも十分チャレンジできる」「部活と勉強の時間の使い方を一緒に考えよう」など、具体的な対応策を示します。客観的な判断材料があることで、安心感を得られることも多いものです。
また、生徒が相談しやすい環境づくりも重要です。日頃から廊下や休み時間での何気ない会話を大切にしたり、定期的な個別面談の機会を設けたりすることで、生徒は自分の悩みを打ち明けやすくなります。進路の悩みは学習面や生活面の課題とも結びつくことも多いため、包括的なサポートを心がけましょう。
悩みの背景を理解しよう
「進路のことで悩んでいます」という言葉の裏には、実はいろいろな思いが隠れているものです。単に志望校をどこにするかでなく、この先の将来に対する漠然とした不安かもしれないし、本人の認識している実力以上の難関校や、本人の希望とは異なる進路に行かせたい「親からの期待」という重圧、ジレンマかもしれません。生徒自身の成績や内面に起因する悩みもあれば、親との関係性や家庭状況といった先生に話しにくい原因のある悩みかもしれません。
先生は、生徒の言葉に耳を傾けつつ、その奥に隠れている本心や、背景にある状況にまで意識を向けることが必要です。時には、日常の会話の中で何気なく質問をしたりして、生徒の悩みの背景にある状況や思いを探ってみましょう。
信頼できる大人として、生徒が安心できるようなアドバイスをしてあげられるのも先生だからこそ。言葉を選び、その場ですぐに解決できる悩みではなくても、状況や心情への理解と、自分は味方でありいつでも力になるということを伝えてあげましょう。
質問の仕方にも気を配ろう
生徒のリアクションは、先生の質問の仕方一つで大きく変わってきます。「最近、どんなことを考えているの?」「今、一番気になっていることは?」といった、「はい」と「いいえ」で答えられない開かれた質問をすることで、生徒は自分の思いを素直に話してくれやすくなります。ときには、全く想定してなかった内容が返ってくることもあり、生徒を理解する上でより多くの情報が得られることになります。
ただ、無理に聞き出すような尋ね方をすると、生徒が圧を感じてしまいます。返答がない場合には、視点を変えて別の話や質問に切り替えるなど、生徒の気持ちを読みながら柔軟な対応をしてください。
また「それは難しいんじゃない?」といった、相手に対して否定的な言葉で返すのは、生徒が心を閉ざしてしまう可能性もあるので避けましょう。「そういう考え方もあるね。他には、どんな可能性があるかな?」というように、まずは生徒の言葉を肯定的に受け止め、前向きな表現を心がけましょう。
進路の具体化に役立つサポート方法を取り入れよう
「進路について具体的に考えたいけれど、自分のやりたいことがわからない」「自分がなにに向いているか、どうやって知ればいいんだろう」などの悩みを持つ生徒は、案外多いものです。いざ自分自身に向き合ってみると、自分のことは知っているようで実はよくわからないという生徒が、多いのではないでしょうか。
お決まりの方法ではありますが、こういった場合には、広く使われている適性検査や性格診断テストなどを活用してみるのも有効です。自分にはなかった客観的な新しい視点から、自分の特性や資質を知ることができるので、診断結果は「コミュニケーション力が高いから、こんな仕事に向いているかも」「やっぱり、いま興味がある分野に進んだらうまくいきそうだ」といった発見やきっかけにつながるかもしれません。
また、社会で活躍している大人の体験談を聞く機会をつくるのもおすすめです。卒業生や、ある分野のプロフェッショナルとして活動する方々の話から伝わってくる、ものの見方や、仕事の現場や社会のリアルな様相は、生徒たちの視界・興味を新たな世界へと広げてくれるでしょう。
大切なのは、生徒自身が「私もやってみたい!」と感じられること。生徒の視野を広げ、選択肢を増やし、初めは小さな一歩でも、そこから着実に前へ進んでいけるようなサポートをしていきたいですね。
大切なのは生徒の話を「傾聴する」こと。言葉の奥にある思いを受け止め、心強い味方になりましょう。
進路相談をするときの注意点
進路相談は、生徒の将来に大きな影響を与えます。だからこそ、教員は慎重に、そして温かい眼差しで生徒に接していきたいものです。ここでは、進路相談を行う際の大切な注意点をご紹介します。
押し付けではなく、導く姿勢を持とう
進路選択の主役は、あくまでも生徒自身です。教員は生徒の選択を支えるサポーターに徹しましょう。
「こっちの方がいいんじゃない?」と誘導するのではなく、「どうして、その進路に興味を持ったの?」「他には、どんな可能性があると思う?」といった問いかけを通じて、生徒本人の考えを引き出していきましょう。
生徒の成長や変化にも、柔軟に対応することが大切です。今の興味や希望は、時間がたつにつれて変わっていく可能性もあります。その場合は、変化を成長と温かく受け止めつつ、他の方向性を一緒に探っていきましょう。
多様な選択肢を提示しよう
人生の道筋は、一つではありません。だからこそ、できるだけ多くの選択肢を生徒に提示したいものです。高校受験一つとっても、普通科、専門学科、総合学科など、それぞれの特色があります。また、より職業に直結した高専(高等専門学校)という道もあります。
さらに高校進学後の進路についても、国内の大学進学だけでなく海外の大学への進学、または専門学校への進学や、就職してから技術系の資格を取るなど、さまざまな可能性があることも伝えていきましょう。
生徒の自主性を信頼して、ゆとりを持って見守ろう
進路の選択は、一朝一夕にはいかないものです。面談時だけでなく、日頃から生徒が十分な時間をかけて、じっくりと自分自身で考えられる環境を整えていきましょう。早い段階から進路について考える機会を設けることで、生徒は自分のペースで、自然に自分の将来を思い描けるようになっていくでしょう。進路の選択は自分探しでもあります。焦らせず、急がせず、ともに一歩ずつでも着実に進んでいく姿勢で、寄り添ってみてください。
また、一度決めた進路でも変更の可能性があることは忘れずに。生徒が成長し、視野が広がっていくにつれて、ものの見方や興味の対象や価値観が変わっていくのは自然なことです。いつそのタイミングが訪れても柔軟に十分なサポートができるよう、日頃からの先生自身の情報収集や、心の余裕も大切になるでしょう。
成長の途上にある生徒たちに、多様な未来への可能性を示し、自主性を信頼して見守りましょう。
親身な進路相談で生徒の未来を支えよう
義務教育を終える中学校卒業というタイミングから、生徒たちには、それまでとは違う人生の選択が始まります。人生の大きな分岐点に立つ生徒たちにとって、先生による進路相談は、自分自身と将来に向き合うための大切な機会です。不安や迷いを抱えつつも前へ進もうとする生徒たちの思いに、丁寧に寄り添う姿勢を大切にしてください。それが、生徒たちにとってなによりの後押しとなります。
生徒に信頼される相談役であるためにも、先生も、変化が常の最新の入試制度や、職業世界の動向と切り離せない社会状況の変化について、絶えず学び続けることが大切です。生徒たちが自信を持って、自らの将来展望を胸に一歩を踏み出せる、そんな進路相談を目指していきましょう。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。