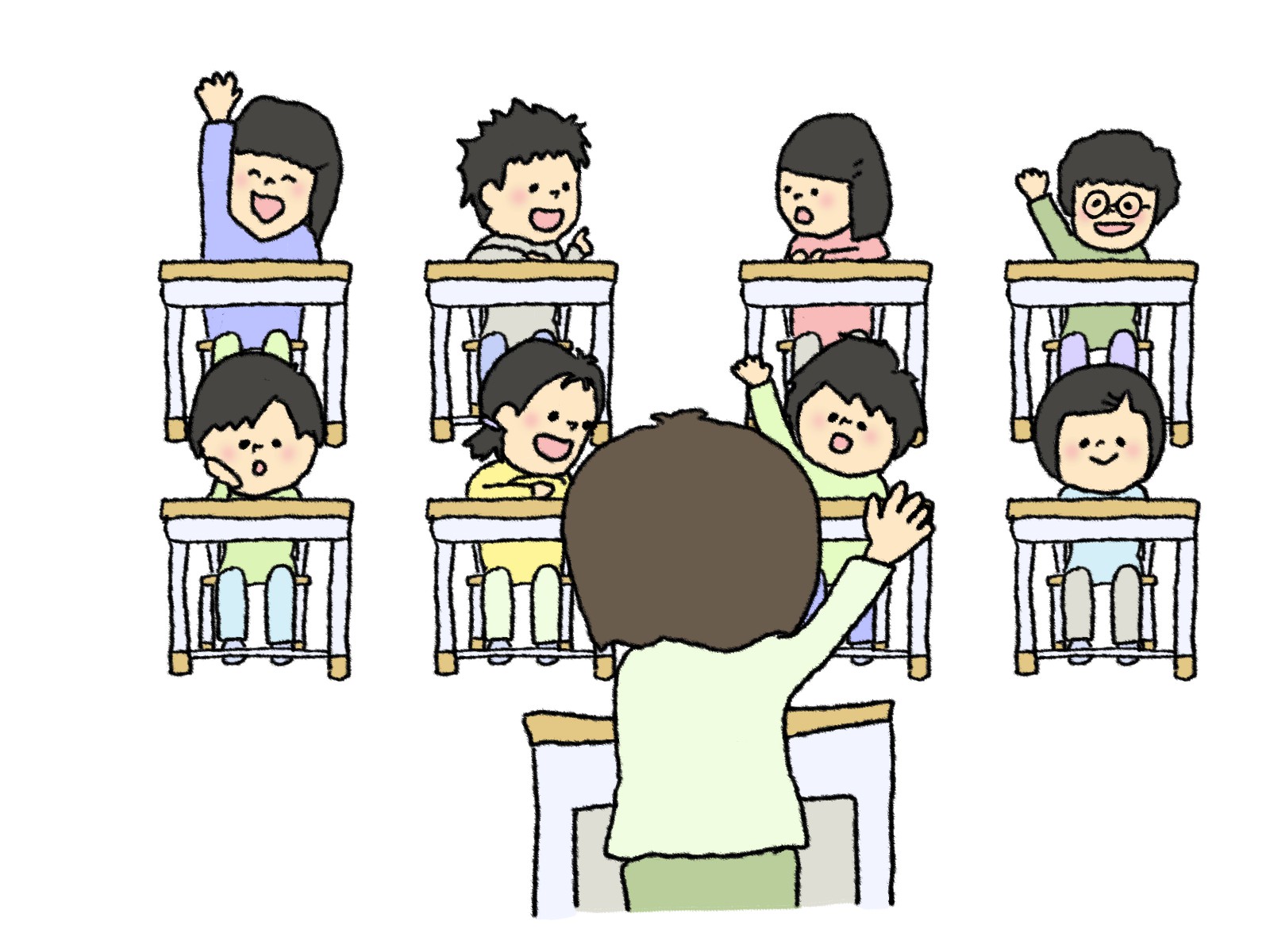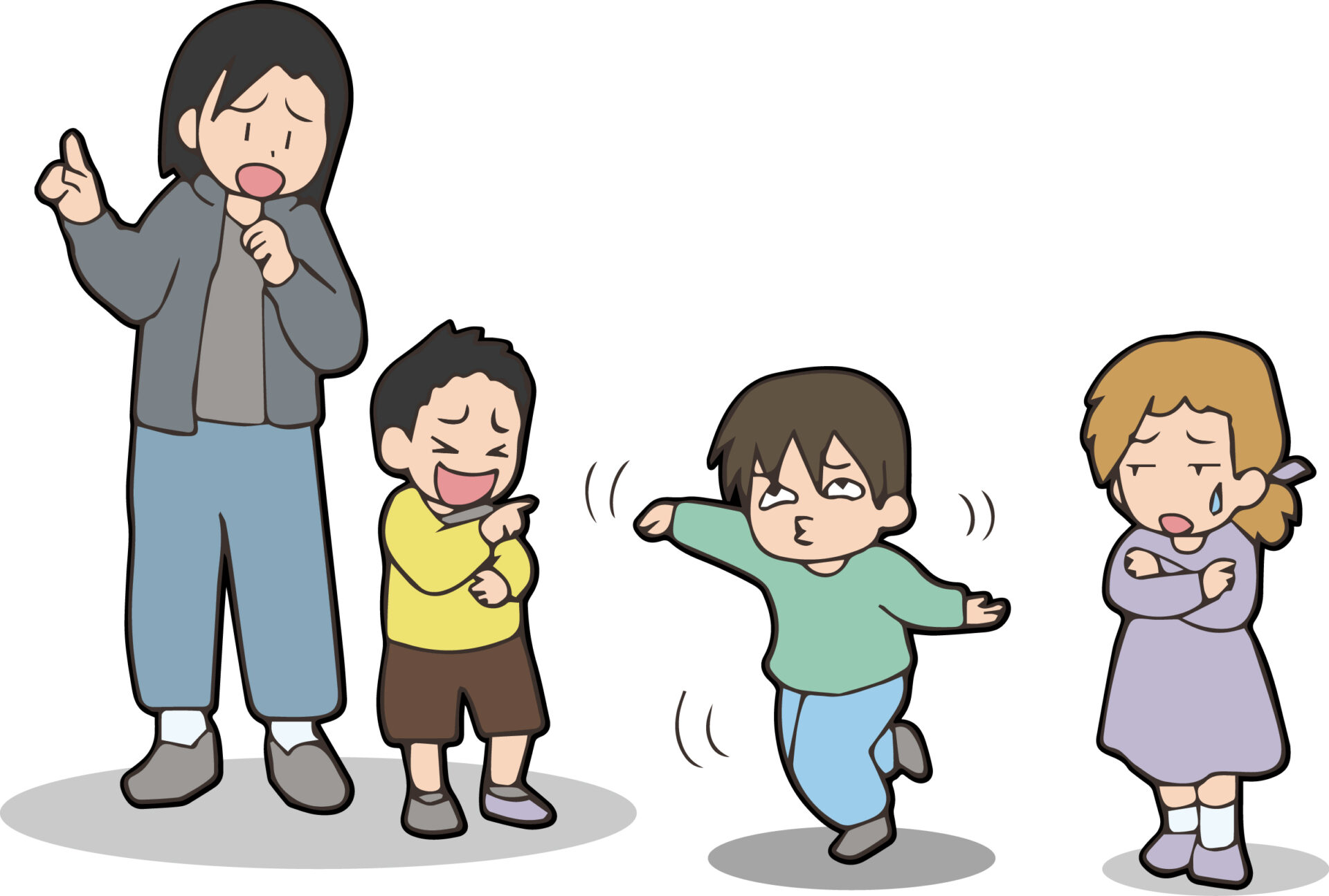目次
「学級目標は、どうやって決めるのがよいのだろう」
「効果的な学級目標を立てるためのポイントを知りたい」
こんな悩みを抱える先生は、少なくないのではないでしょうか。
学級目標は、児童と担任の願いが詰まった、1年間の学級経営の羅針盤となるものです。学級目標を活用することで、児童の健全な成長と、より良い学級づくりに役立ちます。
この記事では、学級目標の役割や決め方、効果的な目標にするためのポイントについて具体的に解説しています。学級目標のつくり方に悩む方は、ぜひ最後までご覧ください。
学級目標は、なぜ必要?
学級目標は、1年間の学級生活において児童と学級担任が共通して取り組むべき「日常の指針」となります。児童の健全な成長とより良い学級づくりのために、欠かせないものといえるでしょう。
学級目標が果たす役割
学級目標を設定することで、学級全体が目指す方向性が明確になります。共通の目標があることで、以下のような効果が期待できます。
▼主体的な行動を促進できる
自分たち自身が決めた目標を掲げることで、学習や学級活動への意欲を高め、主体的な行動を促します。
▼連帯感を醸成できる
クラスメイトと共に目標に向かって努力する過程で、学級全体の連帯感や、互いに協力し合う意識が生まれます。
▼行動の指針となる
学校生活の中で迷ったときや判断に困ったときに、適切な行動を選択する手助けになります。
学級目標を立てるときの注意点
学級目標を立てるときには、児童が「自分たちで決めた学級目標を守る」と思えるようにすることが大切です。
担任が目標を決めてしまうと「先生が勝手に決めた目標」になってしまい、学級目標を守ろうとする気持ちが育ちにくいです。一方で、児童だけで決めさせてしまうと、先生側の願いや「児童に身につけさせたい力」を盛り込むことができず、偏った目標になってしまう可能性もあるでしょう。
学級目標を立てる際には、児童の主体性を尊重しながらも、先生の教育的意図も含める工夫をする必要があります。 また、学年目標がある場合には、その内容も関連付けた目標を設定するようにしましょう。
学級目標はクラスの一体感を育て、主体性を引き出す力を持っています。
効果的な学級目標とは?
効果的な学級目標を設定し共有することで、児童が目標達成に向けてより主体的に努力できるようになります。以下のポイントをおさえて効果的な学級目標を立てましょう。
具体性がある
学級目標は具体性があることが重要です。抽象的な言葉ではどんな行動をとればいいのかわかりにくいため、具体的な行動レベルまで落とし込んでください。
▼例
「休み時間に声をかけ合って遊ぼう」
「提出物は前日に準備しよう」
「困っている人に『大丈夫?』と声をかけよう」
目標が具体的だと、行動に結びつきやすくなるだけでなく、達成度が確認できたり、イメージを共有しやすくなったりする効果もあります。
肯定的な表現を使う
目標を立てるときは、否定的な表現を避け、肯定的な表現を使うようにします。たとえば、「授業中はしゃべらない」と行動を禁止するのではなく、「授業中は集中して話を聞こう」と前向きな行動を促します。
▼例
「廊下を走らない」→「廊下は歩いて移動しよう」
「人の悪口を言わない」→「友だちの良いところを見つけよう」
目標を肯定的な表現にすると、前向きな行動を促し、児童のやる気を引き出す効果があります。児童が学級目標をポジティブに捉えて行動できると、クラス全体の雰囲気も良くなるでしょう。
実現可能性がある
目標が児童にとって高すぎるものだと、途中であきらめてしまう可能性があります。実現可能な目標を立てるためには、以下のポイントに注意しましょう。
- 児童の発達段階に適しているか
- 無理なく達成できそうな目標か
また、学級目標は、誰もが具体的に行動に落とし込めるものであることも大切です。抽象的な言葉やあいまいな言葉だと、行動に移しにくく評価もしづらくなってしまいます。
児童の言葉で表現する
学級目標を立てるときは、児童の言葉で表現するようにします。児童から出た言葉を文言に取り入れることで、目標をより理解しやすくなり親近感も湧きます。「自分たちで目標を立てた」という意識も生まれ、主体的に取り組めるようになるでしょう。
児童の言葉を集めるには、以下のような方法があります。
▼児童の日常会話から集める
- 児童たちが普段使っている表現
- クラス内の発表などでよく出る言葉
- 日常生活や授業内で印象に残った発言
▼話し合いで児童の言葉を集める
- 付箋や用紙に自分の意見を書いて提出してもらう
- グループに分かれて目標について話し合い、案を出してもらう
- クラス全体で学級目標の言葉を出し合って決める
また、先生の視点ではなく、児童の視点からの言葉で目標を立てるようにするのもポイントです。
▼例
「積極的に発言しましょう」→「どんどん手をあげて発表しよう」
「協力して活動しましょう」→「力を合わせてがんばろう」
児童にとってリアルで身近な言葉を使い、具体的な目標を立てることで、児童が実行しやすくなります。
学級目標をつくるときの「学年別アプローチ」
学級目標を立てるときに、児童の発達段階に応じて必要なアプローチをすると効果的です。ここでは、学級目標をつくるときに取り入れたい学年別のアプローチについて解説します。
低学年での工夫
小学校低学年で学級目標を決めるときには、児童が具体的な行動をイメージしやすいものにするとよいでしょう。身近な経験と結びつけて考えられるよう配慮し、「目標が達成できた」と実感しやすいものにするのも大切なポイントです。
また、とくに低学年の児童にとって、先生の言葉の影響は大きいものです。先生の意見ばかりが反映されないよう、先に児童の意見を聞くなど、目標を立てるときは慎重に対応しましょう。
▼低学年の学級目標例
「なかよく たのしく げんきよく」
「えがおで あいさつ みんななかよし」
「おはなしは みみをすまして きこう」
中学年での展開
小学校中学年では、クラスメイト同士で話し合いをもつなど、みんなで協働して目標を立てるとよいでしょう。
グループに分かれて話し合いで案を出してから、学級全体で話し合うなど、積極的に児童が意見を出せるような状況を用意します。
中学年では、少数の意見も尊重するなど、意見の出し合い方や決定の仕方についても工夫しながら、協働のあり方を学べるように促していくとよいでしょう。
▼中学年の学級目標例
「考えよう つたえよう 力を合わせて 前へ進もう」
「思いやりの心で 助け合うなか間たち」
「チャレンジせい神で さい後までやりぬこう」
高学年ならではの深め方
小学校高学年では、児童一人ひとりの主体性を重視し、それぞれの価値観への理解を深める機会にしましょう。目標を決めるまでの話し合いの過程を通して、なぜその目標が必要なのか、目標を実現することの意義などについても考えます。学年目標や学校全体の目標にも目を向けて、学級目標と関連づけていくのもよいでしょう。
▼高学年の学級目標例
「自分を信じ 仲間を大切に 夢に向かってチャレンジしよう」
「一人ひとりの個性をみとめ合い 高め合える仲間たち」
「自分で考え 判断し 責任をもって行動しよう」
学級目標をつくるときには、それぞれの学年の成長度に応じたアプローチをするとよいでしょう。
学級目標を決めるプロセス5ステップ
次に、実際にクラスで学級目標を決めていくときのプロセスを具体的に解説します。以下を参考にして、魅力的な学級目標にしていきましょう。
Step1:話し合いの土台づくり
学級目標を立てる前に、話し合いの土台をつくりましょう。「安心して意見を言えるクラスとは?」「お互いを尊重するには何が必要?」などの問いかけを通して、児童が理想の学級像について考える時間を設けます。
ワークシートを活用したり、グループ内での意見交換を促したりして、どんなクラスにしたいのかイメージを膨らませていきます。この段階では自由な発想を大切にし、どんな意見も批判せずに、多様な意見を集めるとともに、児童が発言しやすくなる基盤を整えることが重要です。
Step2:今のクラスの課題の共有
次に、クラスの長所や課題について振り返る時間をとりましょう。ワークシートなどを活用して、個々に「今のクラスの良いところ」「もっと良くしたいところ」「心配なこと」などを書き出していきます。
一人ひとりが振り返ったら、グループ内で意見交換をします。意見交換の時間では、グループ内で似た意見をまとめたり、優先順位を考えたりしながら、児童たちが他の人の意見も尊重できるような声がけをしてみてください。そして、各グループでまとめた意見をクラス全体で発表し合います。話し合いの過程を通して、クラス全体の意見の傾向や、共通して感じている良さや課題が見えてくるでしょう。
Step3:クラスが目指す姿の明確化
クラス全体での話し合いを通し、「こんなクラスにしたい」「このクラスで、こんなことができるようになりたい」といったクラスの理想の姿の具体化・明確化を促していきます。
意見の食い違いを活かした話し合いを
学級目標を決める過程で、児童同士の意見が食い違うこともあるでしょうが、より良い目標を生み出すチャンスと捉えましょう。対立する意見が出たときには、まず「なぜそう思うのか」という背景にある思いを、双方から丁寧に聞き出してみます。一見相反するような意見でも、実は根底にある願いには共通点があることも多いものです。
具体的な指導の方法としては、「意見の共通点を探す」「複数の意見を融合させる」「時期や場面によって使い分ける」などがあります。たとえば「勉強第一」と「友情を大切に」という意見が対立した場合、「学び合い、高め合う友だちの輪」という形で、両方の要素を含む一つの目標にまとめることができます。
「目標を決めるために出た意見の根底にある【実現したい想い】は何か?」という、目標設定のスタートに児童を立ち返らせることで、議論を建設的な方向へ導きましょう。
Step4:言葉の選択
学級目標を具体的な言葉にする段階では、その年代の児童にとって理解しやすく、行動につながりやすい表現を選ぶことが大切です。以下のポイントを意識して言葉を選びましょう。
短く覚えやすい表現にする
学級目標は日常的に唱和したり、つねに意識に置いたりするものなので、簡潔で覚えやすい言葉を選びましょう。長すぎる文言は記憶に残りにくく、日常での目標の活用が難しくなります。
クラスならではのオリジナリティを出す
クラスの特徴や強みを活かした学級目標にすると、愛着が湧いて意識に定着しやすくなります。たとえば、担任の先生の名前で語呂合わせをした学級目標をつくると、独自性が生まれ親近感も湧くでしょう。
▼例(田中先生のクラスの場合)
「た:たすけあい、な:なかよく、か:かんがえよう」
リズム感のある表現を工夫する
七五調や四字熟語のようなリズム感のある表現を取り入れると、印象に残り覚えやすいでしょう。
▼例
「明るく 楽しく 力を合わせ」「一意専心 日々前進」
具体的なイメージが湧きやすい言葉を選ぶ
抽象的な概念よりも具体的なイメージを喚起する言葉を選ぶと、児童が目標を行動に移しやすくなります。
▼例
「笑顔の花を咲かせよう」「手をつなぎ 心をつなぐ ○○組」
Step5:目標の実践と振り返り
学級目標を決めたら、日常的に意識して実践する心がけが大切です。朝の会や帰りの会で、学級目標を確認する時間をとりましょう。週や月単位など、定期的に学級全体で振り返りの時間をもつことも有効です。
また、運動会や遠足など行事の前には「学級目標をどう活かすか」を考え、行事の後には「目標に沿った行動ができたか」をみんなで振り返ることで、目標と実践を結びつけ、クラスの絆を深めていきます。
一つずつ丁寧にステップを踏んでいくことで、魅力的な学級目標をつくれます。
学級目標を活かした学級経営
前述したように、学級目標は決めただけで満足せず、実践や振り返りを行うことが、児童の成長につながります。児童にとって「大切にしたい、守りたい学級目標」になるように、学校生活にうまく取り入れていきましょう。
以下のような活用法を参考にして、日々の学校生活で学級目標を活かしてみてください。
朝の会・帰りの会での活用
朝の会や帰りの会で学級目標の確認を習慣付け、振り返りの時間をとると効果的です。たとえば朝の会で学級目標をみんなで唱和すると、意識付けにつながります。
そして帰りの会では、その日の学級目標の達成状況を振り返る時間を設けましょう。学級目標を達成できた児童を「今日のキラリさん」として紹介したり(その日、とくに目標に沿った行動ができた児童を褒める取り組み)、クラス全体の頑張りや成長を共有したりすることで、成功体験を積み重ねることができます。
このような日常的な振り返りの積み重ねが、学級目標の実現と児童の成長につながっていくでしょう。
学級活動との連携
学級活動に学級目標を取り入れて、月間テーマの設定や活動内容の工夫を行うと、より良い学級づくりに活かせます。
たとえば、「思いやりのある言葉で絆を深めよう」「互いを認め合い、笑顔あふれるクラスに」といった目標に対して、「言われて嬉しい言葉や、心が温かくなる言葉を集めてカードに記し、大きな木に貼りつけて掲示する」「クラスメイトにしてもらって嬉しかったことを、カードに書いてポストに入れる」といった仕組みをつくるのも一案です。目標が達成されていく様子が目に見えてわかる楽しいアイデアで、学級活動を盛り上げましょう。
目標達成の進捗が目に見える形になると、児童たちの意欲が高まり、クラス全体に一体感が生まれます。日々の成功体験を積み重ねることで、自然とクラスの雰囲気も良くなっていくでしょう。
学校行事での意識付け
学校行事は、学級目標を実践する絶好の機会です。運動会や遠足、学習発表会など、どの行事でも学級目標を関連付けることが可能です。
たとえば「力を合わせる」が目標なら、運動会の練習開始前に「今日は、どんな場面で力を合わせられるか」を考えてからスタートし、練習終了後には振り返りを行います。
行事の前には「この行事で、みんなで学級目標を達成するにはどんな行動をするか」を全員で話し合い、終了後には「学級目標に沿った行動ができたか」を振り返ることで、あらためて目標の意識化と共有・定着を促しましょう。
こうした取り組みにより、学校行事の教育的な意義が深まるとともに、クラスの一体感も自然と強まっていくでしょう。
学級目標を活用して、児童たちが成長できる、より良い学級経営につなげていきましょう。
学級目標を活かした学級づくりを目指そう
学級目標は、単なる言葉ではなく、クラスの成長を支える大切な土台となります。学級目標を決めるときは、児童の考えと先生の願いを共に盛り込むよう工夫しましょう。
学級目標を効果的なものにするには、実感を持てる「児童自身の言葉」を使って具体的に表現した、行動に移しやすい目標にすることが大切です。目標を決める際にも、学年に応じた適切なアプローチを行うと、話し合いが深まります。
学校生活の中で学級目標を活かせるようなアイデアと心がけで、日々、より良い学級経営を目指してみてください。
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。