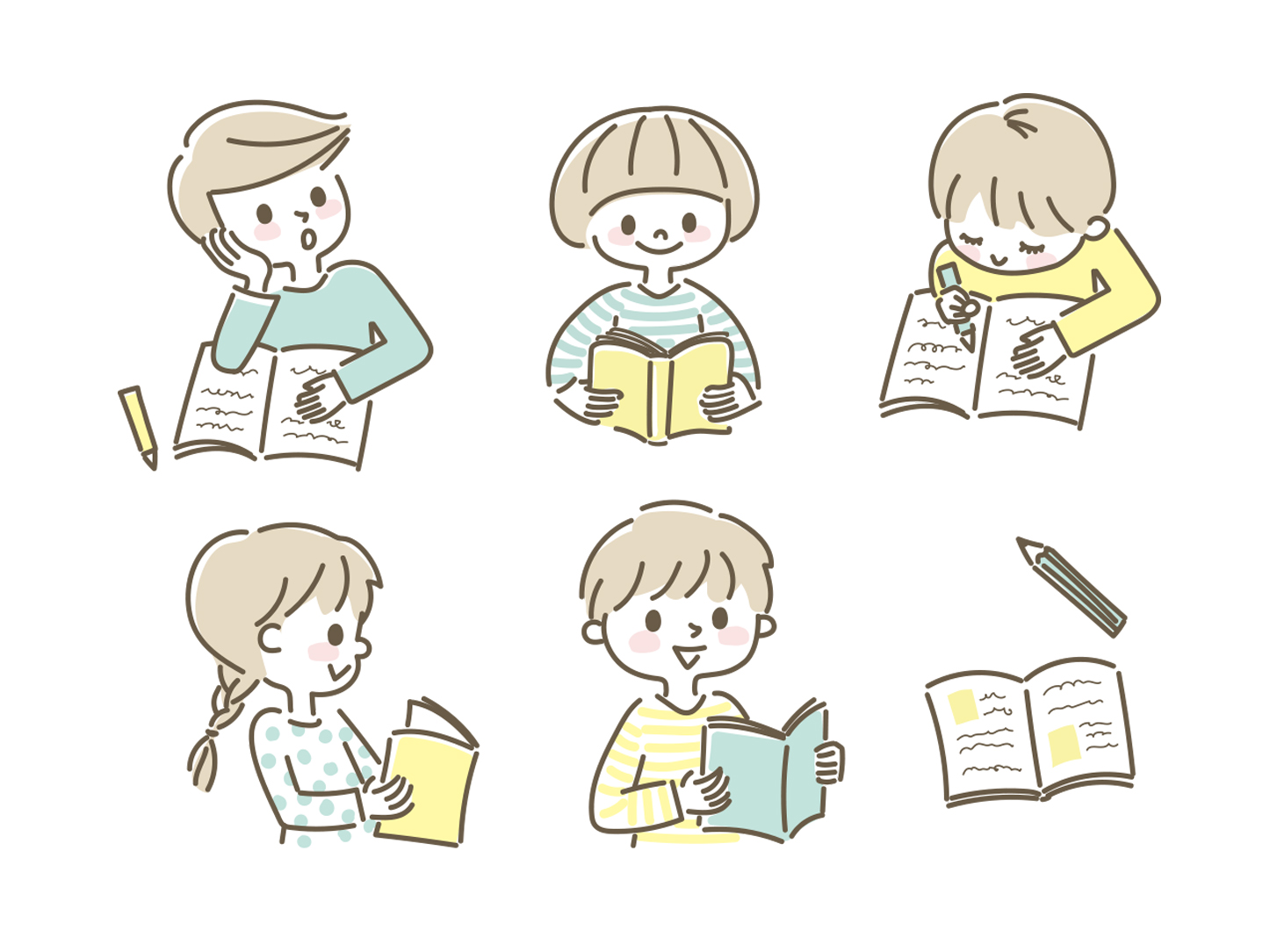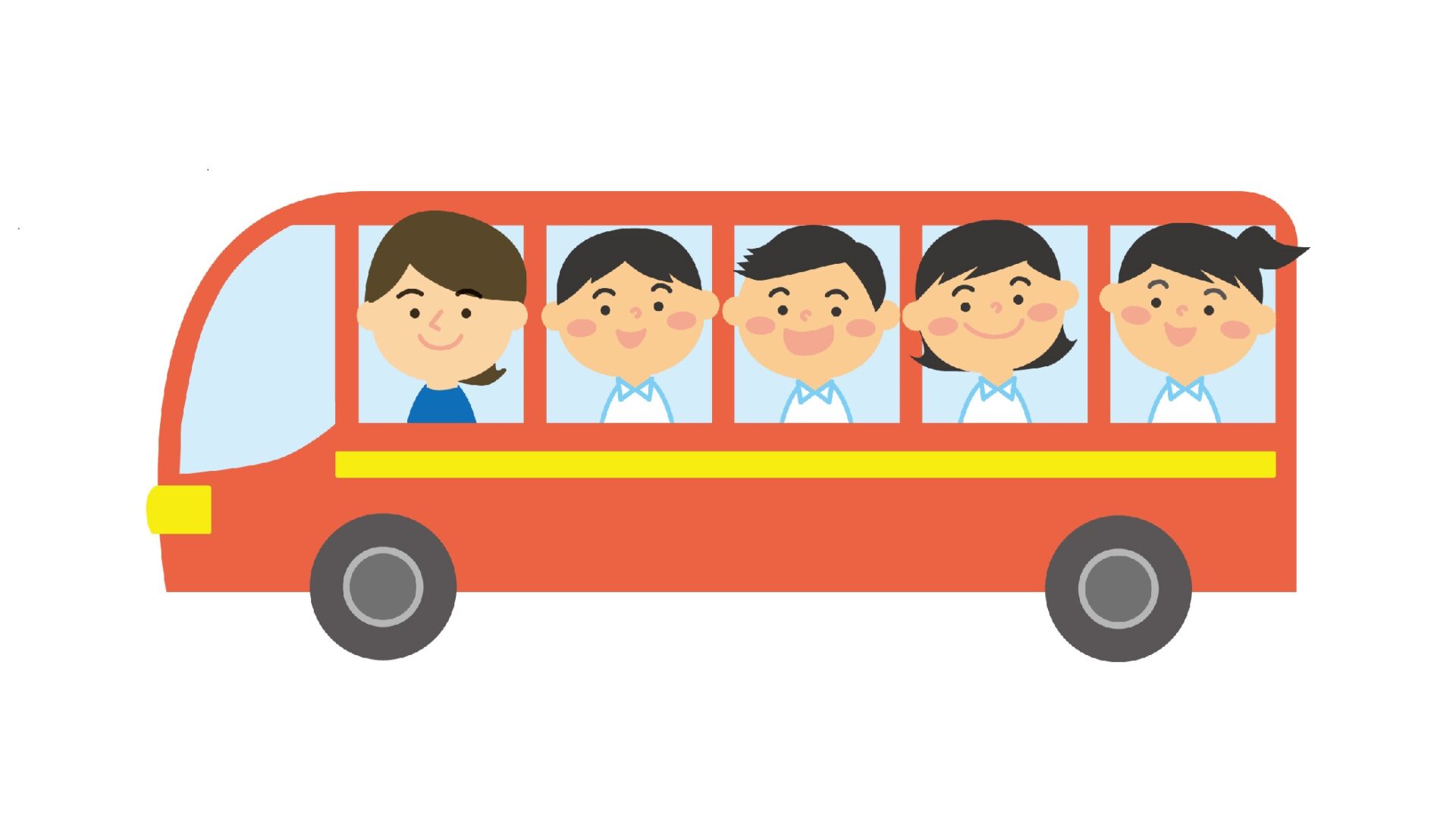目次
「デジタル教材を取り入れたら、どんなメリットがあるの?」
「うちの塾でも使ったほうがいいのかな?」
そうお悩みの方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
近年、学校ではGIGAスクール構想のもと、1人1台端末の整備が進み、授業でのデジタル教材の活用が当たり前になってきました。さらに、生成AIなどの技術革新により、子どもたちの学び方そのものが変わり始めています。
このような教育現場の状況を踏まえ、「塾で使う教材も、時代に応じて見直すべきではないか」と考えるのは、当然の流れと言えるでしょう。
そこで、この記事では、
- デジタル教材とは何か
- 導入するメリットと注意点
- デジタル教材の選び方
- 紙の教材との使い分けのコツ
について、塾で運営・指導に携わる方々の視点に立って、わかりやすく解説します。ご自身の塾に合ったスタイルを見つけるヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。
「デジタル教材」とは?
「デジタル教材」とは、スマートフォンやタブレット、パソコンなどのICT機器を使って学習する教材のことを指します。従来の紙テキストとは違い、動画や音声、アニメーションなど、デジタルならではの機能を活用することで、視覚と聴覚を通じて理解を深められるのが特徴です。
具体的には、次のような使い方ができます。
【動画でイメージをつかむ】
図形の回転や理科の実験の様子などを、映像で視覚的に確認できる。言葉だけでは伝わりにくい内容も理解しやすくなる。
【自動で丸つけ、すぐに見直し】
解いた問題がその場で採点され、どこを間違えたのかすぐに確認できる。復習もスムーズにできて、理解の定着につながる。
【ゲーム感覚で楽しく学ぶ】
タイムを計ったり、ポイントがたまったりといったゲーム的要素により、子どもたちのやる気やモチベーションを引き出せる。
【一人ひとりに合わせた出題】
最近では、AIを活用して、個々の学習履歴や理解度に応じた問題を出す教材も登場。個別最適な学びを実現しやすい点も、デジタル教材の大きなメリット。
このように、デジタル教材には「わかりやすい」「続けやすい」「自分に合った学習ができる」といった利点があり、子どもたちの学びを多角的にサポートしてくれます。
学習の目的や場面、使う子どもの特性を把握して、柔軟に教材を選択できると、学習の個別最適化に大いに役立つでしょう。
塾でデジタル教材を導入する5つのメリット
デジタル教材を取り入れることで、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、塾での活用を想定した5つの利点を紹介します。
1.視覚的な教材で、説明がスムーズに進む
説明に時間がかかる内容でも、デジタル教材を使って「見せる」ことで、よりスムーズに理解できるようになります。
たとえば、平面図形の回転や立体の展開図などは、板書だけでは生徒にイメージさせるのが難しいものです。そうした場面では、動画やアニメーションを活用し、図形が実際に回転する様子を見せることで、理解度が高まります。
また、理科の単元では、実験映像を見せながら説明することで、器具がなくてもイメージを共有しやすくなり、授業もスムーズに進みます。
2.自動採点とフィードバックで、講師の指導が効率化できる
解説付きのフィードバックができる教材では、子どもがその場で正誤や解き方を確認できるため、単純なミスや理解不足を自分で修正できる機会が増えます。その結果、講師がすべての問題を一から解説する必要がなくなり、本当に支援が必要な生徒や、理解が難しい単元に絞って指導できるようになります。
さらに、自動採点機能によって全体の正答傾向を把握しやすくなるため、補足すべき内容の見極めもしやすくなります。
こうした仕組みにより、授業の進行がスムーズになるだけでなく、指導の質を保ちながら、時間的にもゆとりのある授業づくりが実現できます。
3.子どものモチベーションを高められる
タイムアタックの要素があったり、スコアやポイントが見える化されたりといったゲーム要素のある機能は、特に小・中学生のモチベーションアップにつながりやすい特徴があります。こうした工夫によって子どもが学習に前向きな気持ちで取り組めるようになれば、授業の雰囲気がよくなったり、講師との関係性が築きやすくなったりと、さまざまな効果が期待できます。
また、競争心が強い子や、目標があると頑張れる子、達成感でやる気が出る子など、さまざまなタイプの子どもたちが取り組みやすい仕組みである点も、デジタル教材ならではの強みです。
4.一人ひとりに合った指導がしやすくなる
デジタル教材の中には、AIが過去の個別の解答履歴や理解度に応じて、問題の内容や難易度を調整する機能を備えたものもあります。これにより、各生徒への異なる出題・課題設定に自動対応できるため、個別最適な学習が実現しやすくなります。
たとえば、「計算は得意だけれど文章題が苦手」「分数になると計算ミスが多い」というような生徒の苦手分野に対し、克服のために重点的に出題する設定も可能です。講師が自ら一人ひとりに応じた指導に時間をかけなくても、デジタル教材を使えば生徒それぞれの理解度に合わせた内容で学習が進むため、授業全体の効率化につながります。
さらに、解答履歴・学習時間・正答率など、個々の生徒の学習データが蓄積されていくことも大きなメリットです。こうしたデータを活用することで、一人ひとりの理解状況をより正確に把握でき、指導方針の見直しにもつなげることができます。
5.家庭との連携や報告がスムーズになる
デジタル教材の多くは、塾外からもアクセスできる仕組みになっています。そのため、家庭での学習状況もデータとして記録され、学習履歴や進捗を把握しやすい点が大きなメリットです。
たとえば、「どの単元を家庭で復習したか」「いつ・どこでつまずいたのか」といった情報が記録として可視化されるので、保護者への報告もより具体的に行えるようになるでしょう。これは、面談などの場面で非常に有効で、講師と保護者が共通認識を持ったうえで適切な学習支援を進めることに役立ちます。
さらに、学習履歴をもとに「最近、この単元に家でも繰り返し取り組んでいた成果が現れましたね」といった共有をすることで、保護者の安心感や、家庭での子どものモチベーションを向上させる声かけにもつながります。
子どものやる気を引き出しつつ、学習の進捗や理解状況も見える化できる、手軽な学習アプリもおすすめです。授業の効率化と家庭学習のサポート、両方を実現できるツールとして、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
見て、聞いて、書いて。各生徒の認知特性に合わせた「得意な覚え方」で、楽しみながら身につきます!

デジタル教材を導入する際の注意点と対処のポイント
どんなに便利なツールでも、導入には不安や課題がつきものでしょう。塾でデジタル教材を導入する際は、いくつか注意すべき点があります。
ここでは、実際に現場で起こりうるケースと、その対処法をご紹介します。
機器トラブルやネットの不具合が起きたときの対処法
ICT機器やインターネットの接続にトラブルが起こると、授業の進行が滞ってしまう可能性があります。突然の不具合に慌てないためにも、あらかじめ以下のような準備をしておくと安心です。
- 授業前に機器の動作確認をする
- 紙の教材も用意しておく
タブレットやPC、ネット回線が正常に使えるかどうか、授業前のチェックを習慣にしましょう。そうすることで、不具合の早期発見につながります。
また、機器が使えない場合に備えてプリントや補助教材を紙でも準備しておくと、すぐに授業を切り替えられます。
トラブル時の対応手順をマニュアルにまとめておくことで、スタッフ間で共有しやすくなり、混乱を最小限に抑えることができます。
操作に不安を感じる講師へのサポート
講師が操作に不安を感じることなく、スムーズに教材を使い始められるよう、導入前の準備やサポートはとても重要です。特に、これまで紙教材が中心だった場合、デジタル機器の操作に不慣れな講師が戸惑いを感じるのは、仕方がないとも言えます。
そのような場合は、塾として講師に負担をかけずに導入できる工夫が必要です。
- まずは授業の一部だけで使ってみる
- わかりやすい操作マニュアル、運用開始前の操作練習の機会を用意する
- 特に初めての導入の場合、操作が複雑でないシンプルな教材を選ぶ
たとえば、最初は「確認テストだけデジタル教材にする」など、特定の場面に限定して取り入れると、不慣れな講師への負担も少なく、運用がスムーズでしょう。あわせて、操作の流れをわかりやすくまとめた資料があれば、安心して取り組むことができます。
ICT環境のない家庭への対応方法
デジタル教材を家庭学習にも活用するには、各家庭のICT環境の差異に配慮した準備が欠かせません。導入前に各家庭の状況を把握し、環境の差により子どもの学習にデメリットが生じないような利用方法を、検討・準備しておくことが大切です。
対応のポイントは、次のとおりです。
- ICT端末の用意や、必要なネット環境について、事前に確認する
- 自宅での利用が難しい家庭の場合は、紙教材も併用する
- 家庭では補助的に使い、塾での使用を中心にする
タブレットなどのICT端末の購入やネット環境の準備が難しい家庭があった場合は、紙のプリントを併用し、子どもの学習内容に差が出ないようにするなどの対応が必要になります。また、塾内での使用をメインにし、家庭ではあくまで補助的に利用するといった運用で、各家庭の負担を抑えつつ学習効果を高めることも可能です。
デジタル教材を導入すること自体が目的ではなく、子どもにとって学びやすい環境を整えることが本来の目的であることを、塾として常に意識しましょう。
集中力を保つための活用設計とルールづくり
デジタル教材は、便利で魅力的な一方で、画面演出の多さや操作の楽しさから、集中力が続きにくいという場合もあります。導入後に「うまく活用できない」「子どもがすぐ飽きてしまう」といった事態を防ぐためには、導入前から活用目的や使用ルールをしっかり設計しておくことが重要です。
以下のような視点を事前に整理しておくと、使用時の混乱やトラブルを防ぎやすくなります。
- デジタル教材を使う目的を明確にしておく
- 使用時間や使うタイミングについてルールを決めておく
- 「解説→演習→ふり返り」など、一連の流れを設計しておく
たとえば、「計算の定着を目的として、5分間演習として使う」「理解の確認のために、動画視聴後にふり返りを書かせる」など、教材を使う目的や流れを明確にしておくことで、集中しやすい環境をつくることができます。また、「20分経ったら、いったん画面を閉じる」など、子どもに合わせた時間設定や区切りをあらかじめ設けておくのも有効です。
このような活用設計を導入前に整えておくことで、子どもたちの集中力を保ちつつ、デジタル教材の利点を最大限に活かすことができるでしょう。
デジタル教材の長時間の使用は、目の疲れやドライアイの原因となり視力の低下を招く可能性があること、不適切な姿勢で使用すると姿勢の悪化や腰痛などのリスクが高まることなど、健康面への影響も懸念されます。長時間の連続利用は控え、姿勢に気を配ったりストレッチを挟んだりと、適切な配慮のもとで利用しましょう。
デジタル教材の選び方と迷ったときのポイント
「塾としてデジタル教材の導入は実現したいけれど、どれを選べばいいのか迷う」というケースも、少なくないのではないでしょうか。
デジタル教材は、種類も機能もさまざまで、実際に使ってみないとわかりにくい部分も多いため、比較検討のうえ、自分の塾に合うものをじっくりと選ぶことが大切です。
選ぶ際には、以下のようなポイントを押さえておきましょう。
- 無料トライアルなどを活用し、実際に試してみる
- サービス提供会社にデモや導入説明を依頼する
- トラブル時のサポート体制が明確かを確認する
- 他の塾での活用事例を調べて参考にする
トライアルを通じて、「どのくらい操作がしやすいか」「生徒が興味を持って取り組めそうか」といったリアルな使用感を確かめておくと、導入後のギャップを極力減らせます。また、サービス提供会社の担当者に直接話を聞いたり、デモ画面を見せてもらったりして、疑問点を解消したうえで導入を判断すると安心です。
なお、導入後にトラブルが起きた場合に備え、決定前にサポート窓口の有無や対応のスピードなど、サービス提供会社のサポート体制が充実しているかどうかを確認しておくことも、重要なポイントです。
さらに、他の塾の事例を調べてみるのも、後悔しない選択のために有効です。対象学年や指導形態(個別・集団)などが自塾と似ているケースを参考にすると、より具体的に自塾での使い方をイメージしやすいでしょう。
デジタル教材の導入に際しては、機能性だけでなく、必ず「実際の授業での使いやすさ」や「自塾の生徒との相性」も大切な選定基準だと念頭に置いてください。
導入後に「思っていたのと違った」ということにならないよう、事前に自塾での具体的な活用法を想定のうえ、機能の特色や使い勝手も十分に確認し、相性を重視して選びましょう。
デジタル教材と紙の教材|使い分けのコツ
このように、デジタル教材は個別最適な学習への利便性が高く、子どもたちと講師の双方にとって便利なものです。一方で、長年使われてきた紙の教材ならではの良さもあります。
紙の教材には、自分の手を動かすことで記憶に定着しやすい、記述力や文章による表現力を育てやすい、といったメリットがあります。また、自分のペースでじっくり考えながら書いて理解を深めることができるので、復習や自主学習にも紙教材は適しています。こうした活用は、自分の考えを整理し、論理的思考力を育てるうえでも効果的です。
一方で、デジタル教材には、図や動画の活用により視覚・聴覚からの理解を深めやすい、という利点があります。
それぞれに異なる強みがあるからこそ、学習の場面や内容・目的に応じてうまく使い分けることで、学習効果をより高めることができるでしょう。
なお、授業の中での使い分けの一例としては、次のような流れが考えられます。
- 前半:デジタル教材で図や動画を使って理解を促し、用語などの基本問題を解く
- 後半:紙教材を使って演習問題を解き、単元のまとめを書かせる
このように、「理解 → 演習 → まとめる」という一連の流れの中で、各教材の特性を活かすことを意識すれば、インプットとアウトプットのバランスが取れた授業が実現します。
デジタル教と紙教材、両方の特色をよく理解し、自塾の指導スタイルやカリキュラムを踏まえたうえで、学習の目的に応じて使い分けると、塾としてのきめ細やかなサポートにつながります。
デジタル教材のメリットを活かし、最適な学びを提供する塾づくりを進めよう
デジタル教材は、視覚的なわかりやすさや即時フィードバック、ゲーム要素によるモチベーション維持、個別最適な出題など、多くのメリットがある学習ツールです。このような機能は、塾の限られた学習時間の中で、効率的かつ効果的に学びを進めるための大きな力となります。
ただし、操作に慣れていない子どもや講師への配慮、機器トラブルへの備え、各家庭のICT環境の違い、教材選びの基準など、導入時に検討すべきポイントも少なくありません。だからこそ、紙教材との違いや、目的に応じた使い分けを意識し、自塾に合ったスタイルで取り入れることが大切です。
ICT活用促進の流れにより、学校におけるICT環境の整備が進んだ今、塾でもデジタル教材のメリットを最大限に活かした学習環境づくりは必須と言えます。効果的な利用で、子どもたちにとって最適な学びを提供できる塾づくりを進めていきましょう。
書いて考える力を伸ばしながら、演習問題や進捗管理の機能で学習のフォローも効率的に。授業と家庭学習、両方の質を高めるツールとして、こちらもおすすめです。

これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。