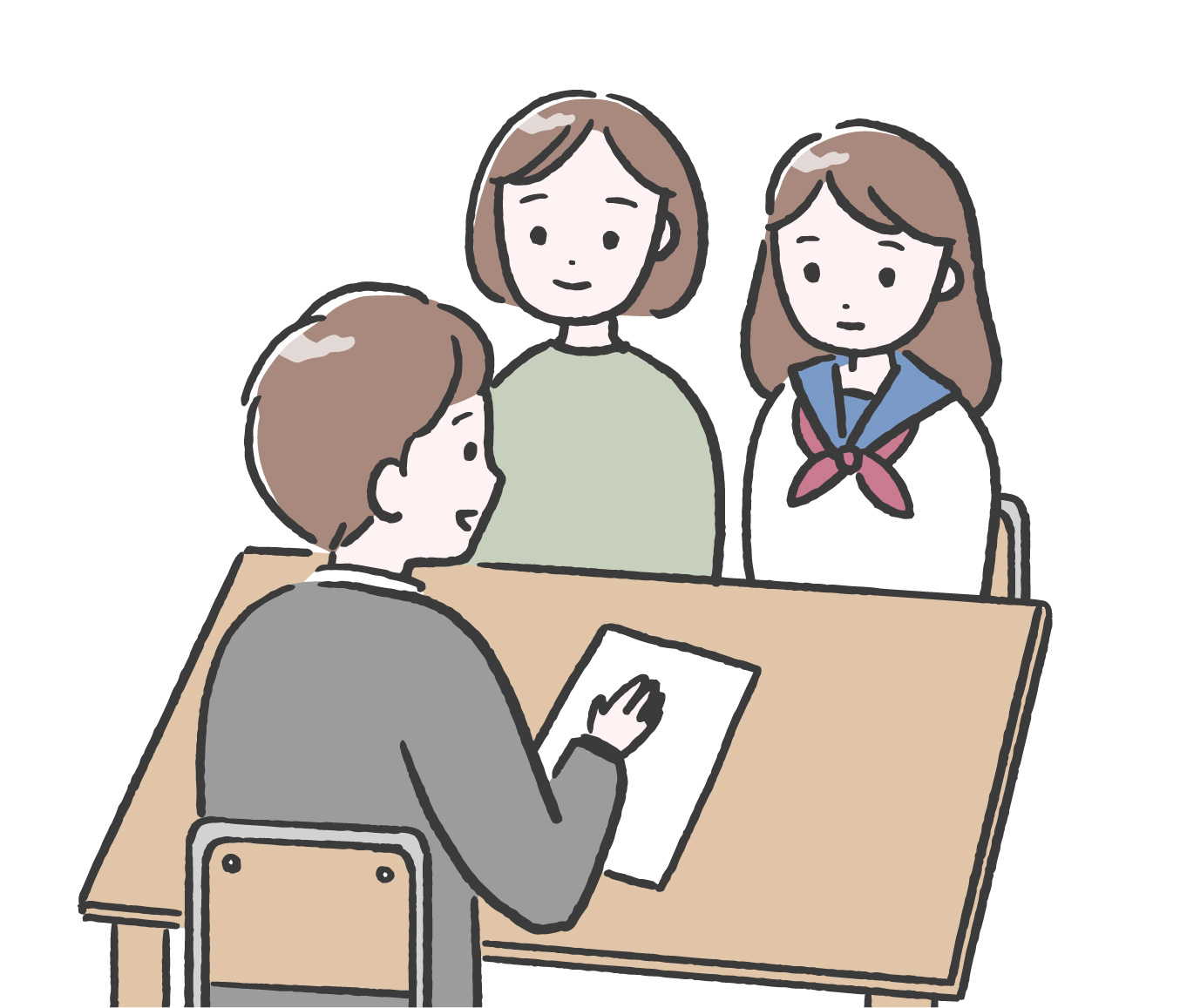目次
「受験を目前に控えた生徒たちを励ましたい」
「受験生の心情に寄り添う適切な言葉がけは、なかなか難しいな」
「応援のつもりで言ったことで、逆にプレッシャーをかけすぎてしまわないか心配だ」
このようにお悩みの先生方は、多いのではないでしょうか。
受験生は、プレッシャーと不安を抱えながら日々がんばっています。心に響く応援メッセージを送るコツは、生徒の不安な気持ちに寄り添いながら、個々の成長を認めることです。
今回は、生徒の心に響く応援メッセージのポイントを、シーンごとに具体例、効果的な応援方法や注意点とあわせてご紹介します。適切な言葉を伝えて緊張を和らげ、学習に集中できるように応援しましょう。
応援メッセージを送るときの重要ポイント4つ
受験生へ応援メッセージを送るときには、彼らが抱えているプレッシャーや不安を取り除くような、やさしい言葉が求められます。生徒の現状や気持ちをよく考えて、前向きな気持ちや行動につながるような言葉を選びましょう。
ここでは、応援メッセージを送るときのポイントを4つ紹介します。
生徒一人ひとりのがんばりを認める
一人ひとりの様子をよく観察し、個々の努力を具体的な言葉で表し、本人に伝えてみてください。
多くの生徒ががんばっている中で、自分のがんばりを認めてもらえるとうれしい気持ちになるものです。「先生は、しっかり見ていてくれるんだ」という安心感を持てるよう、その生徒なりの取り組み方を認めましょう。
🟠 声かけの例:
「毎日、授業時間以外も勉強がんばっているね」
「英語の長文理解が早くできるようになったね」
「以前と比べて〇〇がうまくなったよ」
「この部分の理解が深まっているね」
「問題を解くスピードが上がったね」
受験勉強は小さな進歩の積み重ねです。すぐには成果が現れず、モチベーションが低下してしまうこともあります。大きな成果が見られない生徒に対しても、小さな進歩を見逃さずに伝えましょう。
プレッシャーを感じさせない表現を選ぶ
受験生は、心の中に不安やプレッシャーをたくさん抱えながら生活しています。メッセージを送る際は、生徒がプレッシャーに感じるような表現は避けることが大切です。
避けるべき言葉の例
「必ず」「絶対」といった言葉は、必要以上に言われた生徒の緊張感を高めてしまう危険性があります。本来の実力を発揮できなくなる場合があるので避けましょう。
🟢 避けるべき言い方の例:
「絶対、合格してきなさい」
「必ず志望校に合格するように」
また、つい言ってしまいがちな「がんばって」という言葉にも、注意が必要です。すでに限界までがんばっている生徒にとっては「これ以上、まだがんばらないといけないの? まだ足りないの?」というプレッシャーになってしまいます。
プレッシャーを与えない応援メッセージの例
では、受験生への応援メッセージには、どのような言葉を選ぶべきでしょうか。結果だけでなくプロセスが大切であることを伝え、普段のがんばりを言語化してみてください。
🟠 声かけの例:
「ここまで毎日よくがんばったね」
「いつもがんばっているのを知っているよ」
「今のあなたのがんばりは、間違いなく、未来の自分へつながっているよ」
「〇〇さんのペースで、無理せずにやっていこうね」
「前よりも自主学習をがんばっているね」
なお、他の受験生との比較はプレッシャーを感じる要因になります。周りと比べることなく、本人のペース・姿勢を尊重した言葉を選ぶようにしましょう。
生徒の不安に寄り添う姿勢を示す
「志望校に受かるだろうか」「この勉強方法でよいのだろうか」と悩む生徒には、元気づけるだけでなく、不安な気持ちを受け止めるような言葉を伝えましょう。
🟠 声かけの例:
「うまくいかないときもあるよ。焦らずやっていこう」
「なかなか成果が出ないと不安になるよね。あわてずに〇〇さんのペースで進めよう」
「何について困っているの? 〇〇の分野をもう少し復習しようか」
「わからないところがあったら、いつでも相談に来てね」
不安を感じている原因とその対策を、一緒に考える姿勢を示すのもおすすめです。いつでもサポートする用意ができていることを伝えることで、一人ではないのだと感じてもらえるでしょう。
先生自身の経験を適度に共有する
先生自身の経験を踏まえたアドバイスには説得力があり、励まされる受験生も多いものです。失敗から得られた学びもあることや、つらい時期を乗り越えた経験を伝えると、ナーバスになっている生徒も前向きな気持ちになれるかもしれません。
🟠 声かけの例:
「先生も、受験生のときは同じ気持ちだったよ。でも、乗り越えた先には楽しいことが待っているよ」
「なかなか成績が上がらなくて焦った経験は、先生にもあるよ。落ち着いて、やるべきことをやっていこう」
生徒が今どんな気持ちなのかを考えて、心を込めたメッセージを送りましょう!
シーンに応じた応援メッセージ例
受験勉強をしている期間には、成績が順調に伸びる時期もあれば、停滞する時期もあります。定期試験や模試の結果に一喜一憂し、気持ちが大きく揺れ動く生徒もいることでしょう。
ここでは、入試に至るまでと受験本番前後の各シーンに適した応援メッセージを紹介します。
直前模試や試験の前
模試や試験前には、現在の実力を存分に発揮できるような声かけをしましょう。特に試験の前日などは緊張している場合が多いので、生徒がほっと安心できるような言葉がおすすめです。
🟠 安心させる声かけの例:
「これまで精一杯がんばってきたことを信じて、落ち着いて臨もう」
「〇〇さんなら大丈夫、自分の実力を出してきてね」
頑張りすぎてしまう生徒には、試験前に体調を崩してしまわないよう、健康管理についてアドバイスするのもよいでしょう。
🟠 アドバイスの例:
「体調管理を第一に考えて、無理しないようにね」
「いつもの力が出せるように、前日は早めに寝てね」
試験に対して不安を強く感じている生徒には、いつでもサポートできることを伝えると、安心して取り組めます。
🟠 安心させる声かけの例:
「わからないことがあったら、いつでも聞きに来てね」
「あなたは一人じゃないよ。いつでも話を聞くからね」
スランプや不安に陥ってしまった時期
試験の点数や合否判定に、努力の成果がなかなか現れない時期も訪れます。また、どう努力すればわからないというような、スランプに陥る時期もあるかもしれません。そんな時期には生徒の不安な気持ちに寄り添い、一緒に乗り越えようと励ますメッセージを伝えましょう。
🟠 励ましのメッセージ例:
「先が見えない不安な気持ち、とてもよくわかるよ」
「先生にもそんなときがあったよ。一緒に乗り越える方法を考えよう」
がんばりすぎてストレスが溜まっている生徒には、少し息抜きを提案するのもよいでしょう。
🟠 アドバイスの例:
「これまでがんばってきたのを見ていたよ。少し休むことも大切だよ」
「いつもがんばっているよね。たまには好きなことをして、リフレッシュしよう」
受験直前
いよいよ受験シーズンが到来すると、生徒の緊張と不安が増していきます。最後の追い上げで、気持ちが張り詰めている生徒も多いでしょう。プレッシャーを感じさせる言葉は避けて、安心して最後の確認やコンディションの調整に取り組めるよう、あたたかな声かけやアドバイスを心がけましょう。
🟠 あたたかな声かけの例:
「試験当日までの間に必要なサポートがあったら、いつでも先生に言ってね」
「入試直前でもあわてずに、いつもどおりのペースで大丈夫」
「これまでの自分の積み重ねを信じて、落ち着いて試験を受けてきてね」
自信を失いがちな生徒には、これまでの成果を具体的な数字を使って伝えると説得力が増します。
🟠 安心させる声かけの例:
「がんばって勉強して〇点も上がったんだから、大丈夫」
「この1年でノート〇冊分も学んできたのだから、自信をもって!」
また、受験シーズンには、生徒にとって健康の維持も大きな課題となります。試験当日を心身ともに健康な状態で迎えられるよう、健康を気遣う言葉がけをするのもよいでしょう。
🟠 健康を気遣う言葉がけ例:
「あとは健康管理に気を付けて、試験日まで無理をしないで過ごしてね」
「睡眠を十分とって、元気な状態で力を発揮してきてね」
「自分を信じてリラックスしよう。入試も平常心が大切だからね」
入試当日
入試当日の応援メッセージは、これまでの生徒の努力を認め、前向きな気持ちで試験に臨めるような言葉を選んでください。落ち着いたやさしい言い方で生徒の不安を取り除き、プレッシャーを軽くして背中を押してあげましょう。
🟠 応援のメッセージ例:
「これまでがんばってきたのだから、いつもどおり取り組めば大丈夫」
「これまでの努力をずっと見てきたよ。落ち着いて行ってきてね」
「先生は応援しているよ。行ってらっしゃい」
「リラックス、リラックス。深呼吸して、力を発揮してきてね」
合格発表前
試験終了から合格発表までの間は、期待と不安で落ち着かない時期となるでしょう。これまでの努力を認める言葉をかけて、過度な不安を取り除いてあげてください。
🟠 生徒に寄り添うメッセージ例:
「君のがんばりを先生は知っているよ。これまでの努力は必ず役に立つよ」
「毎日一生懸命がんばったね。どんな結果でも、今までのがんばりを誇りに思っていいんだよ」
不安が大きく「不合格だったらどうしよう」と悩んでいる生徒には、人生の選択肢はたくさんあるということを伝えましょう。
🟠 励ましの言葉がけ例:
「受験勉強のかたわら、〇〇の自主学習を続けてきたよね。そのスキルは、大学だけでなく、専門学校や企業の育成プログラムなど、さまざまな道で活かせると思うんだ。どの選択肢にも、君の頑張りを活かせる可能性があるよ」
時期や状況に応じた言葉選びで、受験生が前向きになれるよう応援しましょう。
受験生の心に響く具体的な応援例
受験生への応援方法には、手書きによるメッセージ、個別面談での声かけ、クラス全体への応援など、さまざまな手段があります。ここでは、各応援方法のメリットや具体例をお伝えします。
手書きメッセージ
手書きで丁寧に書かれたメッセージには特別感があり、心がこもっているという印象を与えるメリットがあります。一人ひとりに合った言葉を書くと、普段から寄り添っていることが伝わり、信頼関係が深まるでしょう。
🟠 メッセージの例:
「〇〇さんは、いつも自主学習をがんばっていたね。努力家の〇〇さんの夢がかなうように応援しているよ!」
「最後まであきらめずに、終盤の追い上げで成果が数字に表れましたね。〇〇さんが力を出し切れるように祈っています。」
「着実に苦手分野を克服してきた〇〇さん。いよいよ本番が近づいてきましたね。毎日遅くまで勉強していたのを近くで見てきました。これまでの努力を思い出して、当日は自信をもって落ち着いて取り組んできてね。応援しています。」
生徒の好みに合わせたメッセージカードを選んだり、お菓子などのギフトに添えたりする心遣いもおすすめです。
個別面談での声かけ
個別面談では、一対一の時間を大切にし、じっくりと話を聞くようにしましょう。他の生徒や保護者の前では言えない本音や、普段は口にできない悩みを聞き出す大切な機会です。生徒が受験に向けてどのような気持ちで過ごしているのかを聞き、一人ひとりに寄り添ったアドバイスを伝えましょう。
🟠 声かけの例:
「テストでここまで点数が上がったのは、毎日の努力の成果だね。その調子で頑張っていこう」
「成績が上がらなくて不安だったんだね。〇〇の部分を一緒に復習していこうか」
「モチベーションを保てない時期があっても当然だよ。今は得意分野のおさらいに力を入れてみようか」
クラス全体での応援の工夫
クラス全体に対して応援する場合は、以下のような方法があります。
- 文章を印刷物にして一人ひとりに渡す
- メールやSNSで全員に対するメッセージを送る
- 教室に応援メッセージを掲示する
手書きの文章を印刷物にするときは、イラストや装飾を添えると、さらに温かい気持ちが伝わりやすくなります。
🟠 印刷物のメッセージ例:
「いよいよ本番が近づいてきましたね。みんなのがんばりは、確実に力になっています。先生は、いつも応援しています!」
メールやSNSでの応援メッセージは、送りたいタイミングですぐに気持ちを届けられます。たとえば、入試前日や当日の朝といった大事な場面の直前に送るとよいでしょう。「返信不要です」の一言を添えておくと、生徒たちに余計な気遣いをさせずに済むでしょう。
🟠 メールやSNSでのメッセージ例:
「いよいよ、明日が入試本番ですね。少し緊張するかもしれませんが、普段通りに落ち着いて取り組めば、必ず力を発揮できると思います。先生たちも心から応援していますので、自分を信じて頑張ってきてくださいね。」
教室にメッセージボードなどを作成する際は、先生からのメッセージだけでなく、生徒同士のメッセージを書き合う等、クラスでの支え合いの雰囲気づくりを心がけましょう。
教室でのメッセージボードの設置については、先生からの応援の言葉を中心に、温かい雰囲気作りを心がけましょう。生徒同士の励まし合いについては、付箋などを用意して自由に書いて貼れるスペースを設けるなど、それぞれの気持ちに寄り添った形で行うことが大切です。強制感のない、自然な形での応援の場となるよう配慮しましょう。
🟠 教室に掲示するメッセージ例:
「目標達成に向けてがんばってきた成果を、自信をもって発揮してこよう!」
「先生は、君たちの力を信じているよ!」
「この壁を乗り越えて、みんなで春を迎えよう」
伝えたい場面に応じて、メッセージを送る手段を選びましょう!
応援メッセージを送る際の注意点
応援メッセージを送るときには、他の生徒との比較や安易な励ましは避けるなど、注意すべき点があります。ここでは、避けたほうが良い表現や、メッセージを選ぶ際の注意点を紹介します。クラスや生徒個々の状況に合った言葉選びを心がけ、。生徒たちの気持ちに寄り添える素敵なメッセージを送れるといいですね。
比較や競争を煽る言葉は避ける
他の生徒と比較することは避け、その生徒自身の成長に焦点を当てて応援しましょう。模試の順位や偏差値の変化を過度に言及することはプレッシャーとなり、本来の能力が発揮できなくなる場合があります。点数や成績の低下で落ち込んでいる場合には深く言及せず、今後の対策やアドバイスを中心に提案してみてください。
🟢 避けるべき言い方の例:
「〇〇くんの方が成績が上がっているね」
「〇〇さんは、もっとたくさん勉強しているよ」
「どうして点数が下がってしまったのかな。しっかり勉強した?」
「前回は3位を取れたのに、今回は10位以下になってしまったね」
🟠 おすすめの声かけ例:
「次回に向けて、〇〇の分野の練習問題を解いて正答率をあげよう」
また、生徒同士の競争を意識させるような表現も避けましょう。仲間と切磋琢磨することは大切ですが、過度にライバル視させることはトラブルの元になります。
安易な励ましや決めつけはしない
現状を加味しない安易な励ましは、生徒に不信感を与えてしまいます。安心させるつもりの発言も、受け手側の心情次第では無責任な言動と取られてしまうことがあるので注意しましょう。
🟢 避けるべき言い方の例:
「まだ大丈夫、試験までには合格ラインになるよ」
「なんとかなるから、焦らなくて大丈夫」
「がんばれば、必ず受かる」
「君なら絶対、第一志望に入れるよ」
「この調子で判定を上げていけば、必ず合格できる」
タイミングと相手に応じて言葉を選ぶ
生徒それぞれ、置かれている状況は異なります。タイミングに応じた応援メッセージを送ることが大切です。生徒全体に伝える場合は、どのような状況の生徒にも当てはまるような表現で応援しましょう。
🟠 全体に向けた応援メッセージ例:
「これまでがんばってきたことを信じて、力を出し切ろう」
特に、生徒が落ち込んでいるときや不安に感じているときなど、モチベーションの低下が気になる際には、個別で応援する場面を作りましょう。
🟠 個別に励ます声かけの例:
「思うように成果が出ないのはつらいね。一緒に対策を考えようか」
「最近どう? 眠れている? 先生はいつでも味方になるよ」
生徒の心情と状況に応じた対応を心がけましょう!
受験生が希望を持てるような応援をしよう
この記事では、受験生の心に響く応援メッセージのポイント、時期やシーン別のメッセージ例や、避けるべき表現について紹介しました。
受験生には、生徒の状況や心情に寄り添い、これまでのがんばりを認めるような肯定感のある応援メッセージが喜ばれます。特に入試直前になると、期待と不安、プレッシャーで気持ちが不安定になりやすい傾向があります。受験生が自信と希望をもって受験に臨めるよう、心に響く応援を送りましょう!
これからの教育を担う若い先生たちに向けた、
学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。
何気なく口にする駄菓子(chips)のように、
気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。